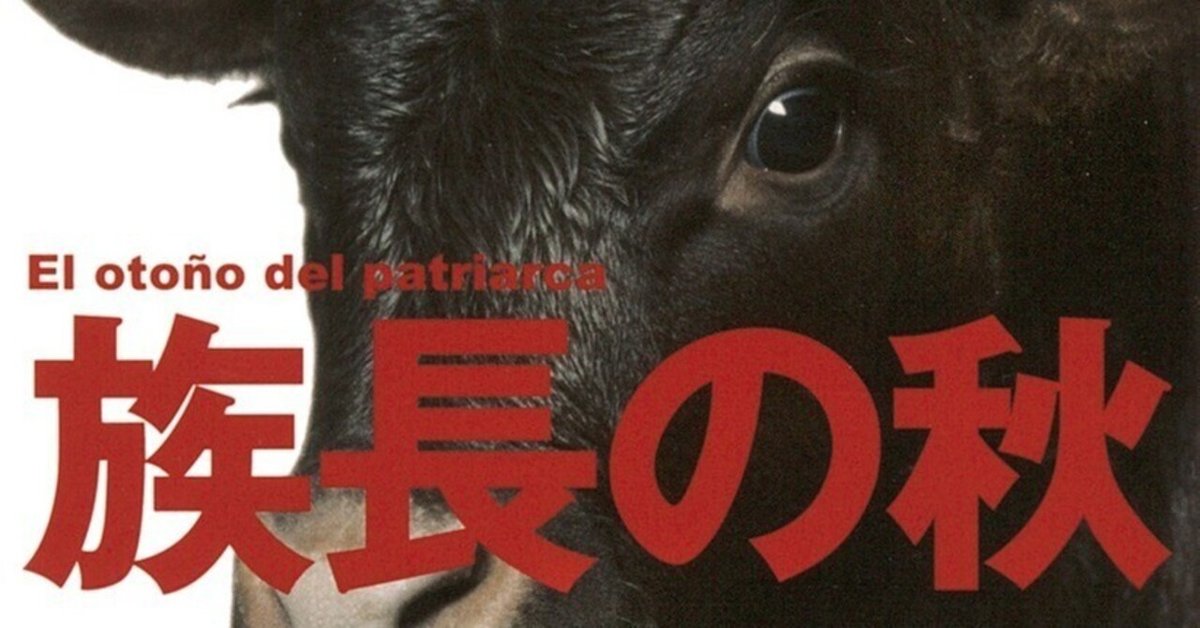
ぼくは族長の秋を読む
ぼくは『族長の秋』を読む。一週間ちょっと前、ガブリエル・ガルシア=マルケスの小説『族長の秋』を読み終わった。ぼくがガブリエル・ガルシア=マルケスの小説を読んだのは、『予告された殺人の記録』『百年の孤独』に続いてこれが3作目である。『予告された殺人の記録』『百年の孤独』の感想については過去にこのnoteで書いたので、暇で暇でしょうがないひとは読んでみたりしてください。
ぼくが『族長の秋』を読もうと思ったのは、『予告された殺人の記録』と『百年の孤独』が面白かったからでもあるが、『百年の孤独』の文庫版解説で筒井康隆が「読め」と言ったからでもある。
本書「百年の孤独」を読まれたかたは引き続きこの「族長の秋」もお読みいただきたいものである。いや。読むべきである。読まねばならぬ。読みなさい。読め。
ぼくは中学生の頃から筒井康隆の愛読者だからな。筒井康隆が「読むべきである。読まねばならぬ。読みなさい。読め」とまで言うなら読まないわけにはいかない。まあ、そこら辺の話については「ぼくは筒井康隆の優しさに感謝する」という記事に書いたので、これもやっぱり暇で暇でしょうがないひとは読んでもらえると幸いです。
『予告された殺人の記録』『百年の孤独』と違って、『族長の秋』の文庫版は現在、品切れ(絶版?)となっている。新品は購入したくても購入できないし、かといってぼくには単行本版(3,520円)を買う経済力がないので、近所の大田区立図書館から借りて読んだ。
読み始めてまず最初に気が付いたのは……って、誰もが必ず気が付くことだと思うが、「改行がない」「カギカッコがない」ということだ。『族長の秋』では改行なしで物語がどんどん進んでいくし、登場人物が言葉を発したとしてもそこにカギカッコが付かない。読者のリーダビリティをあえて無視している。具体的にはこんな感じだ。
それらの存在に気付いて大統領は叫んだ。港だ、ああ、港だ! 港と大統領は言ったけれど、その桟橋は海綿のようにぶよぶよで、そこにつながれているのは、実物よりも長くて陰気な印象を与える、海兵隊の古ぼけた舟艇だけだった。まるで何かにおびえたように駆け抜ける小さな馬車。それをとっさにかわした黒人の女仲仕は、世にも悲しげな目で港を眺める、たそがれた老いぼれを見て、死神に出会ったと思ったのにちがいない。大統領さまだよ! 腰を抜かさんばかりに驚いて彼女は叫んだ、大統領バンザイ! 彼女は声を張り上げた、バンザーイ! 中国人経営のバーや食堂から飛びだしてきて、男も、女も、子供も叫んだ、バンザーイ! 馬の脚が止まり、馬車が立ち往生すると、彼らは最高の権力者に握手を求めた。当然のことながら武器を構えた副官の腕をかろうじて押えた大統領は、緊張した声で激しく叱責した、ばかなまねはやめろ、中尉、連中はわしを愛しているんだ、放っておけ!
まあ、文章の改行の少なさで言えばぼくも他人のことは言えないが、『族長の秋』は改行が一つもないのだから度を越している。しかも、改行なしで次の場面に移ったり、脈略なく語り手が変わったりする。
どっかでこんな形式の小説を読んだことがあったなあ……と記憶の糸をたぐってみたら、ああそうだ、筒井康隆の『巨船ベラス・レトラス』だ。また筒井康隆かよって感じだが、実際、筒井康隆の長編小説『巨船ベラス・レトラス』も空白行なしで場面が次々と転換していくのだからしょうがない。もっとも、『巨船ベラス・レトラス』には改行やカギカッコはあるけどね。でも、『巨船ベラス・レトラス』のあの文章形式は『族長の秋』を真似したものだったのかとぼくは納得した。
さて、『族長の秋』に話を戻す。『族長の秋』は近現代のラテンアメリカの国(たぶん架空の国)の独裁者の物語である。子どもの頃の出来事も書かれてはいるが、一代記というより、大統領としてどう振舞っていたのか、どんな大統領だったのかが語られていく物語だ。『予告された殺人の記録』や『百年の孤独』のように特定の第三者の視点でずっと語られているわけではなく、さっきも言ったように改行なしで次々と語り手が変わっていく。庶民の視点でエピソードが語られていたかと思ったら、次の文では大統領の視点に変わっていたりする。
その一方で、主人公がすでに死んでいる場面から始まって、主人公が生きていた時の話が時系列ごちゃまぜで語られて、最後に主人公の死の真相が明かされる……という全体の構成は『予告された殺人の記録』と同じだ。きっとガブリエル・ガルシア=マルケスはそういうパターンの小説を書くのが得意なんだろうな。文筆家としての「芸風」「作風」っていうか。
……あ、いま「主人公の死」という重大事項をサラッと書きましたけど、それはこの小説を読み始めたら1ページ目か2ページ目ですぐに分かることなので、ネタバレには当たらないと思います。……よね?
コホン(咳払い)。この「主人公が死んでいる→生きていた時の話→死の描写で閉幕」という構成は、生と死のコントラストを表現して読者のカタルシスを招く上手い構成ではあるが、これが許されるのは小説だからこそだよなあと感じる。もし舞台や映画でこれをやったら「どうせ死ぬのが分かっている男の生きていた頃の話なんて興味ねえよ」と思われかねない。
じゃあなんで「小説だからこそ」なのかというと……っていうことを一日半ぐらい考えたのだが答えがまとまらなくて、いや、9割方まとまりかけているのだが、ここでその論考を始めてややこしい長文になるのが自分でも嫌なので、ごめんなさい、その話は今日のところは放棄させてください。ただですね、もしぼくの読みが正しければ、ガブリエル・ガルシア=マルケスが『族長の秋』を改行なしで書いたのは、まさにこの「主人公が死んでいる→生きていた時の話→死の描写で閉幕」という構成を劇的に活かすためのテクニックなんだと思うんです。大胆すぎるテクニックですが……
……あやふやな文学論からはさっさと退却して、そもそもぼくはこの『族長の秋』を楽しんだのか楽しまなかったのか、どっちなんだい!って話をしますね。結論から言うと、たしかに読んでいて飽きることはなかったけど、ぼく的には『予告された殺人の記録』と『百年の孤独』ほどまでにはハマらなかった。筒井康隆が『百年の孤独』の解説で紹介していた荒唐無稽なギャグのオンパレードなのかと思っていたら、別にそこまでハチャメチャではなかったなって感じ。むしろ、淡々とした感じだったっていうか。
まあ、これには、感情移入しやすいキャラクターがいなかったってことが関係しているのかな。ぼくは放送サークルで音声ドラマを作っている人間で、かつて「登場人物の誰にも感情移入できない悲喜劇」の制作に挑戦してみたことがあるのだが、これはなかなかの難題だった。ぼくとしては「感情移入できない物語は悪い物語」という神話に昔から違和感があり、「感情移入がなんぼのもんじゃい!」という気概で制作に取り掛かったのだが、いざ作ってみると、感情移入できる登場人物がいない物語はソワソワする。拠って立つべきところが分かりにくいからソワソワする。
『百年の孤独』は登場人物が変人ばかりではあったけど、各人物に感情移入できる部分があった。『予告された殺人の記録』は語り手の「わたし」が常識人風だったので拠って立つべき視点が明確だった。しかし『族長の秋』はというと、主人公の大統領(名前すら付いていない)は傲慢な性格で感情移入しにくいキャラだし、周りの閣僚やら参謀やらも好感を持ちにくいキャラだし、さらに物語の語り手がコロコロ変わるせいで読者としては「異常な状況を客観的に見る」というスタンスさえ保ちにくい。主人公が分かりやすい独裁者のくせに、『族長の秋』は分かりやすい風刺小説じゃないのだ。
でも冷静に考えたら、そこが『族長の秋』の唯一無二の特色なんだよな。独裁者が主人公で、横暴と忖度に満ちた政権運営を描く小説なら、「政治家を上から目線で冷笑する」みたいな風刺小説になるのが普通だろう。だけど『族長の秋』はそうならない。かといって、この独裁者や周辺人物を「政治のせいでおかしくなってしまった憐れむべき存在」として描くわけでもない。登場人物を「善人」でも「悪人」でも「その中間」でもなく、「人間って結局なんだか分かんない生き物だなあ」って感じで表現して読者を煙に巻く。ぼくにとって『族長の秋』はそんな小説だ。
……ふーむ。ということは、『族長の秋』こそまさしく「登場人物の誰にも感情移入できない悲喜劇」なんじゃないか? ぼくが以前作ったけどいまいち手応えを感じられなかったやつ。しかもよくよく考えてみると、かなりよくできた「誰にも感情移入できない悲喜劇」なんじゃないか。
あと、さっき「『予告された殺人の記録』と『百年の孤独』ほどまでにはハマらなかった」と書いておいてなんだけど、もう一度読み返したいと思うレベルで言うと、『予告された殺人の記録』『百年の孤独』よりも『族長の秋』のほうが上かもしれない。別にいますぐってわけじゃないけど、ぼくは『族長の秋』を読み返したい。掴みどころが分かりにくかっただけに再チャレンジしたい。実際、期待していたような荒唐無稽なギャグではなかったけど、印象的な場面や台詞はいっぱいあったしな。
もう兵隊はいらん、将校もだ、ばかばかしい、連中はミルクをがぶ飲みするだけだ、そのくせ肝心なときには、飼っている主人の手にがぶりと噛みつく、わしはもう、まともで勇敢な親衛隊がいれば充分だ、内閣を造るのもやめた、あほらしいわ、ちゃんとした厚生大臣が一人おればいい、人間が生きていくのに必要なのは、厚生大臣だけだ、
その熱心さに打たれながら大統領は質問した、なぜ、そんな面倒なことに手を出す、死にたい理由でもあるのかね。よそ者は照れるようすもなく答えた、祖国のために命をささげることぐらい名誉なことはない、と思っています、閣下。相手を哀れむような笑いを浮かべて、大統領はそれに答えた、ばかなこと言うもんじゃない、いいかね、祖国とはつまり、われわれが生きていることだ。そうだとも、と自分でうなずきながら、大統領はテーブルに乗せていたこぶしを開き、手のひらのものを相手に見せた。
この死は思いがけないものだった。これでは生きているとは言えない、ただ生き永らえているだけだ、どんなに長く有用な生も、ただ生きるすべを学ぶためのものに過ぎない、と悟ったときはもはや手遅れなのだと、やっと分かりかけてきたが、しかしそのために、いかに実りのない夢にみちた年月を重ねてきたことか。
あとは、大統領がファーストレディーから国語を習う部分も面白かったし、大統領が「女学校の少女」から真相を知らされる場面も面白かった。大統領の下僕となる民間人、ホセ・イグナシオ・サエンス=デ=ラ=バラが活躍するくだりもショッキングではあったけど読んでいてワクワクした(最後はやっぱり衝撃的だったけど。この小説が改行なしの小説であるせいで余計に衝撃的だったけど)。
ぼくは『族長の秋』を読む。うーん。こうやって内容を振り返ってnoteにつらつら感想を書き連ねていると(また5,000字近くいっちゃった)、やっぱり『族長の秋』は面白い小説だったって気がするぞ。これまで読んだことがなかったような小説だった気がするし、いつか読んでみたかったような小説だった気もする。そしてまた再び読んでみたいと思う小説でもある。リアルタイムで読んでいた時には熱狂していなかったけど、時間差でじわじわと面白さがあふれ出てくる感じ。ぼくにとって『族長の秋』はそういう小説だったということで、さて、次はガブリエル・ガルシア=マルケスの短編小説集『エレンディラ』でも読むことにしますか。
