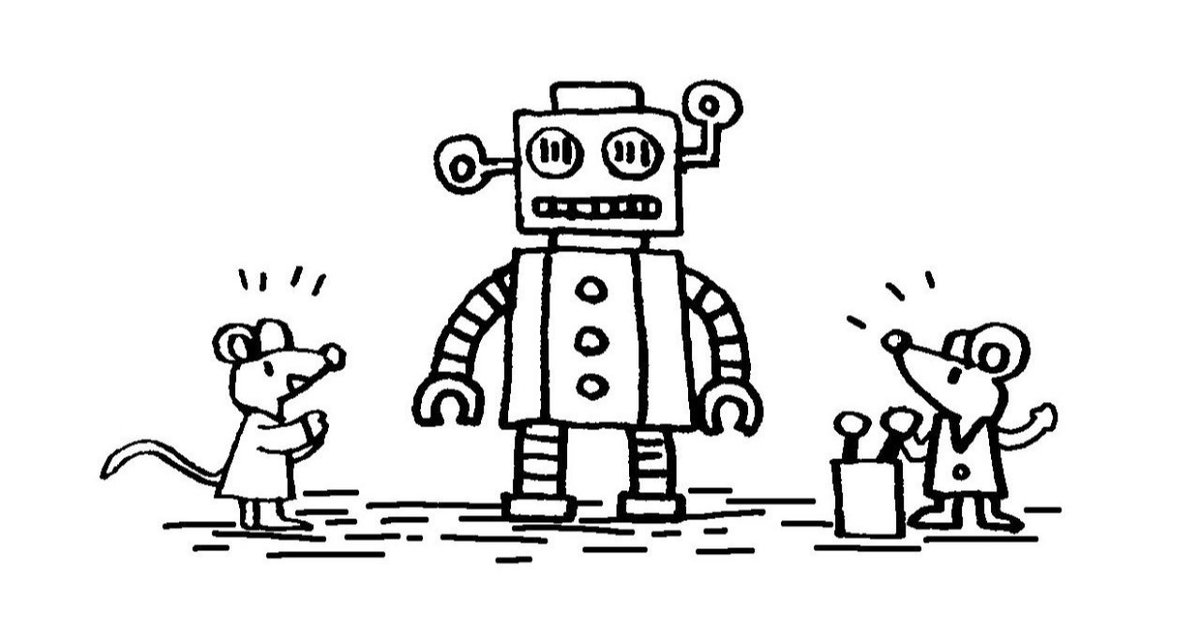
ロボットと哲学②道徳と実存
前回は「ロボット」という語の語源について紹介し、四原因説に従って人間とロボットについて考察したが、今回は「目的性」について別の角度から論考することにより、人間とロボットの存在について再度考察する。
カントの目的論
イマニュエル・カントは人間の理性を「純粋理性」と「実践理性」に分けて考えた。前者は合理的思考能力、後者は善や道徳に関する理性である。純粋理性に関する問題は、量子論や脳科学との関係性から考える方がより建設的であるため、今回は深く扱わないこととする。これは、人間の認識については現代の自然科学の方に軍配が上がるからであるが、カントの純粋理性に関する論考は現在においても研究する価値が十二分にあることだけは明記しておく。 それはそれとして、今回焦点を当てるべきは人間の存在意義に関する分野、すなわち実践理性、とりわけ「仮言命法」と「定言命法」についてであろう。 仮言命法とは「親切をすると、評判が良くなり名声が得られるため人にやさしくしよう」など、端的に言えば他人を手段として扱う考え方である。対する定言命法は「いかなる時も人にやさしくしよう」と、自分の利得とは切り離し、人を手段ではなくて目的として扱う考え方である。 カントによれば、自らの実践理性に従っている状態こそが自由であり、また自らの格率(行動規範)は社会の基準と一致するという(この理想的が達成された状態が、俗にいう「目的の王国」である)。本当に個人と社会の格率(=道徳)が一致するのか、そもそも「道徳」や「正しさ」というものが一意的に決まるのか、このような問題は第4回以降に触れることとする。
道具と自然
カントは「道具」と「自然」を峻別している。道具は、その目的に合わせて作られているが、自然はそれが創られた時には目的などなかった。自然は特定の目的を持って創られたものではなく(旧約聖書の中では、父なる神が創造した秩序だった世界であったが、その目的は描かれていない)、人間が自然の驚異を捉えたとき、経験的な認識を超越した姿を前に畏怖の念を抱くことになる。カントはこの感覚を崇高と名付けた。 しかし、我々は自然を「美しい」と感じることがある。この美しさは、目的の無い美しさである。しかしながら、その対象がふさわしい姿をしているようにも思える。咲き誇る桜の木々や、青々とした山々を観たときに抱く、あの感覚である。この美しさは「目的なき合目的性」と呼ばれる。もちろん、これらはすべて人間の「理性」が持つ判断力によってもたらされる感情である。 さて、これらを総合して(多少の拡大解釈を交えながら)人間とロボットについて考察しよう。ロボットはあくまでも「道具」であり、美(目的なき合目的性)を有さない存在である。一方で人間は(恐らくカントはこのような解釈を望まないだろうが)自然に近い存在であり、目的を持たずに誕生したが、「道徳」や「倫理」をもって美しく生きることが可能である。道徳や倫理の脆弱性や社会と個人の関係に関する複雑な議論を埒外に置いて考えれば、人間は純粋理性によって自由で美しい存在であると結論付けられるだろう。いくらロボットが人間よりも合目的的な存在であったとしても、それは道具として優れてはいるが、人間よりも優れた存在であるとは言い切れない。生産性や技能だけで人を判断するのは、人間を手段として見ている訳であって、定言命法に反している。
道具と人間
フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルは、「道具」と「人間」を明確に峻別している。道具とは目的を持って作られており、それが道具の「本質」であるとした。しかし人間は最初にこの世に存在し、その後の行動によって本質が決まると言うのである。デンマークのセーレン・キルケゴールは、他人と交換できない(共約不可能な)人生を生きていることを「実存」と呼んだが、サルトルにとっては「実存は本質に先立つ」ものであったのである。
ここで前回残した問題「目的なく作られたロボット」と「人格を持ったロボット」の存在について考察しよう。
ロボットと目的性
カントからすると人間の労働を代替する装置に過ぎないロボットは「道具」として人間とは明確に峻別される。だが、「目的なく作られた」ロボットに美しさや芸術性を見出すことができるのであれば、「目的なき合目的性」を有した存在として認識することは可能である(それでもかなりの拡大解釈であることは認めざるをえない)。歴史家であるヨハン・ホイジンガの提唱するホモ・ルーデンス(人間は遊びによって進化した)という考え方を導入すれば、「目的なき道具(ロボット)の作成」を「遊び」と捉えることで、「目的なく作られたロボット」にも目的性を持たせることができる。サルトルに従うのであれば、「目的なく作られたロボット」の存在は目的に先立って存在していると言える。そのロボットの存在意義は社会の中で見出されることになるだろう。しかしながら、このような議論は必然的に多少の硬直性を帯びることとになる。原初のロボット、すなわち人間が行う労働を代替する装置(道具)としてロボットを捉え、「目的性」という尺度でのみあらゆる存在を測定しているためである。議論を次に移そう。
ロボットと自我
「人格を持ったロボット」とはどのような存在であろうか。ロボットが有する人格が人間と全く同じであれば、そのロボットを人間と見做すこともできなくはないだろう。ただし、物事の認識や判断基準がどの程度人間と乖離しているのか、人格がどのように与えられたのか、あるいは獲得したのかによって様々な解釈が可能になる。
現実の問題として、機械が感情を持つことはないだろう。人工知能(Artificial Intelligence)というものがあるが、あくまでそれは計算や論理的な思考が人間よりも得意な機会に過ぎない。確かに、収集した情報を取捨選択を繰り返すことで学習をし、その情報から新たな結論を推論することから、従来のコンピューターやロボットの性質とは一線を画すように思える。しかし人工知能は「与えられた条件の下で分析や計算を行い、その結果を”学習”し結果を改善する」という分野に於いては人間より優れているが、感情や創造性を持たない人工知能が人間を支配するというのは、掃除機や洗濯機が感情を持ち人類を支配するのと同じくらい滑稽な話である。
話をSFに戻そう。ロボットに判断基準を与えるのが人間であるならば、ロボットの感情や人格はそこから生ずると考えるのが自然だろう。しかしながら、そもそもロボットに与えられた判断基準は人間によって与えられたものである。次回はアイザック・アシモフの「ロボット工学三原則」を基に、「ロボット的な合理性の脆弱性」について考えていきたい。
いいなと思ったら応援しよう!

