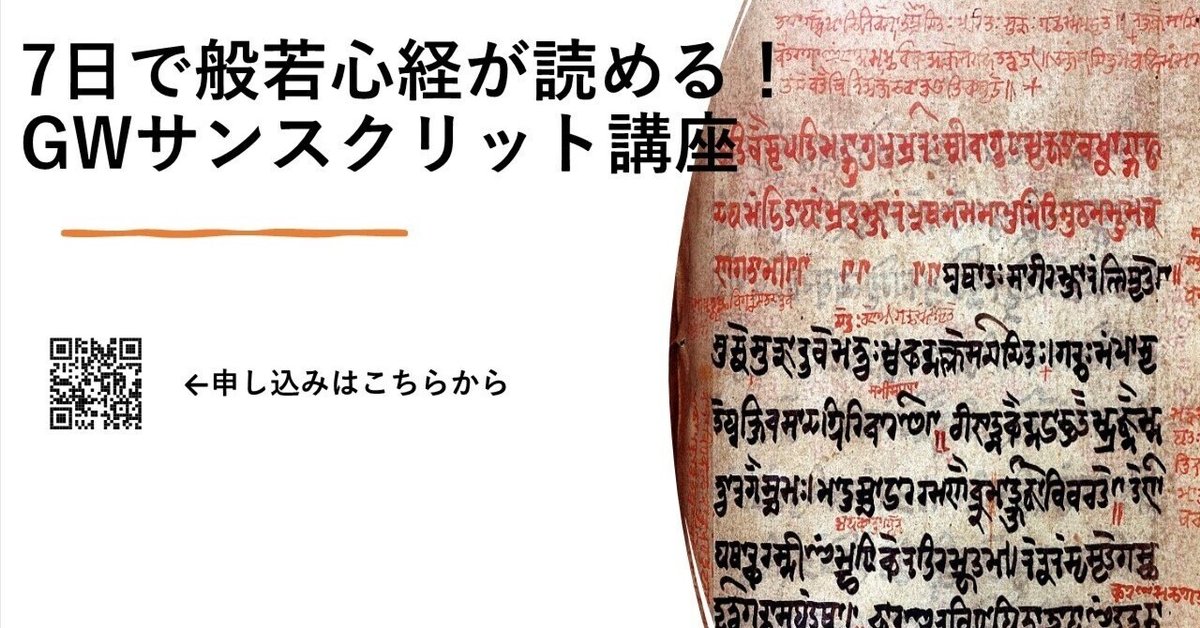
たった7日で、誰でもサンスクリット語で般若心経が読めるようになる! ヨーガやアーユルヴェーダに基づくスーパー学習法の10の秘訣をすべて公開!
カレー屋のメニューにある、上が線で繋がったインドの文字。
絵にしか見えない こんなヤツ「नमस्ते」。
これが文字に見えた瞬間!「ウオーター!」と、叫んだ時の
ヘレンケラーの気持ちになる。
その瞬間、生徒さんの顔がパッと輝く!
おじさんでも、おばさんでも、キラキラになる。
コレを見るのが楽しくて、この講座を続けてきた。
誰でも必ず読めるようになる。それは教え方に独特のコツがあるから。
このコツは、サンスクリットのみならず、全ての語学の習得に役立つ。
ヨーガやアーユルヴェーダなど、インドの哲学に基づいた、
心と体の法則をいかした、10の秘訣を公開しよう!
1:実は3日で十分!アーユルヴェーダで学んだステップアップの力
この講座は、今はオンラインだが、コロナ前には教室で、対面式で教えていた。
その時には、3日間10時間で終わる講座だった。
生徒さんは皆、たった3日でサンスクリットの般若心経が読めるようになった。
秘密の第一は、スケジュールだ。
まず、1日の授業は3時間まで。集中して行うには、これが限界だ。
そして、3日間「連続で」行うことが重要なのだ。
これは、アーユルヴェーダの施術からヒントを得た。
オイルマッサージをする時には、一週間に一度の施術を3週間受けるより、
1ヶ月に一度でも、3日間続けて受けたほうが、格段に高いレベルに到達できる。
理由は簡単。後退する暇を与えないから。
1日目に5合目まで登っても、一週間後には後退してしまうので、
3合目からスタートしなければならない。
連続でやれば、次の日は後退しないまま5合目からスタートできるので、
早く頂上に到達することができる。
だから、3日でも十分に成果が出せるのだ。
間をあけずに、連続で行える日程を作ることが、成功への第一歩だ。
そのため、連休にしかこの講座を行うことができない。
オンラインだと、倍の時間がかかるが、ゴールデンウイークなら 連続で、
その時間を作ることができる。→日程の詳細はこちらから
2:ポジティブオンリーの奇跡! 言い換えゲームで全てをネタに!
連続でやらない場合、時間がムダなだけでなく、心理的に避けたい悪影響が出る。たとえば、 連続ではなく、週に一度の授業だとする。
一週間前のことなど、忘れてしまって当たり前だ。
だが、忘れてしまったことで、「ダメだ….自分には出来ないかも…」という、ネガティブな気持ちが芽生える。これが毒になる。
出来ない、と思うことは、出来ないことを当然と思うことだ。
出来る!と思うと、出来ることが当たり前になるので、自然に大きな力が出せる。
どんな人でも、驚くほどの集中力で、読み書きができるようになるのは、このポジティブ思考のおかげだ。
だから、このクラスの間は、一切のネガティブな言葉を使わないという約束をする。「ダメだ〜!」「むずかしい〜!」こんな言葉を出せば、その現実を肯定してしまう。何もよいことは起こらない。
だから、ポジティブな言葉に言い換えるというゲームをしながら、授業を進める。
「むずかしい〜!」と、言いたい時には「いやあ勉強になるねえ〜!」とか「やりがいあるわ〜」などと、言い換える遊びだ。時々言い間違えて笑いが起きたりする。すべてをネタにして遊びたおす。
楽しいことは、やりたくなる。それが人間だ。
3:小さな自信を積んでいく インドの文字で日本語を書こう!
サンスクリット語には、日本語にない音がたくさんある。
この講座では、その文字を、最初はすべて省いてしまう。
だって難しいんだもの。そんなのに触ったら、自信をなくす。
まずはワカル!読める!楽しい!!それが大切。
だから、最初は日本語の単語をサンスクリットで書く練習をする。
中には、自分の名前や好きな有名人の名前を書く練習もある。
興味のあるものを教材に使えば、取り組みたくなるというもの。
そうやって、日本語の五十音に使う19文字を自由に使いこなせるようにすると、
「自分にも出来る!」という感覚がついてくる。この自信が大切なのだ。
これは、インド料理研究家のメータ・ミラさんの料理教室で、スパイスを最初に習った時の経験を使った。彼女のやり方はこうだ。
まずは、知ってる素材に、知らないスパイスを組み合わせて料理を作る。こうすることで、知らないスパイスの性質を覚える。
次に、覚えたスパイスに、知らない素材を組み合わせて料理を作る。
こうやって、段階的に知っている範囲を広げて、確実に使える知識を積み上げていけば、自信も自然に育てることができるのだ。→お申し込みはこちら
4:イラストとダジャレで覚える イメージの力!
鎌倉幕府の成立年代を聞くと、戦後生まれの昭和の人は大抵1192年と答えられる。
「1192=イイクニ作ろう鎌倉幕府」というゴロあわせで覚えたからだ。
人は意味の無いものを覚えるよりも、意味のあるものを覚えるほうがラクだ。
だから「1192」という無機質な数字も、「いい国」という意味と結びつけると覚えやすくなる。文字も同じだ。
たとえば、これはナという文字だが、水道の蛇口に似ている。
だから、蛇口から水が流れているイラストと組み合わせて「流れのナ」
というあだ名をつけてしまうのだ。このように、意味を持たせると、忘れない。
文字の形をみるだけで、「蛇口→流れ」と連想して
「流れのナ」とカンタンに思い出すことができるようになる優れた方法だ。
だが時々、「蛇口のジャ」と間違って覚える人もいるのが玉にキズである。^^

では、もう1文字。
これは、真四角な折り紙を囲んでいるから、「ましかくのマ」と覚えよう。
2〜3度かけば手からも覚える。書き順は自由だ。だが、文字の形で注意するところが2つある。
下の図の①で上から下ろした筆を右に曲げる角で、クルンとカーブさせること。
②の最後に、右の足を長く伸ばすこと。これだけでmaという文字になる。

さて、ここで問題。
この記事のリードに書いた「नमस्ते」の最初の2文字は、なんと読むか、お分かりだろうか?
よく見て欲しい。あなたは必ず読めるはずだ。
そう、流れのnaと、真四角のmaだ! ここにはナマステと書いてある。
おめでとう!あなたはすでに2文字を読めるようになりました。
「ああ!そうか!」というアハ体験をするたびに、記憶は強くなっていく。
5:発音できない文字を、あだ名で区別する
このやり方には、もうひとつのメリットがある。
それは、文字に名前をつけることで、発音できない文字でも区別できるようになることだ。サンスクリット語には、「流れのナ」の他に、
もうひとつ「ナ」と発音する文字がある。
日本語にはないṇaという音で、我々は耳で聞いても「流れのna」と区別することが難しい。たとえば、インド人に「ナマステ」のナは、どっちのナ?と聞いても、その答えがnaなのか、それともṇaなのかは、聞いただけでは判別できないのだ。

この、もうひとつのṇaという文字は、涙が出ているように見えるので、「涙のṇa」という呼び名をつけた。こうすることで、耳では判別できない二つの音を容易に区別できるようになる。
双子の兄弟のタッチャンと、カッチャンは見分けがつきにくいが、野球部のタッチャンとサッカー部のカッチャンのように言えば、どちらのことかがすぐわかる。
これと同じようなものだ。
他にも サンスクリット語には、「た」「たっ」「だ」「だっ」と聞こえる文字は2種類づつ、「ん」に聞こえる文字は5種類、「s」には3種類も類似音がある。
初学者は必ず混乱する。
だが、文字に名前をつけることで、こうした不要な混乱を解消すれば、知識の吸収がスムーズになる。これが、後に文法を学ぶ時になって、実に役立つのだ。
すべての文字に、こうしたイラストとダジャレ語呂合わせの呼び名をつけることで、イメージに残すことがとても容易になった。たった4〜5時間で、どんな人でも47の文字をすべて覚えることができる秘訣はここにある。
実はこの47文字分のダジャレとイラストを考えるのに10年かかった。笑
たかがダジャレ、されどダジャレ、である。
6:集中は20分まで! 飽きる暇を与えない教材づくり
人は飽きる。1つの作業をして、集中できる限界はおよそ20分。
だから、20分以上同じ作業をさせないことも、教え方のコツだ。
教師の説明を聞く、自分で書いてみる、声に出して読んでみる。
二人一組でフラッシュカードをする。カードで神経衰弱をする。
お札や、広告の文字を拾う。母音体操をする。
こうして、次々にやるべき作業を変えていく。
練習問題の中身も、飽きさせないように工夫した。
こうすることで、飽きずに、脳が興味を保ちつづけることができる。
ものごとを覚える時に、興味があれば面白く感じ、吸収も早い。
興味がなければ、苦痛に感じ、吸収も遅い。
興味は食欲のようなものだ。
食欲がない時の食事は苦痛にすぎず、栄養として身につかないばかりか
未消化物ができて毒素になってしまう、とアーユルヴェーダでは教えている。
学びも全く同じこと。
だから、食欲が出るような、色とりどりで香りのよい
美味しい食事を用意するように、様々な教材を作った。
”キラキラ星”の歌にのせて、英語のABCを覚えるように、
知ってる歌にのせて47のサンスクリットの文字を歌えるように、
合う歌を探した。
インド大使館の講演でこれを教えた時には、20分の講演の最後に
100人以上の日本人の観衆が、全員でサンスクリットのアルファベットを合唱したのでインド大使が笑い転げて感動してくれた。
インドの子供達にも使えるワザだと思うのだが…世界進出の話はまだない。笑
7:太いサインペンで 感覚を総動員する
この講座を受ける時には、かならず太いサインペンを使うことが条件だ。
文字を大きくハッキリと書くように指導する。それは、感覚を総動員して覚えるためだ。手を動かして触覚に訴える。耳から発音を聞いて聴覚に残す。そして目からも黒くハッキリした文字のイメージを焼き付けるために、太いサインペンが望ましい。これは、長い教育経験の中で観察して得た秘訣だ。
ほそい文字、薄い線、小さい文字を書いている人は、覚えが遅い。間違いが多い。
間違えていても、自分で気づかず、そのまま覚えてしまうからだ。
ハッキリ大きい文字を書いている方が、覚えが早く、間違いが少ない。
それは、目から入ってくる印象が強く、黒くハッキリした文字であれば、間違いがすぐにわかるからだろうと思う。
特に、オンラインになってからは、生徒さんがカメラの前に出す課題の文字が見えにくい。判別に時間がかかるので、短縮をしたいという目的もあって、
太いサインペンが必須になった。
8:反応をしない 的だけをみる
ネガティブな思考に限らず、何かを吸収しようとする時に、
心に夾雑音が多いと、うまくいかない。
「あ!間違った」「恥ずかしい〜」「え?どうしよう」「できるかな〜?」
こんな夾雑音が生まれると、その処理に時間とエネルギーをとられる。
その時間とエネルギーを習得へ振りむければ、早く進める。
こうした感情は、反応から起きる。
だから、自分の心を観察して、反応を無視する。
そのためには、目的だけをみて、今その瞬間に必要なことだけに集中することだ。
それが、インド哲学が教える、生き方のコツだ。
矢を射る時に、弓の角度はこれでいいかな…もっと強く握るべきかな…アラ風向きが変わった…というようなことに、いちいち反応しては、射そんじる。
ただ、的をみて、的と心がひとつになった時に矢を放てば、自然に矢は的へ飛んでいく。学ぶ時にもそのようにすれば、最短距離でゴールに到達することが出来る。
そのためには、いちいち目の前でおきたことに反応しない癖をつけることだ。
今やることだけに集中して進めばよい。「英語もできなかったしな〜」という過去の情報や、「私だけ出来ないかもしれない..」という未来の不安に心を飛ばさないことだ。それらはただの幻だ。心をむけてもなんの良いこともおこらない。
たった数日の短い時間に、サンスクリットの読み書きができるようになる、という大きな目標に向かって走るのだ。
これは細い丸木橋を全力疾走して渡るようなものだ。
その時に、大きな荷物を持っていたら、バランスを崩して、フラフラしたり、落ちてしまう。だから、丸木橋を渡るまえに、すべての荷物は捨てて、身一つで走るのだ。そのために、いちいち反応せずに目的だけに集中すること。
難しいように思うかもしれないが、実は、
すべての人は、過去にこのように生きたことがある。
それは赤ちゃんの時だ。
赤ちゃんは、立つ。
「立てないかもしれない」、などと思わないし、
「転んだらどうしよう」とも思わない。
最初はハイハイ、つかまり立ちして、転んだり泣いたりしながらも、
いつかは立って一歩を踏み出すことに成功する。我々は皆それをやってきた。
諦めないで、ただ、歩くということに挑みつづけたから、今、歩いているのだ。
それと同じようにすればいいだけ。
あなたは、すでに成功した経験がある!
9:俯瞰するための地図を作り、文字に背番号をつける
冒険には地図が要る。今、自分がどこにいるのかを わかる必要がある。
47文字を覚えたら、次はそれらの文字を組み合わせて、結合文字を作る練習が必要になる。いままで、いくつかの学校でサンスクリットを習ったが、どこも、この作業を詳しく教えなかった。結合された文字のサンプルを見せて、たくさん書いて覚えるようにするだけだ。だが、結合するにはルールがある。そのルールを解きほぐして、わかりやすく整理した。次から次へと出てくるルールに、あとどれくらい覚えたら終わりがあるのかと、泣き出したくなることもあるだろう。
だが、そんな時に、自分が全行程のどこを歩いているのかがわかれば、やるべきことも見えてくる。そのために、全体の行程がわかりやすくなるように、地図のように、テキストを編集した。47文字を覚える時には、五十音表のようなものに並べ、すべての文字に背番号をつけた。自分が探している文字が、どこに並んでいるのかが、すぐわかるためだ。この表をきちんと覚えておくことは、後に文法の学習の中で必要になる。全体を俯瞰する地図と、現在地がわかる背番号。これであなたは冒険に出られる。
10:甘いものを用意する
脳を動かす唯一の栄養素は糖だ。頭を使うのだから、糖分を補給する必要がある。
だから、生徒さんには、必ず甘いオヤツをもってくるように連絡している。
アーユルヴェーダでは、体を使ったら手入れをすることが大切と考える。
脳を酷使したら、手入れをするべきなのだ。
糖分を補給せずに続けていくと、だんだん覚える能率が悪くなったり、低血糖でイライラしたり、間違っておぼえて凡ミスをしたり…というようなことが増えてくる。これは、アーユルヴェーダでいうと、風の性質であるヴァータが増えてきた証だ。
ヴァータを鎮めるには、甘いもの、脂っこいもの、暖かいもの、液体のものとることが有効だ。一番いいのは、甘くて温かいミルクココア。ギーをいれて飲めば最高だ!
断糖をしている人でも、ブドウ糖を少し取り込むことをおすすめする。
最後に…笑いの力! 自分を信じる
笑いは人をゆるませる。緊張していては、何ごともうまくいかない。
だから、授業の中でも10分に一度は笑いを挟むことを心がけている。
アハ体験だけでなく、心を動かすことは大切だ。
そして、ほとんどの生徒さんが、最終日に必ず言う言葉がある。
「絶対に読めると思いませんでした!」
「まさか読めるようになるなんて!」…というのだ。
「ならばどうしてお金払ったんですか〜!」と、いつも大笑いになる。
この講座を信じて、選んだ。それはあなたがやったこと。
だから自分を褒めてあげよう!がんばれたことを認めよう!
だって、読めなかった文字が読めるんだもの。これは疑いようのない事実。
一週間前の自分より、確実に成長した自分がそこにいる。
体験してみたいと思われる方は、GWにオンラインでお待ちしています!
詳細はこちらへ→https://form.os7.biz/f/31d54943/ (録画有)
