大内青巒著「六祖法宝壇経講義」を読む(第一 行由-07 慧明に説法する)
[壇経講義本文]

五祖の門弟等、師の衣法を米搗きの慧能に付嘱せしことを暁り、迹を追いてその衣鉢を取りかえさんとせり、その中に慧明という一僧あり、衆に先だちて走り、まさに六祖に追いつかんとす、六祖これを見てすなわち衣鉢を一磐石の上に置き、この衣は信を表するの具のみ、取らんとせば取れと、去りて叢の中に隠れて竊に窺う、この段伝灯によるに曰く、
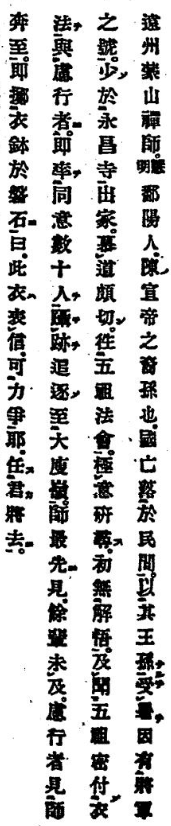

慧明磐上の袈裟を取らんとするに動かず、すなわち喚んで曰く「我は法を求めんが為に来る、袈裟を得んが為にあらず」と是に於いて六祖出でて石の上に坐す、慧明礼して説法を請う、六祖説いて曰く、先ず「諸縁を屏息すべし、一念を生ずるなかれ」と諸縁とは吾人が見るも聞くも立つも座るも皆諸縁なり、諸縁は分別に起こる、分別を離れて之を縁に任せ境に随い、私の分別を用いず、住着する処なきを屏息というなり、別に諸縁を屏除し、息滅すというにあらず、一歩過らば灰身滅智の小見に陥るべし、「坐禅せば四條五條の橋の上、ゆききの人をみ山木と見て」住着することなからんを要す、しかしてなお一歩進めば「ゆききの人をゆききの人」と見ながら坐禅し、万境歴々分明の儘なることを得べし、良久とは閉口の場合をいうことあり、維摩の一黙の如きをいう場合もあり、今は慧明が茫然として自失せるをいうなり、六祖次いで諸縁を屏息し一念を生ぜぬ時の有様を述べていわく、不思善不思悪と、吾人は善悪邪正と彼此相対して分別するが故に、愛憎好悪の念を生じて、本性がくらむなり、故に若し善をも思わず、悪をも思わず、分別を離れたる時に、汝が本性即ち本来の面目が顕るるぞといえるなり、即ち本来の面目が顕る時は、善の思うべきなく、悪の思うべきなし、是もなく非もなく超善悪なるなり、

慧明六祖の説法を聴きて、言下に豁然として大悟せり、しかして再び問えるには、今まで承った外にはなお五祖より相承せられたる有りがたき秘密のことありやと、六祖曰く、今述べたることは何も秘密という訳はなし、汝もし返照して内に省みば密は汝にあらん、元来他人より伝附せられるべきものに非ざるを知るべしとなり、返照とは、肝要の語にして、又却来とも、退歩ともいうと同意味なり、即ち「あともどり」することにて、真宗に所謂還相もこの事なり、承陽大師は重に退歩の語を用い「退歩の学を学すべし」ともいえり、百尺竿頭一歩を進むというも亦此却来の意也、

慧明教誨を蒙りて喜び禁ずる能わず、吾れ五祖黄梅の会下にありて年来研尋すれども、未だ安心を得ず、唯道を他に求めて毫も自己本来の面目という処に気づかざりしが、今は指示を蒙りて自性を了ずるを得、恰も実地に水を飲みて冷暖自知するが如し、(冷暖自知とは実地に知るをいうなり、熱きことを知らね者に如何ほど熱さの講釈をするも分かるものにあらず、之を覚らしめんに焼け火箸を当てて見よ、其の熱き実地を知らしむるを得べし)吾は行者を師と仰がんといえば、六祖いわく、汝若し爾が思わば、吾と汝と共に五祖を師とせん、善く護持せよと、護持とは吾等仏者が互いに遵守すべきことなり、古人も「相続や大難」といわれ、最も大切にして難事なるは此の正法護持にあり、勉旃勉旃、
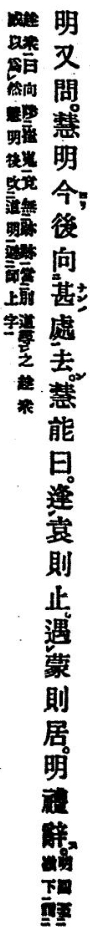
五祖の口吻に倣いて袁に遇わば止まれ、蒙に遇わば居れという、後人の捏造なること論を待たず、
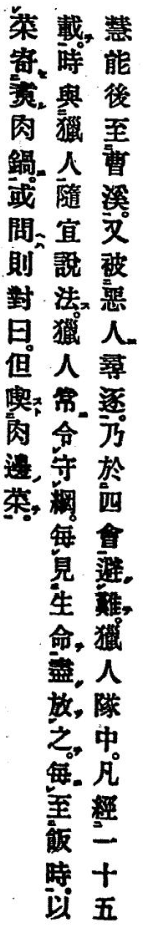
六祖曹渓に至り、又悪人に逐われ、難を四会に避けて、猟師の仲間に入りて網番すること十五年間なりという、天桂師のいう如く、時興猟人以下四十一字は信用すべからず、猟人等に説法せば人の怪しむことなかるべし、又生命を見てことごとく(原文は「盡く」)之を放つ者をして網番を為さしむるの猟人もなからん、後の昧者が濫造説、虎を書かんとして却って狗を成すが如く、功を弄して拙となすもの、抹殺し去るべし、
