
大内青巒著「六祖法宝壇経講義」を読む(第一 行由-01 生い立ち、金剛経を聞いて悟る、五祖に会いに行く)
行由 第一
[大意]
「六祖法宝壇経」の書名の解説、いつどこで説かれたかなどの解説。
「菩提の自性本来清浄。但用此心直了成仏」が仏法の大目的であり、壇経の主旨でもあること。
経歴が説かれる。
金剛般若経の「応無所住而生其心」を聞いて悟り、五祖弘忍大師に会いに行く経緯が説かれる。
[壇経講義本文]
この書は六祖大鑑慧能禅師の説法を門弟の集録したものである、法宝とは五祖弘忍の六祖に法宝及び所伝の袈裟を付すということに根拠するともいい、あるいは三宝中の法宝であるともいい、甚だしいのは宝林に壇を建て説法するによって名づけるというなど、種々の説あり、かくのごとき詮索は今の要にあらず、壇というのは六祖を韶陽の大梵寺に請し、土を封じて壇を造り、もってその説法の場所となしたのによる、経とはこの書仏説の体裁にならって集録したるが故に門人の尊崇して経と名づけたるなり、もともと、経と称するのは仏の説法のみに限るが如きも(仏以外の説法には「~論」と名付けられる)、すでに馬鳴の所造を経と題した例があり(馬鳴造「大荘厳論経」だろうか)、あながち出すぎた振る舞いともいうわけではないか、この書の中には後人の誤って紛れ込み付加された所が少なからずあり、それは文中にて述べよう。
この経に十段あり(或いは十一段に分かつもあるが非なり)、行由とは行状由来の義にして、文中「且聴慧聴行由得法事意」とあるより取るのである。
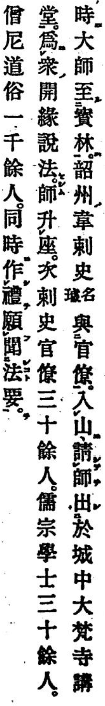
物々しく経文の体裁に模擬し、まず初めに六成就をつらねたり、六祖慧能は入滅された後、唐の憲宗、大鑑禅師と諡し、宋の太宗、大鑑真空禅師と加諡し、宋の仁宗、大鑒真空普覚禅師と加諡し、更に宋の神宗、大鑑真空普覚円明禅師と加諡せられたり、すなわち禅師号は四朝の諡号あるけれども、いまだ大師の諡号なし、さればここに大師とあるのは諡号ではなくて、門弟等の尊崇した敬称と知るべきだ、宝林とは宝林寺である、韶州の曹侯村に曹叔良なるものあり、双峰山の渓谷に伽藍を建立して宝林寺と号す、曹渓南華寺というものこれなり、六祖、黄梅の東山を去って錫を宝林に留むるや、韶州の刺史(太守)韋璩、山に入りて請うところあり、六祖嘉納して韶州府の大梵寺の講堂において説法す、時に唐の儀鳳二年二月八日なり、
[要約]
六祖慧能を大師というのは、正式な諡号(おくりな)ではなく敬称と知るべきだと。四朝の諡号はすべて禅師号で大師号はない。
六成就とは、「主成就」(だれが)、「処成就」(どこで)、「衆成就」(だれに)、「時成就」(いつ)、などのこと。経文の体裁に模していると。
[壇経講義本文]
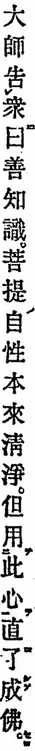
善知識とは師にも友にも用いる語なり、六祖大師まず一座の大衆を呼びて禅知識という、すなわち友達扱いをせらるるなり、菩提とは支那(中国語)に訳して覚といい、また道という、道というは義訳なり、道の語はもと喩よりきたる、支那人の最も尊ぶ語なり、西洋人は道を訳してprincipleという、菩提をもって仏法の主義原則というもまた得たり、天桂の注釈に「道之極める者を称し菩提と曰く、及びこれ自心の異号、故に経にいう、菩提を知ろうと欲せばまさに自心を了ず(あきらかにする)べし、もし自心を了ぜば菩提を了ず」(本文は漢文だが、書き下し文にした)云々とあり、菩提とは道の至極せるものなり、道の至極せるものとは他にあらずして自心なり、自心とは我々相互の自分の心の本性なり、されば菩提を知らんと欲せば自心を了ずべし、自心を了ずとは実のごとく自心を知るなり、実のごとくとは心の実性は本来清浄、もとより法爾自然に清らかにして、垢つき汚れたるものにあらずと、冒頭にこの二語を出してまず仏法の大目的を示す、この意十段の終わりまで徹底するなり、しからばいかにして了ずべきや、曰く但用此心直了成仏(ただこの心を用い直に了じて成仏せよ)、我々はすでに自心を失っているが故に、菩提と煩悩とを別にし、善と悪とを隔つ、この顛倒妄想の心をよび戻して、その実性にもどしむれば、直了成仏なりと、前二句は目的を挙げ、後の二句は方法を示したるなり、
[要約]
菩提自性本来清浄。但用此心直了成仏。が解説されている。
菩提を求めるなら自心を知るべきだと。
[壇経講義本文]

六祖大師大衆に対してその経歴を説けるなり、大師俗姓は盧氏、その先は范陽の人なり、父は行瑫という、罪あり、かつて新州の嶺南(五大嶺の南)に流され、ついに居をここに占めて百姓となる、六祖不幸にして三歳(貞観十五年)の時に父を喪い、老母と孤遺とともに貧窮困乏を極め、艱難辛苦をなめ、市に柴(小さな雑木や枝)を売りてようやく糊口せり(食いつないでいた)という、
[要約]
六祖の父は左遷され百姓をやっていたが、六祖が三歳の時に父は亡くなったと。このような生い立ちもあって六祖は文盲だったと言われる。
[壇経講義本文]

ある時一人の客あり、六祖から薪を買い、命じてその客店に送らしむ、六祖薪を送り届け、その代金を得て門外に出ずるに、また一人の客ありて経文を読誦しているのを見る、六祖その経語を聞き、忽然として心に開悟せりという、いう所の経語とは金剛経の応無所住而生其心の文なり、五灯会元に曰く「一日薪負い市中に至る、客が金剛経を読むを聞き、応無所住而生其心というに至り感悟する所あり」(本文は漢文だが、書き下し文にした)と、応無所住而生其心とは、およそ我々は目に物を見、耳に声を聞くなど、縁にしたがい境に対すれば、必ずその心の生ずるものなり、しかるに我々は常に我を認めおるが故に、境に対して愛憎好悪の念を生じ、これに住着するなり、この住着の情執を離れて、心の発動を縁に任すが、応無所住而生其心なり、例えば明鏡の物を映ずるがごとし、万象これに対すれば影生じ、去れば影滅す、胡漢来るも拒まず、美人去るも追わず、生滅去来一に縁にしたがう、かくのごとく我々の心の縁に触れ境にしたがいて動くは動くままにて可なり、ただこれに住着するなからんことを要す、勝海舟翁、かつて西郷南洲を評して曰く「世の中に命を惜しまず、銭を欲しがらぬ奴ほど始末のつかぬ者はない、南洲は命を惜しまず、銭も欲しがらぬ男だった」と、命を惜しまず、銭を欲しがらぬは、住着する所なければなり、孔子曰く「心の欲する所に従うも矩を踰えず」と、心の欲するままにして、しかも法に違わざるは、住着する所なきが故なり、孔子の言、海舟の談、ともに自ずから応無所住而生其心の旨にかなうというべし、
[要約]
薪を売った帰りに、金剛経を聞き、「応無所住而生其心」の一節を聞いた時に心に開悟することがあったという。
応無所住而生其心の解説がされている。
[壇経講義本文]

六祖、応無所住而生其心の経語を聴き、にわかに感悟する所あり、復故の買柴翁にあらず、すなわち客に問うて曰く「誦する所は何の経なりや」客曰く「薪州の黄梅県なる東禅寺より来る」と、しかして客かの寺の事情を告げて曰く「かの処には五祖弘忍大師という大徳ありて化導したまい、その門に入るもの一千余人あり、大師常に道俗を勧めて金剛経を誦持せしめたまう、かの処にある者、皆自ら自己の心の本性を徹見して、直下に即心成仏す」と

六祖、客の黄梅の状況を談ずるを聞き、心大いに動きたるがごとし、過去世よりの因縁にやありけん、客、六祖の意を察し、十両の銀を取り出し、六祖に与えて、老母が衣食の費に充てしめ、黄梅に行きて、五祖の門に投ずべきことを勧めたり、六祖いかでかためらうべき、にわかに母に請うて、法のため師を尋ねるの意を告げ、辞し去りて、黄梅に到り、五祖を礼拝せり、時に感享二年なりきという、
