
冷たさと美しさ。冬の記憶。
玄関の扉を開ければ、いつも遠くに見える山並み。
深い緑の中に、まだらに紅い色が差し、そのうえに霧が広がりはじめていました。
凛とした朝の空気を頬に感じながらその光景をながめ、天然のクリスマスツリーのようだ、と思います。
そう思ったあと、幼い頃の記憶が心に浮かんできました。
わたしが通っていた幼稚園は、カトリック教会が運営する園でした。
洗礼を受けておらず、信仰も持ってはいないのですが、あの場所で過ごした二年間のことは、鮮明に記憶に残っています。
なにしろ、毎日唱えていたお祈りのことばを今でもそらんじているくらい。
頭も心も柔らかく、素直だった頃に身に染ませたものは、長く自分の中にとどまり続けるのでしょうか。
"罪ぶかいわたしたちのために、今も死を迎えるときも、
祈ってください"という聖母マリアに向けて願う一節は、何か心を捉えられるものがあり、原罪などということばの意味は理解できずとも、存在することの哀しみのようなものを、幼いながらに感じていたように思われます。
教室や聖堂、ステージと呼ばれていた講堂、階段の踊り場、そして園庭。
広い園内のどの場所にも、幼な子を抱いたマリア像が佇んでいて、その顔には笑みが浮かべられていました。
"見守られている"という感覚と、"常に視られている"という感覚。人智を超える存在を前提とした空間で過ごした時の記憶は、自身の中に深く根を下ろしています。
一年の中で、神さまと呼ばれる存在を最も強く感じるのは、クリスマスの日。
わたしの前に"クリスマス"という日は、賑やかなイベントを開く日ではなく、大きな存在の誕生を祝う日として目の前に現れました。
聖堂の椅子は常に硬く冷たかったのですが、クリスマスの日はふだんよりもその冷ややかさを鋭く感じました。
ミサの間に語られた内容は細かくは覚えていないのですが、高い天井と磔刑像、円いステンドグラスの窓を見上げていたことが印象に残っています。
ミサを終えたあとは、ステージに移動します。
ろうそく型の灯りを手に持ちながら歌った讃美歌。
そして演じた、聖書のものがたり。
今思えば、劇の中でサロメとヨカナーンのくだりなども園児が演じていて、あの年頃で内容が理解できていたのかどうかおぼつかないのですが、大人になってから福田恆存が訳した「サロメ」を読み、ビアズリーの挿絵をじっくりと見て、あの頃に見たものやふれたものが自分の美意識に強く影響を与えていることに気がついたのです。
何を美しいと感じるのか。
どのような美しさに心を惹かれるのか。
人を大きく包み込みながら、同時に人の理解を峻拒するような、透徹した聖夜の美しさ。
運命というものの残酷さ、生きることの不条理と、それゆえに生じる虚無感。
繰り返し読んだ、芥川龍之介の作品、「奉教人の死」「黒衣聖母」「西方の人」。
折にふれて聴き返す、L'Arc〜en〜Cielの"殉教"を描いた『いばらの涙』や、"争い"を描く『forbidden lover』。
世界史の資料集で、目にした瞬間魅了され、大原美術館まで会いに行ったエル・グレコの『受胎告知』。
深く静かに、けれども心と体ごと揺らぐような感覚を味わった物語と音楽と絵画の数々は、ふりかえってみれば幼い日を過ごした二年の間に培った感性が、惹きつけられてやまないものだったのです。
寒い季節には、グレーの修道服にカーディガンを羽織っていたシスター。
担任の先生でもあったシスターは、いつも背筋をまっすぐに伸ばして歩くひとでした。
振り返ってみれば、当時の彼女は今のわたしよりも若かったのだと思います。明るい声の響きは、その声を聞く人の心に温もりと穏やかさを感じさせるものだったな。そんなことまでふと思い出しました。
夜になり、家路を急ぎながら降り仰げば、皓々とあたりを照らす満月が浮かんでいます。
荘厳、ということばが脳裏をかすめ、そのことばが何よりも似つかわしいこの季節の冷たさと美しさを、わたしは心から好きなのだと感じたのでした。
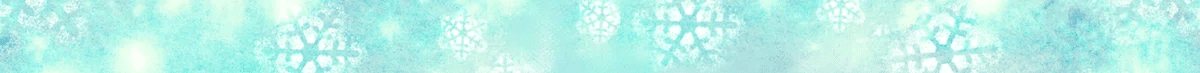
はじめて聴いて、そしてMVを観たときの衝撃を
いまだに忘れられません。
壮大で美しく、その世界観にひきこまれてしまいます。
いいなと思ったら応援しよう!

