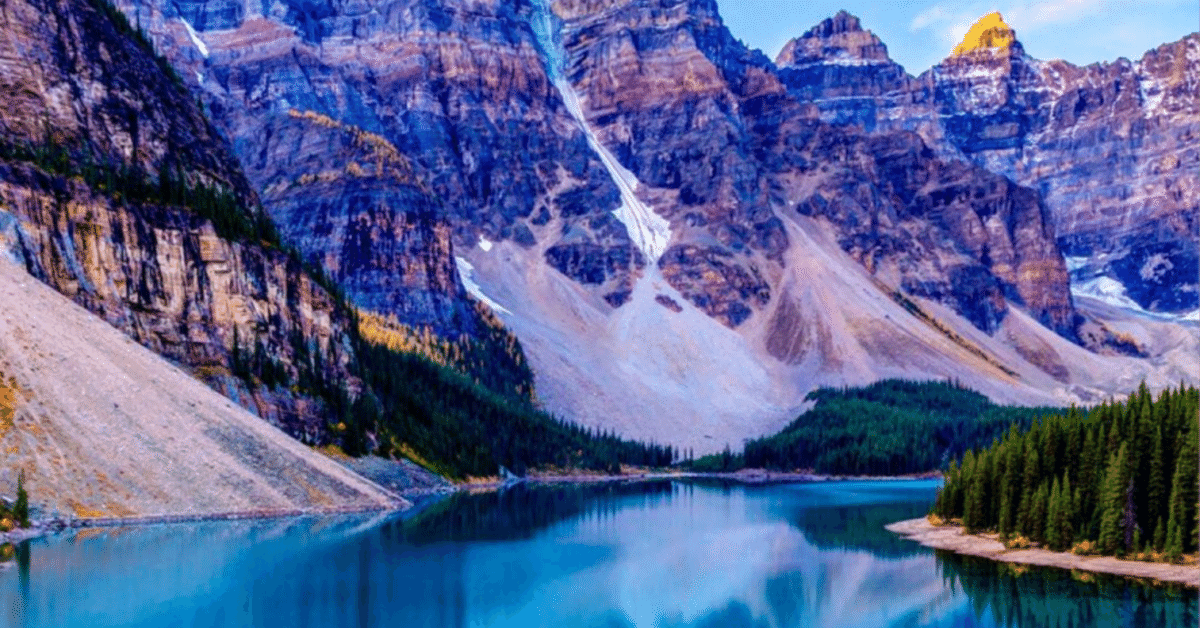
『どの様な「食材・食品」…』 これまでの「体質・体調別」を考察してみよう。 【めまい(眩暈)】[氣2節]〜食薬(漢方理論)編②
【氣2節】〜『めまい(眩暈)でお悩みの方々へ』「めまい(眩暈)の改善に、効果的アプローチがある東洋医学的理論&成分(食材・食品・生産物)」について【⑨】「前ファイル」〜 ◉『食薬(漢方理論的、解釈による食材分類)』について、… の解説
・ここで云う『食薬』は、「広義の意味」なので、…『食材・食薬・生薬・ハーブ 等』全てを含む事となります。
(※何故なら、…「その食材を摂取する事」で、…「必然的に、めまい(眩暈)に効果がある」と認めているからです。)
●『食薬』の解説、…
[1]【食材/野菜・果物類】〜[効果]
■『キュウリ🥒』、
・「ウリ科の食材代表のきゅうり」は、水分が豊富で、「体内の熱と余分な水分を解消するのに最適な食材」です。
(※「キュウリ🥒」に含有される「シトルリン」は、「血流を改善する」事によって、「体内に蓄積された余分な水分」が体外へ排出され易くなる為、場合により「むくみ」の解消に効果的である。)
■『大根⚪』、
・「大根⚪」には、「消化を促進して気の巡りを良くする」作用があり、「胃もたれ/嘔吐、お腹の張り/便秘 等」消化器症状に効果があります。
(※大根の薬膳的効能として、「➀気の巡りをよくして消化を促す」、「②熱による痰を取り除く」、「③停滞した気や上逆した気を下ろす」、「④胃腸の活動を穏やかにする」等。)
■『羅漢果🟢』、
・「朝起きれない/頭痛/めまい/胃腸の調子が悪い 等」で学校に行けない子どもが増えています。「起立性調節障害」と診断され、血圧を上げる薬等を処方されるものの、中々改善出来ないものに「羅漢果」が良いとされる。
■『山芋⚪』、
・「目眩の症状の改善が期待できる」と思われる「野菜類」は、「ネバネバ成分のムチン」が含まれる野菜「オクラ/山芋/レンコン/里芋/キノコ類 等」に含まれます。
(※「“水”は体を潤す液体(汗や尿、リンパ液など)を表す」。「尿の出が悪かったり、耳鳴り、めまいが起き易い人は、利尿作用が高い食べものを取ると良い」〜「山芋・オクラ・里芋・蓮根」等。)
■『蓮根🟤』、
・「目眩の症状の改善が期待できる」と思われる「野菜類」は、「ネバネバ成分のムチン」が含まれる野菜「オクラ/山芋/レンコン/里芋/キノコ類 等」に含まれます。
■『里芋🥔』、
・胃腸の働きを整える「和胃(わい)」「調中(ちょうちゅう)」の作用があるとされています。また、「カリウムのように余分なナトリウムや水分の排出を促して、むくみを改善する」効能がある。
(※「里芋」に含まれる「カリウム」を摂取する事で、体の余分な水分を尿と一緒に排出し、「むくみ」対策に役立ちます。)
■『オクラ🟢』、
・「目眩の症状の改善が期待できる」と思われる「野菜類」は、「ネバネバ成分のムチン」が含まれる野菜「オクラ/山芋/レンコン/里芋/キノコ類 等」に含まれます。
■『柿🟠』、
・「柿」に含まれる渋みの基である「シブオール」と酵素である「アルコールデヒドロゲナーゼ」は、共に「アルコールを分解する働き」があります。
更に柿には「利尿作用を持つカリウムが多く含まれる」為、「二日酔いの予防」にも良い。
■『梨🍐』、
・梨には、「消化が促進され易く、胃腸の働きも改善され易くなる」「ペントザン」と云う成分が含まれております。
(※「梨」に含まれる「カリウム」を摂取する事で、体の余分な水分を尿と一緒に排出し、「むくみ」対策に役立ちます。)
■『シトラス🍋』、
・「胃腸の働きを正常に保ち」、働きとしては、「抗鬱/鎮痙/健胃/整腸/鎮静作用」があり、「消化障害/食欲不振/鼓腸/軽い吐き気等」に用いられます。
・上記(全て)[ファイル➀の分類]〜[水]
【「めまい」漢方解釈】〜④ 「(※)痰湿(たんしつ)体質」、…
[「津液」の代謝が「実(停滞・悪く)」になる体質]タイプ
※[上記の効能により、「めまい改善効果」があると考察できる。]
[2]【食薬類】〜[効能]
■『アロエ🌿』、
・「アルコール」を分解する時、有害物質「アセトアルデヒド」が発生する。
これを抑える成分として、「アロエチン」がある。(※「肝臓の機能を回復させる」のも、「二日酔いの解消」に繋がります。)
■『ヨモギ🌿』、
・「全身の臓器が低酸素状態に陥る」事で、「めまい/頭痛/耳鳴り」が起こります。
・良質の「葉緑素や鉄分」を豊富に含む「ヨモギ」は、これらの「症状の改善」に有効と云えます。
■『スギナ🌿』、
・「むくみ」は体内に余分な水分が溜まってしまう事で起きますが、「スギナの葉緑素には、この水分を排出させる効用がある」為、「むくみの解消」に効果を発揮します。
■『明日葉🌿』、
・「明日葉」に含まれる「クマリン/ルテオリン」には利尿作用があるとしてよく知られています。この働きにより、「むくみが改善」されます。
■『グァバ葉🌿』、
・アマゾンのティクナ族は、「グアバ(シジューム)の葉/樹皮」を煮出し、下痢の治療に用いています。
・「樹皮/葉」の温浸出茶や煮出し茶は、「下痢/喉の痛み/吐き気/胃痛/眩暈/生理不順 等」の用途で多くのアマゾン先住民族により利用されています。
■『フコイダン』、
・「フコイダン」には、肝細胞の再生を促す働きがあり、特に「コンブやメカブのフコイダン」は、「肝機能のサポート作用が高い」事が分かっている。
(※「肝機能up」は「眩暈予防」となる)
■『大茴香🌿(フェンネル)』、
・「フェンネル」には「消化を促す作用」があります。消化酵素の分泌を刺激して、消化を促す効果がある為、「胃もたれの予防効果」が期待できます。
・「冷えによる胃の痛みや消化不良、おなかの張り 等」の症状に効果があります。
■『ハトムギ(薏苡仁)』、
・「ハトムギ」の殻を除いて乾燥したものは、「ヨクイニン」と呼ばれ、生薬として用います。「ヨクイニン」は体の余分な水分を排出する働きがある為、「むくみ/下痢」に用いられる事が多い。
(※「水を巡らせ、浮腫や尿量減少/胃腸虚弱による軟便/下痢/倦怠感」等を解消する。)
・上記(全て)[ファイル➀の分類]〜[水]
【「めまい」漢方解釈】〜④ 「(※)痰湿(たんしつ)体質」、…
[「津液」の代謝が「実(停滞・悪く)」になる体質]タイプ
※[上記の効能により、「めまい改善効果」があると考察できる。]
[3]【生薬系(民間生薬)🌿類】〜[効能]
■『合歓木(🌳)』、
・「合歓花(ゴウカンカ)」には、[「心神不寧(心気が不足して、精神が不安定になる事)」、「肝気鬱結(肝気が滞り、気鬱になる事)」〜何方も「めまい(眩暈)」の病理に近い「身体症である状」]上記の症状を改善する効能がある。
■『百合根⚪』、
・「カリウム」には、「体内の余分な水分を排出し、血圧を下げる働き」があり、「百合根」は含有率がトップクラスである。
「塩分や水分の摂りすぎでむくみが気になる人」には、意識して多く摂取すると良い。
(※「百合根」には、「鉄」の含有率も高く、「鉄」は、不足すると貧血を起こして、「めまいや立ちくらみ」等疲れ易くなります。)
■『唐黍(髭)』、
・「雨が降ったり」、「気圧が下がったり」すると、「体から水分が出て行き難く」なり、「東洋医学的には水毒と呼ばれる状態」になります。(体の余分な水分と考える。)
・「水毒の時に出易い症状」は、代表的なもの「めまいと頭痛」があります。
■『棗(ナツメ)』、
・「干し棗」は、「気血を増やす作用(漢方解釈)」があります。
・「気血不足」の方は、「顔が蒼白」で、「疲れ易く」、「冷え易く」、「めまいし易い」です。
■『ネズミモチ』、
・主に「滋養強壮」、「精神安定」、「めまい(眩暈)の予防」の効能がある。
■『山茱萸🔴』、
・「山茱萸を漬け込んだ薬養酒」には、効能として、「滋養強壮/腰痛/めまい/耳鳴り」等がある。
・上記(全て)[ファイル➀の分類]〜[血]
【「めまい」漢方解釈】〜「(※) 気血両虚(きけつりょうきょ)体質」、…
(※)漢方的に解釈すると、…
[「内因・不内外因」の影響により、「気/血」が共に「虚(不足)」する事で、「身体・全体で(エネルギー・血津液)」が不足する体質]
[4]【茶葉(乾燥葉)🌿類】〜[効能]
■『イチョウ葉🌿』、
・「血行が悪い為に起きてしまう様々な症状」に「イチョウ葉」は効果を発揮します。
「高血圧症/耳鳴り/めまい/更年期障害/頻尿/冷え性/アレルギーの改善」に効果がある。
■『杜仲葉🌿』、
・「杜仲葉」に含まれる「ゲニポシド酸」は、杜仲の樹木の葉にある“杜仲葉配糖体”と呼ばれる成分の中に含まれる成分で、「血圧そのものを下げる効果」が期待されます。
・また「高血圧によるめまい」や腰痛 等の症状にも効果が期待できると云われています。
■『ドクダミ🌿』、
・「ドクダミ(十薬)」は、「尿の出が悪く、浮腫み易い方」に、その効能を発揮します。
・また、昔から「十種類の薬効を有している」から、そう呼ばれています。
「利尿/便通/浮腫み/めまい/高血圧」 等の予防に効果がある。
■『エビス(決明子)草』、
・「決明子」を乾燥させた「ハブ茶」には、「プチ鬱/目の張り/めまい」等を改善する効果がある。
■『柿の葉🌿』、
・「柿の葉」には、「ヒステリー気味のとき、なかなか寝付けない時や、頭痛、めまい」等に効果があります。
■『ナズナ(薺)』、
・「鉄分」が多く含まれている「ナズナ」には、「増血作用やめまいの予防 等」が期待出来ます。 」
以上で、『めまい(眩暈)にアプローチする、…』【氣2節】を終わります。
次回、…『頭痛(頭重)にアプローチする、…』【氣3節】に、移ります。
