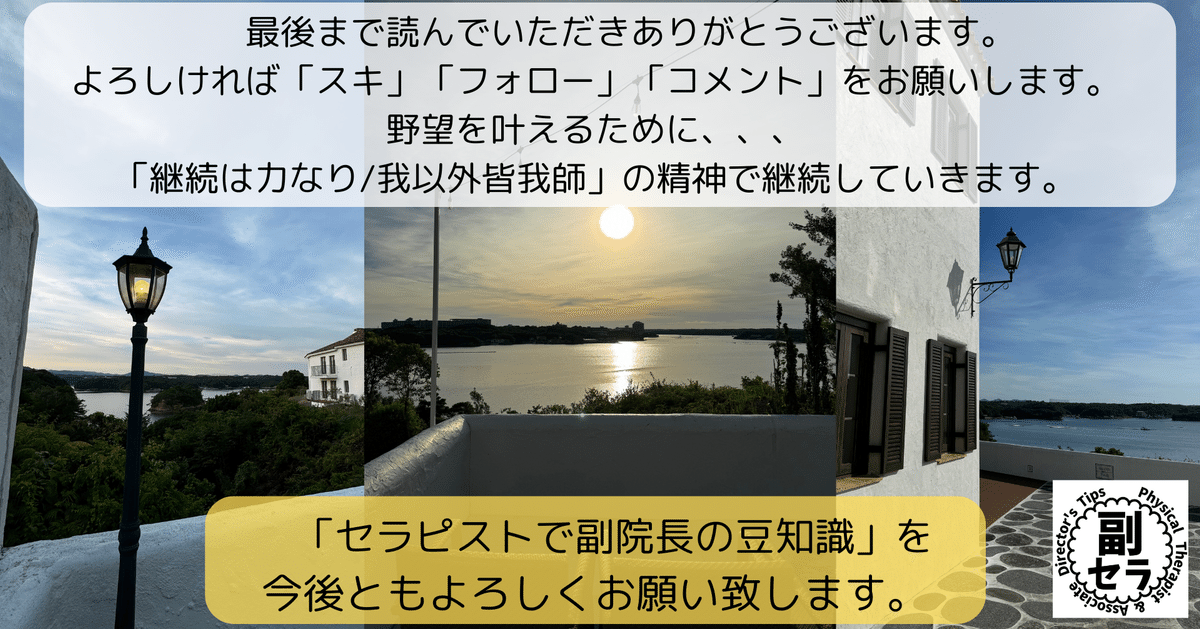痛風は他人事ですか?身近に潜むリスクを知って回避しよう!
痛風の言葉は多く認知されていると思います。ビールが関係しているやプリン体が関係しているなど一般的にも知られていることもあります。
今回はそんな痛風について簡潔にまとめました。疾患を知ることで予防に繋げていきましょう!
1.定義
痛風(gout)とは、体内に過剰に産生された尿酸が関節に蓄積して結晶化し、炎症を引き起こして腫れや痛みを生じる病気です。(日本リウマチ学会より)
2.名前の由来
日本語:「風が吹いても痛い」「風が吹くようにやってくる」という説があります。
英語(gout):ラテン語の「gutta」(液体の「滴」)に由来しています。中世の医学では、尿酸が血液から関節に「滴り落ちる」と考えられていたため、この名前がつけられました。
The English term "gout" first occurs in the work of Randolphus of Bocking, around 1200 AD. It derives from the Latin word gutta, meaning "a drop" (of liquid).[111] According to the Oxford English Dictionary, this originates from humorism and "the notion of the 'dropping' of a morbid material from the blood in and around the joints".(Wikipediaより引用)
3.症状のポイント
・急激な関節の痛み(痛風発作):足の親指の付け根が赤く腫れて熱を持ち、強い痛みを伴います。
・発作は数日間続くことが多いですが、その後は痛みが収まることが一般的です。しかし繰り返し発症する可能性もあります。
・痛風結晶:症状が長引くと、関節に尿酸結晶が蓄積され、「痛風結節」と呼ばれるしこりが形成されることもあります。
4.原因
痛風のキーワードとして「尿酸」や「プリン体」という言葉をよく聞くかと思います。
尿酸は、食事に含まれるプリン体という成分が体内で分解されてできる物質です。腎臓での排泄がうまくいかなくなると発症する可能性を高めます。
・食生活:プリン体が豊富な食品(レバー、魚の干物、ビールなど)を過剰に摂取すること。
・肥満:体脂肪が多いと尿酸の排泄が難しくなり、血中尿酸値が上昇します。
・アルコール:特にビールや日本酒は尿酸値を上げることがあります。
・遺伝的要因:家族に痛風の人が多いと、遺伝的に発症しやすくなることがあります。
・薬の影響:利尿剤など、一部の薬が尿酸値を高めることがあります。
💡豆知識①〜気づかずに摂取している?プリン体を含む食品を知ろう〜💡
プリン体を多く含んでいる飲食品として、ビールや魚卵などのイメージがあるかと思います。
実はその他にも様々あります。その食品を単体や、許容範囲内で問題なく摂取していても、気づかずにプリン体を多く含む食べ物を重ねて多く摂取してしまっている可能性もありますので整理していきましょう。
・肉類:レバー、肉
・魚介類:魚(サンマ、サバ、イワシ、アジなど)、貝類(ホタテ、アサリ、カキなど)、甲殻類(エビ、カニなど)、魚卵(いくら、たらこ、数の子など)
・加工食品:ハムやソーセージ、缶詰
・アルコール:ビールや蒸留酒
・乾物:干ししいたけ、上記の肉類、魚介類の乾物
・発酵食品:味噌、醤油、納豆など
💡豆知識②〜日本人は痛風になりやすい?〜💡
日本における痛風患者の90%は男性です。また40歳代以上が多いとされています。以下が要因として考えられています。
・遺伝的要因:日本人の遺伝的な要因として、尿酸を排泄する能力がもともと低めということがあります。
・食肉摂取の増加などの食生活の欧米化:時代の変化による食肉の摂取の増加と肥満の増加が進んでいます。
・アルコール摂取文化:日本では多様なアルコール飲料があり、最近では減りましたが飲み会文化など摂取する機会は多くあります。
5.対処法
・生活改善:尿酸値を上げる原因に対して生活改善を行います。また水分補給を行い結晶化しにくくします。
・薬の使用:尿酸値を下げる薬や痛み止めで症状の緩和を狙います。
6.時代で変化していること
・新しい治療薬の開発
・治療中の尿酸値の目標値の変更:尿酸値を6.0mg→5.0 mg/dL未満に変更
・個別化治療の重要性:原因ごとのアプローチを行う
・腸内フローラ(腸内細菌群)と痛風の関連性
・生活習慣の重要性の再認識
・痛風の早期診断の重要性
7.最後に
今回は痛風について簡単にですがまとめてみました。まわりに痛風を発症している人、まだ発症はしていないが尿酸値が高い人は、多くはないと思いますが意外といるものです。生活習慣で予防できることも多いので注意していきましょう。
※プリン体が含まれているものを接種したら必ず発症するわけではなく、摂取が少なくても尿酸値が高い方もみえます。状態が気になる方は医療機関で相談してくださいね。