
最終回season7-5幕 黒影紳士〜「色彩の氷塊」〜第一章 流雪蔦
第一章 流雪蔦
流雪蔓
雪柳が咲く
桜を前に
白き雪の名残を讃えた

――――――――
染井吉野が咲く頃、小さな白い雪の花がぽつりぽつりと咲き始めた。
温かな風に吹かれ、其れは軈てふんわりと嫋やかに揺れるのであります。
真っ黒な猫が一匹…その白い雪柳の簾を掻き分け現る。
「あっ……「先生」じゃないか。……ほら…花弁だらけじゃないか。さては遊んでいたな?」
微笑む青年が一人、其の「先生」と呼ばれる猫を抱き上げた。
手には…今時、大きな風呂敷を持っていた。
父親の名前は「黒影」……探偵である。
父に隠していたものがある。
探偵職の父に何時バレるかとはらはらしたものだが、母の「白雪」の協力もあり、何とか隠し通している。
夢を叶えた日…此の事を父に話そうか、未だ迷っていた。
余計な事をと烈火の如く叱られるのではないか。
其れとも……喜んでくれるのだろうか。
喜んでも……本当は家業の探偵社を継いで欲しいかも知れない……とか、色んな想像をした。
愛するシャンソン歌手のブルーローズがメジャーデビューを果たした。
近頃は顔を合わせる度に、
「鸞は如何するんだ?」
と、ブルーローズを幸せに出来るのかと、聞きたい様でもあり、しっかりしなさいと言いたい様でもあった。
「……ねぇ、黒影……」
父さんの部屋をノックし、声を軽く掛けた。
母さんに聞いたら、自室にいるって教えてくれた。
夢を見ているかも知れない。仕事をしているのかも知れない。父さんは何時だって気にしなくて構わないと微笑むが、本当は何時も働き過ぎなのだと知っている。
母さんが僕に話す事と言えば、父さんの過労やら傷を作って帰って来てばかりいると言う心配事だ。
「鸞からも何とか言って。鸞からなら、黒影も少しは考えて暫くは効果あるのよ。し、ば、ら、く……だけど」
と、母さんは良く僕に言うのだ。
其の「し、ば、ら、く……」の為に、毎回こんなに緊張したくなんか無いよ。
其れでも……ふと思った。
緊張……しなくて済んだかも知れない。暫くしか効果が無くても、何回も言って……もう少し話していたなら。
母さんはやっぱりコミュニケーションが得意だ。
父さんだって……確かに人たらしな面は無くも無い。
其れでも……僕にはやっぱり、その背中は大きく……違う……。
そう、鳳凰の翼があるどデカ級な訳で……越えるどころか、避けて通りたいと思う訳だ。
「……帽子を持って来てくれないか?」
と、部屋の中から声がした。
……父さん……母さんと間違えてるし……。
また何かに熱中し、帽子がいると言う事は出掛ける準備だと分かる。
……今は話しても無理か……。
僕はゆっくり話がしたかったので、諦めて一階に父さんの大事な帽子を取りに行こうと、扉に背を向けた。
「……あっ、すまない。鸞だったんだな。如何した?」
父さん気付いて慌てて部屋を出て来た。
「黒影、出掛けるんでしょう?今度で良いよ」
と、僕が言うと、
「今は仕事じゃない。……父さんで構わない。……その……鸞が来るなんて珍しいじゃないか。大事な話でもあったんだろう?」
黒影は何だか気まずそうに言うのだ。
……そうか……母さんの言う「心配症」の所為だ。と、僕は思った。
僕が変に昔から母さんには大丈夫なのに、父さんにだけ緊張するのは、父さんが先に心配しておどおどするからだと気付く。
「話があったんだけど……お仕事でしょう?今度で良いよ」
僕は諦めてそう言った。
「何を言っているんだ、鸞。気にするなと言ったじゃないか。……其れに……其の……」
「……父さん……キャピキャピ眼鏡。慌てて付けっぱなしですよ」
割り切れない言い方をするので、僕はきっぱりと「慌て過ぎです」と言いたい気持ちで、作業用にだけ掛ける眼鏡を外し忘れていると指摘する。
「あ?……あっ、本当だ。……先方は特に時間は気にしないんだよ。だから気にしなくて良い。……だから……何て言うか……まぁ、入って安楽椅子に掛けてゆっくりすると良い」
其のあまりの普段とは違うキョドり具合に、流石の僕も気付いてしまった。
「……父さん……知っていましたね?」
と。
「へっ?何の事だろう……」
父さんは声を裏返して言うと、天井を見て考え事をするフリをして、部屋へ先に戻って行く。
僕はズカズカと部屋に入って、勢い良く偉そうに安楽椅子に腰掛け言った。
「父さん!……嘘、下手だから言わないんじゃ無いんでしたっけ?……何時から調べているんです?息子を調査対象にするなんて、重罪ですからね!」
と、ガツンと此処は言わなければ、心配症が過ぎてプライベートまで無くなってしまう。
「……悪気は無かったんだよ。……最近の裁判記録を調べていたら、其の……判事の最新情報も出て来たんだ。……そうだな、鸞の方から聞きたかった。僕も見付けて残念と言うか……嬉しいと言うか……だ」
と、父さんは言い辛そうではあったが、経緯を説明した。
「……嬉しい?……黙っていたの、怒らないの?」
僕は小言の一言でもあると思っていたのに、不意を突かれた様に肩の力を抜いた。
そうだよな……。本当に反対なら、知った時に止めるか叱ったに違いない。
「……何故だ?……僕はてっきり鸞が他に無いから探偵社を継ぐ気なのかと思っていたのだよ。本当は鸞に何も無い真っ新な道から行く道を歩んで欲しかった。まさか……ふっ」
父さんは最後に笑う。
「判事になるのが、そんなに似合わないですか?」
僕が口を尖らせ不服そうに言うと、
「……今はね。新品のスーツや制服と同じだ。其れが馴染む頃には愚痴の一つや二つ、出る程余裕になるものだよ」
と、父は言って微笑む。
何時も忙しくて、強くて……阿修羅の力を持ってからも、其の闘う姿は遠過ぎて……少し……怖いとさえ思っていた。
そんな気持ちが、自然と普段の父まで怖いと思わせていた事に気付く。
記憶にある父は……忙しさの合間をぬって話した時、何時だって微笑んで聞いていた。
死にたくなった日も、そっと寄り添って見ていた。
「……鸞?」
僕が黙っていたので、父は如何したのかと気にする。
……そうだよね……出来る限りの精一杯の愛情をくれていたのに……気付かないフリをしていたのは、僕の若さだった。
もっと普通にキャッチボールとかしてみたかった。
他の仲間は親切に僕と遊んでくれた。孤独すら感じた事は無い。でも、一番甘えたかった人だったのだと思う。
「……ううん、父さんは何でも知っているなって。だから、本当は……色々もっと沢山の事、聞きたくて仕方なかったんだなって……」
と、気付いたら何も考えずに口にしていた。
父は其れを聞くと、何故か指笛を吹いた。
窓の外が輝き、鳳凰の鳳(ほう)が飛来する。
鳳は父を見るなり、肩に乗り懐いて何時もの頬擦りをしている。
「鸞……鳳、触ってみるか?ふかふかなんだよ」
父は唐突にそう言って、大きな鳳を僕の膝に乗せた。
「……背中、撫でるとうとうとする」
と、父は扱い方を追加で言う。
「あ……うん」
びっくりしやしないかと、そっと背中を撫でた。
鳳の目が半分になり、心地良さそうである。
首を丸め、次第に眠りそうになって来た。
「……能力者専用の裁判を扱うのだろう?」
父が聞いて来た。
「……う、うん……そうだけど……」
鳳の所為でアニマルセラピー効果と言うか、さっき迄あった緊張感はとっくに薄れていた。
「……佐田 明仁(さだ あきひと)……そうだな?」
黒影は其の名を口にした。以前、黒影が逮捕した能力者で、サダノブの父親だ。
「そうだと言ったら、反対しますか?」
鳳でリラックスしていた空気も、一気に張り詰めた。
「……一つ聞きたい」
「はい」
「僕が捕まえたから、サダノブの父が可哀想だとか思うならば、正直裁判官には向いていない。能力者案件専門ならば、能力の使い方については平等で平和的で無くてはならないと僕は考える。同情等では無いのだね?」
……やっぱり黒影だ。事件の話をする時、穏やかな父は目付きが変わる。
僕の膝の上で、今……父と生命共同体とも言える鳳がいる。平等と平和を司る此の存在を前に、同情と言う不平等すら赦されはしないだろう。
鳳も気になるのか、一度眠りに入ろうとして曲げた首を戻し、僕をじっと見詰める。
「同情ではありません。佐田さんは、脱獄したとは言え、其れは世界を救う為だった。其れを鑑みた同情の余地ならある筈です。せめて脱獄で量増しした服役刑に関しては。……他に止められる能力者が居なかった。いれば、佐田さんは頭が良いから無駄な事はしない。居なかったから動かざるを得なかった。サダノブのお父さんだからとか、黒影が逮捕したからだとか、そう言う理由からじゃないです。……司法取引は日本では無いけれど、明らかに善意の脱獄でした。善意が量刑になるのが、僕はおかしいと思った。だから、改めてその事実に刑がいるのかと、考えていたんです。……其れこそ、不平等だと僕は感じた。僕の平等への考えは間違っていますか?」
父としてでは無い。黒影としての意見が欲しかった。
僕は此れに疑問を覚え、気付いたら分厚い六法辞書を開いていた。
「……平等はとてもシンプルだ。善悪が無い。今の、法も関係ない領域にある。ある疑問をもって確かめるのは、実に好奇心があって良い事だ。然し、もしも生半可な気持ちで佐田 明仁の件に触れるのならば、僕は鸞に説法の一つでも聞かせねばならないかと思っていた。……だけど……其の真っ直ぐな目を見て安心した。……証明は難しいぞ」
「……分かっています」
黒影の言葉に、僕は返した。
揺るぎない物を持って……。
「ほら、鳳……眠るなら、こっちだ。鸞が動けなくなる」
黒影は鳳をに言って、膝を軽く叩いて呼んだ。
「……其の内、佐田 明仁さんに面会に行く」
黒影がそんな事を行った。バサバサっと羽音を鳴らし、鳳は黒影の膝に移動し、首を丸め寝始める。
「何か用事ですか?」
僕も同席したいなと、少し気になった。
「……其れは、裁判官。法廷で出て来る「真実」のお楽しみだよ。……hav1024のDATAが欲しいんだ。彼は色々詳しいからね。其れとサダノブには未だ言っていない。真実が不確かであれば、不安にさせるだけだ。分かったら伝えるつもりだよ。……FBIと僕の所に佐田 明仁逃亡時のDATAが多少ある。証拠能力がどれ程になるか分からない。能力者案件専門裁判では少しは使えるだろうな。」
と、黒影は言う。能力者管理しているFBIと、能力者専門に扱う夢探偵社の証拠能力は強い。
「……協力……してくれるんですか?」
僕は単純に嬉しくてそう言った。
「……サダノブの為、佐田 明仁さんには正しい量刑で償って頂きたい。「真実」を曲げるのが、嫌いなだけだ」
と、黒影は言ったが、そう言って鳳を見詰める横顔は見知った父の微笑みだ。
「有難う!父さんっ!」
僕はそう言って部屋を飛び出す様に出た。
止まっている暇は無い、急いで過去の裁判記録を再確認しなくては!
……平等と平和は……まるで天秤の平衡に似ている……
均衡を保つ為に動く何かに……見えた。
――――――――――
黒田 勲(黒影の本名であるが、此処に現れたるは黒影から約20年程前に離れ存在する影で、通称「勲さん」と呼ばれている)は、羽瀬 寄子(はせ よりこ)と、ある場所で落ち合う約束をする。
焼かれた村に残った伝説の様な話を頼りに。
此の村周辺にだけにある黒水晶は特殊な物で、未来の黒影が云うには、
「其の周辺住民のみに耐性が出来ているんだ。だから僕も調べに行きたいのだが、行けなくてね。其の水晶を科学爆発を起こして大気に撒く事で、Hav1024とほぼ似た物質となり、大量に人や植物を殺せる武器に変わってしまう。出来るだけ、撤収したいんだ。移動領域のコピーした正義崩壊域の地下都市を壊滅に追いやったのも、その黒水晶が粉々に粒子に変わったからだと思われる。吸い込むと呼吸器や肺器官に巣喰う。一度吸ったら死滅は不可能。五元素全ての性質を持って切り替わる。能力者が爆発的に増えたのが、五元素のバランスが崩れた時……。世界のパワーバランスが壊れた要因に、五元素を持つ未知の物質。……何か、大きな崩れの前兆の様に思えてならない。何かしらの関係性もあるかも知れない。サンプルが欲しいんだ。原石の。」
と……詰まり、耐性があるらしい私(勲さんは一人称が言葉が古めかしく丁寧なので男ですが私です)に、解明や研究の為に黒水晶の原石を探して欲しいと言う依頼を受けたのです。
寄子さんは周囲数メートルを過去に変えてしまう体質になっているからと、自分から遠慮して余り周囲を変えないか如何か、先にゆっくり出て確かめるなんて言い出したのです。
私は、
「そんな事、気にする事はありませんよ」
と、言ったのですが、
「念の為です。……念の為」
そう言って俯き、そのまま我々が居候になり、お世話になっている寺を後にしたのです。
寄子さんは未だ薄霧の掛かった早朝に、早々と出掛けたのだ。
「住職……何だか、寄子さん……元気がありませんでしたね」
と、僕は何か引っ掛かり朝食を食べ乍ら聞いたのです。
「そんな気もするね。……如何しても周りの物を古くしてしまうから彼是触るなと、つい言ってしまいますから。……案外、顔には出さなくても、新しい環境で窮屈な想いをさせているのかも知れないよ」
住職は何時も寄子が座って食べていた座布団を、心配そうな面持ちで見ている。
「私は……如何も、人の心の繊細さが分からない。それでも、愛していた筈の人が未来で犯罪者として逮捕されたのです。悲しくない訳は無いですね」
と、口にする。
黒影から聞いた事件関与で逮捕された事を、寄子さんに伝えた時……寄子さんは暫く無言で聞き……最後に、
「……そうですか」
と、言っただけ。
黒影に言われていたのです。「勲さんは余り気にしないところがあるから、こう言ったデリケートな話しはタイミングを気を付けて伝えて下さいね」
そんなアドバイスをされましたが、全く……やはり理解に苦しみ、ただ時間が空いていそうだと話してしまった。
「……住職」
「ん?……如何しました?」
「……未だ寄子さんに、正義崩壊域の崩壊に、彼が関与していた事は言わない方が良かったのでしょうか。……環境の変化に私は無頓着でいられますが、他は違うかも知れない……」
私は気難しく感じ、思わず眉間に皺を寄せて腕組みをしていました。
「……そうかも知れないね。勲さんは悪気がある訳でも無い。本当は優しいのに、事件を追い過ぎて「事実」に目が行ってしまう。「事実」は厳しく、間違いが無い。けれど……人の心は間違いばかりなのですよ。……気掛かりなのでしょう?勲さんが言う「事実」で言うならば、勲さんは今私に聞きましたね。聞いたと言う事は気になっている。以下程かは分からないけれど、後悔しているのでしょう?行っておやりなさい。……後悔しない為に」
そんな言葉で住職は己に無頓着な私の感情を教えてくれたのです。
私が他の下宿処では無く、この寺に居座り出したのは、此の住職に己が足りない事を教えて貰える気がして……良く話し込むうちに、彼方此方に泊まってまた来るのも面倒だからと、住職の言葉に甘えている。
優しさと言うものが、未だ何かと聞かれれば私にははっきり答える事も出来やしないのですが、ただ……関わりの中に漠然と生まれる何かであり、それが安心に繋がる事を知ったのです。
何が出来るでもない……。
けれど……関わる事で何か変われば……そんな想いが強くなり、居ても立っても居られない衝動に駆られたのです。
「……行ってみます!」
私は箸を置き、気付けば立ち上がっていた。
「……はい、行ってらっしゃい」
と、住職は朗らかな笑顔を見せた。
その方が良いと、言いたいらしい。
私は寺を飛び出す様に後にしました。
朝霧が深く、此の村の早朝は気温も低い。
寺の玄関脇に備え置いてあった、黒い鉄枠の硝子を嵌めた洋燈にマッチで火を付け、其の明かりを頼りに慣れない教えられた道を、走っていたのです。

理由も説明出来ない胸騒ぎと言う物でしょうか。
初めて感じる感覚で、そう喩えて良い物かすら分かり兼ねますが、知識として知る中の感覚で言うならば、其れが一番近かった様に思えてます。
急に開けた道になる……。
霧がふんわりと辺り一面に広がっていた。
足元を洋燈で照らすと、原っぱの様な所に来ていた様です。
白い小さな花が咲いている。
その花は綺麗なのに、原色が差し、やや毒毒しくも感じます。
「……白い……菫……」
思わず、口から溢れる様に出た言葉。
私は己の其の言葉に、少しぞわりと致しました。
……其の花言葉は……「死」。
胸騒ぎらしき想いが加速し、其の道を進みつつ、気付けば叫んでおりました。
「寄子さぁーん!寄子さん、いますかー?」
そう白霧に向い呼んでみても、返事もありません。
随分と早くから出掛けたのですから、未だ暗かったでしょうに……。……?
私は其処である事に気付いたのです。
寺の玄関に備え付けてある洋燈は一つ。
何故に寄子さんは、見渡しが悪いと分かりきった道を……洋燈も持たずに出掛けたのでしょうか。
――――――――――
真っ白な世界が次第に闇を明らかにして行く。
私を追い掛けてくる筈の光輝は、遠い未来で……私よりも何時の間にか先に行ってしまった。
此の虚無感に名前等無い。
恋だか愛かも分からなかった。私は今……、逃げる必要も無くなった。
これから、一体何を目的に日々を過ごせば良いかも分からない。
知らなかった人の温かさ……当たり前の生活……。
幸せな筈なのに私には、不釣り合いに見えて。
また逃げたい……そう思ってしまったの。
だから、早めに行くと適当な口実を付け、また逃げ出してしまった。
逃げ出してみれば何も無い、以前と変わらない空っぽの私。
……ずっと……此のまま……此の白さに包まれ眠りたい。
そう思って私は手を伸ばしていた。
「寄子さーん!」
その声にドキッとした。
何故、聞き慣れた此の声に驚いたかは分からない。
ただ……貴方に、見つけられたくは無かったのかも知れない。
弱すぎる……普通すら似合わない私の姿を……。
淡く揺れていた……ふんわりと、黒い……影……。
――――――――
「寄子さん!何て事をっ!」
勲は寄子の肩を揺らし、正気に戻らせる様に言った。
寄子が咥えていた、菫の根を其の唇から奪い取る様に捨てる。
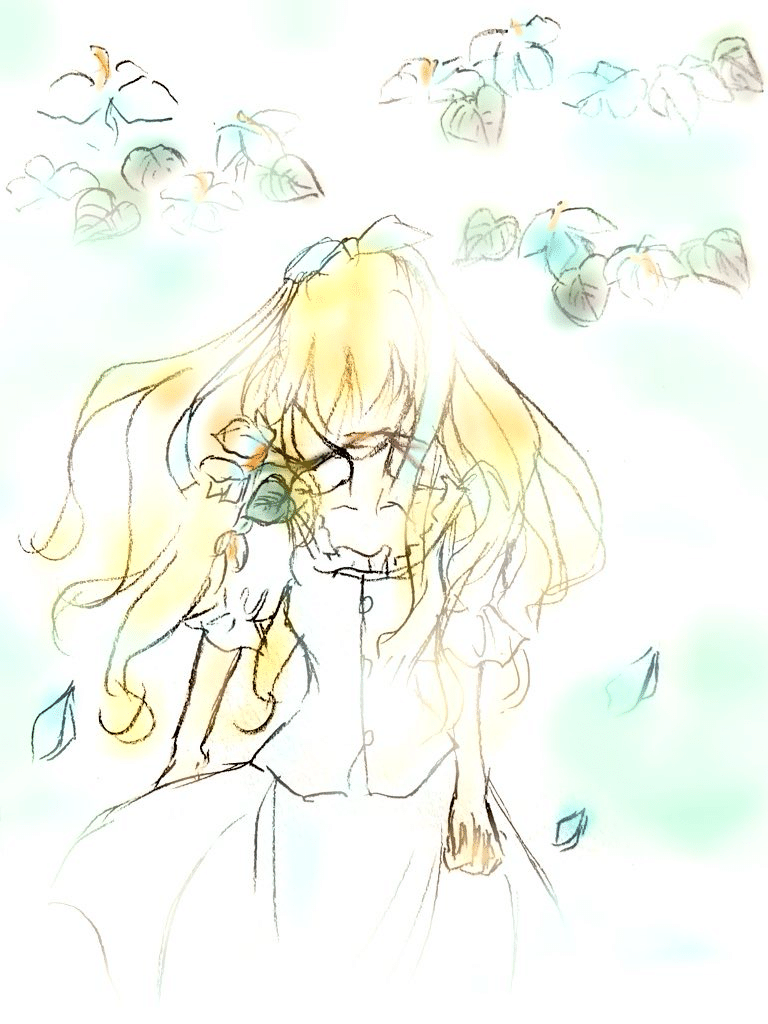
毒の汁を唇を奪い吸い出しては、地に吐き捨てた。
寄子は放心状態で、白霧囲む菫の花々の上に倒れたのだ。
「早く病院へ!」
勲は寄子を抱き抱え様とすると、寄子の力無い手が、腕を引いて止めようとする。
「大丈夫……違うの……」
今にも消えそうな、か細い声で寄子は言った。
「違う?……何が違うんだ!」
勲は真剣に怒っている様である。
ただ、其の憤りは何処か苦しそうでもあり、悲しそうにも見えた。
……自分の所為とまでは自覚出来ていなくても、何か痛切なものを感じてはいた。
滅多に感情等、表には出さない。
其れは感情も制御出来ない事が子供の様に思えたから。
犯人や事件を追うだけの日々にそんな物は無用だと切り捨てきたのかも知れなかった。
ただ、そんな物を恨み続け、取り残されその概念だけが黒影と離れ生まれた影。
其れを知ったところで何も感じはしなかった。
消えるかも知れない覚悟もしていた。
其れが生きて……感情等持って、何の役に立つと言うのか。
けれど、黒影……否、僕等の選んだ道は……別々で在り続け、生きる事だった。
其れを決めた後、気が付けば感情を知りたくて仕方無い己に気付いていた。
こんな時、掛ける言葉も見付からない。
「勲さん……」
「あ……はい」
腕の中で寄子が話し掛けた。
其れが言葉も思い付かない勲には救いの様にも思えた。
「勲さんは何度でも私を救ってしまうのね……。此れからも?」
「……ええ、助けるのが当たり前ですから。……でも其れで依存して何度もされちゃあ、困るんですよ。変な癖を付けないで頂きたい」
勲は今、自害しようとした寄子にも、容赦なくきっぱりそんな言葉を言ってしまう。
突き放す様だが、生きる目的を失った寄子に、己を目的にして欲しくは無かった。
自分の道を少しずつでも、どんな僅かでも良い……自分で見付けて欲しいから。
「……勲さん……。私、勲さんを好きになっても良い?」
「えっと……其れはですね、単に吊り橋効果と同じで、良くレスキュー隊等に救われると好きになってしまったり、結婚して幸せになると言う例も有りますが、私は人自体が……」
「人が苦手」
寄子は勲が挙動不審に並び立てた言葉を、遮った。
「……ええ、そう出逢って直ぐに私は寄子さんに言った筈です」
「……そうよ、分かってるわ。勲さん、私に打つかりそうになった時、避けたもの。けれど、今は触れているじゃない」
と、寄子はこれは何かと言いたい様である。
「其れは、救助の為で……感情だとかは別に割り切っていますから」
「聞きたく無い!……言い訳なんて。助けた理由も、救助だからなんて言葉も要らないわ。勲さんを好きになるのに理由なんて要らないものっ!……私には勲さんが普通に出来る当たり前の暮らしも分からないし、周りを過去にしてしまうのよ?!……分かる?勲さん。貴方が居なければ私はこの今すら知らずに生きていたの。貴方なんて貴方なんて……出逢わなければ良かったと思うのに、貴方と普通の生活をずっと送りたいと思ってしまった。全部全部勲さんの所為よ!……ずっと……一緒にいてくれる?……私はまた一人?」
寄子が勲の瞳をじっと見ている。
「其れは……」
勲は考えていた。確かに、此のままの状態で一人生きたり、以前の様な暮らしに戻るのは酷と言う物だ。
「私は貴方じゃなきゃ嫌なの!助けてくれたからでも無いし、勲さん……私が色んな物を過去にして壊しても、困ったと言うけど、何時も微笑んでいた。勲さん……未だ気付いてくれないの?最初に見せた作り笑顔じゃない、貴方のもっと自然な笑顔をみていたいの。責任取って!」
「えっ?何のですか?」
「私を助けて連れ去ったわ」
「だからそれは……」
「だからじゃないの!……今度は……今度は……もっとちゃんとキスしてよ」
勲は少し驚いたのか、目を少しだけ大きく開いたが、其の時、何とも言えない感情をまた一つ覚える。
これが恋か愛かも分からない。
けれど……ずっと探していた、感情……。
名もなき……安寧……。
静かに……ゆっくりと舞い降りた口付け……
優しさとは……相手を想った時、生まれる……
君を想う時……毒の花すら……美しい……。
――――――――――
「……もう、大丈夫なんですか?」
起き上がり、探しに行きましょうと行った寄子に勲は言った。
「……ええ、其れより手を繋ぎましょう?」
そう言って寄子は勲にふと手を出した。
「ちょっと……」
相変わらず、勲は反射的に其れを避ける。
「嘘でしょう?今さっきキスしたのに、手は駄目なの?」
寄子は呆れて言った。
「……人の温もりとか、体温を長く感じるのが苦手なんですよ。私は其の……低体温ですから、大概の人は熱苦しくて。だから、悪気無いのです」
そんな事を、勲は申し訳なさそうに白状したのだ。
「……そんなの……私が直して上げるわよ」
と、寄子は憤(むつく)れて言った直後に勲に抱き付いた。
「だから本当に苦手なんですよっ!」
そう言って、勲は寄子を解くと走り出す。
寄子は態とそんな勲を揶揄って追い掛けだ。
……あれ?……何時の間にか……笑っている……
勲はそんな己に気付き、何だか其れが妙に嬉しく原っぱの彼方此方へと楽しそうに逃げる。
何時も追うだけだった男が追われ……
何時も追われた女が追う……
もう昔とは……違う二人。
勲が突然止まった。
寄子は急だったので勲の後ろ姿に衝突する。
「痛い……」
思わずそう言って、勲に如何かしたのかと聞こうとして、勲の視線の先を探す。
長い漆黒のロングコートが風に靡き、羽音を立てる。
日の光が、霧から光の筋を通し、其の光の中には黒く輝く星が散りばめられている。
「……黒水晶はこの辺りの様ですね」
其のまま二人が進むと、入り口の小さな洞窟を見付た。
人が一人通れる程の入り口で、入るなと言わんばかりに、〆縄が掛かっていた。
勲は其の端と端を丁寧に外すと、中へ入っていく。
洋燈の明かりだけを頼りに……。
寄子は思わず勲の肘を怖がり獅み付いたが、勲は何故か気にしない。
……目の前の「事実」を確かめたい……。都市伝説の様に風化した場所。こんな所が本当にあったなんて。……追い掛けて、捕まえたくなる……。
勲は「事実」を前に夢中になり、体温が云々の話も其方退けだ。
寄子はここぞとばかりに怖がって抱き付いてみるが、勲は「事実」を確かめたいと言う思いでいっぱいで、気にも留めないどころか、其の後ろから回った寄子の手を無意識にしっかりと握り、進んでいた。
真っ暗な闇に一筋の太陽の光が差し込んでいる。
きっと外の霧がようやっと晴れたのだろう。
くっきりと鮮やかな輝かしい光の中に聳え立つ、大きな漆黒の柱。太陽の光を受け、乱反射し美しい光と影を洞窟いっぱいに作り出している。洋燈を掲げ、辺りを見渡せば、この洞窟内の壁全てが、此の原石を包み込む様にあり、黒の中に、小さな光を無数に放つ。
寄子も其の景色に圧倒され、辺りを見渡すだけだ。
「……そうだ、原石」
持って来たクサビとハンマーで原石を掘り出して行く。
カーンカーンと言う音が、中をぐるぐると共鳴する。
瓶に取れた黒水晶を密閉し、任務を終えた。
小さな欠片はこっそりとポケットに仕舞って。
数日後、其の小さな二つの欠片は、黒い革紐で器用に結ばれ、二人の首へ飾られ揺れる御守りとなるであろう。
次の二章を読む↓
いいなと思ったら応援しよう!

