
◆読書日記.《三島憲一『ニーチェ』――シリーズ"ニーチェ入門"6冊目》
※本稿は某SNSに2021年3月31日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
三島憲一『ニーチェ』読了。
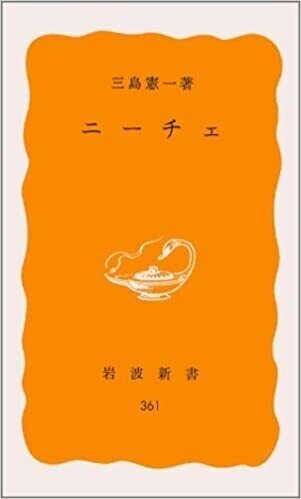
ドイツ思想が専門の哲学研究者によるニーチェの解説本。
これは、役に立った! さすが専門家。
今までの読んだ6冊の本とはまた別の角度からニーチェ思想を一から解説していく本書、認識を改めさせられた。
◆◆◆
哲学というのは非常に難解な抽象概念や今までになかった考え方を扱うために、自然と表現が難渋になり易く、そのために誤解や誤読が多い。
誤読や誤解といったものについては、どの思想家も多かれ少なかれ付いて回る問題である。実際「この人の思想には誤解が多い」と言われている思想家は数多い。
フッサールの超越論的現象学も誤解が多いし、ハイデガーも「実存主義」と誤解される事も多い。フロイトの精神分析も誤解が多かった。
かなり明快な文章のマルクスでさえ「共産主義思想を作り上げた」という誤解が多い。
きっちり屋のカントでさえその思想が誤解されることが多い(まあカントについては「本場のドイツ人でさえ頭を抱えるほど難渋」と言われるほどだから無理もない)。
難解だからこそ、どんなビッグネームでも、研究者によって多かれ少なかれ何かしらの解釈の違いが存在していたりもするのである。
ニーチェもそういった「解釈の違い」が多いかもしれないが、ニーチェの文章は、それらの思想家とは若干、色合いが異なっている。
ニーチェ以前の哲学者は、建築物のように論旨を一から積み上げていくタイプの人ばかりだったので書いている事は明確だが、考え方とその表現が難解なので誤読が生まれやすい。
それに対してニーチェはアフォリズムという形式で思想を分散して記述し、明確な一つのテーゼを立ち上げるようなタイプではない。
ニーチェのアフォリズムは、まるで「謎かけ」のような記述であったり、詩を模した文章になっていて象徴的であったり、きっちりした定義づけをせずに仄めかすような表現であったり、例えが多くて明快な解答が見えなかったりする。
ニーチェ思想は、重点をどこに置くかによって様々な部分が強調されるのだろう。ニーチェは、よく言えば柔軟、悪く言えば曖昧な所がある。
まさしくニーチェの文章は彼の主張した「遠近法主義」的に個人個人のパースペクティブによって解釈が千変万化するのである。
本書に引用されている部分で少々実例を挙げれば、ニーチェは「学問性――真理に対する巧妙な正当防衛」「今日行われているような学問が可能であるという事は、生における一切の根本的な本能がもはや機能せていない証拠である」と学問に対して否定的と思える言葉がある反面、次のように学問を称揚するような事も言っている。
「我々は、キリスト教、哲学者、詩人、音楽家のおかげで感情の深い揺さぶりを沢山知っている。しかし、こうしたものがはびこって我々を覆いつくさないために、我々は、学問の精神を呼び起こさねばならない。学問の精神こそは我々を全体としてもう少し冷静に、懐疑的にしてくれるものである」
どちらなのか。学問を、批判しているのか擁護しているのか。
ぼくからしてみると、これらはむしろ一貫して学問を擁護しているように思えるのだが、それもニーチェに言わせれば、ぼくなりのパースペクティブのなせるわざなのかもしれない。
このように、ニーチェの言葉は読者の受け取り方によって180度違う内容のものになりうる危険性がある。権力者に悪用されるわけである。
ニーチェ以外の思想家は、論旨は明確だが、表現が難解で分かりにくい。
だが、ニーチェは論旨そのものが多様な解釈を許す書き方だからこそ、分りにくいのだ。
まるで、近現代アートや文学が、あらゆる多様な解釈を許すだけの「スラック(余裕、遊び)」を持っているように、ニーチェの思想も大きなスラックを作っているようなのである。
それがニーチェ思想の大きな特徴となっているからこそ、学者間の解釈でも印象がガラリと変わる場合がある。
しかも、多様な解釈を許すからこそ、本格的な専門家でもない、ニーチェは専門に研究していない研究者でも「私なりのニーチェ解釈」という論を展開する事ができる。
「偏った解釈だ」と言われるものも多い。
だが「多様な解釈を許す」とは言え、明らかに「偏った解釈」であるものというのは、ニーチェを研究している人にはすぐに判別がついて、その代表例が「政治的な言論にニーチェを利用」したナチス政権である。
だが、ぼくはその「多様な解釈」のスラックがどこからどこまでなのかという感覚が掴みたいと思っていたのだ。
本書を読んで、その展望が少しだけ開けた気がする。
◆◆◆
著者に言わせれば「ニーチェという現象はあまりに巨大で、あまりに多岐にわたり、あまり複雑であることも確かである」と言っているだけあって、「ニーチェのいわゆる全体像を描くということは放棄せざるをえなかった」とも書いている。
だが、本書は他のニーチェ入門書・解説書とはけっこう違う視点でありながらも、立派に「ニーチェ入門」と呼べるものを書いている部分が面白い。
ぼくが読んだニーチェ本のほとんどが後年の主著『ツァラトゥストラ』をメインに置いて解説しているのに、本書ではニーチェの処女作『悲劇の誕生』をメインに置いているのだ。
『悲劇の誕生』は、他の入門書の中では「ワーグナーを称賛するために書かれた」という文脈でサラリと流され、他の思想書との関連が書かれる事がない場合も多い。なので、ぼくも本書を読むまで『悲劇の誕生』は重要視していなかったほどである。
それほど『悲劇の誕生』はニーチェの他の著作と趣を異にしているのだ。
だが、本書の著者の主張に寄れば『悲劇の誕生』はニーチェの「芸術論」の本丸であり、その古代ギリシアに元々あった芸術観に理想の始点を置く観点は、何と晩年の著作に至るまで一貫してニーチェの理想として育まれ続け、その流れによってニーチェの「力の意志」も「永劫回帰」も生まれたというのである。
そのニーチェ思想の重要なスタートとなる主概念が先日もご紹介した「アポオン的」と「ディオニュソス的」であった。
この二元性の合一によって様々な芸術が生まれてきたが、古代ギリシア芸術の中でもその中心が円形劇場で演じられる「ギリシア悲劇」だったのである。
どうやら古代ギリシアでは芸術というのは単なる憂さ晴らしではなく、公共的なものの一部であり、人と人とを繋げる紐帯でもあったらしい。
古代は現代よりも人間は簡単に死ぬ、「死に近い存在」であった。巨大な自然の力に翻弄され、未知の病気におかされ、争いや不幸な事故で人は簡単に死んでしまう。
キリスト教道徳のなかった時代の、古代ギリシアの神々は冷酷であった。
彼らは何を心のよりどころにしたのか。――野蛮や、自然や、人々に起こる悲劇を、人は「美」によって昇華させていた。
幸福の束の間も、巻き起こされる「悲劇」も、全て含めて「美」であり、そういった己の生を「美」と調和させていたのである。
自然との和解。人と人との和解。生を「美」によって「然り」と肯定する。
ディオニュソス的的なものは美しいし、アポロン的なものも美しい。
古代ギリシアにあっては、それらは全て混沌として、それでいて調和していた。ニーチェはディオニュソス的なものを描写した次のような文章を残しているそうだ。
……人間は歌いつ、踊りつ、ある高次の共同体の一員であることを表現するのであって、もはや歩くことと語る事を忘却し、踊りながら空中に舞い上がろうとしている。……人間はもはや芸術家ではなく、芸術作品になっている。(ニーチェ『悲劇の誕生』より)
現代の我々の生活の中では社会的な要請として、金を稼いで生きていくため、または限られた資源を奪い合って自分を有利にするために、人と人とは分断され、文明は自然から遠く離れて都市や町や硬い殻を持つ家に引きこもった。
自然と人、人と人、それぞれがバラバラになってしまったが、我々がそれらの分断から回復し、真に和解したときの高次の共同体にあっては、「富の分配の重要な要素である「歩く」ことも、また取引の重要な能力である「語る」ことも、そうした手段であることをやめ、「踊り」と「歌」に変容する。それによって、我々自身が芸術作品になる(本書より引用)」のである。
この考え方が行き着く先が、ニーチェの考えた美と同化した生の在り方――「超人」だった。
"美と同化した生"!!
"そこではもはや人は芸術家ではなく、芸術作品になっている"!
――翻って、われわれ現代人にとって「芸術」とは、どのようなものになっているのか。
芸術は、社会の隅々にまで行き渡り日々の生活の大半を占領するようになった勤労の片隅に追いやられ、日々の憂さ晴らしのようなものとして使われる。
資本主義の枠組みにガッチリ収まって流通され、商品化される芸術というものは「高級感を満喫できる娯楽」として消費される、一種のステータス商品なのである。
エンタテイメントというのは、芸術の堕落した形式なのではない。今の時代は、むしろ芸術ほうが"娯楽の一種"に成り下がってしまっているのである。
芸術作品という形で流通している芸術は今日、結局の所、何によって存続しているのか。余暇のある大多数の者たちが――実際、こんな連中の為にだけそのような芸術は存在しているにすぎない――音楽や劇場や美術館行きなしには、また、小説や詩を読まずには、自分たちの暇な時間が片付かないと信じている事によってである。――ニーチェ『さまざまな意見と箴言』175番より
ニーチェは明らかに芸術家志向であった。事実、芸術家(というより音楽家)を目指していた事もあるほどである。
だからこそ、と言うべきかニーチェにはある種、芸術によるユートピア思想の如きものがあったのではないかという事が伺わせられるのだ。
本書はこのようにニーチェ思想を、他の解説書ではほとんど触れられていない、「ニーチェの芸術観」を強い軸と想定し、処女作から晩年に至るまで一貫してその「美」思想が付きまとっていたという事を解説していく。
これにはぼくも参った。これは、ぼくには初めてのニーチェ解釈であり、非常に刺激を受けた一冊であった。
