
◆読書日記.《内田樹/編『日本の反知性主義』》
※本稿は某SNSに2020年4月10日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
内田樹/編『日本の反知性主義』読了。
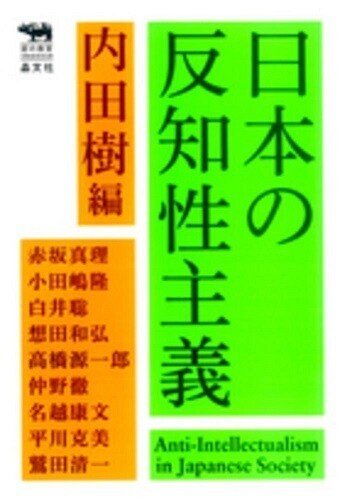
仏文学者の内田樹が編者となって各ジャンルの有識者に「反知性主義・反教養主義」をテーマとして書いてもらった文章を集めたアンソロジー。
執筆陣は内田樹のほか作家の赤坂真理や高橋源一郎、コラムニストの小田嶋隆、政治学の白井聡、生命科学の仲野徹、精神医学の名越康文など。
昨今「反知性主義」という言葉は何となく巷にフワフワと漂っているが、元々はリチャード・ホーフスタッターの『アメリカの反知性主義』からとってきた考え方なのだそうだ。
なので「反知性主義」のそもそもの意味はホーフスタッターの定義によるだろうが、これが一般語となって流布されている現状、それだけでは収まらないだけの広がりが、この言葉には出来てしまっている。
だからこそ本書では、まず冒頭に内田樹の「まえがき」と論文「反知性主義者たちの肖像」にて、本書の制作意図と元々のホーフスタッターによる「反知性主義」の定義を述べ、その後の論者については各自思うままに「反知性主義」について書いて貰っているようだ。
◆◆◆
政治哲学の白井聡はホーフスタッターの定義を「知的な生き方およびそれを代表するとされる人々に対する憤りと疑惑」であり、「そのような生き方の価値をつねに極小化しようとする傾向」と『アメリカの反知性主義』を引用しながら説明している。
だが、この言葉の意味はこれだけにとどまらないのが重要な点だ。
内田樹によればホーフスタッターは「反知性主義に陥る危険のない知識人はほとんどいない。一方、ひたむきな知的情熱に欠ける反知識人もほとんどいない」と半ば逆説的な事を言っている。
映像作家の想田和弘は「反知性主義的態度は、本人がそう自覚せずとも、知らず知らずのうちに忍び寄るものだということ」と説明する。
両者の言っている事はほぼ同じような意味だ。
「頭が悪い人間が反知性主義になる」とは限らないのである。
ホーフスタッターも「指折りの反知性主義者は通常、思想に深くかかわっている人びとであり、それもしばしば、陳腐な思想や認知されない思想に憑りつかれている」と言っているのだそうだ。
つまり「反知性主義」というのは「頭の良し悪しの傾向」ではないのである。
同じく「反知性主義」というのは「知識のある/なしの差」の事でもない。
頭が良かろうが悪かろうが関係なく、全く非論理的な思想に憑りつかれたり、根拠のない説を掘り下げようとしたり、全く馬鹿げた主張を繰り返す人というのは確実にいる。
定義しにくいにも関わらず、確実に存在しており、現在の社会を世界的に蝕みつつあるこの「反知性主義」とは一体何なのか?
この謎を解明するため、本書では十名の論者がそれぞれの専門分野の視点から、その分野を蝕み始めている「反知性主義」を説明していき、その事で徐々にこの漠然とした現象の正体を浮き彫りにしていく。
◆◆◆
本書の面白い所は、まだ定義が漠然としている現象を、十名の論者の手による多視点的な切り口によって、その輪郭を明確にしていこうという編集意図にある。
物事を判断するうえでは「多視点的な切り口」というスタンスは非常に重要だ。
これは、近年亡くなった保守思想家の西部邁氏が昔言っていた事を思い出す。
真実というのは円形を為している。それに対して、我々の視点は線的なのである。だから、我々が「真実」の一端に触れても、接点部分の「点」以外は徐々に遠ざかり、全体としての「円」の姿は見えてこない。
だから、いろんな角度の視点から「真実」を見て総合する、という意識がなければ「真実というのは円形を為している」という事にすら気がつかない。
だから、本書のように未だに答えの見えない現象については、様々な専門分野の人間が、それぞれの専門分野の知に則って様々な視点から考える、というスタンスで理解しようという姿勢は正しいと思うのだ。
西部邁氏の例えで言えば「反知性主義」は、「線」で見る一個の視点に拘って視点を変えない人とも言えるだろう。
実際「自分の説に固執する」というのは、本書の幾つかの論者が指摘している「反知性主義」の特徴でもある。
映像作家の想田和弘は言う。
「知性が間断なく活発に発揮されるためには、苦労して到達した地点にしがみつくことなく、いつでも捨て去り更新する勇気や気力を維持することが必要になる」と。
内田樹も「反知性主義の本質」として「反知性主義者たちもまたシンプルな法則によって万象を説明し、世界を一望のうちに俯瞰したいと願う知的渇望に駆り立てられている。それがついに反知性主義に堕すのは、彼らがいまの自分のいるこの視点から「一望俯瞰すること」に固執し、自分の視点そのものを「ここではない場所」に導くために何をすべきか問わないからである」と言う。
つまり、多視点的なスタンスをとる事なく、自説に頑固に固執してしまう人間と言うのは「反知性主義」に陥る素養を持っていると言って良いだろう。
本書ではこのように「反知性主義」の解釈について、それぞれの立場の専門家が、それぞれの立場で考えているが、何しろまだ定義がアヤフヤな部分があるので、多くの論者がどう書いたものかと悩んでいると本文にて告白している。
そこで多くの論者が「では逆に何をもってして"知性がある"と言えるのか」という事に考えが及んでいる、という傾向があるのも読んでいて面白い点であった。
「反知性」は「非知性」ではない。「知性がない」「知性が低い」ではないのだ。
近代啓蒙主義的な考え方というのは、人間は知性を上げて豊かな内面を持つことで人間性豊かになると信じられ、それを達成するために様々な学問を学んで人間的に完成しようという考えがあり、それが社会おも豊かにすると考えられてきた。
だがポストモダニズムの時代になるにしたがって、それがだんだんと形骸化してきたようなのである。
どの論者も認めているように、啓蒙主義的な「豊かな知性と内面を持った完成された人間像」の正当性が否定されるような事態が、各現場に徐々に浸透してきているというのである。
「啓蒙主義的な人間像が否定される事態」のキーワードとしてしばしば出て来るのが「資本主義」である。
例えば、映像作家の想田和弘は、かつてテレビ局のドキュメンタリーにあった「真実を報道する/真実を写し撮る」という使命が現在もはや形骸化している事実を指摘する。
テレビ局のドキュメンタリーには「企画書」と「台本」があり、その意図によって撮影する対象や編集するフィルムが取捨選択される。
しかも、「納期」や「放送日」が決まっているため取材期間も決められており、その期間内に自分達の意図した映像を切り取ってこなければならない。
これでは「真実の切り取り」にはならない。
また生命科学者の仲野徹は、研究と大学の「資本主義化」を指摘する。
研究分野と「儲け」が手を結んでしまう現状と言うのがしばしば存在していて、研究費の投下に見合った「役立つ成果」が求められる問題があると言っており、また国立大の予算削減による大学職員の雇用状況の変化も問題視している。
こういった資本主義的・実利主義的な問題の弊害は広く行き渡っているのではないかと思わされる。
「実利」を優先するあまり、「本当の事はどうなのか?」「それは真実なのか?」「倫理的にはどうなのか?」という、近代まで重要とされてきた「内実」が骨抜きになってきている、という状況だ。
これが一層深刻なのが、やはり政治分野においてと言えるだろう。
これは内田樹も政治思想家の白井聡も指摘している事だ。
勿論、現在日本の政権与党の「反知性主義」っぷりは目に余るほど酷いものであるが、これは世界的にもちらほらと現れてきている傾向なのだそうだ。
白井は「20世紀における反知性主義者のワーストテンに必ず参入されるはずの人間に、ジョセフ・マッカーシー上院議員がいる」とロービア『マッカーシズム』の文章を引用しながら、彼が権力を握ったことによってトルーマン、アイゼンハワーという二代にわたる大統領の権限を「半身不随」に追い込んだ言動を紹介している。
詳細は是非本書を読んで確認して頂きたいが、その言動がまさに現代日本の某政治家の言動を思わせるのがお分かりになるだろう。
彼は常習的なウソつきであり、金に汚く、卑劣漢であった事には無数の証言があると言うが、そんな彼に何故権力が与えられていたのか? これは現代日本の政治問題ともパラレルなのではないか。
考えるのをやめてはならない。
内田樹は反知性主義者の際立った特徴を「無時間性」と指摘した。
今の為政者たちは、政策の適否は長い時間的スパンの中で検証されるものであって、自分たちが今犯した失敗の「負債」は自分たちが死んだ後、まだ生まれていない何代もの世代に引き継がれる事になるというふうには考えていない。彼らは自分たちの政策が歴史的にどう検証されるかという事には何の興味も持っていない。彼らが興味を持つのは「当面の政局」だけである。
内田樹/編『日本の反知性主義』より
――以上「反知性主義」について様々な専門家たちの多視点的な考えが挙げられた。
これを踏まえてどう「円を為す」かは、我々一人一人の「知性」にかかってると言えないだろうか。
最後に……本書は十分面白いアンソロジーだったと言えるのだが、欲を言うならば最後に本書を包括するような視点の言及が欲しかったところでもある。
けっきょく「反知性主義」とは、現時点でどういったことが言えるのか?
……だた結局、これも「自らの頭で考える事」が、最も重要な事なのではあるが。
