
◆読書日記.《千野栄一『言語学を学ぶ』》
<2023年4月23日>
千野栄一『言語学を学ぶ』読了。

チェコ語を中心としたスラブ語学が専門の言語学者による言語学について学ぼうとしている人のために著者なりの説明を踏まえたブックガイド&近代言語学を築いてきた著名な学者の紹介。
長編解説書というよりかは、それぞれのテーマについて短く纏めた文を集めた短編集といった感じである。
◆◆◆
ぼくが今年想定している「私的課題書」はソシュールの『一般言語学講義』である。
と言う事で以前から書店や古本屋で見かけるたびに少しずつ買い集めていたソシュール関連、あるいは言語学関連の本を先日書庫から引っ張り出してきた。

10冊前後と決して多くはないが、伝え聞くところによれば『一般言語学講義』は、カントやヘーゲルといった他の思想家のような超難解な内容になっているわけではなく「いかなる説明をも要しない、むしろ、噛んで含めるような、教育的で、啓蒙的な内容なのである(田中克彦『言語学とは何か』P.24より引用)」というそうだから、さほど副読本や解説本は多く必要ないだろうと判断したわけである。
恐らく日本のソシュール研究の第一人者である丸山圭三郎さんの本を読んでおけば大丈夫だろうと考えたわけだ。
そういう事で、今回はソシュールを学ぶ課題の前段階の学習として千野栄一『言語学を学ぶ』で、まずは言語学の全体像と、その中におけるソシュールの位置づけを把握しておこうと考えたわけである。
しかし、これは困った。
読み終えてから理解したのは、本書の内容を紹介するにも、ぼくなりの考えを述べるにしても、かなり慎重にならざるを得ないという事だった。
本書に関しては「入門」という事をじゅうぶんに意識されて書かれているようなのだが、著者は言語学をひと言で簡単に説明するのは難しいといった内容の事を本書で何度か表明しているのである。
本書の「手頃で、言語学の全貌がよく捕らえられ、しかもその言語研究者の言語観がよく分かるような本は待望久しい本である。待望久しいということは、そのような本はないということを示している(本書P.164より引用)」や「自分が言語学の勉強を始めたときも何とはなしに言語学なるものがはっきり掴めず不安で、繰り返し読めば言語学なるものが理解できるような本はないかと探し求めた。(本書P.164より引用)」「正直にいって「言語学の初歩」や、「言語学入門」の講義で、うまく話せたとか、面白く説明できたという記憶は全くといっていいほどない。実は私こそそのような本を求めているのである。(本書P.165より引用)」といった記述に、その困難さの一端が示されている。
この困難さの理由の一つは「言語」というものの曖昧さにあると言って良いだろう。
言語というものは直接観察できない。音なり文字なり、聴覚あるいは視覚で捕らえられるものは、音形あるいは文字によって指示されている形にすぎず、その指示されたものを直接にとり出すことはできない。ここに言語をある角度から追いつめていくと、その網から何か大切なものがもれてしまう一原因がある。
「言語学」というものを簡単に説明する事の困難さというものは、先日から読み進めている田中克彦『言語学とは何か』にも、ほぼ同様の記述が見られる事からも、どうやらこれは言語学の中では共通の認識としてある事なのかもしれない。
たとえば、アメリカ・インディアンの諸言語を研究し、独特の言語観に到達したB・L・ウォーフは、「言語学を一般人向きにすることなど不可能であり、……そのようなことを試みる意味はないことを悟っていた」という事である(J・B・キャロルのことば)。
この困難さを田中は、同じく『言語学とは何か』から、近代言語学を切り開いた立役者であるソシュールの考え方を引きなら説明しているので、その箇所を紹介しよう。
より過激な言い方をすれば、言語についての正しい認識をさまたげているのは、知識の欠如ではなく、むしろ、自分はことばについてのもの知りだと思い込ませている、さかしらな、誤った知識である。だからソシュールも、この『講義(※ソシュール『一般言語学講義』)』を、言語について学問あるいは知識が作ってきた偏見から次々に脱却してきた三つの段階を回顧するところからはじめる。
――こういった一般に広まっている言語における考え方を転換したからこそ言語学は「近代」において劇的な転換が行われたのであり、その端緒をひらいたからこそソシュールは後に大きな影響を与えたと言われているのである。
千野栄一『言語学を学ぶ』を読む限り、恐らく「言語学とは何か?」「そもそも言語とは何か?」という基本的とも思える疑問に、多くの言語学者が慎重な姿勢をとっているのは「言語」というものが、そのものからして曖昧で、一般にも偏った固定概念が多いからという理由があるのではないかと言う事が伺えた。
読み始めてすぐは、未知の領域に分け入っていく知的興奮を覚えたのだが、しだいに自分がいつの間にか右も左も分からない巨大な密林の中に迷い込んでいる事に気付いたかのような困惑を覚えている。しかし、この感覚も悪くない。
言語学についてはソシュールの関連で基本的な知識くらいはおさえておこうという腹づもりだったのだが、これは深入りするのは相当厄介そうだと思えた。
千野栄一『言語学を学ぶ』で紹介されている本の何冊かは読んでみようと思うのだが、専門書にまで手を伸ばすのは、ぼくの今の能力では無理だろう。
そういう事情があるので当然の事だが、本稿を読んでおられる方の中で「正確な内容を知りたい」と思う向きがあるならば「本書を読んでください」としか言いようがない。
こういった微妙な分野を知りたいと思うならば、手間暇を惜しんで楽をしようと思わない事である。
◆◆◆
――という予防線をあらかじめ引いた所で、以下つらつらと本書を読んで学んだ事や思った事を書いていこう。
ぼくの先入観からすれば、近代言語学の重要な分野といえば記号論や文法についての研究だと思っていたのだが、どうも違うらしい。
それどころか、ソシュールはこの「世にいう文法というもの」の研究についてからが、科学としての言語学がやるものではないと否定さえしているというのだ。
言語事象をめぐって組みたてられた科学が、その真正、独自の対象がなんであるかを認識するまでには、あいつぐ三つの段階をへてきたのである。
まず手始めは、世にいう「文法」を編むことであった。この研究はギリシャ人が口火をきり、おもにフランス人が受けついだものであって、論理を土台とし〔ていたために〕、言語そのものにたいする科学的な、公平無私な見方を欠いている。それはもっぱら正形、不正形の別を立てるべき規則を供するのがねらいだ。つまりは規範学であって、純粋観察をへだたること遠く、その見地のせまいのもまたやむをえない。(9)
では、言語学という分野の中では何が重要となってくるのか。
例えば千野栄一は『言語学を学ぶ』の「音声学」の項目の冒頭で次の様に言っている。
音声学というのは言語の音声的手段を研究する言語学の一部門である。一部門といってもすべての言語はその表現手段として音声を用いているので非常に重要な一部門であり、筆者の考えでは言語の研究者がプロであるか、アマであるかのメルクマールが音声学の知識である。プロである限り音声学の知識は不可欠であり、アマであっても音声学の知識のあるなしで、言語研究の領域は狭くなってくるうえ、正しい理解のための一つの基盤が失われることになる。
このくだりを読むに至って、ぼくは言語学について専門領域に入るのは今のぼくにはムリだと心折れてしまったほどだった。
言われてみれば確かに、文字のない民族は多数あれど、発話でコミュニケーションしない民族はいないだろう。
人間の言語は発話のほうが先にできて、文字はその後に出来るものなのだから、どちらが言語学にとってより重要なものなのかというのは明らかな事だったのかもしれない。
音声学は、世界中にある言語の発音(音素だけでなくアクセント、強弱、相対的長さやリズム)を正確に聞き取って記録し、その記録を読んで正確に再現する事が必要となる。
著者によれば、音声学は自然科学と呼ぶに相応しい精密さを備えており、具体的な成果も上がっている分野なのだという。
この音声学を学ぶのは「座学」や「独学」ではムリで、千野栄一はこれを水泳を習う際に「座学」や「独学」で習うようなものだと表現している。
つまり、音声学は実践学でもあって、そのスキルを習得するためには実際に練習してみて身に付けなければならないものなのである。
泳ぐときの体の動かし方を座学で完璧に理解したからといって、実際に泳げるようになるわけではないのと同じ事で、音声学も誰か師匠についてトレーニングしなければならないのだ。
音声学の学習が終了したときはこの地球上のありとあらゆる言語の音が聴き分けられ、発音でき、記述できるはずだが、そのような状況になる可能性はごく限られた才能に恵まれた人だけにあるにすぎない。
この音声学は言語学の分野では非常に重要になってくる。言語学が科学として成り立つ基盤の一つになっているほどである。これによって例えば、言語学では非常に重要な言語調査などの研究を行う事ができるようになる。
言語学のあらゆる分野の中で最初から存在し、現在も重要な部分を占め、現存する莫大な数の言語からみて、今後も依然として重要な部分であり続ける分野が言語調査である。言語調査の目的はその言語の記述にある。
ソシュールは確かに、近代言語学を切り開いた先駆者であり、その後の言語学だけでなく西洋思想にも大きな影響を与えた人物かもしれない。
だが、ソシュールを理解した所で、それで近代言語学を理解したという事にはならないのだろう、という事が読者諸氏にもご理解頂けたのではないだろうか。
ぼくが今年ソシュールの『一般言語学講義』を課題書としたのは、あくまで西洋思想史の観点からソシュールが重要だったからだ。
ソシュールについてはあくまで構造主義や記号論への影響と言う観点から考えるのがぼくにできるせいぜいで、言語学についてまでも理解していて言及できる等といったウヌボレや出しゃばりまでは慎む事にしなければならないだろう。
◆◆◆
ところで地球上には一体いくつの言語があるのであろうか。三千五百は数え上げた。ほかに名前だけ分かっている言葉があることが分かっていて、言語名以外の情報がない言語が、なんともう三千五百ある。そして、まだ、千や二千の言語があるのであろうから、ざっと一万弱ということになりそうである。
言語研究の難しさの一つが、この言語の種類の多さというものにある。
例えば数十か国語、数百か国語の言語を習得した人でさえも、地球上にある言語の数パーセント程度しか理解できていないという事になる。
だから、自分の知っている範囲の言語から帰納して「言語とは〇〇である」と言う理論を導いたとしても、自分の知らない莫大な数の言語の中から例外が見つかればその定義は使えなくなってしまう。いわゆる「ヘンペルのカラスのパラドックス」に常につきまとわれているというのが、言語学の難しさの一つなのかもしれない。
世界にはまだ調査中の言語もあり、更にはピジン諸語、クレオル諸語といった現在進行形で新しく発生してきてる言語の研究も未発達段階にあるという。
そういう状況であるから未だに地球上の言語を概観して「言語とはこれこれこういうものだ」といった結論を述べる事は簡単ではない。
例えば、われわれが英語やフランス語を学んでいると、彼我の差からしばしば「ああ、言語というものはこういったものなんだな」という気づきを得る事がある。
しかし、こういった気づきは単にわれわれの「日本語」というパースペクティブから英語やフランス語を眺めた時に気付く事を言っているにすぎない。
これによって「言語」の全体像を理解したつもりになってしまうというのも、わりとありがちな誤解ではないだろうか。
このようにある言語を通して他の言語を観察し研究する分野を、著者は「対照言語学」と言っている。
この対照言語学は翻訳などの問題にも関わってくる事であるにもかかわらず、今まであまり発展してこなかったのだそうだ。
つまり、しっかりとした理論が確立していないままの状態で、今まで様々な言語が翻訳されてやり取りをされてきたという事なのである。
言語学には種々な分野があり言語のいろいろな面を様々な角度から研究している。ある分野の研究は非常に進んでおり、すでに多くのことが解明されているのに反し、ある分野の研究は遅れていて、基本的なことすら分かっていない、この進んでいる面と遅れている面とのアンバランスが障害となって、現在いろいろな面でその害が現れつつある。
翻訳についても、外国語教育についても対照言語学のような理論研究は必要であるにも関わらず、理論的な裏付けがなされていないままに実用的な部分が進行してしまっているという現状があるという。
本稿は冒頭から「難しい、難しい」といった事しか言っていないように思えてくるが、初学者が分かったような事を言うよりかは幾分マシというものだろう。
ある分野の学問に対する理解として、正しくその学問の「困難さ」を学ぶ事は間違いではない。何よりぼくが本書から学んだ事の多くは「言語学を学ぶ上での"困難さ"の在処はどこにあるのか」であったようにさえ思えるのである。
◆◆◆
さて、千野栄一『言語学を学ぶ』を一冊読めば分かるような事をいちいち書くのは屋上屋を架すようで心苦しいが、いちおうぼく自身にとってのメモがわりに、そして本書の情報をアップ・デートする意味合いでも、以下本書で挙げられている推薦図書のうち幾つかをピックアップしてみる事にする。
本書の前半は本格的に言語学を学んでいきたいと考えている人向けのブックガイドとしても優れているが、本書が書かれた時期が2002年という事もあってか、記載されている書籍の出版年がけっこう古い。
著者としては、年月が過ぎても内容が古びないレベルで基礎的な情報が載せられているものを選んでいるようなのだが、何より問題なのはその多くが「品切れ」と書かれていて、書店で手に入らないものが多いという事だ。
と言う事で、いちおうぼく個人が本書を読んで「読んでみたい」と思った書籍の中で、現在比較的入手しやすいものに関しては、AMAZONなどのネットショップをチェックして在庫や金額が分かるようにここにリンクを貼っておくことにしたい。
・エドワード・サピア『言語―ことばの研究序説』(岩波文庫)

本書ではほとんど手放しで褒められているほどの推薦図書である。
エドワード・サピアは20世紀アメリカ構造主義言語学を主導した天才言語学者と呼ばれる人物で、本書でも近代言語学を築き上げてきた人物の一人として挙げられている。
そのサピアの著書の中でも、著者も「入門書というより必読書」と言い、書かれてから半世紀以上も経っているというのに今でもその価値が失われていない、内容的にも古びていないというほどの名著なのだという。
こと言語に関する概論書の中でも、これほど評判の良い本も他にないそうで、これに比べればソシュールの『一般言語学講義』の内容さえも古さを感じてしまうほどなのだそうだ(これはソシュールに問題があるわけではないのだそうだが)。
この本の欠点の一つは「入門書としてはいささか高等すぎる」というそうなので、気軽に読めるようなものではないようだ。
サピアの『言語―ことばの研究序説』の良い所は岩波文庫という入手しやすい形式で出されている事で、今でもネットショップを探せば割と簡単に見つけ出す事ができる。
・ピーター・トラッドギル『言語と社会』(岩波新書)
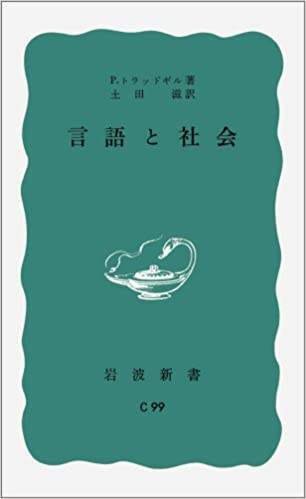
これも若干、古い本だ。
著者はのトラッドギルはイギリスの社会言語学者であり、言語調査も行っている研究者である。
「社会言語学」というのは、千野栄一によれば「社会によっていろいろな影響を受けた言語を研究する」学問なのだという。より詳しく言うと「言語伝達の社会的条件、言語と社会との関係、言語使用者と言語の関係を研究する言語学の一分野」という事となるらしい。
「訳者あとがき」で「私たちが知らなかった、あるいはついぞ気がつかなかった、言語についての驚くべき一面が、やさしく、しかも実証的に書かれてある」と言っているのにも興味がある。
とにかく言語学に興味が惹かれる理由の一つは、近現代言語学は一般の人の想像を遥かに超えて発展しているために、しばしば一般人が知ると意識が覆るような驚きを感じると言われている点にもある。
トラッドギルの『言語と社会』が良いのは、新書という入手しやすい形式で出版されているという所にもあるだろう。ネットでも割合、簡単に見つける事が出来る。
新書と文庫は、いつでも初学者にとって心強い味方である。
・南不二男『現代日本語の構造』(大修館書店)

やはり自分としては、自国語の謎を追求するというのは興味のある所である。
多くの言語研究者も、様々な外国語を研究した後、再び自国語の研究に戻って来るそうである。何より自分にとって最も良く使い、最も良く知っている言語であるからこそ母国語を研究する事には意味があるのだろう。
上にも書いたように地球上には一万以上もの言語が存在しているというのにも関わらず、人間は母国語以外の外国語を一つ習得する事にも難儀するのである。
母国語は、空気の様に自らの周りを満たしており、子供の頃からそこにドップリと浸かって生活をしている。だからこそ、なかなかそこから距離を置いて客観的に見る事ができない。
母国語は、難しいのだ。
多くの言語学者が、他言語の研究を経て母国語に戻ってくる理由もそういったわけがある。
さて、そんなわれわれの母国語を理解するのに適した入門書はと言えば、千野栄一『言語学を学ぶ』では南不二男の本が紹介されている。
南不二男の専門分野は日本語なのだそうだが、ここに挙げたものはあくまで「言語学」の立場から「日本語も言語のうちの一つ」だというスタンスで書かれているというのが興味深い。
◆◆◆
