
◆読書日記.《永野潤『図解雑学サルトル』》
※本稿は某SNSに2022年1月18日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
サルトル解説本の4冊目。永野潤『図解雑学サルトル』読了。
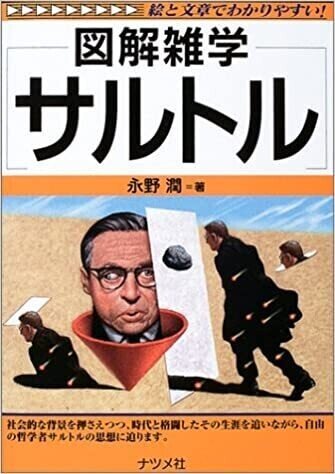
哲学研究者によるサルトルの正当な入門書。先日も書いたが、これは今まで読んだサルトル解説本の中で最も分かり易く、文章も平易で読みやすい。サクサク読めた。
学生でも読めそうなのでサルトル研究に入る第一ステップとしての入門書としてオススメできる内容。
今まで読んだサルトル解説書としてはこの永野潤『図解雑学サルトル』を第一ステップ、第二として澤田直の『新・サルトル講義』、第三段階として村上嘉隆の『人と思想34 サルトル』と言ったように読み進めるのがベストと思われる(ポール・ストラザーン『90分でわかるサルトル』は読まなくていいかも/笑)。
本書の特徴は何といってもサルトル思想の全体を一貫して「関係の哲学」という視点から説明していくという内容にある。
サルトルの思想は現象学の影響の元にはじめられた実存主義的スタンスからスタートする「個」を考えるものであった。
だがサルトルにとって「個」は常に個の外に自らを投企していき、「自らを乗り越えていく個」であったと言えるだろう。
だからこそ、サルトルの個は常に独我論的状況ではなく、外に乗り越えられている個であった。
実存的不安を抱えた『嘔吐』のサルトルは、モノとの関係性によって実存というものを考えていた。
人間には「意識」が「モノ」のようにあったり、「私」が「モノ」のようにあったりするものではない。
現象学的に言えば意識は常に「志向性」を持つ――即ち「何ものかについての意識」であった。
サルトルはそういった「志向性」を「意識とは世界との「関係性」である」と捉えるのである。
意識というものは「モノ」のように「ある」ものではなく、意識とは「関係性」それ自体を言うのだと。
つまり、サルトルは「私の意識」というものを否定しているのである。
「私がコップを意識している」とは考えず、「コップについての意識」と「"私"についての意識」という関係性のみがあるという考え方である。
何かしら本質的で固定的な「私」があるわけではなく、世界との関り方そのものが人間の在り方を決めるのだと。
その後サルトルは『存在と無』によって世界との関りを考えるようになる。
「人間は自由の刑に処されている」
人間は否も応もなく「自由」が与えられているのだ、というのである。
人間は生まれてきた環境によって様々な形で拘束を受けているようにも思えるが、サルトルが言う「自由」というのは、そういった「状況」の中で、自らがどういう「選択」をしてどういう「決断」をするかというのは「自由」なのだと考えるのである。
そういう「状況」に受動的に流されていくのも、その人の「選択」した自由であり、その「状況」に影響を与えて自らの関わる社会を変えていこうと試みるのもその人の「選択」した自由である。
本書で説明されているサルトルの「自由」とは、例えば牢屋の中に囚われている人間が、牢屋から出獄されて「自由になる」という事を言っているのではない。
牢屋から出ようと試みるか出ずにそのまま牢獄に囚われたままになるか……と自分がどういった人間"である"のかを自分で自由に決断する「自由」である。
人間は、現在にも過去にも囚われず、常に現在の自分から脱出して、自らを未来に向けて投げかけている「投企」をしている……とサルトルは考えるのだ。
だが、何をしても自由で何の責任もない……というわけではない。
自らの決断には「責任」が付きまとう。それが「自由」というものだというわけである。
サルトルは、人間は自由な存在であると同時に、人間はだれしも自分の生きる時代の「状況」に拘束されている、とも言っている。
サルトルは第二次世界大戦に従軍したが、人間はいかに戦争から逃れようと、戦争から「無関係」ではないのだ。
戦争に従軍するのも、戦争から逃げるのも「戦争と関わっている」と言えるのだ。
だから、サルトルからすれば第二次世界大戦はサルトルが従軍しようと従軍から逃れようと、サルトルの責任とは関係のない戦争ではないと考えた。
どのように関わろうと「戦争」という状況は否応なくサルトルと関わっているのである。
サルトルにとってそういった「状況に積極的に関わる」という事は「戦争に従軍する」という意味ではない。
積極的に政治活動を行うという事でも戦争から逃げて他国に亡命するという事でもない。
サルトルが「戦争に積極的に関わる」とは、人間はその時代の状況から逃れる事なく関わってしまっているという事を直視し、その状況の中で自分がどのように行動していくのか、という事を自ら能動的に「選択」していくという事なのである。
それがサルトルの言う「アンガジュマン(社会参加)」なのである。
戦場で戦うというのもアンガジュマンであるとするのならば、「戦争から逃げる」という選択肢を選ぶというのも、その人なりのアンガジュマンなのである。
サルトルは自らのアンガジュマンとして、ボーヴォワールやメルロ=ポンティ、レイモン・アロンらと共に雑誌『現代』を創刊し、自ら編集長になり論説委員になり、その時期の状況をどう見てどうあるべきか積極的に発言するようになる。
こういったサルトルの姿勢が後に「普遍的知識人」といったイメージを作り上げる。
「普遍的知識人」というのは、自分の専門分野であっても専門外の事柄であっても、常に積極的に自らの考えを開陳して発言をする知識人の事を言う。
サルトルは晩年、自らの専門の中に閉じこもってタコツボ的に自らの専門領域から出てこない「専門家」は「知識人」ではないと考えたのである。
例えば、ただ単に核技術に関する専門知識を有していてそれを研究している人間は「専門家」や「研究者」であっても「知識人」とは言えない。
彼らが核兵器の恐ろしさに気づき、核技術の兵器利用を批判する政治的発言を行って初めて彼は「知識人」となる……それがサルトルの考える「知識人」であった。
サルトルにとって「専門家」とは、個に閉じこもって関係性を拒否する存在だと考えたのだろう。
サルトルは常に、閉じた個を打ち破って積極的に世界と関わっていく「関係性の哲学」を実践していた思想家だったのである。
サルトルは知識人であろうとした。
しかし、現在サルトル的な意味での「知識人」というのは、フーコー以降はほとんど見られていないと言われている。
ぼくが思うに、サルトル的な知の番人としての知識人というのは、現代日本ではどこか「胡散臭い存在」になってしまったのではないかと思う。
それは例えば、現代日本において「知識人」的に専門外の事でも積極的な発言を行っているタイプの人間が橋下徹であったり西村博之であったり小林よしのりであったりといった、メディアに乗って煽情的な極論を繰り返し「刺激的な娯楽物」となるような輩――つまりは「芸人」的な「偽の知識人」ばかりが目立ってしまっているからだろう。
サルトルの晩年は様々な理由から、その影響力は低下し誰からも見向きされなくなった。
それは思想界では構造主義が主流になってきてサルトルの実存主義が「流行遅れ」になったからだし、世間的にもサルトルが共感を示していた共産主義が斜陽になっていったという理由があった。
彼の発言自体にも、誤解や間違いも普通に見られたというのも大きいのではないかと思う。
ぼくがサルトルをあまり好きではないのも、思想・哲学の考え方を多く利用しながらもそれを結構雑に流用していたからだし、「普遍的知識人」といった彼のスタイルもどこか胡散臭さを感じてしまうからでもあった。
また、ソ連を擁護したり(スターリニズムは批判していたが)マオニストの若者たちを擁護していたりといった晩年の行動にもどうにも共感しにくいものがあったためでもある。
だが、サルトルはそういった事も気にせず、とにかく間違えても良いからその時期の自分のベストの「選択」をして、出来る限りに世界と関わっていこうとしていたのであろう。
サルトルの思想は、個である実存から出発して自分の外へ果敢に自分を乗り越えていき、世界と関わり、世界と関わる上で無視できない「状況」を考え、さらに個の集まりである「集団」へと「関り」への考えを発展させていった。
それは本書の著者が言う通り、サルトルの思想が常に「関係性の思想」であったからなのであろう。
