
◆読書日記.《エトムント・フッサール『デカルト的省察』》
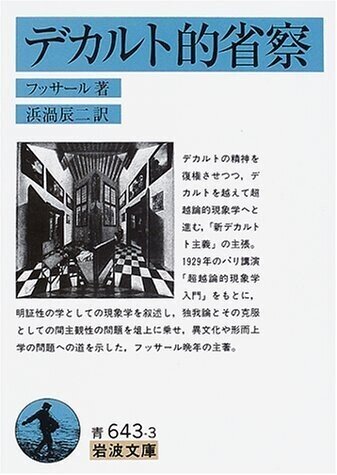
<2019年11月26日>
エトムント・フッサール『デカルト的省察』読み始めましたよ♪
ぼく的には今年のメインとしていたフッサール研究はこの本でラストにしようと思っている。もう11月になっちゃった事だし、そろそろ読んでおこうかと。しかし、一年の研究成果が出ているのか、今のところ割とすんなり読み進められている。
一日でほぼ半分ぐらいのところまで読んだ。
これはぼく自身がだいぶフッサール用語とその概念に慣れたというのと、本書が相変わらず超越論的現象学の「原理論」を繰り返している内容だということも手伝っている。
ぼくとしては、本書を今年一年のフッサール研究の総復習といった感じで読み進められている。
◆◆◆
フッサールの現象学を勉強するときの大きな壁のひとつが「超越的」と「超越論的」という考え方の違いだ。
この専門用語について専門家はどういう説明をしているのか、岩波文庫版『デカルト的省察』の訳者・浜渦辰二氏の説明を引用してみよう。
「『超越論的』と『超越的』とは、対をなす相関的な概念である。『世界の超越性』に属するものは『超越的』と呼ばれ、その根拠に関わるものは『超越論的』と呼ばれる」
この説明では正直、哲学初心者やフッサール初心者には、どういうものなのか全く分からないだろう。
多分ぼくも、フッサールを勉強してない状態でこの文章を読んでも何のことやらサッパリ分からなかったと思う(笑)。
この両者の区別については竹田青嗣&西研さんの「現象学研究会」の人たちの著書を読むと割と分かり易く説明してあるのでお勧めだ。
これを理解するには西洋哲学の昔からの認識論を分かっていないと難しい。
西洋哲学の認識論の古典的問題には「主客の一致」というのがあって、それは我々が見た"もの"のイメージと、実際の"もの"の実態とは、一致しているのかしていないのかと言った感じの問題だ。
人間はどこまで行っても"もの"の情報を五感によって受け取っているだけの「主観」に過ぎない。
人間は自分の脳の外に出て、自分の知覚したものと、実際の"もの"とが同じものなのか確認するすべがない。
――このような「疑惑」がある理由の一つに、我々がしばしば「夢」を「実際に体験している事」と錯覚しているという問題が挙げられる。
我々が頼りとしている五感は、しばしば我々を「裏切る」のだ。
人間の五感は、「夢」という形であったり「錯覚」とか「幻覚」などと言った様々な形で我々の知覚を裏切るのである。
では、果たして我々は自分の目の前にある"もの"を、ちゃんと「そこにある」と言い切るすべがあるのか。……斯様に我々はいつまで経っても自分の脳の中から出られないのである。
――といった感じの主観と客観に関する「疑惑」が「主客の一致」という西洋哲学の古典的問題である認識論的なものだと思って頂きたい。
で、自分の脳の外にあるものは「確実に存在している」と前提して物事を考えるのが「超越的」な考え方の立場と言う事となる。
それに対して「超越論的」というのは「脳の外に外部があるかどうかは一端考えないでおこう」という立場で物事を考える事となる。
換言すれば、例え我々の意識が映画『マトリックス』状態になって騙されていようと、目の前の現実が実際にあるものなのかそれとも幻なのかという判断は横に置いておいて、それを「私達の脳内で起こっている現象だ」という前提に立って考えようじゃないかという事。
「超越」と言っているのは何を超越しているのかと言えば「脳の中を越えた、脳の外のこと」を「超越」と言っているのである。
因みに、脳の中を超越した外の世界にある"もの"の事を「超越物」とか「もの自体」とか言ったりする。
科学や心理学はこういった「超越物」がある事を前提にして研究をしなければ研究が進まない。
だからそれらの学問はフッサールから言わせれば「超越的」な立場で物事を考える学問だということになる。
そこには「主観」はないかのようで、神様のようなスタンスで、空中から俯瞰しているかのような立場で物事を考える見方。
それに対して、我々が五感によって知覚している様々な脳内現象を、脳の中のみで考えていくのが「超越論的」な立場で物事を考えるフッサールの「超越論的現象学」の立場なのだ。
この「超越論的な立場」というのは、何かに似ている。
デカルトのいわゆる「コギト‐エルゴ‐スム(我思う、ゆえに我あり)」である。
知覚は我々の認識を裏切る。だが「視覚」という「脳内現象」が脳内で起こっているという事は間違いない。
「"見ている"と私が感じている」という「感覚が(脳内に)起こっている」のは間違いではない事実である。
「超越物」が実際にあるのかどうか、脳内に閉じ込められた我々には分からない。
だが、その脳内で起こっている脳内現象を「起こっていない」などとは言えない。
だから、それは自分にとって自分にだけ分かる「真実」なのだ。
フッサールはこのようにデカルトの「我思うゆえに我あり」を展開して超越論的現象学を構築する。
フッサールの超越論的現象学の発端となる発想はデカルトの「我思う、ゆえに我あり」を批判的に継承した考え方なのだ。
だから彼の晩年の思想をまとめた著書に『デカルト的省察』という題名が付いているのである。
<2019年11月27日>
エトムント・フッサール『デカルト的省察』読了。
「超越論的現象学」を打ち立てた思想家フッサール晩年の主著。
とりあえずフッサールの主著はだいたい抑えたので、今年のフッサール研究はこれで締めくくりとすることにしよう。まだ読んでないものもあるが、今後余裕を見て読んでもいいと思っている。
本書の構成は第一省察~第四省察までの前半部でおおよそ『イデーンⅠ』までに築き上げた静態的な現象学が語られ、第五省察以降はそれに加えて動態的な発生的現象学と、「間主観性」のテーマが取り上げられて一通り説明されるという形になっている。
「間主観性」の問題とは「他者」を現象学的に考えると言う事だ。
超越論的に「主観」しか持たない己の世界の中で、「他者の持っている主観」というものは一体どういうものなのか。
また、他者の見ているものと自分の見ているものは同じなのか違っているのか。
自分と他人との考えている事はどこに共通点と相違があるのか。
そういういった「他者との比較」から始まる疑問が「客観的思考」というもののスタートに繋がる。
そのようにして、人間は人生経験を重ね他者と交流していく事で「他の人間の持っている自我のある認識主体=他我」と「自我」との共通点がどれほどあるのか、という部分を意識的にも無意識的にも延々と探っていく。
それらの共通点への志向性(=ノエシス)が構築されていくことで、「常識」や「客観的なもの」(=ノエマ)が現れる。
それによって同時に「他者」というものも、自我の中で構成されていく。
つまり「常識」と言われているものや「客観的なもの」というものは、多くの他者との間に交わされる、(自我の)主観と(他我の)主観との共通点という事ができる。
その共通点への確信が「常識」というものに構成される。
我々が普段信じている「常識」や「客観性」といったものは、主観(自我の主観)と主観(他我の主観)の間で行われる確信構造によって築かれていく――それがフッサールの考えていた「間主観性」だと言えるだろう。
あと、今回本書を読んでいて、他者を理解する間主観的な「自己移入」というのは、ある種の原初的な「アナロジー思考」なのではないかという印象を受けた。
つまり、フレイザー卿が『金枝篇』の中で示そうとしていた、人間の太古からの類型的な思考のクセである「類感呪術的思考=アナロジー思考」というのは、そもそも人間が「他者」を「単なる動く他の生き物だ」という認識ではなく「自分と同じタイプの生き物だ」=「他我」と感じる原初的な思考に紐づいていたのではないかと思うのだ。
人間が「"似ている"というのは、それだけで全くの無関係なものではなく、何かしら重要な意味があるのではないか?」と考える思考的な類型を根強く持っている理由は、そもそも人間が「他者」を「自分と似たタイプの生き物だ」「自分と似たタイプの生き物と言う事は、自分と同じ"我"を持っているのではないか」と見る、幼児期における原初的アナロジー思考を展開させていたことの名残があるからなのではないだろうか。
だが、フッサールは本書においては、人間が他我を認識するための「自己移入」というものは、「アナロジーではない」とハッキリ否定している。
これをフッサールは、アナロジーのような推論的な思考ではなく、ある種の志向作用としての「統覚」だと言うのだ。
以下、フッサールの文章を引用してみよう。
「ここで言う統覚とは推論ではないし、思考作用でもない。私達が眼前に与えられた対象を、例えば眼前に与えられた日常世界を直ちに把捉し、確認しつつ把握し、一目でその地平を伴った意味を理解するのは、この統覚においてである。そして、このような統覚は全て、類似の意味を持ったある対象が初めて構成された『原創設』の場面を志向的に遡って指示している。(略)こうして日常の経験は全て、類似の意味を持つものとして対象を予測的に捉えるという仕方で、根源的に創設された対象的な意味を新しい場面へと類比を通じて転移するという事を含んでいる」(フッサール『デカルト的省察』第五十節より)。
フッサールはあくまで「志向性」にこだわるのである。
ここでぼくがフッサールのほうに考え方を寄せてみれば、これは逆に人類の持っているアナロジー思考=類感呪術的思考のほうが、アナロジーではなく「統覚」の働きを持っているとも言えるだろう。「統覚」のほうが人間の思考の原初的なクセなのかもしれない。
発生的現象学の立場として自我と他我の発生を考えるというならば、もう一つ抑えておきたいと思うのが、人が幼児期の原初段階に発生させる「自我」の確立と「他我」の発見だ。
この事でぼくが真っ先に連想するのは哲学者であり精神分析のジャック・ラカンが提唱した「鏡像段階」という考え方である。
ラカンの「鏡像段階」へと至る道を、フッサール用語で説明してみよう。
幼児期の人間は、ばらばらだった肉体の感覚(=ノエシス)がひとつに統合されること(=ノエマ)によって、「自分」と「その他」とを分ける輪郭線を認識する「鏡像段階」へと進む。
肉体感覚を統合させて「鏡像段階」へと進んだ人間は、「私」という「自我」に目覚め、そこで初めて自分の肉体と似ているが、自分ではない存在(=他者)に気づき、そこから「自分以外にある自分と似たような認識主体=他我(アルター・エゴ)」の存在を理解し始めることとなる。
つまり「鏡像段階」もフッサール的に考えれば、人間の原初的な「統覚」という志向性の働きによって生まれる認識だと説明できる。
フッサール思想は前期~中期~後期によって微妙に考えを変えているのだが、後期の発生的現象学でも一貫しているのは人の「志向作用」であり、それによる「統覚」という考え方なのだろう。
