
◆読書日記.《マルティン・ハイデガー『存在と時間』(岩波文庫版)上中下巻+副読本1冊――シリーズ"ハイデガー入門"9~12冊目》
※本稿は某SNSに2020年9月5日~10月22日のあいだに投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
<2020年9月5日>
ハイデガー研究の9冊目にして本丸と目していたハイデガーの『存在と時間』上中下巻を、やっと読み始めた。
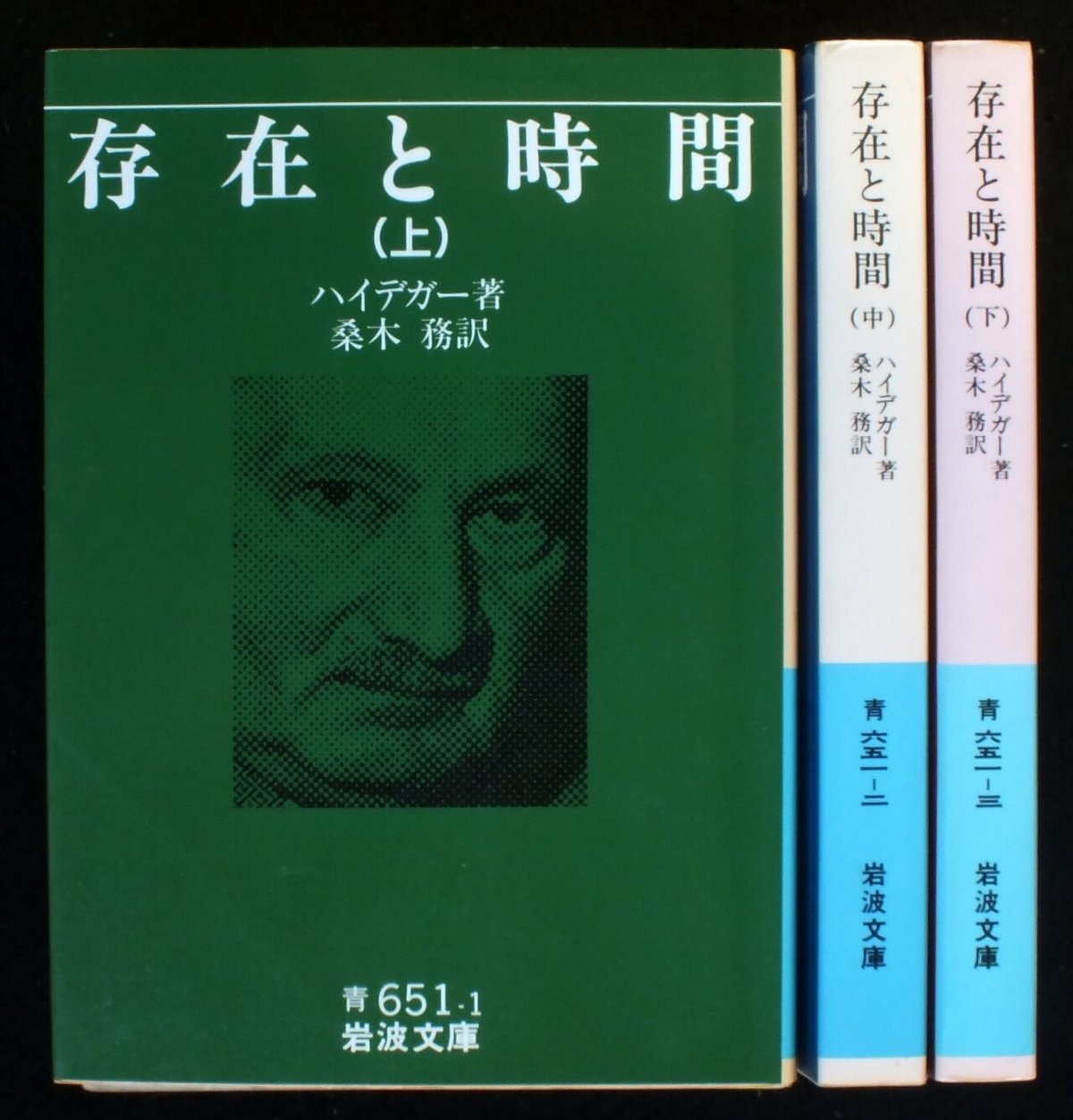
今回はこの『存在と時間』の副読本として、アメリカのノーザン・イリノイ大学哲学科主任教授マイケル・ゲルヴェン教授による注釈書『ハイデッガー『存在と時間』註解』を並行して読む事とする。
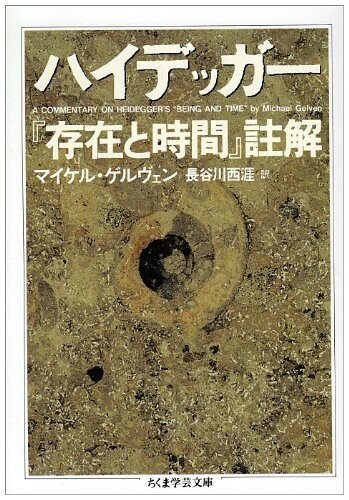
ゲルヴェン教授の本はアメリカでも訳書が出回りだした頃に出版された、学生や一般向けに書かれた註解書といった性格のものらしい。
やはり『存在と時間』は英訳でも難解で、しかもハイデガーは伝統的な西洋哲学の概念を、伝統的な哲学用語を"使わずに"書こうとしたために翻訳問題としても結構厄介な本だったらしい。
ゲルヴェン教授の本が副読本として適切なのは、『存在と時間』の内容を一節ごとに解説しているからだ。
『存在と時間』の解説書は内容を大づかみで説明しているものが多いのだが、副読本として重要なのは部分部分ごとの詳細な解説がある事で、それによって誤解ないように読み進めることが出来る。
これはぼくがカント『純粋理性批判』を読んだときも、ヘーゲル『精神現象学』やマルクス『資本論』を読んだときも同様に利用した方法だ。
特にハイデガーの『存在と時間』は難解で誤解・誤読をしやすい本だと言われているので、いちおう用心してこのような補助輪を付けながら読もうと思っているのである。
マルクスやフッサールを勉強した時は、事前に入門編的な解説書は最低十冊以上は読んで、複数の学者のあいだに共通して存在する基本的な認識を作り上げてから本丸に臨んでいた。
だが、どうも今回ハイデガーについてはそのプロセスが非常にかったるい。ハイデガーはどうもぼく好みの思想家ではなかったらしい。
だから、という事もあって早々に事前準備は切り上げて本丸に乗り込もうと考えた訳である。
『存在と時間』の岩波文庫版3冊+副読本1冊で計4冊分なので、恐らく見込みとしては2~3週間で読了できればいいかな、くらいの目安で考えている。
◆◆◆
ハイデガーが主張する伝統的な西洋的な思考というものは、例えば「〇〇がある」と言った場合、従来の科学的思考や哲学的思考では、この対象物である「〇〇」のほうを考察する事がメインとなってきたという認識である。
それに対してハイデガーの「存在への問い」というものは「がある」のほうを考える学なのだ。
これをハイデガー的に言えば「存在者が存在するという事は、どういう事なのか?」という問いになる。
そういった「存在する」という事の意味を追及するために、ハイデガーはまず存在そのものではなく、存在そのものと接して、考えて、味わっている「現存在(人間)」を分析する事から始めたのが『存在と時間』の内容だ。
これは「現存在分析」をしてから「存在分析」へと向かうという構想で書かれたのだが、実際はその全体構想の三分の一の分量で中断されてしまった。だからこの本は「人間の分析」までで終ってしまっている。
だから「人間とは、生きるとは何か?」といった実存主義的問題を扱っていると勘違いされたのだ。
我々は普段、例えば「目の前にコップがある」といった場合の「"がある"とはどういう意味か?」などと考える事はない。
当たり前すぎて、考えないのである。
これは我々が経験したり学習したりする前から既に了解しているア・プリオリな認識だ。
そういった当たり前すぎる問題を「何故当たり前なのか?」と考えるのは、確かに現象学的な考え方だと言える。
つまりは、ハイデガーの「存在への問い」は、ある意味では現象学的な態度だとも言えるかもしれない。
だが、彼の追及方法はフッサールの所謂「超越論的現象学」とは違った方法にしか、ぼくには見えない。『存在と時間』を読む上では、その辺を見極めたいとも思っている。
<2020年9月8日>
「現存在(人間存在)が、それに対してこれこれの態度をもつこどができ、なおかつつねになんらかの態度をとっている当面の存在自体を、わたしたちは「実存」と名付けます」――ハイデガー『存在と時間』上巻(岩波文庫版)P.30より
我々は否応に関わらず、いつの間にか生きてこの人生を送っている。
何故か分からないが、それでもいつの間にか「生きる」という仕事を遂行してしまっているのが、我々人間という存在だ。
だが、我々が他の生命体と違っているのは、その「いつの間にか」というこの不思議な事態に気付く事ができるという事だろう。
我々は「存在している」。が、何故「存在している」のかは分からない。
だが「何故存在しているんだろう」という所に疑問を付す事ができる生き物というのは、我々人間以外にいないのである。
ハイデガーは"そこ"に、他の生き物に対して優越する人間のアドバンテージがあると考えた。
我々は意味は分からないが「存在している」。だが「存在している」という言葉の意味は分かっている。
「存在している/していない」は、我々は容易に判断している。
つまり理論的にではないものの、我々は「〇〇がある」という事を理解しているのだ。
「存在している事」という事の意味を知っている唯一の生物が人間なのだ。
人間には、そういった特徴がある。
だから、我々は自分に対して自己反省的な視線を向ける事が出来る。
「自分はどうあるべきか?」「自分はどういう存在か?」「自分はどう生きていくか?」と自分の態度を了解し選択するのも人間の特徴だ。ハイデガーはそういった人間の実存的な意識の面に注目するのである。
では「存在している存在」である我々人間は、「存在する」という事をどう見ているのか。
「存在」が「存在する」をどう見ているのか。
それを分析するのが「現存在の存在分析」という事となる。
そういう存在の持つ「存在」という事の意味を理解する事で、ハイデガーは「存在」そのものの分析に繋がると考えた。
そして、その「現存在の実存論的分析論」を書いたところまでで中断された書が『存在と時間』という本だったのだ。
そういう経緯が分かれば、これをWWⅠ後のアプレゲール青年らが「我々はどう生きるべきか?」という内容の本と勘違いしてしまったというのも、あながち分からない事もないと思える。
ハイデガーの『存在と時間』を読むうえで最初のハードルとなるのは、ここらへんの「存在者」や「〇〇がある」「現存在」「実存」等という、「存在」という概念に関わるビミョ~な意味の差を理解しなければならないという点にあると思う。
そういったビミョ~な意味の考え方をドイツ語とラテン語独特の言い回しを使って説明するのだから、翻訳された本を読む身となってみれば、かなりツライだろう(ぼくの場合は事前準備のおかげで大分ラクしているが)。
「なるべくなら原著で読んでもらいたい」と主張する研究者が多いのも頷ける。
<2020年9月16日>
ハイデガー『存在と時間』、そろそろ上巻が読み終わりそうな所まで読み進めています。
ハイデガーの文体は――恐らく翻訳者の解釈でしょうが――どこか切々と訴えかけてくるようなニュアンスがありますね。
語りかけて来るようなですます調で、通常問題を提示するさい「これは〇〇でしょうか?」とする所を「これは〇〇ですか」と、まるで読者のほうに問いかけてくるかのような語り口を持っている。
やはりこれが木田元さんなんかが言っていった「黙示録的な雰囲気」を持った一種異様な厚みを持ってWWⅠ後のアプレゲール青年らに迫ったのかもしれませんね。
◆◆◆
ハイデガー『存在と時間』の「存在への問い」の「問い方」の第一段階として出て来るのは「現存在の実存論的分析論」であった。
現存在の実存論的な追及の仕方がその次の「存在への問い」に繋がっているという構想の元に、まず「現存在」の分析がある、というわけだ。
ハイデガーが「現存在の実存論的分析論」を行う際のもう一つの条件は「現象学」の方法を利用するという事だった。
これをハイデガーはさかんにフッサールを持ち上げて説明しているが、実はハイデガーの現象学とフッサールの現象学は明らかに違っている。ここにはハイデガーの欺瞞があったと言うべきだろう。
実際に、ぼくが現在『存在と時間』の副読本として読んでいるマイケル・ゲルヴェンの著書にも、フッサールの現象学との違いをはっきりと明記している。
彼の現象学はカントの提唱したものでもヘーゲルが『精神現象学』の際に用いた概念でもなく、ましてやフッサールの「超越論的現象学」でもなかった。
ハイデガーが『存在と時間』の際に用いた現象学はいわゆる「解釈学的現象学」と言われているものだそうで、この方法論には結構あれこれと疑問が付されているらしい。
まず、第一にハイデガーの主張している現象学というものは「事柄それ自体を純粋に見て事柄そのものに語らせる」ものだったと言われている。
これをハイデガー自身の言葉で記せば「自分を示すものを、それが自分みずから自分を示すように、それ自身から見させること」となる。
しかし、ハイデガーの方法論は同時に解釈学的なスタンスもとるという。
事柄についてそれ自身何の解釈も付されない剥き出しの事実というものはない、というスタンスだ。
一方で「事柄それ自体に語らせる(=現象学的)」でありながら同時に「"学"として自分の解釈を付す(=解釈学的)」というのは、マイケル・ゲルヴェンに言わせれば「このような事は矛盾とまではゆかずともあるジレンマを含んでいるように思われる」と説明している。
このジレンマについてもゲルヴェンは「矛盾とまではゆかない」という意味を次のような感じで説明するのである。
ハイデガーの「解釈学的現象学」は、決して自然科学的な問題に適用される事はなく、あくまで「実存論的分析論」として採用されるからこそ双方のスタンスが矛盾なく並立しているのである、と。
つまり、「観察する側(解釈学的スタンス)」と「観察される対象の側(現象学的スタンス)」が、どちらも同じ「現存在」である事という条件が重要なのだ。
この場合、純粋に語らせるべき「現象そのもの」は自分だし、それを主観的に解釈するのも自分だからこそ「解釈学的現象学」は「実存論的分析論」のみで成立する。
ハイデガーの「解釈学的現象学」と「実存論的分析論」というのは、そういった関係性で成り立っているわけだ。
そしてハイデガーは次の段階として、実存論的に自分(=現存在)を分析した場合の「現存在」の在り方を「世界-内-存在」として説明する。
これをハイデガーは、1)世界の「世界性」とは。2)内・存在とは。3)現存在の存在とは。と三段階に分けて説明していく事となる。
『存在と時間』の上巻はこの「世界の『世界性』」を説明する所までの内容となっている。ここでハイデガーはやはり哲学史家としての本性を少しだけ開示しているように見える。
西洋の伝統的なものの見方としての存在論をデカルトからカントに至る時代に分けて説明していく事で「世界性の分析を際立たせる」という事をやっているのである。
ハイデガーは『存在と時間』の本来の目的であった「西洋の伝統的思想の超克」のための布石をいくつか打っているようなのだ。
ここではカントやデカルトの持っていた世界解釈を説明し、それら近代思想を批判する事で自分の提出する新たな視点を際立たせようという意図があったのだろう。
しかしこれはある意味ハイデガーらしく「野心的な試み」だったのかもしれない。「世界性分析」はもう少し続くが、今の所わりと興味深く読み進めている。
<2020年9月29日>
いまハイデガー『存在と時間』の中巻読んでますよ♪
なかなか時間かかってますけど、まあマルクスの『資本論』を通読したときは三か月くらいかかったから、まあこれぐらいのペースで順調と思いますかねぇ……。
しかし、マイケル・ゲルヴェンの『ハイデッガー『存在と時間』註解』がなかなか優れた注釈本で助かってます。
やっぱり入門書だけでは気付かない事がけっこうありますね。
『存在と時間』もいま現在第二篇・第五章を読み終えたばかりなんですが、割と懐疑的だったハイデガーの「頽落」「非本来的」という考え方についても、ハイデガーの説明の流れの中でやっと自分なりに納得のいくものとなってきました。
ハイデガーは「頽落」や「非本来的」という考え方に入る前に「現存在と語り、言葉」について説明しているんですね。
ハイデガーはその節で、人々の会話や発話というのは実存論的に考えるとどういうものなのか、というのを分析しています。
人は日常的に他人と何気ない会話をするときに、様々な「受け売り」や「伝達」や「伝言」を用います。
それは、その会話をしている両者が共に直に経験した事ではなくて、例えば「こう聞いたよ」とか「あの人がこう言っていたよ」とか「あんな事があったらしいよ」とか「あの人があれを見たって言ってたよ」とかといった内容の事がしばしばあります。
そう考えると、何気ない日常会話の中で交わされる情報というのは「私が」「直に」体験や経験したり、考えたり、感じたりとした事ばかりでなく、他から与えられた情報をバケツリレー的に伝達されていく事が非常に多いのではないか。
われわれは日々、テレビや本やネット等で得た様々な間接的情報をバケツリレーする。
その中に直接自分で試して、考えて、経験してみた情報がどれほど入っているのか。
不思議な事に、われわれはそういった多くの「間接的な情報」をどこか「事実」であるとものとして自然と受け入れています。
われわれの知っている知識の多くは、間接的に他からもたらされた情報なのではないでしょうか。
語られたこと自体は、広く円周を描いて〔輪をかけて〕ゆき、権威的な性格を帯びます。人がそういうから、そうなのだ〔事柄はそうだ〕という事になります。このような受け売りや吹きまくりにおいてはそのためにすでに初めから欠けている土着性が、全くの根無し草に昇華したときに、<おしゃべり>が構成されます。しかもこの<おしゃべり>は、声を出しての受け売りにかぎられることなく、書き物において「書きなぐり」〔拙文悪筆〕として広められるのです。受け売りは、ここでは<うわさ話>〔聞き伝え〕に基づいているというよりも、むしろ<拾い読み>で養われているのです。 ――ハイデガー『存在と時間』より引用
この<おしゃべり>というのは、他のハイデガー関連本では「空談」という単語で表現されることが多い考え方です。
この「空談」によって間接的な知識を広めていく原動力となっているのが「好奇心」で、これによって人々は自分が世界の遠くの事実までも把握しているし、様々な事実を把握できると考えます。
現存在は常に<現>に、すなわち相互存在の公共的な開示性においてあいまいに在り、"そこ"では最も姦しいおしゃべりと最も目ざとい好奇心とが、その「作業」を継続していて、"そこ"では日常的にすべてが起こりながら、実は何事も起こってはいないのです。このあいまいさがいつも、好奇心に対して、それが求めているものをそっと握らせ、おしゃべりに対しては、そのなかでなんでも解決されるような見掛けを与えるのです。
――ハイデガー『存在と時間』より
これがハイデガーの言っている「空談」「好奇心」「曖昧性」という「頽落」の三要素ですね。
よく考えてみれば、われわれが知っている事というのは自分が直に経験して確実に確かめたものではない、間接的に与えられた知識ばかりになっているのではないでしょうか。
このテーマを考える時は、ぼくはジャン・ボードリヤールの「奇書」ともいえる長編連載評論『湾岸戦争は起こらなかった』を連想させられます。
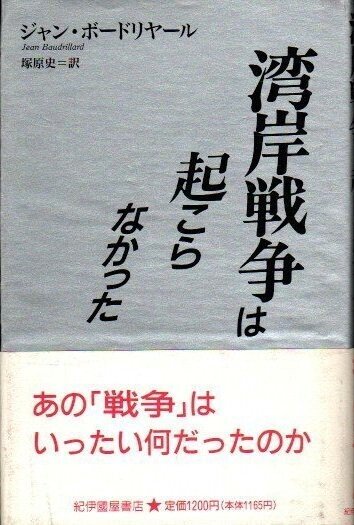
この評論は1990年の湾岸危機の際、社会学者のボードリヤールの「湾岸戦争は起こらないだろう」というタイトル論文から始まっています。
ですが、実際にこの湾岸危機は湾岸戦争へと発展した。ボードリヤールの予測は外れてしまったわけです。
が、その続きの連載からこの評論は奇妙な色彩を帯びていきます。
湾岸戦争が起こっている最中のこの続きの論文のタイトルは「湾岸戦争はほんとうに起こっているのか?」になり、最終的にこの戦争の総括をする論文では「湾岸戦争は起こらなかった」というタイトルで締められます。
これがもう、凄まじい言い訳にしか見えないのですが(笑)、その言い訳が抜群に面白い。
しかも、ほとんど怪我の功名的に、実にクラクラするようなテーマをボードリヤールはこの論文の中に見出します。それが湾岸戦争におけるメディア報道の在り方です。
湾岸戦争は、世界中の人々がかたずをのんで注視していたにも関わらず、その現場に立ち会って経験した人というのはほんの一握りでした。
第二次大戦のように世界中の人々が多かれ少なかれ経験した戦争ではなく、局地的な戦争であるにも関わらず、この戦争は世界中の人びとがテレビを通じて「経験した」。
だがその戦争で現れた姿は機銃掃射や爆撃によってバラバラにされたグロテスクな残骸ではなく、夜のバグダッドに飛び交うミサイルの光や、砂漠仕様の兵装をした米兵たちがイラクに展開している模様や、イラクの国民が空に機銃を打ち放って解放された喜びを表現している様子や、流出したガソリンによってドロドロになった海鳥たちの様子といったような――「カメラの外側」にいる何者かによって既に編集しつくされた映像でしかありませんでした。
われわれは、何者かの意図によって編集され尽くされた映像を見て「湾岸戦争を体験した」。――これは一体何なのか?
その体験は、ハリウッドで製作されたリアルな戦争映画を見たのと、どういった違いがあったのか?
「湾岸戦争は起こったにきまってるじゃんか!」とは、何を根拠に感じている確信なのだろうか?
ボードリヤールはこのように、全力をもってして自分の予想が外れた言い訳をする事で、読者の固定観念をグラグラと揺さぶってくるのです。
このわれわれの認識の不安定さというのは、ハイデガーの「空談」「好奇心」「曖昧性」という「頽落」を構成する三要素の考え方に通底しているのではないかと思うのです。
ハイデガーは、彼の「頽落」という考え方を「非本来性」と称していますが、これは度々『存在と時間』の中で否定的なニュアンスの言葉ではないという事を強調しています。
ハイデガーは、われわれの日常的な感覚や傾向というのはそういう風になっているのだという事を実存論的に分析しているにすぎません。
事実、そういう「間接的にもたらされている情報」によってわれわれは多くの正確な知識を得ているのですから、必ずしもこれが正しくない事ではないのです。
ですが、ハイデガーとしては、そういった日常的態度というのは、ハイデガーの求める「存在への問い」を追及する目的のためには、障害になる態度なのだと考えるわけです。
この「空談」「好奇心」「曖昧性」を説明する件りは『存在と時間』の中では割と理解し易い叙述であると同時に、非常に面白い論考となっている点が注目に値します。
ぼくの読んでいる『存在と時間』もやっと後半戦。これからどういう展開を迎える事になるのか、粘り強く読んでいきたいと思っていますよ♪
<2020年9月30日>
「あなたの御子息が病気です」。このセリフを言われた母親はその意味を取り違えようもない。
だが、これが彼女の一人っ子の息子が、自分の母親に向けて言ったセリフだったならば、たちまち何やら全く別の、裏の意味がありそうな言葉に変化してしまう。
言語の劇的な変身。斯様に言葉は「文脈」から逃れられない。
◆◆◆
これはハイデガー的な問題でもある。
言葉というものは誰が、どういった状況で、誰に向けて、どういう背景の下で言っているのか、という条件によって全く意味が違ってくる。
だからこそハイデガーは、言語の基礎的な部分は西洋的な思考である文法や命題や論理等といったものではなく「語り」であると言うのだ。
つまり、言語の基盤は本質や論理といったものを元にしているわけではなくて、現にわれわれが日常生活の中でやりとりしているこの生の会話のこの実存論的な感覚がベースとなっていて、そこから本質や論理が後付けで抽出されてきている……というのがハイデガー的な考え方だと言えるだろう。
コミュニケーションは実存的な立場で考えねば正確に把握できない。
この主張は何かというと、物事の本質的な意味や物事の真理といったものについて、論理や命題で考えがちな伝統的西洋思考を覆そうというハイデガーの西洋思想批判なのである。
存在の意味について考える場合、ロジックを先行させるのではなく、あくまでベースにあるのは「私」という実存的な感覚にあるのだ、というのがハイデガー的な「存在への問い」の第一歩なのである。
ハイデガーの『存在と時間』の前半部分の多くがこの「実存論的分析論」に費やされているのは、そういった意味がある。
<2020年10月7日>
やっとハイデガー『存在と時間』(岩波書房版)、中巻まで読み終わりましたよ♪
けっこう助かってるな、と思うのは副読本として読んでいるマイケル・ゲルヴェンの『ハイデッガー『存在と時間』註解』ですね。
この副読本として読んでいるハイデガー解説本には2つの点で他のハイデガー解説本とは違う特徴があります。
1、日本人学者の間で共有されているハイデガー理解からは影響を受けていないアメリカのアカデミーによるハイデガー理解であるという事。
ゲルヴェン教授はありがたい事に、アメリカの哲学研究者によるハイデガー解釈の傾向はどんなかというのをしばしば例示して説明してくれてるんですね。これは日本では貴重な意見です。
2、ハイデガー用語の多くはラテン語まで遡って言葉の意味を再解釈するのでドイツ語とラテン語との緊密な関係の上に成り立っているが、本書ではそれをアメリカ英語を使っている学者はどのように理解し、どのように翻訳してきたかという、英語圏の立場からのハイデガー用語の解釈が述べられているという点。
この2点によって、ハイデガーの『存在と時間』に対して、日本の入門書/解説書などからはまた別角度の「解釈の光」を投げかける事ができる。これがぼくにとってはありがたかったわけですね。
ハイデガーの難しい所は、今までの西洋思想の伝統を踏まえ、それを覆すために古代ギリシャまで言葉を遡行させるという点にもあると思います。
何故そうしなければならないかというと、西洋思想の伝統的な存在観を覆すためには、読者(この場合はドイツ人の読者)の意識を覆さなければならない。
そのためには、西洋思想の伝統的な言葉を使って説明したのでは、伝統的西洋思想の考え方に読者が引きずられてしまう。
だからこそ、西洋思想の伝統的な用語の考え方からしてまず考え直し、ラテン語の語源から再考してみるというプロセスが必要だった。
だから、『存在と時間』を読んでいて出て来る「配慮」だとか「気遣い」だとか「関心」だとか言う日常語は、われわれが普段日常的に使っている感覚とは違っているわけです。
この言葉の感覚のズレにクラクラきてしまう読者も多かったのではないかと思います。
ハイデガーによる用語解説をしっかり読み込んで、ちゃんと意味を理解しながら読み進まないと「気遣い」とか「配慮」とかいう用語の使い方のズレが大きすぎて意味が全くわからなくなってしまうというわけです。
関心という表現の存在論的な意義は、次の「定義」において表現されました。すなわち<(内世界的に出会う存在するものの)もとに=存在することとして、=(世界)内に自分に=先立って=すでに=在ること>)。これをもって、現存在の存在の基礎的な諸性格が表現されています。
――ハイデガー『存在と時間』中巻P.231より
――というのが「関心(ゾルゲ)」の意味。
『存在と時間』において「関心」という言葉は上に出てきた定義によって語られて行きます。だからこそ本文をぱっぱと飛ばし読みしていると混乱してしまう。
どうしてもこの『存在と時間』を読むには、用語の意味を取り違えないように用心して読み進まなければならないのです。
ハイデガーの重要用語である「本来性/非本来性」というのも誤解しやすい言葉で、例えばハイデガーは、実存論的に現存在が本来的な理解を持つには、現存在が「死に向かって在ること」を理解し、それを「いつか死ぬだろう」と考えるのではなく「常に私に迫っているもの」だと捉える事が「本来性」だと主張する。
……等と説明すると、言葉の表面上の意味から「何でいつも自分がいつ死んでもおかしくないものだと感がるのが本来の人間の姿なの?」という疑問が当然湧いてきますが、これが典型的な誤解という事なのですね。
ハイデガーが「本来性」という言葉を使う場合は、「存在への問い」という謎を解くために、存在論的な捉え方をするためのスタンス、といったようなニュアンスがあります。
恐らくこれは「本来、古代ギリシャ人はこういった存在観を持っていた」からこそ「本来性」という言葉をあえて選んだのだと思います。
ハイデガーの解説書が共通して言っているのは、ハイデガーが「死」や「本来性」や「良心」等と言う概念を分析する場合、倫理や道徳、実存主義的、自己啓発的な意味合いはほぼ"ない"という事です。
ここを気を付けないと、言葉の表面上の意味につられてハイデガーの考え方を誤解し、混乱してしまうのです。
という事で、ハイデガーの考え方は非常に「言葉」を扱うのが難しい。
自分の言葉に噛み砕いて説明するというのがなかなか難儀な事なので、ぼくも『存在と時間』の暫定レビューをするのには躊躇してしまうのです。
お次はいよいよ下巻!『存在と時間』のキモである「時間性」とは何なのかを追っていきたいと思います。
<2020年10月13日>
ハイデガーが人間の事を「現存在(Dasein)」と奇妙な言い方で表現したのには訳がある。
「Dasein」はマイケル・ゲルヴェン教授によれば元々の語源に従って訳すならば「ここに在る事」という意味になるという。
「私」でも「自己」でも「自我」でも「主観」でもなく「現存在」という表現が必要な意味とは何か?
以前から紹介していたようにハイデガーは西洋の伝統的な存在観を覆すために読者に対して意識の変革を求めている。
だからこそ物事を説明する際、今まで使われてきた西洋の伝統的な用語と使うと、それだけである種の先入見を読者に与えてしまう。それで読者に先入見の入らない視方をさせるための造語なのである。
「造語」とは言うが、ハイデガーの依って立つスタンスは古代ギリシャの存在観の復権であった。だからこそハイデガーは「語源」に拘った。
語源を辿っていく事で読者の意識を古代ギリシャの時代まで遡らせようと言うのだろう。
ハイデガーが「"在る"とはどういう事か?」という問題を考える際にまず区別したかったのは「存在的問い」と「存在論的問い」だった。
「存在的問い」は存在を「対象」として問う考え方だとすれば「存在論的問い」とは在るという意味に関する問いについて問う考え方だった。
この「存在論的問い」を分析するには「自己」を実存論的に問わなければならなかった。
実存論的に問うにしても、「自己」や「自我」等と言う言葉を使うと、これを「対象」的に捉える意識を与えてしまうので、読者を伝統的な考え方のレベルに引き戻してしまう。
これを「私」と表現すれば、今度は読者に「私=著者=ハイデガー」といった意識を持たせてしまう。
いずれも「私」を「私」として実存論的に捉える考え方ではなく自分を「対象」として観察する考え方なのである。
そういった先入見を避けるために『存在と時間』では「Dasein」が持ち出されているのである。
「私が私を見る」というのは、一見いわゆる「循環論」的に思える。
それを西洋の伝統的な存在観の見方で言うならば「私が"主観"を見る」や「私が"自己・自我"を見る」といったように、ある種自分自身を切り離して客観的に「対象」として見ようとするからこそ「循環論的」に見えるのであって、ハイデガーはそういった見方も否定していたようだ。
そうではなく実存論的に「私」を見るという事は、今われわれが見て感じている「これ」をそのままに見てそれをそのまま分析すべきだ、といった感じの意味だと思えば良いだろう。
ハイデガーの実存論的分析論とは、隠されていたものの覆いを取っ払ってありのままに見る事、という意味でもあるのだ。
<2020年10月21日>
9月の頭から読んできたハイデガーの『存在と時間』ですが、いよいよ残り1章の所まで読み進めました!
ハイデガーは自分の方法論を「現象学」と自称していましたが、ここまで読んでくると、暗にフッサールの超越論的現象学を明確に否定するかのような考え方が浮かび上がってきました。予想通りでしたが(笑)。
フッサールの超越論的現象学はある種実存論的な「主観」をその方法論に取り入れていて、それによって人間が「本質」を抽象して把握してくる認識システムを「主観」の側から研究していくものでした。
それに対してハイデガーの「現象-学」は、同じ実存論的な主観から現象を分析していく方法論を持っていますが、それによって「本質」を抜き出す事は、いわば「非本来的」という枠組みで捉えているわけです。
物事の意味を考えるとき、そのものの本質や物質的な状態に「意味」を求めるのが伝統的な西洋的思想であって、その意味について人は言葉や命題によって意味付けを行ったり考えを深めていくという見方がされてきた。
「はじめに言葉ありき。言葉は神と共にあり、言葉は神であった。 言葉は神と共にあった」――ハイデガーの考え方はそれを否定しています。
そうではなくて、もっと感覚的に「これは〇〇としてあるものだ」といったような「として-構造」等の「了解」が実存的な現存在の意味の取り方なのだという考え方なのです。
「存在」を主観との関りにおいて「対象」として見て「本質」を抜き出すという方法は、ハイデガーからしたら西洋の伝統的な思考の枠組みにはまり込んだ所謂「形而上学」だった。
ハイデガーはそういった西洋の伝統的な思考の枠組みを覆したかったわけです。
ハイデガーは、「存在者」を「対象」と見做してその本質を研究する考え方を「存在的」な考え方と表現し、それに対して自らの実存的な「現存在」としての意味の取り方から存在者を捉える方法を「存在論的」な考え方として、両者を明確に区別したのです。
とすればハイデガーからすれば、フッサールの現象学は言わば「存在的現象学」であり、自身の現象学は「存在論的現象学」という事ができるのかもしれません。
このように明確にフッサールの理論とは逆の考え方に立っているというのに、ハイデガーはフッサールと同じように自身の現象学の方法論こそが「学問の基礎付け」となる考え方だと主張している節がみられます。
フッサールの、伝統的な形而上学に囚われた考え方ではなく、自身の実存論的な感覚的捉え方こそが、学問的な意識の前段階にある、と言っているのです。
ということはやはりハイデガーは、『存在と時間』で何かとフッサールの名前を出して持ち上げているにもかかわらず、明確にフッサール的現象学を否定していたのでしょう。
実際に、大学のポストに就く際にフッサールから多くの便宜をはかってもらっていながらも、裏で友人のヤスパースにフッサールの悪口を言っていたと言われていたそうなので、まさに面従腹背という感じだったのでしょうね(笑)。
<2020年10月22日>
今年の目標、ハイデガー研究9冊目にして本丸と目していたハイデガーの『存在と時間』上中下巻プラス副読本のマイケル・ゲルヴェン教授による注釈書『ハイデッガー『存在と時間』註解』の計四冊読了。
9月頭から読み始めて約2ヶ月ほどかかった。まあこんなものだろう。
ハイデガーの『存在と時間』は、フッサールの『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』とテーマを同じくする所があった。
それは「ヨーロッパ諸学の危機」に基づく西洋伝統思考の超克と、諸学の基礎付けという意図が共通しているようだ。
その方法論の一つとしてハイデガーが持ち出してきたのが「実存論的分析論」だった。
人間は機械ではない。
いくら科学や論理を研究する学者とて、機械のように客観的に、自動的に、メカニカルに自然の法則をデータ化し、解明しているわけではない。
それ以前に彼らは生まれてきて、生きてきて「それをやろう」という意識が芽生えて、その場にいて、それを自らの人生としているのである。
つまり、いくら客観的なものであっても、彼らの学問に感情や性格や人間の生の感覚や人生観が全く関わっていないなどとという事はないだろう。
つまり、学問が始められる前には何かしらの「実存論的問題」が横たわっているのである。
そうだとしたら、彼らの研究成果というものは、彼らと全くの繋がりのないものではなく、彼らの人生に深くかかわっているものだ。そう言えるのではないか。
日本では職人的な感覚が庶民の間にも良く知られているので、こういった感覚は違和感がないのではないか。
職人は精密な手仕事によって機械のように製品を作り上げていくが、彼らの仕事の神髄は「機械になること」ではないし、彼らは機械のような意識でもって製作しているわけではない。
「作ること」そのものが彼らの「人生」を表しているし、それはつまりは製作自体が実存的な意味を持っている。
製作や、研究や、果ては論理にあっても、それらはまず個々人の生きている在り方に関係している。
彼らの製作行為、研究行為、学問的行為、理性的行為、論理的行為には、まず実存的な下地がなければあり得ないのだ。
とすれば、科学的研究の意義とは、ハイデガーからしてみてら存在的意義と存在論的な意義とがありそうだ。
存在的には、科学的な恩恵によって様々なテクノロジーの開発や自然環境の分析/予測等が可能となるだろう。
存在論的に言うならば、それを研究する事によって「"あなた"の生にどんな意義があるのか?」という問題意識を生じさせるだろう。
ハイデガーは何も「物事を実存論的に見るべきだ」という事を言っているわけではない。
「モダニズム」という問題によって現代知が限界に達しているこの状況を覆すひとつの方法論として、伝統的西洋思考に対置する考え方としての実存論的分析論をもってして、これまでの存在観の覆しを図ったという事なのだろう。
では、まずハイデガーが覆したかった西洋的な考え方とはいったい何だったのだろう。
ものごとを考えるさい、それを「対象」として自分の感覚とは切り離し、抽象化してその本質を取り出そうという科学的視点――つまりは事物を「存在的」に見ること、だったのではないか。
19世紀末~20世紀初頭と言う時代は、そういった科学的な知見が様々な点から疑問符に付された時代だった。
だからこそのハイデガー的な「存在への問い」だった。
「存在はいかにして可能か?」「"在る"とはいかにして可能か?」――または「知るとはいかにして可能か?」もっと言えば「科学はいかにして可能か?」とも言っていいだろう。
そして、現存在が存在者を可能にしている在り方としてハイデガーが持ち出してきたのが「時間性」だった。
「時が止まっている状態での精神を分析する」という事が不可能なように、精神は時間が流れているから存在している。
「精神の時が止まった状態」を何というのか?――それが「死」である。
だが、「死」イコール「精神が止まっている状態」ではない。
現存在が「死」を迎えた場合、精神は止まるのではなく、無くなってしまうのだから。
つまり現存在もその精神も、延いては実存というものも全ては「時間性」があるからして成立する。だから、実存は「時間の中にある」と言う風に表現されるのだ。
現存在の存在の在り方の本質が「時間性」である限り、現存在が見出すところの存在者が「時間性」から切り離されて存在しているなどという事は言えないだろう。
ハイデガーのように「実存」という観点から見るならば、時間の中にあるからこそ存在者というものには意味が発生しているという事となる。
だからこの本のタイトルは『存在と時間』なのだ。
以上のように、この本はハイデガーが実存論的分析論を使って西洋的な事物存在的存在感を覆すという意図の下に書かれたものだと言える。
では何故「実存論的分析論」に拘ったのかと言えば、恐らくそれがハイデガーの思想の源流となったと思われる、古代ギリシア的な人間の素朴なものの見方――隠れていないこと/非隠匿的にそのままの在り方で見ること――の復権という意図があったのだろうとぼく的には思っている。
さて、『存在と時間』は良く知られている通り予定の三分の一の所で未完のままとなっている。という事は、ハイデガー思想はここで完了ではないのだ。
という事で、ぼくの今年のハイデガー研究もここで終わり、とは言いにくい。
既に他のハイデガー研究書にてハイデガー思想の全体像はだいたい頭に入ってはいるのだが、やはりもう幾つかの解説書を当たってみたいと思う。今年もあと2ヶ月。今年いっぱいは、ぼくのハイデガー研究は続きそうだ。
