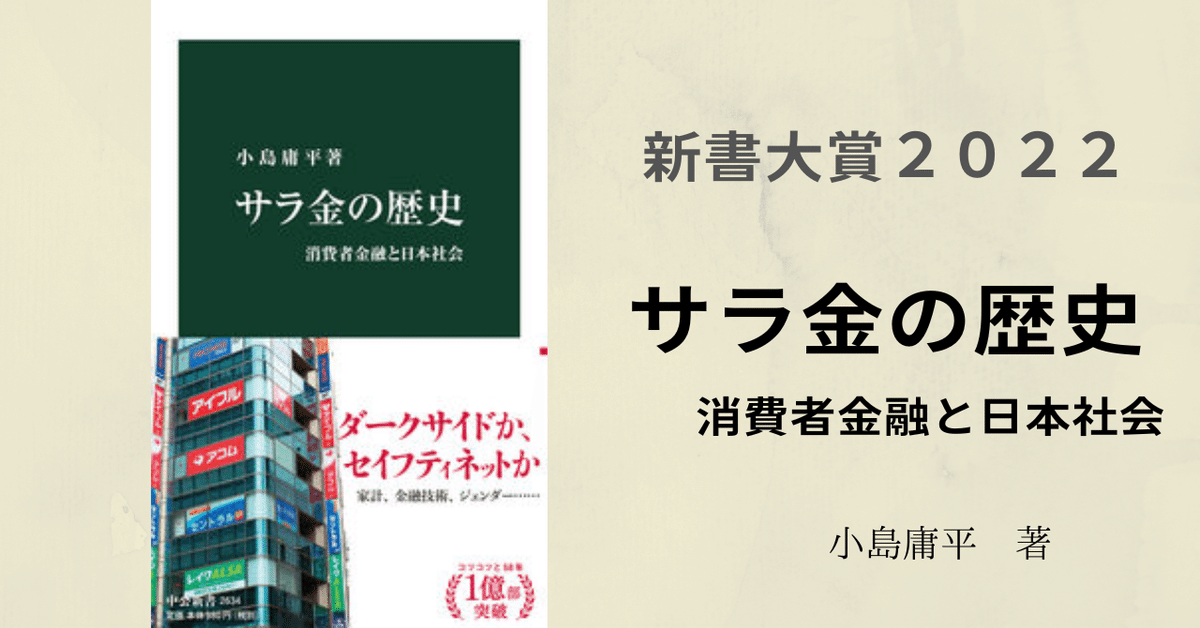
【新書大賞2022】「サラ金の歴史 消費者金融と日本社会 」(小島庸平著 中公新書) ~歴史への問いと方法
新書を取り上げてみます。
結構ページ数がある硬派な内容です。新書大賞2022を受賞した「サラ金の歴史」です。
いわゆる「売れ線」のテーマかというと必ずしもそうではない気がします。しかし、今まで光が当たっていなかった、あるいは当たっていたとしてもバイアスがかかって屈折してしまっていたと思われるテーマを誠実に調査研究し、その成果、到達点を整然と鮮やかに披露されています。
新書ですが、一つ一つの文章を丁寧に積み上げて、一体となった体系に仕上がっている感じは、さながら学術的な論文のようです(学術的な論文をちゃんと読んだことはない(笑))。
あと、接続詞が少ない(!)気がします。
接続詞が少ないのに説得的な文というは、それだけ論理展開が明快で他の解釈を挟む余地の少ない文章だと思います。
こんな文章も書けるようになりたいと憧れます。
一方で、アウトローギリギリのストレートを正確にバンバン投げ続けてくるような文章で、気を抜いて読める文(?)がないので、逆に漫然と読むとちょっと途中で何かを見失うかもしれません。
この本を読むに当たっては、あらかじめ問いと視点をつかんでおくとよりスッと入ってくる気がします。
問い 一見して不合理なのに合理の謎
なぜ、サラ金は貧しい人にお金を貸せるのか
本書では、「サラ金がセイフティネットを代替した「奇妙な事態」が生まれた歴史的な背景」を考えてみたい とされています。
「奇妙な事態」というのは概要以下のロジックです。
貧しい人ほど借金の返済能力は低い。
→返済能力が低ければ、債務不履行のリスクが高い
→金融機関はお金を貸しづらい
→貧しい人は金融機関からお金を借りることができない
→貧しい人はサラ金からお金を借りるしかない
→サラ金が貧しい人のセイフティネットになっている
この「奇妙な事態」から浮かび上がってくる問いが
「なぜ、サラ金は貧しい人にお金を貸せるのか?」
となります。
貧しい人にお金を貸すサラ金が一時でも隆盛を迎えたのは、「部分の非合理が全体の合理に転化した」ということができるかもしれません。
この「一見したら部分的な不合理が、全体の合理に転化する」というのは、「ストーリーとしての競争戦略」のクリティカル・コアのロジックと思われます(ただ、そのあと外部環境によってサラ金は窮地に立ちますが)。そういう意味では、経営のプラクティスとして見ることもできると思います。
「部分の非合理が全体の合理に転化する」というのは意外性があり、問いのしがいがあるというものです。
そして、そこにずばりの「問い」を立てられます。ビシッ!
「なぜ、サラ金は貧しい人にお金を貸せるのか?、その謎をひもとく!?」と思いながら(忘れたら思い出しながら)読むと、より頭に入ってきやすい気がします。
視点 マクロっぽいものとミクロっぽいもの、あるいは、客観っぽいものと主観っぽいもの
視点の立て方も押さえながらだと読みやすいと思います。
緩急のついた2つの視点です。
金融技術
一つ目は「金融技術」です。
これはIT系の技術だけじゃなくて、地道な作業も含みます。
信用審査、債権回収、資金調達といった各過程において、どのような金融技術が駆使されているのか。
金融機関は、事業を効率化し、収益を最大化するための努力を積み重ねていますが、サラ金は、資金力が乏しく、優良な企業と取引が難しかったので、銀行以上に金融技術を磨いており、「革新」を実現したといいます。
「むじんくん」とかを当時の最先端をどんどん取り入れる感じですね。
人
二つ目は「人」です。
個性的なサラ金創業者がたくさん登場します。歴史で、特定の人に焦点を当てるのは、王道だと思います。偉人伝的な記述の部分は読みやすいです。
また、金を借りる人、金を貸し、取立てる人にもドラマがあります。こういう点にも注目したドラマチックな記述もあるとおもいます。
さらに、働き方、消費の在り方、家族関係、ジェンダーといったところにも派生をした記述があります。思考の庭が広がります。
バランスの良さ
この二つの視点は、客観っぽいものと主観っぽいもの、マクロっぽいものとミクロっぽいものを(「っぽい」といっているのはイマイチ合っているか自信がないから)双璧にしつつ、論旨展開しています。
何色かは分からないのですが、黒と白、赤と青みたいな違う色を併用しているので、本全体のバランスがすごく整っている気がします。
私はマーカーを引いていないですが、マーカー色分けして読んでいったら綺麗に別れそうな気がします。
なお、記述の順序は、基本時系列です。
したがって、縦軸に時系列、横軸に「金融技術」と「人」ということを頭に入れるとスッと入ってくる気がします。
スタンス
サラ金を一方的に糾弾しない
本書は、「サラ金そのものへの過剰な批判を意識的に抑制するように努めた」とされています。
サラ金への負の感情は、ときに憎悪や差別に容易に結びつく危険を孕むと言います(古くはユダヤ人だから悪質な高利貸しと非難されたことなど)。
サラ金を批判する言説が酷薄さや異常性を強調し結果として、特定の職業への差別的なまなざしを強化していたとしたら問題であると喝破します。
サラ金を正当化しない
一方で、本書は「サラ金を正当化もしない」。
サラ金が過剰金融に走り、多くの人を自殺や貧困に追い込んだことも当然問題視します。
その作者がとった態度が、「サラ金の歴史を内在的・構造的・批判的に描き出す」ことです。
つまり、サラ金創業者の崇高な理想の一方で、膨大な数の被害者が生じてしまったという現実を構造的に捉えるためにこのスタンスを貫き通します。
具体的には、当事者にインタビューはしないで、文献学の手法を用いたそうです。「英雄たちの選択」みたいな感じですかね(歴史上の人物には直接インタビューできないですし)。
サラ金の問題は、ひとまず業界とは距離を取り、歴史として批判的に整理される必要がある。だが、かといって被害者側の視点からだけでは、問題の全貌を明らかにすることは難しい。サラ金業者の主体的で革新的な経営努力が、なぜ多くの人びとを破滅に追いやったのか。その具体的なプロセスを、サラ金業者と利用者の双方の事情を踏まえ、可能な限り内在的に説明しようというのが、本書の試みだった。
このバランスを貫き通していることが、本書の特長であり、それを意識して読むとさらにスッと入ってくるような気がします。
金融と人と人との繋がり
最後に、本書は「自分ごと」としてサラ金問題を考えるべきと述べます。
サラ金が一時、隆盛を極めたのは、「人的関係」をお金に換えてきたことにあるといいます。
サラ金の歴史を上記のスタンスを通して、正面からひもとくと、サラ金が人的ネットワークに巧妙にかつ極めて合理的に入り込んできたことが分かります。
それは、人と人との繋がりを換金する技術であったとも言い換えることができ、行き過ぎた換金技術は人的関係を食いつぶしながら発展してきたとみることもできるといいます。
そうであれば、「他人事」ではなく「自分事」と捉えることが必要です。
他ならぬこの日本社会が生んだサラ金の歴史を正面から見定めると、思いがけず私たちの暮らし方・働き方に深く関わっていたことが明らかになる。
多重債務に陥った人びとを「自己責任」と切り捨てるにはあまりに身近なところで、サラ金は成長してきた。サラ金が引き起こしてきた問題を、他人事ではなく「自分事」として認識することで、初めて将来のあるべき金融や経済のあり方を冷静に議論し、真の意味で人と人とのつながりに支えられた社会を構想できるのではないか。
真の意味で人と人との繋がりに支えられた社会を構想するための基礎を「サラ金の歴史」からひもとけると思って読むと、思いがけない深読みができるかもしれません。
まとめ
以下まとめてみます。
コントロールされたストレートが投げ続けられるとそれ自体は鮮やかですが、球数が多いと疲れます。そのときに、ちょっとタイムをかけて、思い返してみたら、役に立つかもしれないことをまとめてみます。
問い
「なぜ、サラ金は貧しい人にお金を貸せるのか?」
(部分の非合理が全体の合理に転化した謎をひもとく)視点
「金融技術」と「人」
マクロとミクロ 主観と客観、バランスが良くて鮮やかスタンス
一方的な糾弾も正当化もしない
「サラ金の歴史を内在的・構造的・批判的に描き出す」
歴史文献学として見る。発展/深み
真の意味で人と人との繋がりに支えられた社会を構想する
以上です。また新書読んでみます~
こちらのご本人解説動画もとても参考になります。
※Amazon のアソシエイトとして、この記事は適格販売により収入を得ています。
