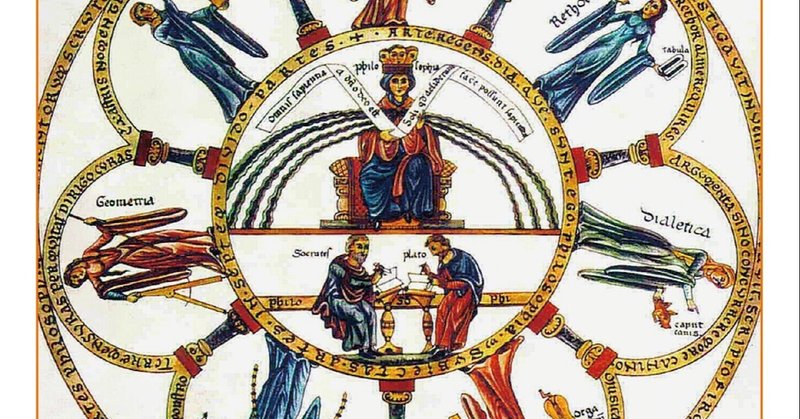2021年11月の記事一覧
雑考・日記・メモ「復讐ってなんだろうと問う事」
今日、農作業をしながら考えていたこと。
「復讐」って何なんだろか?
この問いに、感情のステージのその臨場感そのものでもって答えるのではなくって、理性・悟性のステージで「何なんだろうか?」と問い答えようとするのならば、はたしていったい「復讐って何なんだろか?」。
色々と考えましたが、答えとして纏まるまで至りませんでした。
私は「復讐心を無くしましょう!それでは救われませんから・・・」と宗教的に答える
雑考・日記・メモ「エビもタコもイカも感覚を有する。そんなの当たり前!と思う事を問う」
https://gigazine.net/news/20211122-lobster-octopus-crab-sentient-being/
この感性と言うのか何というのか・・・私には良く解りません。エビもタコもイカも感覚を持っているし、茹でられれば苦しいに決まっています。わざわざ科学的に証明しなければそれは文化にはならないのだろうか?
と、先ずは欧米文化に対するステレオタイプな批判をしてみて
雑考・日記・メモ「生涯学習者の共同体としての探究の共同体はありうるのか」
生涯学習の当事者性を考えた時、「探究の共同体」は何も「こども哲学」の特許ないだろう。「探究の共同体」は広く「生涯学習」と言う視野から考えてみても良いのだから。だから私はいわゆる「単なる年齢としての子供」を対象とした「子供哲学」にはどうも馴染めません。と言うのも私が関心があるのは単なる年齢の区分ではない「老人=こども」であり、そのような「老人=こども」が自ら自治する「生涯学習」であるのだから。
こ
哲学・日記・メモ「アートと哲学・直感とひらめき・形式と内容」
アートと哲学・直感とひらめき・形式と内容
アートは直感。哲学はひらめき。
そして直感は形式。ひらめきは内容
形式は言葉にできない故に直感であるしアートである。内容は説明しうる故にひらめきであり哲学である。
だからアートは形式である。だから哲学は内容である。
そして形式は内容の沈殿から抽出されるものである、とするならば、形式の涵養の前提には内容がなければならない。
かくしてそもそもの始まりには、形
哲学・日記・メモ 「信じる者と疑う者と問う者について」
信じる者と疑う者と問う者について
人が何かを語った時、「問う者」は「この人は何故このような事を語るのだろう?」と自らに「問う」。「本当にそうか?」と彼を「疑う」のではない。「何故?」と自らに先ずは「問う」。だから彼は「問う者」なのだ。
そして「問う者」は「本当にそうか?」ではなく「何故?」と問う故に「疑う者」ではない。「疑う者」は「本当にそうか?」と「疑う」のだから。と同時に「問う者」は「信じ
哲学・日記・メモ 「物語とメモと」
物語とメモと
私は昔からメモ魔で、と言っても何でも見たこと聞いた事を記しておくメモ魔ではなくて、見たこと聞いた事に対して考えた事をメモししているのだけれども・・・そんなメモ魔なようです。
しかしそうしているとメモが溜まってくる。だからたまにはそれらを見返して新たなメモを作ったりしてもいる。するとそんな感じでメモが何となく形になって、散文になったり詩になったりしてくるのだけれども、私は作品の為に
雑考・日記・メモ「絵本 エミリー」
エミリー・ディキンソンをモティーフとした絵本。
エミリー・ディキンソンは実在した人物です。詩人である彼女は生まれた町から出ることは無く生涯を終えました。世界各国の多様な文化を知る事もなく、それに触れる事もなく。
しかしだから不幸であったのか。
「天国をみつけられなければ ー 地上で ー 天上でもみつけられないでしょう たとえどこへうつりすんでも天使はいつもとなりに家を借りるのですからー」
雑考・日記・メモ「稀人について。自分が住んでいる街よりも、住むことのない街により関心がいくのは何故だろうか?」
稀人について。自分が住んでいる街よりも、住むことのない街により関心がいくのは何故だろうか?
自分が住んでいる街よりも、住むことのない街により関心がいくのは何故だろうか?稀人(客人)が来訪する理由は、来訪がその土地に幸をもたらすにせよ、稀人(客人)にとってはその土地に幸をもたらそうという意図はなく、歓待を受けると言う、来訪する側の幸を動機とするのかもしれない。と思う。あくまで稀人(客人)側の動機と