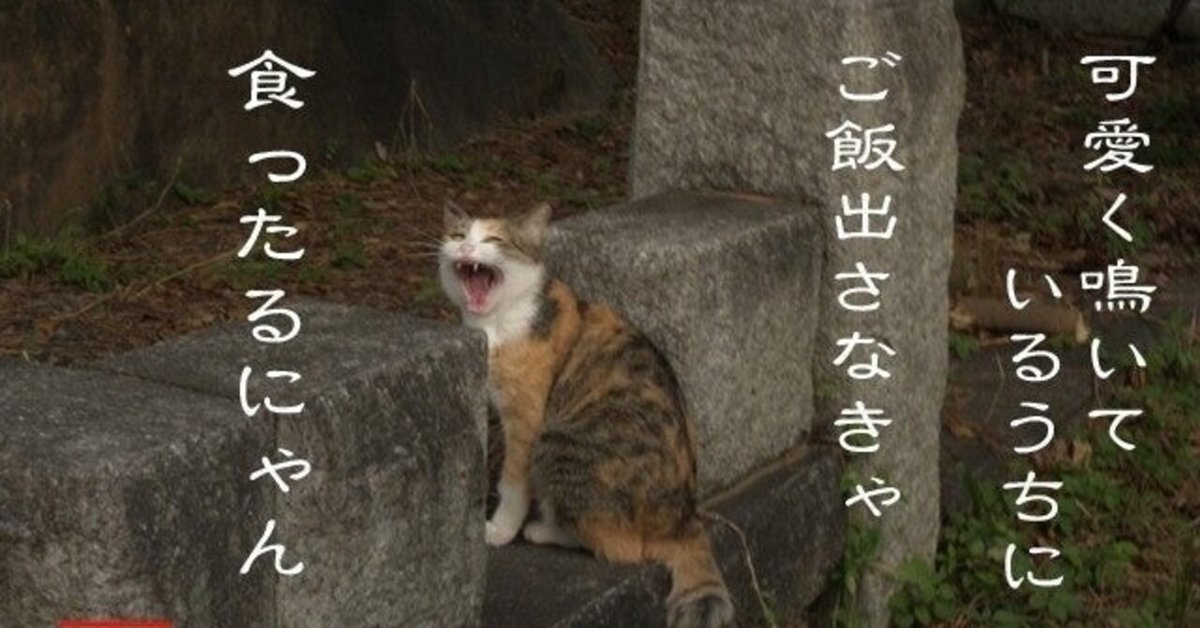
「食べるために働く」ということが実は全然当たり前ではないこと〜ポランニー『時代遅れの市場志向』を読んで思ったこと
現代の社会では、働く目的は「食べるためだ」または「金を稼ぐため」というのが当たり前のように考えられている。しかしこれだけでは虚しいから、もう一つの選択肢として「やりたいことをやるため」が挙げられ、これらの間で常に葛藤が生まれているように思われる。実際、僕も初めて就職活動をした20代の頃、「何のために働くのか」と悩んでいたような気がするが、基本的にこの二つの選択肢の間で揺れ動いていた。
「やりたいことをやるため」というのは青臭い考えだとも思われている。しかし一方で、物質的な目的のためのみに働くということが、いかに現代人の心をすり減らしているか、実感できない大人はいないだろう。そして、結局はこれら二つの目的を、できる限り両立させるしかないのだと考えていた。今も多くの人々が、同様の悩みを通過して、学生から社会人になっていく。
実はこの「食べるために働く」という考えが、極めて特殊なものだとしたら、意外に思う人が多いのではなかろうか。例によってこれも僕のオリジナルな考えでは全然ないのだが、数十年も前にカール・ポランニーという人がそんなことを書いている。
少なくとも僕は、その考え方を初めて知った時、はっとした。自分もやはり知らず知らず、現代の価値観に犯されているというか、視野を狭められているということを思い知らされた。
飢えを防ぐために働くという考えは、せいぜいここ200年くらいの間に当たり前になったに過ぎない。言い換えれば、19世紀以降、市場経済のシステムが世界中を覆うようになってからである。なぜならば市場経済のもとでは、あらゆる生活必需品は貨幣との交換によって入手される。労働が商品化され、とりたてて財産をもたない大衆は、自らの労働を売ることによってしか、貨幣を入手することができないからである。
では昔は、市場経済が浸透する前の社会では、どうだったか。山奥や絶海の孤島で一人で生きている人以外にとっては、食べるための活動は、少なくとも個人的な行為ではなかった。畑を耕すにせよ、狩りをするにせよ、基本的に一人でできるものではない。同じ共同体の人々と一緒に活動しなければならなかった。つまり、
ある個人の腹がへっても、彼のしようとすることが決まっているわけではない。
(カール・ポランニー著、玉野井 芳郎 他 訳 『経済の文明史』[2003]ちくま学芸文庫、p57、第2章「時代遅れの市場志向」)
集団で動かなければ、食料を生産することはできなかったわけである。従って昔は飢えは社会的なものであったが、市場経済が発達した後の時代でのみ、飢えは「経済的」なものになった。これを「食べる」から「着る」「住む」にも範囲を広げても同じことだ。服を作るには麻やら綿やらを生産しなければならないが、これも畑仕事である。織機を作るには集団で木を切るところから始めなくてはならない。「住む」に関して言えば、昔の日本の村落では、茅葺屋根の吹き替えは、その家に住む世帯だけで行うのではなく、周辺住民総出で行うことは珍しくなかった。
もちろん、食料を用意するにはそれなりの労働は必要にはなる。しかし昔の社会にとっては、「食べるための労働」は「労働」の100%を占めているわけでは、必ずしもなかった。
実際、
人間は、実のところ、物が適当に用意されているところでは、さまざまな理由で労働を行うものである。僧侶たちは宗教的理由で交易を行い、修道院をヨーロッパ最大の交易施設にした。…
(前掲書、同第2章、p62)
以下、西メラネシア人、アメリカ先住民、17世紀の重商主義時代のフランス人などが様々な、経済的でない理由で働いたという例が続く。
とはいえ、今さら中世や古代のシステムを復元するわけにはいかないのは良くわかっている。とすると、こんなことは夢想だろうけれども、やはり次のように思わずにはいられない。働くという日常的な行為によって、物質的にも精神的にも満たされる、そんな社会や経済のシステムと、それにふさわしい新しい価値観が誕生したら、どんなにか世界が良くなるだろう、というとこだ。
いいなと思ったら応援しよう!

