
【全文公開】 CHAPTER 2-02 自然の中にあるデザイン〜エモーショナルとロジカルの狭間〜
「デザイン読書日和」という同人誌即売会&交流会で出典した『 田舎暮らしを科学する仕事っぽくないデザイン』(¥300)全60Pのスローライフエッセイ、全文公開チャンレジです。
今回は、CHAPTER 2-02 自然の中にあるデザイン〜エモーショナルとロジカルの狭間〜の記事公開です。
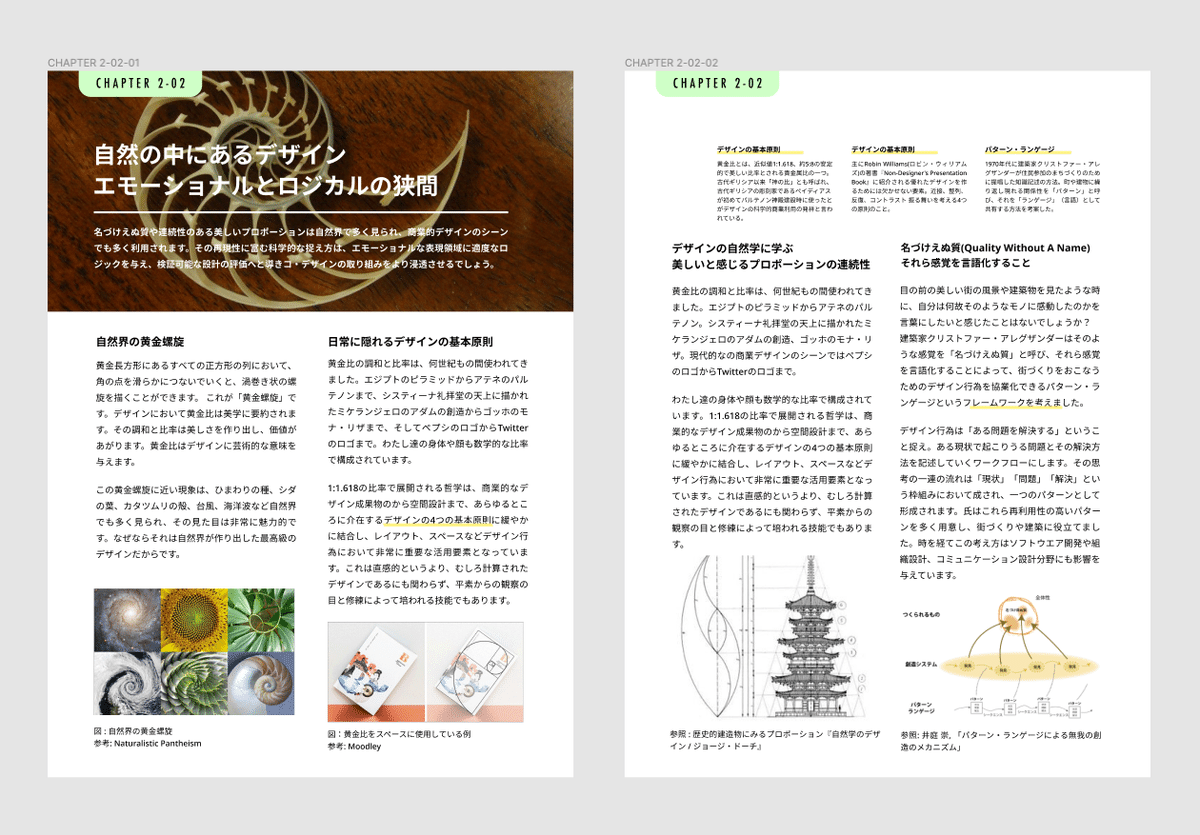
CHAPTER 2-02-00 自然の中にあるデザイン〜エモーショナルとロジカルの狭間〜
名づけえぬ質や連続性のある美しいプロポーションは自然界で多く見られ、商業的デザインのシーンでも多く利用されます。その再現性に富む科学的な捉え方は、エモーショナルな表現領域に適度なロジックを与え、検証可能な設計の評価へと導き、あらゆる共創的活動を漸進的な取り組みと変えることができるでしょう。
CHAPTER 2-02-01 自然界の黄金螺旋
黄金長方形にあるすべての正方形の列において、角の点を滑らかにつないでいくと、渦巻き状の螺旋を描くことができます。 これが「黄金螺旋」です。デザインにおいて黄金比は美学に要約されます。その調和と比率は美しさを作り出し、価値があがります。黄金比はデザインに芸術的な意味を与えます。
この黄金螺旋に近い現象は、ひまわりの種、シダの葉、カタツムリの殻、台風、海洋波など自然界でも多く見られ、その見た目は非常に魅力的です。なぜならそれは自然界が作り出した最高級のデザインだからです。

参照: 自然界の黄金螺旋 『Naturalistic Pantheism』
CHAPTER 2-02-02 日常に隠れるデザインの基本原則
黄金比の調和と比率は、何世紀もの間使われてきました。エジプトのピラミッドからアテネのパルテノン。システィーナ礼拝堂の天上に描かれたミケランジェロのアダムの創造、ゴッホのモナ・リザ。現代的なの商業デザインのシーンではペプシのロゴからTwitterのロゴまで。
わたし達の身体や顔も数学的な比率で構成されています。1:1.618の比率で展開される哲学は、商業的なデザイン成果物のから空間設計まで、あらゆるところに介在するデザインの4つの基本原則に緩やかに結合し、レイアウト、スペースなどデザイン行為において非常に重要な活用要素となっています。これは直感的というより、むしろ計算されたデザインであるにも関わらず、平素からの観察の目と修練によって培われる技能でもあります。

参照:黄金比をスペースに使用している例『 Moodley』
CHAPTER 2-02-03 デザインの自然学に学ぶ美しいと感じるプロポーションの連続性
建築デザイナーのジョージ・ドーチの著書『デザインの自然学』では、生命が、何故にかくまでも美しく存在するのかという疑問を、恐竜・クジラから犬まで、多彩な花々と草木、チョウや昆虫、 そして魚や貝類など、多種多様の形態を見較べ、独自の手法によって探究した成果を記録しています。 あらゆる「かたち」 は、最も美しいプロポーション〈黄金分割〉 比率へと収斂することを解明し、 自然界のダイナミズムと調和の意味するものを、全くユニークで大胆な思想へと構築しました。 暗黙知的に美しい、良いとされていたこれらの現象は一定の再現性を持つ形成過程のパターンが存在し、私達の身近なプロダクトに建造物、街づくりに活用されているということを科学的なアプローチで紐解くのは好奇心が掻き立てられますね。

参照 : 歴史的建造物にみるプロポーション『自然学のデザイン / ジョージ・ドーチ』
CHAPTER 2-02-04 「名づけえぬ質」それら感覚を言語化すること
目の前の美しい街の風景や建築物を見たような時に、自分は何故そのようなモノに感動したのかを言葉にしたいと感じたことはないでしょうか? 建築家クリストファー・アレグザンダーはそのような感覚を「名づけえぬ質」と呼び、それら感覚を言語化することによって、街づくりをおこなうためのデザイン行為を協業化できるパターン・ランゲージというフレームワークを考えました。
デザイン行為は「ある問題を解決する」ということ捉え。ある現状で起こりうる問題とその解決方法を記述していくワークフローにします。その思考の一連の流れは「現状」「問題」「解決」という枠組みにおいて成され、一つのパターンとして形成されます。氏はこれら再利用性の高いパターンを多く用意し、街づくりや建築に役立てました。時を経てこの考え方はソフトウエア開発や組織設計、コミュニケーション設計分野にも影響を与えています。

参照: 井庭 崇, 「パターン・ランゲージによる無我の創造のメカニズム」
まとめ
この節では章の冒頭で説明したフィールドワークの楽しみかたや感覚的な発見の嗜み方から一転して、科学的な観点や数値的な構造美について学説的な側面も交えながら説明しました。
自然の中や現代建築や都市設計に見られる、表現することが難しいクオリティ、体験の心地よさ「名づけえぬ質」について言及し、その連続性や普段我々が行う創造的活動への洞察に方法について言及してみました。
小難しい内容を小難しく語ってるフシがあるので、もう少し具体例などを交えて希釈しないと本書の全体として浮いてしまう感があるので次のバージョンでは大幅に加筆しようと考えています。
今回は僕の大好きな、ジョージ・ドーチさん、クリストファ・アレグザンダーさんの話に触れるのでオタクの饒舌があふれる節でした。
次回に続く。@norinity1103でした
いいなと思ったら応援しよう!

