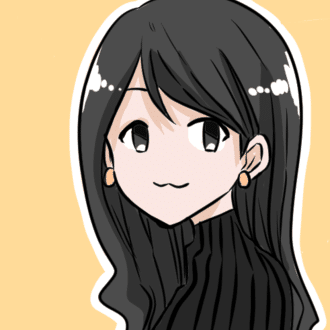最後の扉の閉まる音
一つずつ、一つずつ。
泣いて、泣いて、最後に、ああ、そういうことじゃなかったんだ、"最初から"と、自分に刻み込んで。
真っ暗な瞳と泣き腫らした眼のまま、言葉もなく、ただただ体育座りをする幼き私を、何度、置き去りにしてきただろう。
扉は、期待したものの数だけ、存在した。
それは、かなり最初に挫かれて、最初から閉じることを決めていたものほど、簡単に、バン!と音を立てて、怒ったまま、少し乱暴に閉めても平気なものだった。そんなに大事に思っていなかったのだろう。期待もしていなかった。その程度だと、最初から思っていた。
最後まで、閉めたくない、お願い閉めないで、きっと違う、まだなんとかなると、泣いて泣いて、ドアノブに力無く小さな手をかけて、抵抗したものもある。それでも、背中越しに、本当に小さな声で「ごめん」と、大人の彼女に呟かれて、私のものよりずっと大きな、憧れの手で、とても優しく閉められた。
私が、見張られていない隙に、こそりとそれを再び覗かないように、カチリと、一度だけ、金属質な音を立てて、スッと引き抜かれた鍵。それを仕舞おうとするその手に、歯を立てて血が出るほど噛み付いて、認めないと暴れたらよかっただろうか。
でもそんなことをしたら、何も進まないことはわかっていた。噛まれた彼女は、私の細い髪を撫でながら、私が諦めるまで…いや失望するまで、再び鍵が開くことは絶対にないと理解するまで、何時間も困ったように微笑み続けたに違いなかった。
他の私たちは、私たち全員が前に進み、新たな景色を見ることを、賛成多数で可決し、そのための犠牲が、最初の…オリジナルの私が、何かを諦めることだった。
小さな犠牲。
攻撃的な私はこう述べる。
「だいたい、それは本当に犠牲だったのか?」
私は力無く答える。
「こんなに泣いている私を見て、そんなことを言うの?」
わがままを滅多に言わない私。
欲しいものも欲しくないものも好きなものも嫌いなものもわかっていて、欲しがるものは多くない。だから、せめて、これくらいは、手にしたって、いいじゃないか。
そんな私が泣いているのだ。
考えに考え、我慢を重ねたから、泣いている。
「それは最初から"存在しなかった"のでは?」
一体どこからそんな絵空事を仕入れてきたのかという突き放すような口振り。
手に入れている人はいるではないか。
それともそれは嘘偽りか。私に真実が見えていないだけか。他の人が持つそれを奪い取ったとて同じ現象は私には起こらなくて、特定のものにしか、それを抱かない。
滅多に発生しないそれ。
見つからなければ淡い期待だけ心の奥底に持ち、青い鳥のように探し続け、見つかっても時間が経てば変異して違うものになったり、よく見たら違うものであったりした。
そしてそれが随分と自分勝手なこともわかっていた。だから手に入らずとも奪うことはなく、出て行こうとするものを追いかけることもなく、変わってくれと縛るより前に自ら去る。ただ、ああ、ああ、そういうものだよと、少しずつ自分を納得させる過程を、どうやら、大人になる、と呼ぶものらしかった。
見つかっても手に取らせてすらもらえないことも多々あった。特に幼少期は。
だめだよ。
あぶないよ。
きみにはまだはやいよ。
あなたにその資格はないよ。
なに、それ。
火傷で掌が爛れようと、痛みに泣こうと、それは私の自由ではないか。血を吐きながら笑って死ねるなら本望かは、私が決めたかった。
だけれど、いつも、いろんな理由がついてきて、それだけが、手に入らないのであった。
手に入らないから青い鳥なのかも知れないことをわかっていて、その事実を見たくなくて、そっぽを向いている自覚もあった。豪胆な台詞を吐いておきながらも火傷をしたら直ちに泣き出すのかも知れなかったし、そんな苦労などせずとも、すでに腕の中にいてくれている兎を撫でるべきなのかも知れなかった。
喉が渇く。
お願い、どうか、水が欲しい。
ジュースなんかいらない、お茶じゃなくていい。
何の味もしない水でいい。
土混じりでも、湧いたばかりの、そのままの源流がいい。私はただ、オアシスに辿り着き、その側で暮らしたいのだった。
そんな…色付けされたものばかり出さないで。
これが欲しかったのだろうと差し出されるそのどれもが、キャラクターだの色だの味がついていて、そのどれもが私を見誤っている事実に勝手に悲しくなる。
差し出されるその気持ちは嬉しい。
笑って欲しいと願われていることがわかるから笑う。
相手は念願叶ったと、自分の見立ては合っていたとガッツポーズをし、それを見て、私は笑顔を顔に貼り付けたまま、バレないようにそっと扉に鍵をかける。
外行きの私は笑うのがどんどん上手くなり、幼き私は閉められた扉の脇でずっと泣いている。
水は与えられることなくただ流れ出ていき、私は渇く。
水くらい出せというセリフに聞こえるが、否、そもそも、水自体が貴重だと、私たちはとてもよく知っている。
「水を飲めたことに感謝しなさい」
実は、水がじわじわと川のように供給されていたことにたまに気づき、目を腫らしたまま、母乳のようにそれを飲む私の頭を撫でる彼女が、後方をゆっくりと振り返る。ぽたぽたと水滴を垂らしたまま口をぬぐい、彼女の視線の先を追えば、水を飲めなかった私が、遠い背後で干からびて死んでいた。
いつでも、ああなっていてもおかしくなかったのであった。
私は、自らが渇き、踏まれ、苦痛の日々を暮らしていた頃、抱いていた"誰か"への激しい憎しみを、忘れてはならないのだった。
痛みは、踏まれているほうにしか、わからない。
干からびて死んでいる私は、水を口にする私に、呪いの言葉を浴びせていたのかもしれなかった。私以外のひとたちも同じことを思っているのかも知れなかった。
水にありつけた私には泣く資格など最初からないのかもしれないことを、ひとときでも忘れてはならなくて、渇いて死んだ私のために、私は一歩でも前を向いて進まねばならなかった。そして死んだ彼女は私の幸せを祈っていたかもしれないことも忘れてはならないのだった。
だから泣かないのよ、と、ゾッとするほど優しい声と手が私の頬を撫でる。慰めているのではなく、お前が勝手に生み出した無意味な理想は全て自ら首を絞めて殺せという一方的なオーダーであった。これは極めて正当で合理的で、私にはとても残酷なことであった。
「あなたが渇いて死んでいないのは、あの時、扉を閉めて、前に進んだからでしょう」
並行世界の中で生き延びるルートに進めたのは、どれかの自分の理想を殺したからだ。理想の優先度は、水よりも低いと、このひとたちは判断した。
わかる。わかっている。
そして進んだ先に、期待する未来などなくて、それは冷たい彼女がいうように最初から幻想で、これまでの道のりに落としてきた涙や、抜け殻や、死体や、閉めてきた扉そのものが、旅であるだけだと知る結論だと、もう全員がわかっている。
だから、笑って、楽しむことを覚えないといけないのだった。
それでもいいじゃないか、過程で水を補給できて生き延びた、ただそれだけが真実だ。
理想が旅を悲観的にさせるなら、もう、砂漠を楽しむことを受け入れなければならなかった。
泣きながら扉を閉める旅は、もう、ここで、終わりにしないといけなかった。
「失礼なやつだな、ほんと」
冷たい彼女が吐き捨てるように言う。
勝手に何かに期待したことについても、自分が恵まれていることについても、きちんと努力し進んできた私たちを認めないことについても、過去の私が望んだ場所に立てていることに気づかないことについても、そのどれもだ。私もそれを理解している。わあわあ泣いていないだけで、私以外の皆が怠惰にやってきたわけでも、傷ついていないわけでも、なかった。
「しかも、これまでも笑ってた時のことは忘れてるときやがる」
不貞腐れたようにぽつりと言う。
悲しい時にしか扉は閉めず、笑っている時の道標を残してこなかったから、いつが幸せの分岐点なのか、私たちはあまり理解できてこなかった。
ただ必死だった。その場所に到達することが目的で、そのために何を犠牲にするかが決議事項だった。狂わないためのメソッドだけ馬鹿みたいに得意になった。
完璧なコース料理はずっと頭の中で決まっていて、どんな素材で、どんな順番かも決まっていて、それが食べられたら別にいつ死んでも良かったのだけれど、それが揃うことはこれまで終ぞなかったし、きっとこれからもなくて、それは生きる他のひともそうなのである。
「立って」
優しい大人の彼女が手を伸ばす。
手を取るのが怖い。
理想とのギャップへの怒りや失望がガソリンだった。青い鳥を信じていたからここまで歩いた。
砂漠の中を楽しく生きる方法を見出せるだろうか。扉を閉じきると言うことは、生涯嘘をつくということだ。
「もう、ほかのところでは、上手になったでしょ?」
今までと何が違うのかと平然とした表情で言われる。
全てが試練である。
私は、震える手で、はじめて、自ら扉の鍵を握り、鍵穴にかけた。
いいなと思ったら応援しよう!