
経絡・流注から養生を考えてみた
こんにちは。
養生担当“ のぶ ”こと千葉宣貴です。
当月も宜しくお願い申し上げます。
⇩ 購読はこちらから ⇩
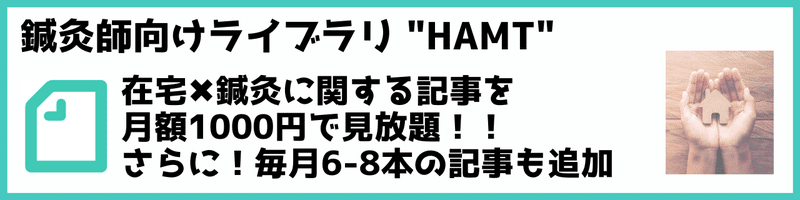
前回は在宅鍼灸師が養生するメリットをお伝えしました。
⇩ 前回記事も読んでみてください⇩
そのなかで養生と施術のつながりをもつことが重要とかきました。
それを施術にも反映させれば"養生×施術"となり、東洋医学をとおしてやることや考えることがシンプルですみます。
それは施術と養生がおたがいに"気の調整"を目的におこなえるから。
わたしの場合はそこに"呼吸"をかけてよりシンプルにアップデートしています。
また患者さんも施術でおこなったことを普段の生活でもおこなえばよいので、やることがシンプルになりますよね。
在宅鍼灸師は施術効果を高めたいという思いで休日も勉強しているのではないでしょうか?
ただし、われわれが患者さんと関わる時間はたかがしれています。
その他の時間はコントロールできません。
患者さん自身に施術の効果を維持、さらには次回のそれを引き出す準備をしていただくことが理想です。
またわたしは施術をあくまで"対症療法"ととらえるようにしています。
いわゆる”根本”"本質"は患者さん本人のなかにしか存在しません。

施術、養生で顕在意識の部分の変化を積み上げることで潜在や根本の部分の変化をはかることが、鍼灸師の役割です。
わたしはそんなときにこそ、施術でつかう経絡・流注を養生でも"共通言語"としてつかえたらと考えています。(当然ですが、患者さんは経絡・流注を理解する必要はありません)
経絡・流注のふりかえり
まずは正経十二経絡の経絡・流注を再確認しましょう。
手の太陰肺経~足の厥陰肝経までの12経絡の"共通点"をさぐっていきます。
『霊枢』経脈篇第十の文面を参考にします。
訳を載せると膨大な文字量になるため原文を紹介しますが、キーワードは"太文字"にしますので原文を理解しようとしないでください。
手の太陰肺経
肺手太陰之脈、起干中焦、下絡大腸、還循胃口、上隔属肺。
従肺系横出腋下、下循臑内、行少陰心主之前、下肘中、循臂内上骨下廉、入寸口、上魚、循魚際、
出大指之端。
其支者、従腕後直出次指内廉、出其端。
経絡・流注のはじまりは手の太陰肺経ですね。
鍼灸学生時代の最初は皆さんはここからスタートしたと思います。
手の太陰肺の流注は胃(中焦)からはじまり、大腸(下焦)をまとい横隔膜をとおって肺(上焦)に属します。
つまり、手の太陰肺経に刺激をあたえることは三焦すべてに影響をおよぼすことが期待できます。
手の陽明大腸経
大腸手陽明之脈、起干大指次指之端、循指上廉、出合谷両骨之間、上入両筋中、循臂上廉、入肘外廉、上臑外前廉、上肩、出禺骨之前廉、上手干柱骨之会上、下入缺盆絡肺、下膈属大腸。
其支者、従缺盆上頸貫頬、入下歯中、還出挟口、交人中、左之右、右之左、上挟鼻孔。
手の陽明大腸経の流注は頸部にある缺盆穴(足の陽明胃経)から上・下方に向かいます。ですので頸は柔らかくしておきたいですね。
上方は顔面下部や下歯に至ります。噛み合わせや歯の健康食べ方が大腸に影響を及ぼすと考えられます。
また「よく噛んで食べなさい!」「かたいものを食べて顎を鍛えなさい!」といいますがこれらは排便(デトックス)の助けになるとも考えられます。
一方、下方は肺(上焦)をまとい横隔膜をとおって大腸(下焦)に属します。缺盆穴(足の陽明胃経)とのかかわりもあるため、手の太陰肺経同様三焦すべてに影響をおよぼすことが期待できます。
足の陽明胃経
胃足陽明之脈、起於鼻、之交楹中、旁納太陽之脈、下循鼻外、入上歯中、還出挟口環唇、下交承漿、却循頤下廉、出大迎、循頬車、上耳前、過客主人、循髪際、至額顱。
其支者、従大迎前下人迎、循喉嚨、入缺盆、下膈、属胃絡脾。
其直者、従缺盆下乳内廉、下挟臍、入気街中。
其支者、起干胃口、下循腹裏、下至気街中而合、以下髀関、抵伏兎、下膝臏中、下循脛外廉、下足跗、入中指内間。
其支者、下廉三寸而別、下入中指外間。
其支者、別跗上、入大指間、出其端。
足の陽明胃経は"顔面にあり"と忘れないようにしたいですね。
鼻から始まり足の太陽膀胱経に入って、上歯や口(唇)に入ります。
鼻のとおりや手の陽明大腸経同様、歯の健康や食事は胃にたいしても好影響をあたえれると考えられます。
頸部にある缺盆穴から胸部、横隔膜をとおって胃に属し脾をまといます。
またさらに下りて臍をこえて気街(股関節)までいきます。
ということはヨガなどの呼吸運動を意識しながら全身をのびやかに動かすことは、足の陽明胃経の養生にピッタリですね。
足の太陰脾経
脾足太陰之脈、起干大指之端、循指内側白肉際、過核骨後、上内踝前廉、上喘内、循脛骨後、交出厥陰之前、上膝股内前廉、入腹属脾絡胃、上膈、挟咽、連舌本、散舌下。
其支者、復従胃別上膈、注心中。
足の太陰脾経は脾に属し胃をまとった後、横隔膜をとおり咽喉を挟んで、舌の根にいたり舌下に分布します。
また胃から横隔膜をとおり心に注ぎます。
脾は陰中の陰といわれることから"陽気"を上焦からもらいながら機能しています。ということは上焦と中焦をへだてる横隔膜は柔軟にうごかせていることが必須。現代人は"吐けていない"吸いすぎ"なのでゆっくり、長く吐いてください。
くわえて舌にいたるので舌の筋トレが大事。
最近は高齢者のオーラルフレイルが話題になっていますので、若いころから口腔内の機能に興味をもち実践してみましょう。
ちなみに舌の機能が引き出せると鼻呼吸がしやすくなるので、肺や胃の養生にもなりますよ。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜
200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
