
うるおいと睡眠
こんにちは。
養生担当 “ のぶ ” こと千葉宣貴です。
当月も宜しくお願い申し上げます。
⇩ 購読はこちらから ⇩
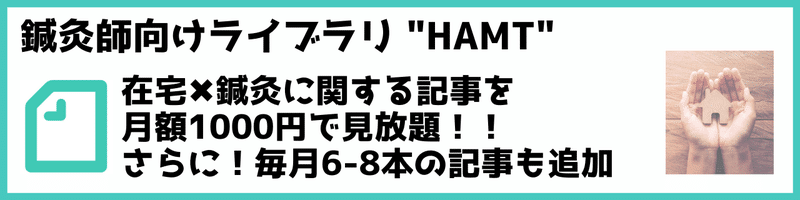
はじめに
前回の記事では『うるおいと呼吸運動』と題して、うるおい(陰液)と呼吸運動のつながりで養生を考えました。
今回はそこでみた【うるおい】が睡眠とどうつながるか書きます。
これまで養生は呼吸改善がスタートであり"軸"とお伝えしてきました。
それら睡眠と呼吸運動を相互に支えあうために"うるおい"(陰液)があるととらえましょう。
⇩前回記事はこちら⇩
"うるおい"とは
東洋医学では、うるおいを"陰液"とかんがえています。
気血津液でいうと血・津液にふくまれます。
血 → 栄気(営気)+津液
津液= 津(さらさら)+ 液(ネバネバ)
それらを気の推動作用で全身にいきわたらせています。
臓のはたらきでは、肺の宣発・粛降作用がその役割を担っています。
つまり"うるおい"を活かすには、呼吸(とくに呼気)は必須と頭にこびりつくほど覚えておきましょう!
どこにあるの?
血・津液が貯蔵されている場所は肝・腎。
だからこそ "うるおい" は生きる(息る)うえで肝腎なんです。
なにが動かしているの?
ひとつは前述したとおり気をうごかすのは"肺"です。
一方血は"心"。
西洋医学の面からみても、心臓には全身に血液をおくる循環器としての役割がありますからイメージしやすいでしょう。
それを東洋医学では心の生理作用のひとつで "主血" といいます。
またおさらいですが東洋医学では肺を "相傳の官" といいます。
「肺は相傳の官、治節出ず」
これは肺が君主である心の生理作用をサポートする臓であること。
広くとらえると肺は"うるおい"に支えられながら、気血をうごかして全身にとどけているといえます。
つまり、気がうごけば血がうごく。
わたしが呼吸運動にこだわる理由はコレです。
いつどこでつくっているの?
夜寝ているあいだに脾胃を中心とした臓腑でつくっています。
中心の脾胃では気血津液の素となる"後天の精" "水穀の精微"を生成。
これに生成後のそれを心や肺に運ぶまでを脾の"運化作用"といいます。

自律神経からとらえると睡眠時は副交感神経優位で消化器のはたらきは高まります。その状態が東洋医学の"うるおい"生成と同義です。
一方、交感神経優位では心肺機能が高まるのでうるおいを全身に届けてつかうといえます。
つまりうるおいをより多く生成するには、しっかり息を吐いて副交感神経優位をつくりやすくすることが重要。
それが睡眠の質を高めることを助けます。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜
200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
