
【歴史の話】豊田有恒の目を通して見る「加藤清正」
以前の記事では、勝海舟についての、一般の評価と歴史作家・司馬遼太郎との違いを書きました。
今回は加藤清正について、SF作家であり歴史作品も手掛けた豊田有恒の目を通して見た評価を書きたいと思います。
みなさんは、加藤清正にどのようなイメージを持ってますか?
豊臣秀吉の数少ない血縁者で、秀吉の子秀頼を守った忠義の士
賤ヶ岳の七本槍の一人で、大槍を振るう豪傑
文知派である石田三成・小西行長らとたびたび対立した、武断派の軍人
ざっとこんなところ(付け加えるなら、「意外に、築城が得意」くらい)ではないでしょうか?
豊田有恒は著書『知謀の虎 - 猛将加藤清正』の中で、いろいろな事例を挙げながら、これらのイメージを覆すストーリーを展開しています。
秀頼を守った忠義の士か?
1611(慶長16)年、伏見城での徳川家康と豊臣秀頼との会見に同席した清正は、浅野幸長とともに「家康と刺し違える覚悟であった」と考えられています。
秀吉の生前には「地震加藤」のエピソードもあり、私たちは律義な忠義者というイメージを持ちます。
しかし豊田氏の結論としては、「いやいや、加藤清正という武将は自己プロデュース力に長けた野心家であり、秀吉の合理的なやり方を徹底して真似していた。彼のイメージ戦略に、当時の人たちはもちろん、後世の我々までが騙されている」ということになります。
アピールが上手い
1592年の文禄の役では、清正の第二軍は小西行長らの第一軍から五日遅れで上陸し、第一軍が敵を蹴散らした後を進み、京城(ソウル)には半日遅れで到着しました。
このとき清正は、行長と会談して、虫のよいことを提案したというのです。
「秀吉公への報告、貴殿と拙者との連名にしてくだされぬか?」
多くの敵と戦って先に京城に入った行長は、一番乗りの手柄を分け合う意味が分からず、断ります。
すると、清正はすぐさま独自に使者を立てて秀吉のもとに派遣し、「加藤清正、京城に一番乗り」を報告させました。
それを一時は秀吉が信じたことで、それが史実であるかのように誤って広まってしまったとのことです。
計算高い
清正の「虎退治」は「虎狩り」であり、精力の衰えを感じていた秀吉に虎肉を献上することが目的であった。
秀吉の気質を知りぬいた上での自己アピールだったと、豊田氏は断じています。
ほかにも、清正はパレードに力を入れていたなど、計算高さを示す実例をいろいろと書いています。
ただ、『知謀の虎』は文禄の役とその後日談までが主なテーマです。
だから、秀吉死後の、たとえば関ヶ原戦役で東軍についた経緯や、伏見城の会見の話などは出てこない。
そのため、清正が忠義者だったのかについては、家康が秀吉に服従したときの彼の心中を想像して書いているのみです。
加藤清正は、このとき、徳川家康の存在を肝に銘じていた。計算だかい彼としては、秀吉と互角にわたりあった、もう一人の覇者に、おおいに関心を抱いたのも当然である。
筆者の想像ですが、伏見城の会見のときは、計算高い清正ならこう考えたのではないでしょうか。
「(豊臣)秀吉の死後、幼い秀頼では天下を支えきれず、徳川(家康)に天下が渡った。いま家康が死んだとしたら、再び豊臣(秀頼)に天下が戻るかもしれない。それに備えて、布石を打っておこう。」
大槍を振るう豪傑か?
清正は、周囲に槍の名手だと思わせることで、豪傑のイメージが生まれて得になると計算していた。
しかし実際には槍ではなく鉄砲が得意だったと、豊田氏は想定しており、その根拠をいくつか書いています。
槍か鉄砲か
清正は、実に鍛冶屋との縁が深い人物です。
清正の生母お伊都の父親は、清兵衛という名の鍛冶屋
姉婿の五郎助は津島の野鍛冶
秀吉の領地北近江には、火縄銃の生産拠点である国友村がある
そして、清正が成人してからの武功には、なぜか鉄砲が多く関係しています。
天正十(1582)年六月 近藤半助(明智光秀配下の鉄砲隊組頭)
天正十一(1583)年三月 近江新七(滝川一益配下の鉄砲隊長)
同年四月 仁波隼人(柴田勝家配下の鉄砲隊長)
「たまたま清正の目の前に敵の鉄砲隊長がいた」という偶然が続くとは考えにくく、「鉄砲隊どうしの銃撃戦を制した」と考えるほうが合理的です。
また彼は、配下の部隊には先進的な装備を持たせました。白兵戦ではなく、鉄砲による銃撃戦を想定して、徹底的に最適化したのです。
「加藤勢に具足なし」と文献にある。
:
清正が具足を廃止した理由は、もっと先見的なものだったろう。
どんな鎧を着ていても、銃弾をふせぐことはできない。ならば、兵士の機動性、敏捷性を考えて、鎧は廃止してしまおうということになる。
:
清正が、雑兵にいたるまで、冑を支給したことを伝える文献がある。冑の鉢は、鉄製である。
鉄のヘルメットに、コンバット・スーツというスタイルが、清正軍の兵士の制服(ユニフォーム)である。
「具足廃止」は、たいへんな先見である。ヨーロッパでも、銃士(マスケティーア)ですら、胴鎧くらいの簡単な防具は、身につけている。
さらには、足軽だけでなく、馬に乗る指揮官も鉄砲を装備しました。「加藤の馬上鉄砲」と言われていたようです。
虎狩りの実情
上述のように、豊田氏は「虎退治」ではなく「虎狩り」であったと考えますが、加えて「清正自身が鉄砲を射って仕留めた」とも書きます。
清正虎退治は、講談、軍記物などで、おおいに脚色されてしまうのだが、
『常山紀談』の記述が、いちばん真相に近いだろう。
:
鉄砲隊が山野に展開し、勢子が一頭の猛虎を追いたててきた。鉄砲隊が発砲しようとするのを、清正は、おしとどめた。
『常山紀談』の記録は、リアリティがある。口語訳する。
「その距離、三十間(五十四メートル)ばかりで、虎は、清正をにらんで立ちどまった。
人々は、鉄砲をそろえて射とうとしたが、清正は射つなと命令した。
自分で射殺しようとしたのである。こうして、虎は、近くまで猛進してきた。
口をあけて、とびかかるところへ発射した。
虎は、そこに倒れ、起きあがろうとしたが、致命傷だったため死んでしまった」
「清正虎退治」の顛末は、この『常山紀談』のとおりに進行したにちがいない。
武断派の軍人か?
理系男子
清正が築城に長けていたことは、ご承知の通りです。
城の縄張りができたということはつまり、数の計算にも強かったようです。
ずっと後のことになるが、女婿の榊原家の財政が赤字になったとき、清正は、帳簿を点検し、的確なアドバイスを与えている。
清正の娘の古屋姫の夫であった榊原康勝にしても、義父に公認会計士のようなことをやってもらい、おおいに驚いたらしい。
:
清正が、築城の天才であったことは、よく知られている。この異色の武将は、自分をショウアップして、周囲の人々に印象づける能力も、じゅうぶんすぎるくらい持ちあわせている。マルチ・タレントと言ってもいい。
ただ、この天才に欠けている点もある。第一に「武」である。理財家、名射手、築城技術者、ヒューマン・リレーション・コーディネーターなど、多面的な才能に恵まれているが、荒っぽいこと、武張ったことは、大の苦手なのである。
ちなみに清正は、「主計頭」という官職をもらっています。朝廷の会計担当です。
律令制度上の官職は当時有名無実と化していましたが、対象者の適性を多少は考慮した任命だったように思います。
京城にて
清正は前線の指揮官というよりも、経営向きであった。
野心家でもあった彼は、朝鮮では自分が担当した方面で切り取った領地をもらって経営するというモチベーションが高かったと、豊田氏は描きます。
文禄の役のときに日本軍が京城で小休止したことは謎の一つとされますが、豊田氏は「清正が、領国として支配を固めるための準備を始めたからだ」と断じます。
日本軍の進撃が、京城で停止したことについて、多くの書物が、小西行長の厭戦気分だとしている。
:
加藤清正が、京城で、占領地行政にとりかかったせいである。戦争は嫌いだが、経営は大好きである。
肥後の北半国を、あっというまにまとめあげ、完全な収奪システムをつくりあげ、一万の大軍を拠出できるまでにしたてあげた清正にとって、肥後も京城も同じことだったのである。
拙者請取之国
清正は、朝鮮半島を行軍しながら、自分の領地とするつもりの土地を探していたようです。
清正が東路を北進した理由は、領土獲得の構想のためである。浅野長政にあてた書状には「拙者請取之国」という表現がある。
清正自身は、外国である朝鮮の北東の一部 --- 咸鏡道を、自分の領国として請取った気になっている。
肥後の北半分を与えられ、赴任したときと変わらない心理である。
北方の会寧府で二王子を捕虜としたことを本国の浅野長政に報告する手紙で、このように書いています。
「良い国なのですが、兀良哈(女真族)が抵抗しているあいだは、望みがありません。
しかし、中国との国境という重要性を考えて、この地を受けとりたいと思います。その他の領国では、日本国内でも嫌です。どうか、そのつもりで、(秀吉と)談合していただけませんでしょうか?」
具体的には何をしたか。清正は、鉱山開発を始めたのです。
1992年七月十五日、咸鏡道の端川を通りかかり、住民の通報によって、近くに銀鉱があることを知った。
ここには、九鬼広隆に一部隊を与えて駐屯させ、銀山を開発させた。
また、この年の年貢米も取り立てて、撤退時には兵糧として持ち運んでいたとのことです。
彼の支配に抵抗する民兵(いわゆるパルチザン)を「一揆之奴輩」と呼んでいることも、注目に値します。
清正も秀吉と同様、朝鮮出兵を国内の統一戦の延長と見ていたのですね。
余談
『週刊 歴史のミステリー No.51 デアゴスティーニ』の中に、「歴史検証ファイル “鬼将軍”加藤清正の実像」という記事があります。
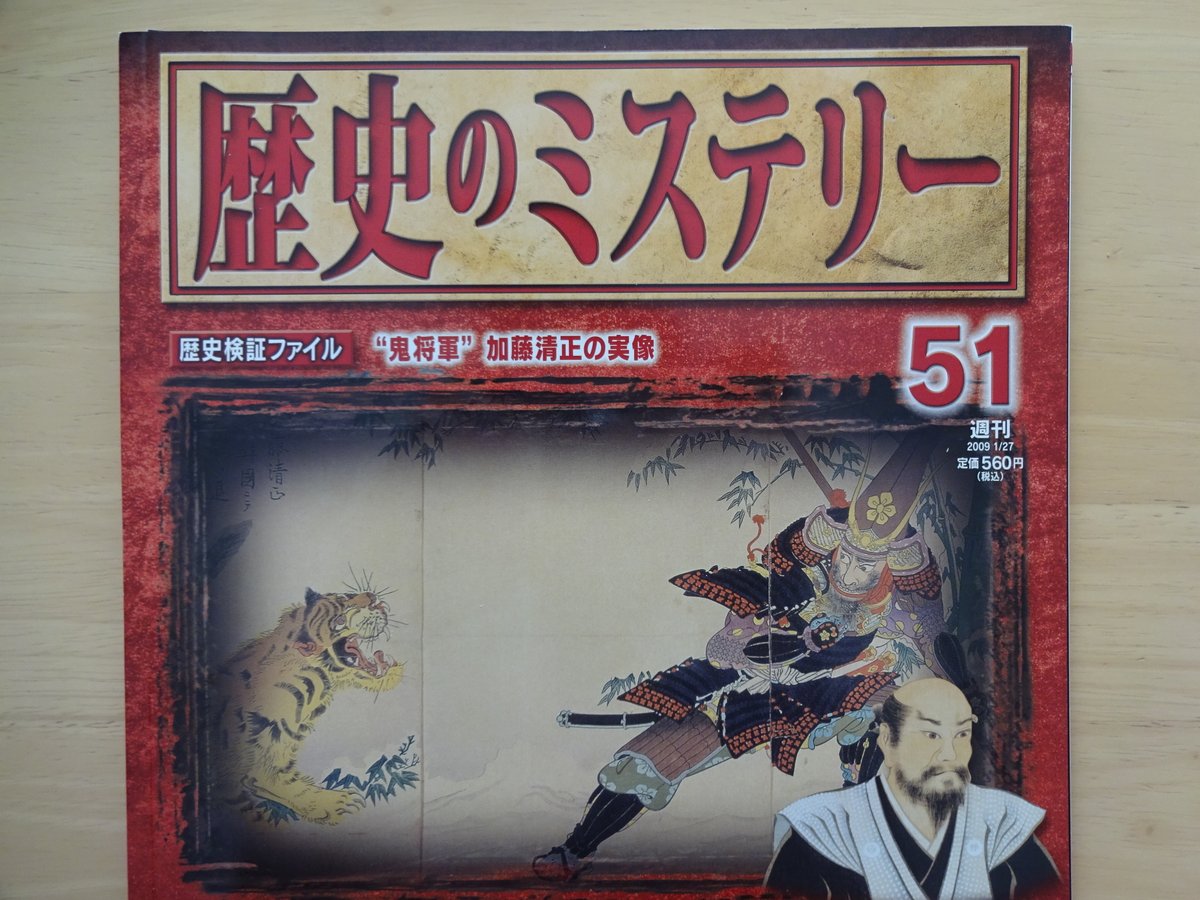
そこで展開されているストーリーは、こうです。
清正は、猛将であるだけでなく、民政や築城術に長けた名政治家であった
秀吉とは血縁関係にあって、死後も秀頼を守るべき立場にあった
文知派が憎いため東軍に参加したが、消極的であった(上杉征伐や関ヶ原の決戦には参加しなかった)
二条城で家康と秀頼が会見したあと、家康は豊臣恩顧の諸将が邪魔になった(ため、清正は毒殺された)
つまり、清正毒殺説を結論としており、その背景として、「秀吉の次の天下人は家康だと思い、自らの意思で東軍に投じた」という"定説"が誤りで、「家康に心を許しておらず、秀頼への忠誠心が篤かった」のが"真相"だと言うのです。
その根拠としては、
清正は家康に毒殺されたという噂が当時からあった
熊本城本丸御殿の奥にある「昭君の間」は秀頼を迎えるためだったと推測する研究者がいる
という点を挙げています。
『知謀の虎』を読んだあとでこれらを見ると、清正のイメージ戦略にまんまと騙されているように思えます。
『歴史のミステリー No.51』の発売は2009年。当然、1989年に刊行された『知謀の虎』を参照することができたはずですが、ちょっと残念ですね。
いいなと思ったら応援しよう!

