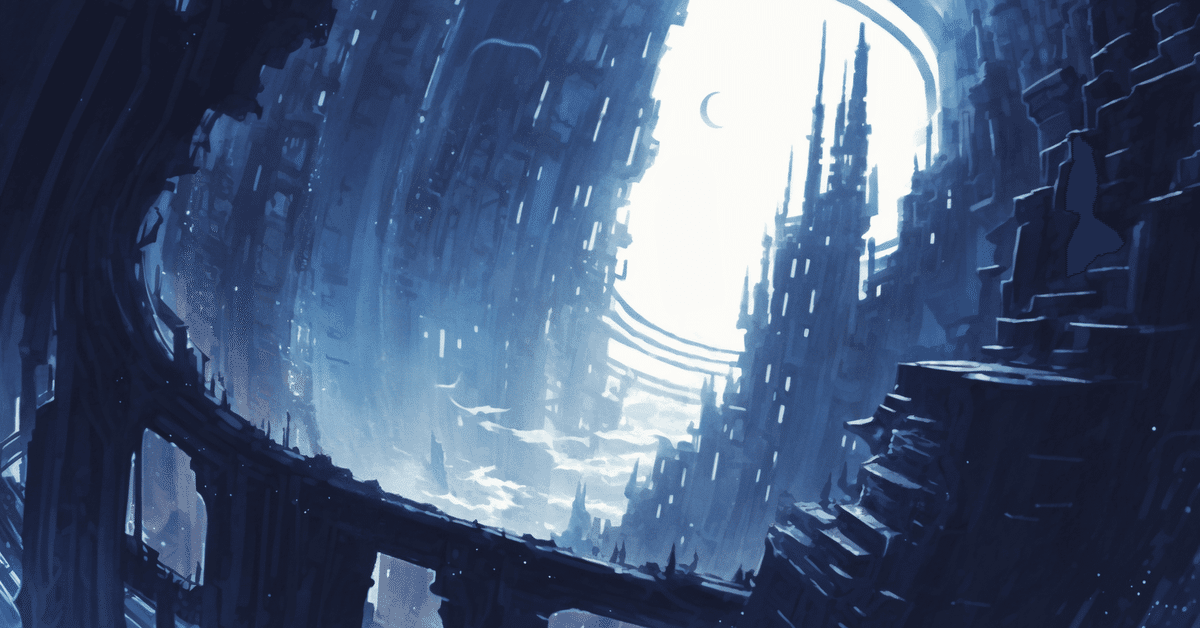
タルコフスキーのストーカー(1979年@ソ連映画)【最近、映画紹介がひそかに見守っている「タイホダ」まだ何も言ってナイゾ】
旧ソ連の天才映画監督。
タルコフスキー。
旧ソ連は社会主義リアリズムという、
あらゆる芸術作品はソ連国家の宣伝でなければいけないという、
無茶な規則がありました。
このため、音楽家以外の芸術家は大変な苦労を強いられました。
(音楽家も大変だったけど)
しかし、多くのソ連作家たちは、あの手この手で規制を潜り抜け、
検閲をパスした上で、自分の主張したいメッセージを込めた作品を発表していきました。
したがってこの時期のソ連映画は非常に難解で、哲学的な作品が多いです。
パッと理解できる作品はありません。
むしろ理解不可能。
理解できるようなら、検閲でざっくりやられちゃいますから。
また検閲官の皆さまがお給料分のお仕事ができるよう、
分かりやすく検閲しやすい場面を残しておかないといけない。
(まあ、中にはそういうのが漏れてしまう場合もありますが)
大事な場面を守るために、生贄の場面をあらかじめ作っておく。
なので、とにかく編集も難解。
だから、タルコフスキー映画を観る際は、考察本が欠かせません。
「ドルアーガの塔」みたいなもんですよ。
いまだになんであのゲームが流行ったのがわからん。
まあ、私も攻略本片手に家族総出でクリアしましたけど。
では、ざっくりんぐとしてあらすじ。
***
まず主人公は、
文明が荒廃した世界に住んでいます。
(核戦争後の世界か?みたいな)
しかし、ある聖域があって、
そこを見つけ出すことで希望が手に入る、と言われます。
なのでそこを目指して旅をする。
考察によると、
旧ソ連は、矯正収容所列島と呼ばれ、国中に政治犯収容所がありましたが、
あれの逆になっているわけです。
つまり外の世界が苦しくて、
収容所的な場所が楽園になっている。
だけどそれは隠されている。
だから見つけないといけない。
もうこの時点でありとあらゆる考察が展開されます。
宗教的な救済とは何か。
旧ソ連の体制批判。
西側も含めた現代文明批判。
環境問題。エトセトラ。
資本主義世界への批判とも取れます。
(少なくとも検閲官の皆さまにはそう説明したはず)
しかしもちろん、それに明確な答えは出ません。
わけが分からないまま、独特の雰囲気を残して映画は終わります。
****
最近、西側世界でも本質的な意味では言論の自由なんてないんだな。
と感じることが増えてきたような気がします。
まあ。仕方ないのです。
完全な言論の自由なんて、人間の社会では元より無理なのでしょう。
もちろん犯罪予告とかテロ肯定とか、
そういう話以前の、本当にただの問題提起の部分であっても、
やはり体制に色はあって、
ポリコレとか、そういう基準への忠誠心がないと、
意見表明すらしてはいけないんだな。
というようなことが、散見されてきました。
社会の寛容さなんて、最初から期待できるようなものではなかった。
それが現実でしょう。
まあ、どんな社会だって思想統制したいという誘惑には抗えないもの。
メリットがありますしね。
民主主義といっても例外ではない。
民主国家と独裁国家に本質的な差などないのです。
ただ表面的な自由の建前をせめて守ろうとはしてくれるだけでも、
まだ良心的と評価するべきでしょう。
だからこそ、ガチガチに検閲がきつかった独裁社会。
タルコフスキーのやり方が、現在に復活される余地があると思うのです。
すなわち、
本当に言いたいことはオブラートに包んで、
分かる人にだけわかってもらえるように暗号化しておく。
それが文学なのだ。それがアートだ!
タルコフスキーは不滅なのです。
もうお分かりですね。
聖域は私たちの心の中に存在するというのが、
私なりの解釈ですが、まあこれは私が考えただけです。
たぶん作品を観られた方の数だけ、解釈があります。
もうひとつの「2001年」
#映画感想文 #SF映画 #ソ連映画 #抽象的 #タルコフスキー
#一見してわからない #もうひとつの2001年 #難解
#解釈 #多様な解釈 #観た人によって異なる #検閲対策
#ソ連の検閲 #哲学 #荒廃した世界 #能力 #部屋の秘密
#宗教 #神秘 #ソ連時代 #収容所列島 #謎 #知的冒険
#人が期待するもの #絶望 #希望 #現実 #奇跡
