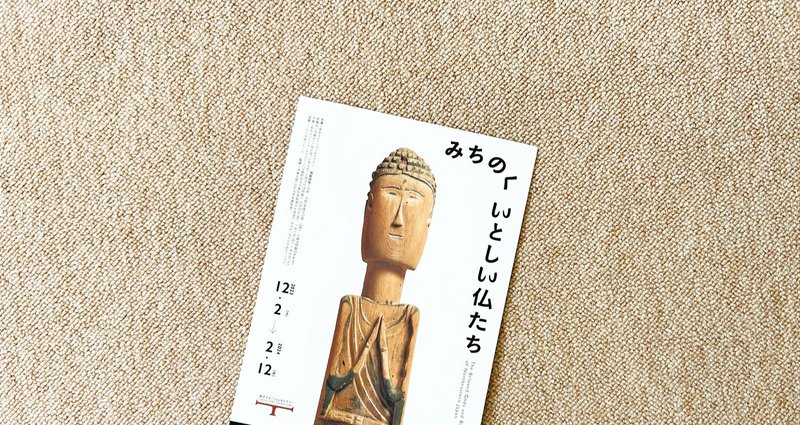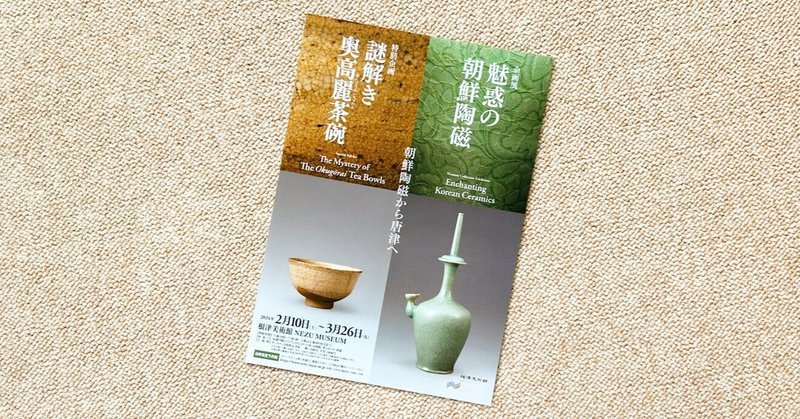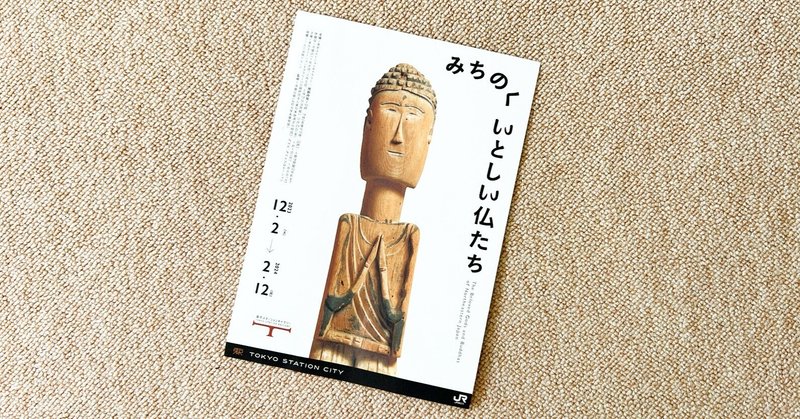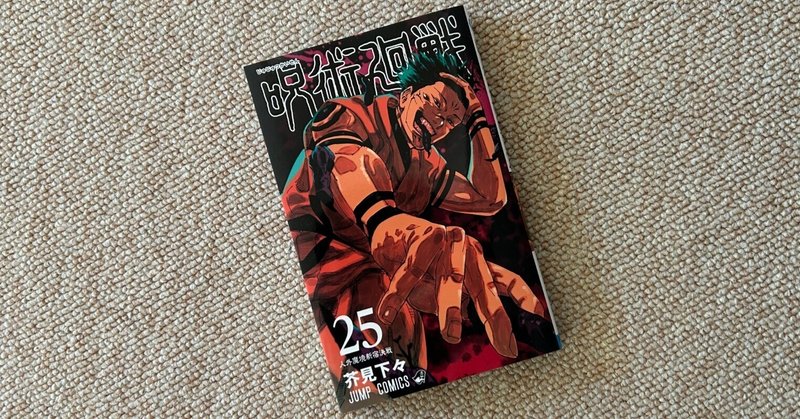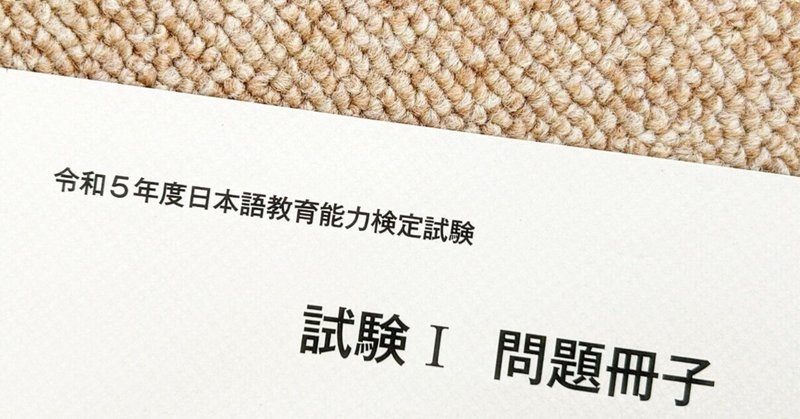#考察
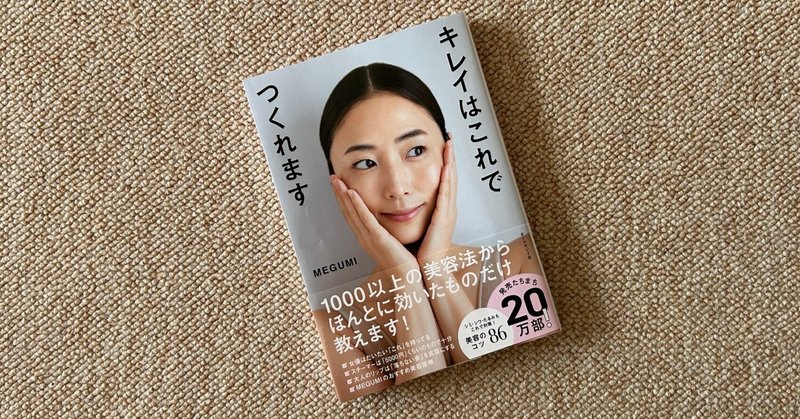
[OldCityBoy的「カルチャー」考察] 美容の本質は、紫外線対策、保湿、そして、ほんの少し身体に生命の危険を与えること
加齢とともに美容に興味を持ち始め、色々試していると、褒められることが妙に多くなり、社内の女性と美容トークをしていると、自身の考え方が、"男性目線で面白い!"、とのことで、せっかくなのでここでも記載しておきますね。 男性目線、というかゴリゴリ理系目線から美容を語ると、 美容における老化とは、肌の保水量が減ることであり、その原因は紫外線である。ならば、美容はその逆をすればよく、紫外線を防ぎ、保湿をすればよい。 となります。 ここでポイントなのは、 美容品の質(金額)ではなく、

[OldCityBoy的「カルチャー」考察] "新しい学校のリーダーズ"の売れるスピードが予想より倍速だった件、と2024年の予測
未来予測に凝っているゴリゴリ理系です。なぜなら、未来が分かるのであれば、現在どこに投資すれば良いかが分かるので。 "人間は未来など絶対に予測できない"、 とよく聞きますが、そんな時は、 "何も食べないと明日にはおなかが減るのは予測できますよね?" な返しをすると、なんとも微妙な顔をされるのですが、 人間は直近の未来は確度高く予測でき、また、過去をきちんと分析し、今の状態をよくよく観察すれば、もう少し先の未来も予測できる、という自分なりのメッセージです。 というわけで、今の