
#49 姿勢とボディスキーマ(身体図式)
パーソナルトレーニングジムSISEIの宮谷です。
久しぶりの投稿になってしまいました…
みなさんは毎日さまざまな姿勢で生活されていますが、その姿勢はどうやって形成されていると思いますか?
姿勢はボディスキーマ(身体図式)という地図をもとに作られています。
本日はボディスキーマ(身体図式)がどのように作られ、姿勢にどんな影響を与えるのかを、簡易的に説明させていただきます。
ボディスキーマ(身体図式)とは?

ボディスキーマ は“身体の図式”と言われるように、「自分がどんな姿勢なのか」「どんな動きをしているのか」が目を閉じていても分かる無意識な認知機能のことです。この地図(図式)は、生まれたての赤ちゃんの頃から作られていきます。
人間は産まれたての赤ちゃんの頃は、手足の存在を知りません。
自分のカラダや周りの環境にある色んなものに興味を持ち、カラダを動かし目で見て手で触れ、さまざまなものを認知していきます。
また成長に伴い、“膝立ち”や“つかまり立ち”ができるようになることで、膝や足の裏で体重を感じ、自分には足があることを徐々に認知していきます。
またハイハイや歩くことができるようになることで、それが自分で動かせることに気が付いていくのです。
このように、多くの情報が脳に記憶されていくことで、ボディスキーマ(身体図式)は徐々に作られていきます。
しかし、このボディスキーマは日常生活のさまざまな習慣により変化します。

例えば、毎日長時間のデスクワークで猫背や巻肩の不良姿勢を続けると、自分では気が付かないうちにボディスキーマは変化してしまいます。
それは身体が歪んでいても、人間の頭部は視界を水平に保とうと無意識に位置を修正するため、どんな不良姿勢になっていてもそれを真っ直ぐだと認識してしまうためです。
このようにボディスキーマ は日々の生活習慣によって書き換えられ、不良姿勢が正しい姿勢だと誤認識されてしまうようになってしまうのです。
ボディスキーマの構成要素

ボディスキーマ の形成に必要な構成要素は、3つの感覚が関与すると言われています。
1.体性感覚
体性感覚は、カラダの状態や外部の刺激を感知する感覚の一つです。
皮膚、筋肉、関節などにある受容器(感覚器)が、触覚、圧力、振動、痛み、温度、体の位置(運動感覚)などの情報を脳に送ります。
この感覚は私たちが日常的にカラダを動かしたり、周囲の物と触れたりするときに重要です。

体性感覚は、感覚ニューロンと経路からなる複雑なシステムで、身体の表面や内部の変化に反応します。また、身体の位置に関する情報を脳に伝え、脳が適切な運動反応や動作を起こすことで、姿勢のバランスを保つことにも関与しています。
感覚ニューロンとは?
特定の種類の刺激を信号(活動電位)に変換する神経系の神経細胞である。
2.前庭感覚
前庭感覚とは耳の奥にある三半規管や耳石器によって得られ、体の傾きや加速度(スピード)、回転などを感じることができる感覚です。
前庭感覚は傾斜面に立ったり、凸凹の場所に立ったり、目を閉じた状態で立ったりするときなど様々な環境下で、感覚の方向性と適切な感覚の手がかりを用いて体幹を垂直にします。また、傾いたりするような姿勢運動の際に頭部を安定させます。

前庭感覚と視覚が相互関係によって調整されることで、寝返りや起き上がりなど複雑な頭頚部と体幹、四肢の協調運動が成立します。
3.視覚
視覚は感覚器であり、バランスを維持するための感覚情報の主要なシステムです。
開眼と閉眼ではバランス感覚の差が大きく、このことからも平衡感覚と密接に関わっていることが分かります。
ただし先述したとおり、姿勢が歪んでいても脳は目線を水平に保とうとする働きがあるため、視覚からの情報が正しい姿勢に導かれているとは言えません。
目線が真っ直ぐでも、カラダは歪んでいる可能性はあります。

健常な成人では動作時、体性感覚70%、前庭感覚20%、視覚10%の割合で身体図式が生成されていると言われています。
さまざまな状況下によってその割合は変化し、目を開けて立っているときは約70%を視覚が占め、逆に目を閉じているときは前庭感覚が約60%を占めるとされています。

この3つのシステムの中で1つでも不十分な場合、姿勢制御やバランスに影響を与えてしまいます。しかし、1つのシステムが影響を受けた場合でも、他の2つのシステムを訓練して代償することが可能です。
運動経験がない、運動不足な生活を過ごしているとどんどん感覚が鈍り、筋肉が固まったりバランスが崩れてしまうことで、ボディスキーマは間違った情報へと書き換えられてしまいます。
一度崩れたボディスキーマは自然に修正することは難しいため、自分のカラダに対する意識と関心を高めること、バランスや協調性を養うためのエクササイズやスポーツを行うことで改善される可能性があります。
ボディスキーマを整える

みなさんが日常で感じる身体の不調もボディスキーマの崩れが原因かもしれません。
正しいボディスキーマを形成するためには3つの感覚を磨くことが大切です。
トレーナーとして特筆したいのが、「可動性(モビリティ)」「安定性(スタビリティ)」を高めるトレーニングを行うことです。
人間のカラダにはさまざまな関節が存在し、関節に関わる筋肉によってカラダを動かしたり、支えたりしています。
それぞれの関節にはモビリティ(可動性)とスタビリティ(安定性)という正反対の働きがあり、モビリティ優位なタイプとスタビリティ優位なタイプに分けられます。
モビリティ関節とスタビリティ関節は交互に積み重なっていると考えられ、アメリカの理学療法士グレイ・クックと、ストレングスコーチのマイク・ボイルにより提唱された理論を「ジョイント・バイ・ジョイントセオリー(理論)」と言います。

モビリティ(可動性)関節の動きが筋肉の緊張などで抑制されてしまうと、動かずに支える役目のスタビリティ(安定性)関節を動かそうとする代償動作が起こります。
その現象が一部の関節や筋肉、靭帯に負担をかけてしまい、身体の痛み・機能的な不調が生じることにつながります。
例えば、長時間座りっぱなしのデスクワークなどを不良姿勢で過ごしていると、頸椎・胸椎や股関節の可動性が失われてしまいます。

特にやりづらくなるのが「振り向き(体幹の回旋)動作」です。
正常な振り向き動作は、頸椎50°、胸椎35°、腰椎5°、あとは股関節の内旋・外旋の相反動作で行われています。よくゴルフなどの捻転スポーツで「腰をねじる(ひねる)」と言われますが、腰椎は5°しか回旋しないスタビリティ(安定性)関節です。
※ 体幹の回旋についての詳しい情報は、下記の記事を参考にしてください。
モビリティ関節である頸椎(上部)や胸椎、股関節の可動性が失われると、スタビリティ関節である腰椎や膝関節をねじろうとする捻転ストレスが加わり、腰や膝を痛めてしまう原因になる可能性があるのです。
モビリティ優位な関節がスムーズに動かせ、スタビリティ優位な関節がしっかりと安定していれば、各関節や筋肉などの受容器(感覚器)に正しく信号が送られ、美しい姿勢のボディスキーマが構築されるでしょう。
では、可動性と安定性を高め、ボディスキーマを整えるためのエクササイズを3つご紹介します。
❶ 胸椎回旋エクササイズ
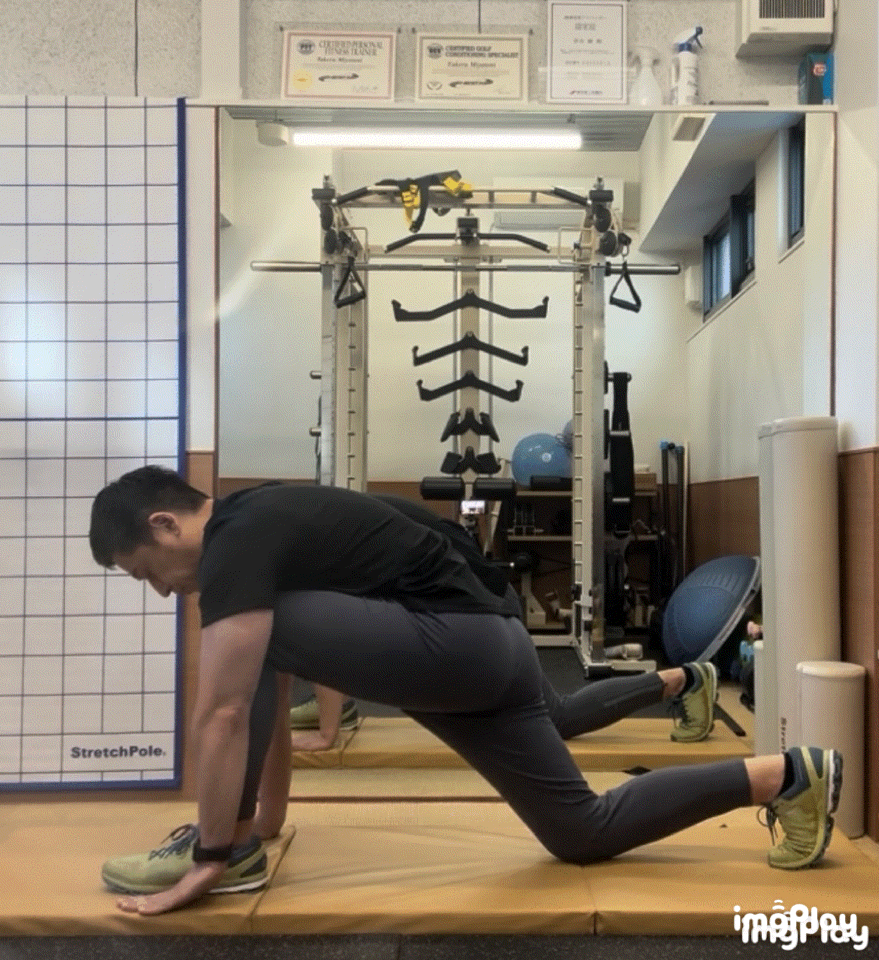
① 前後に大きく脚を開き、前方の足の横に手を置きます。
② 後方の足の膝を伸ばし、前に出した足側の手を反対の肩に置きます。(写真では左手を右肩に置いている)
③ 胸を開くように肩で軸を回転させ、天井に向けて腕を伸ばし、指先を見つめた状態で5カウントキープします。
④ 反対側も同様に行います。
❷ 体幹・バランス強化エクササイズ

① 四つん這いになります。
② 対角線上の腕と脚を上げ、腕から脚までが一直線にピンと張るように伸ばします。
③ 伸ばしていた腕と脚の肘と膝を曲げ、カラダを丸めながらくっ付けます。
④ 2と3の動作を繰り返し行います。
⑤ 反対側も同様に行います。
❸ 【難易度高め】胸椎回旋➕体幹・バランス強化エクササイズ
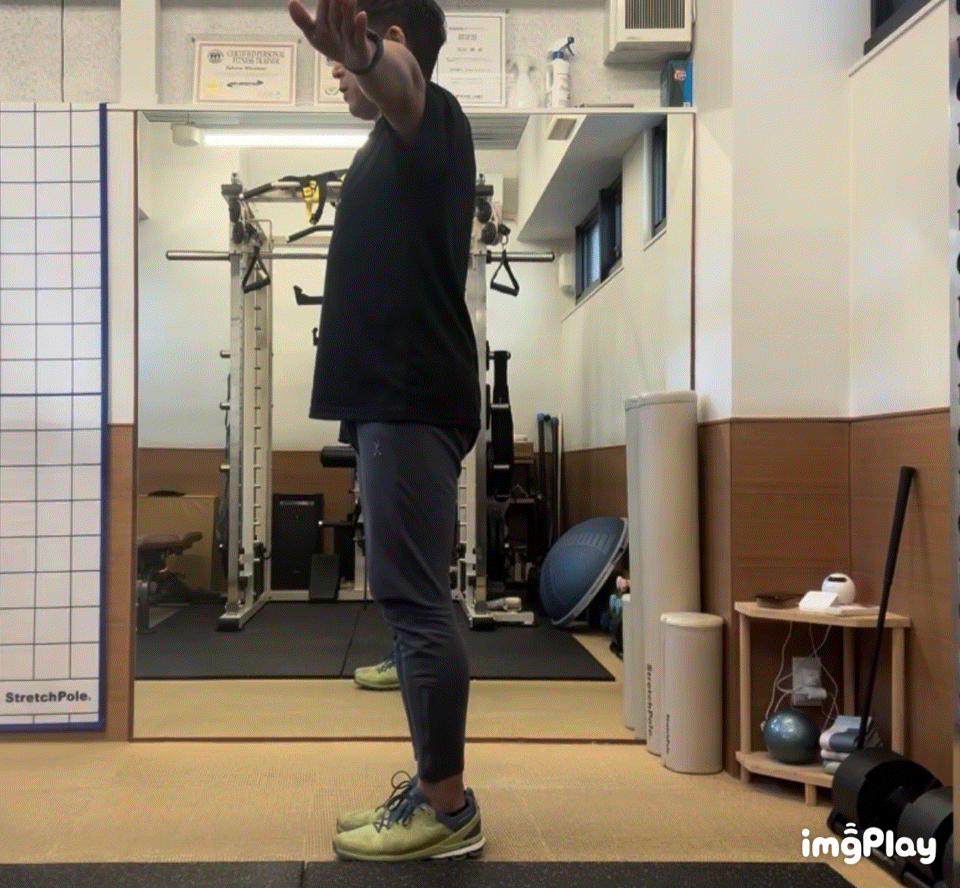
① 腕を広げて立ちます。
② 片足を後ろに上げながら、上体を前に倒します。このとき、頭から足先まで1本の棒が入ってるように、連動して動かしましょう。
③カラダを床と水平まで倒したら、立っている軸足の方向にカラダを回旋させます。
④ 反対側も同様に行います。
この3つのエクササイズを行う上での注意点としては、呼吸を絶対に止めないことです。
カラダをねじったり、丸めたりするときには、息をゆっくり大きく吐きながら行いましょう。
呼吸を止めてしまうとカラダが力んで、筋肉が緊張状態になってしまうため、思うように動かせなくなります。
この3つのエクササイズではカラダを支える体幹の筋力が備わっているか、モーターコントロール(運動制御)が上手くできるかが重要になります。
モーターコントロール(運動制御)とは?
脳や神経系が筋肉を制御し、適切な動作を実行する能力のことを指します。
エクササイズ中に自分の想像した手足の位置と、実際に動かした手足の位置にズレが生じていないかということです。
その誤差が少ないほどモーターコントロールが上手く働いていることになります。
このエクササイズを反復練習することでモーターコントロールの精度が上がり、ボディスキーマを改善することが可能になります。
エクササイズを行う際には私のようにスマホで動画撮影し、自分の思い描いた動きと実際の動きに違いがないか確認してみましょう!
今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
崩れてしまったボディスキーマは自然に改善することはありませんので、毎日を正しい姿勢で過ごす意識を持ち、カラダを動かす習慣を身につけて可動性と安定性を高め、モーターコントロールを磨いていきましょう。
