
心象の世界とまなざし
上賀茂神社参拝後、歩けるところまで歩こうと鴨川沿いを歩き、荒神口まで。

artspace co-jin で行われている展示「ル・ガール 山崎俊生と心象の世界」を観に行った。

京都府立洛南病院で絵画教室を務めていた山崎俊夫さんの作品と、その絵画教室で制作された方々の作品の展示。
この絵画教室は山崎さんが同志社大学院在学中に精神医学や心理学の研究をしていたことから現場での学びを求め、知人の看護師を頼りに洛南病院を訪問。精神疾患の治療を受けている方々と交流した際に、たまたまお会いした病院の院長に「何か表現をする時間が必要なのではないか?」と提案したことから絵画教室を開催する運びとなったそうで、そこで生まれた作品の数々が展示されている。

観ていて明るい気分にはならない。
むしろ不安や不安定なものを感じる。
しかし、その絵を描いている人は、それが内側に「ある」のだ。それが住んでいるのかも知れない。
言葉にできないような感情は生き物のようで、無視しようとすればするほど力を持つ。例えそれがどんなものでも、観た人がどう感じようと、自分が表現して出すということは、どんな薬を飲むよりもずっと魂を解放して心を癒すことにつながる気がする。
八重山に住んでた頃「心の杖として鏡として」というドキュメンタリーを観た。精神病院にアトリエを作り、創作活動をする方たちのドキュメント。
石垣島の闘牛場の近くの施設で観たと思う。福祉施設だったのかな? あまり覚えてない。映画を観た後にいろいろ感じてボンヤリしていたらひとりの男性に声をかけられ、映画の感想を求められた。うまくまとまらないけどポツリポツリと伝えた。何を言ったのか思い出せない。男性が私に何を話したのかも思い出せない。だけど、その男性は私から感想の言葉を求め続けた。嫌な気持ちにはならなかったのでロビーでしばらく話していた気がする。その方はどうやら当事者の方だったようだ。
私がこんな風に文章を書き始めたのは、ある人にメールで自分の思い出をエッセイみたいに書いて送ったことがきっかけだった。文章を書くのは好きだったけど、自分のことを書いたものを人に読んでもらうつもりはなかった。だけど、何かその人を笑わせたり元気づけたいなと思いつつ、ふつうにメールを送っても反応無いし、これで最後にしようと思って書いたら何かわからないけど喜ばれた。喜んでもらえると嬉しくなって調子に乗りやすい私はその後も書き続けた。
だけど書いてる内に、その人の為にではなく、私が自分の心を解放する為に書いてることに気づいた。誰かを元気づける為ではなく、実は私の傷を癒やす為に書いてたんじゃないかな。
歌もそうで、どんとの「おめでとう」という歌を聴いた時に自分でもよくわからん魂が震えるような感動があり、その時の感動をもう一度味わいたいとか、アレは何だったのかを知りたくて私は歌い始めた。
歌い始めてから「もっといろんなバリエーションを持って」「もっと人を楽しませることを考えて」とアドバイスされて、そうしてみようとすればするほど自分の感動や喜びから離れていく。それだけでなく、いい歌を歌えてる感覚から離れていった。私は結局、自分が喜んでないと出来ないんだと思った。
自分にとって大切なものは、どんなひとりよがりに見えても、私が喜んで、私が納得することを1番にしたい。人から評価されたいのではなく、自分が喜びたいんだ。歓喜して自分らしく生きたい。そしてその歓喜が伝わる人に伝わればいいな。
co-jinから歩いてかもがわカフェに行き、珈琲を飲んで本を読みながら、そんなことを考えていた。
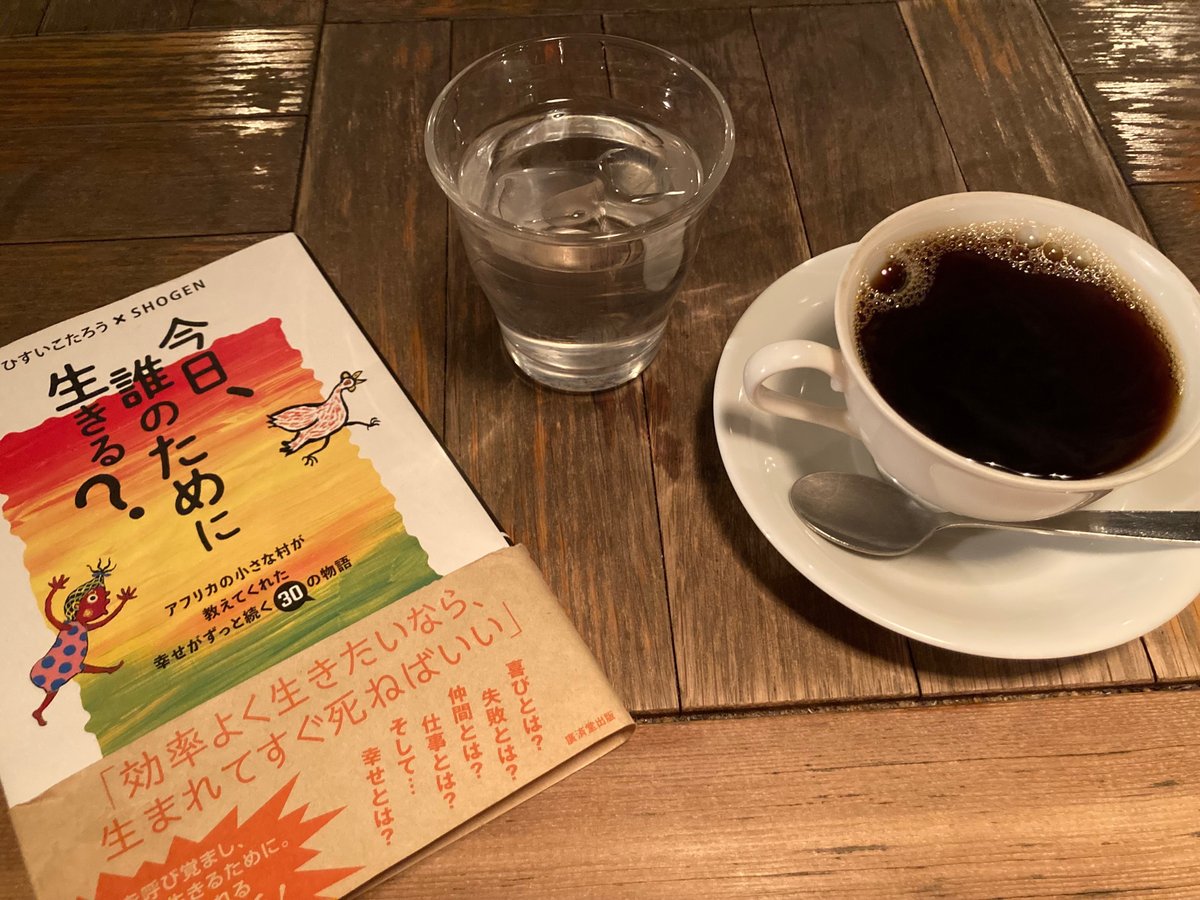


いいなと思ったら応援しよう!

