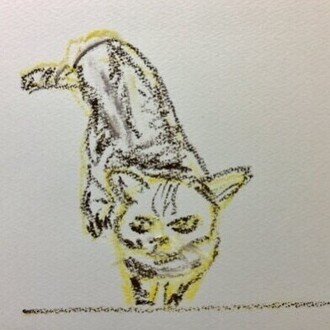記事一覧

「まちづくり協議会」の新役員が選出されたことを「市民センターだより」(6月1日号)で知って考えたこと——ココログの記事の紹介
まちづくり協議会の新役員選出にともなって、まちづくり協議会に「相談役」という役職が新設されたこと。また、それ以外の校区2団体(社会福祉協議会、自治連合会)にもその役職が同時に新設されたようであること。 いままでの例から考えると、同一メンバーが、まちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会の役員(新設のものを含む)に就任した可能性があること——相互に関係のある複数の団体の役職を同一人物や同一メンバーが務めていれば、「利益相反」の問題が生じる。 おそらく、まちづくり協議会では