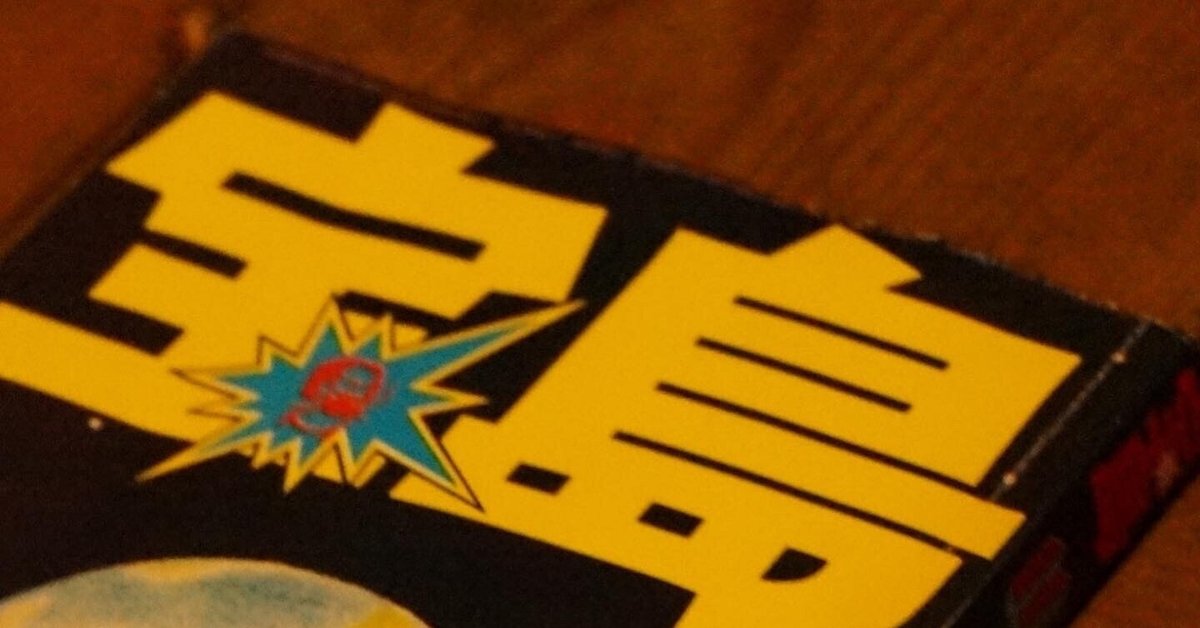
【書籍紹介】宝島 第3巻11号 全都市カタログ

宝島 第3巻11号 全都市カタログ
植草甚一責任編集
1975年発行
ーーーーー
企業とのタイアップによってふんだんに金をかけ、レイアウトに凝り、グラビアで印刷されたカタログに、文化なんぞはあるわけがない。
あるものは、いらないものをきれいごとのように押し付けるいやらしさだけだ。
『全都市カタログ』は、断じて文化なのではない。それは、生活そのものなのだ。
ぼくたちが、生き残るための基礎知識なのだ。
ーーーーーー
1970年代、日本では角栄ブームの真っ只中。
工業化と消費社会化が急激に進む一方、
資本主義に異を唱えるカウンターカルチャーも最盛期を迎えていました。
当時、ヒッピーのバイブルとして世界中で読まれていたのは、
米雑誌『ホールアースカタログ』<1968年ー1972年>でした。
「自分たちの手で、生活をつくる」
いわゆるDIY<do it yourself >の思想で個人に力を与えようとした
『ホールアースカタログ』の影響は、もちろん日本にも及びます。
当時、アメリカ文化に憧れ、タバコをふかしながら洋楽レコードを漁り、小難しい哲学書をたまに読み、政権批判や映画談義に花を咲かせるような、尖った日本の若者たちがいました。
彼らがこぞって読んでいた雑誌が「宝島」。
日本のヒッピー文化の先頭を走る「宝島」が『ホールアースカタログ』の流れを受け、真っ先にオマージュ的な特集を組んだのです。
『全都市カタログ』は、「ヒッピーのための書籍カタログ」のような構成です。
約120ページにもわたる、植草甚一さんによる書籍紹介。
都会に住みつつも、「DIY」を実践するために必要な知識やツール、マインドを得るための書籍が並んでいます。
一番はじめに『荘子』が紹介されているのがグッときました。
(余談ですが、日本のヒッピーが東洋思想を逆輸入しているのが面白くて、深掘りしたいんですけどまた今度・・・)
大きな資本に頼らず、自分たちの手で生活を作り、理想を追求していこう。
社会主義ぽさもありますが、政治的なメッセージ性はうすく、個人をエンパワーメントする、という小さな枠に収まっています。
自分だけのバイブル本をこぞって探す、
当時の尖った若者たちの様子が目に浮かぶようで面白いです・・・(私もその時代を生きてみたかった)
『ホールアースカタログ』『全都市カタログ』が出版されてから約半世紀。
止まることを知らない資本主義のサイクルのなかで
「小さな範囲で自分たちの生活をつくる」という視点と実践は、
個人の幸せの範疇にとどまらず、社会的にも必要になってきているのではと・・・。
そう思いながら、自分のできることを少しずつ積み重ねていく日々です。
商品購入はこちらから
https://matatabibook.base.shop/
https://matatabibook.base.shop/
