
紺野登の構想力日記#06
POV【2】
能から学ぶ「離見の見」の視点
◇ Innovation is About Changing Perspectives
前回は少々ネガティブな日記となってしまった。
世界にあまり明るい未来は見えていないのだから、まあ仕方がないかもしれない。
いまの日本の硬直化した状況には未来は無い、とまで言われる。だから、これこれの課題を解決せよ、と。
しかし、たくさん掲げられる(似たような)課題をどう解決したらいいのかの筋道が示されることは稀だし(少なくともこれまで解決できなかった)、あるいは解決したところで、よりましな世界が訪れるというだけ(遅れを取り戻せ、的な)のようにもみえる。
コロナ問題についても、このあいだお会いした科学者のK先生(お名前は伏せる)がこんなことを言っていた。
「国際会議でもいろいろな議論が起きるが、なかなかユニークな解決案は出てこないんです」
積極的なイノベーションや構想が提示されなければならない。
構想力日記の6日目。「POV=視点」シリーズの2回目なので、今日は、視点の鍛え方について書いていく。
構想の起点には「視点」がある、だから視点がとても大事なんだと前回書いた。視点がズレていたために、悲劇を経験した企業の例なども紹介した。ではどうしたらいいのか。
憂き目にあわないための、良き目のはたらかせ方を考えてみよう。
◇ 潜望鏡をのぞいているのは誰?
ある企業がイノベーションを起こしたいと心を決め、とはいえオフィスの外に出ずに一生懸命情報を集め、いろいろな手法を用いて分析をする。いくつもマトリックスを描いたり、どの方向にイノベーションの可能性があるかを見定めようとする。
よく行われていることだと思うけど、それでその企業にとって有効なイノベーションの領域が見えてくる可能性は、ほぼゼロだろう。
これって、ちょうど潜水艦から潜望鏡で海上の世界を見ているのと同じなんじゃないかと思う。自分は海底深く沈んだ潜水艦の中にいて、そこから垂直に伸ばした潜望鏡をのぞいている。潜望鏡をくるくる回転させていろんな角度から海上の様子をとらえる。そして一生懸命観察する。なるほど、見えたぞと納得して、海上の世界の全容が把握できた気になる。
でも、実際に見えているのは潜望鏡のレンズで「切り取られた世界」だ。潜望鏡をどれだけ高機能にして観察したところで、映し出されるのはその切り取られた世界の分析結果にすぎない。
潜水艦のなかは快適だ。何不自由なく過ごし、昨日も今日も、たぶん明日も、潜望鏡をのぞいて海上の世界を観察する。集まった情報を並べて分析する――。
論理分析的思考とは、そもそもこういったものなのだ。
分析するって、いったい何を?
そもそも何のために?
論理分析的思考が犯す過ちの多くは、この「潜望鏡からの視点」とセットになっている。
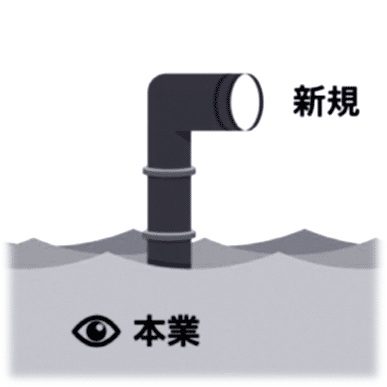
自分の居場所(例えば本業意識とか専門意識とか)に浸りながら、外の世界を観察し分析し、理解したと錯覚してしまうのだ。でもそれは錯覚、見ているものは幻像なのだ。
幻像から構想を起ち上げることはできない。潜水艦から抜け出して、しっかりと地に足をつけよう。
ということでこの日記もちょっと舞台を移す。
◇ 離見の見~他者のまなざしを、わがものとする
じつは、隠れ坂東玉三郎ファンである。隠さねばならぬ理由があるわけではないが、なんとなく、隠れファン。
どの公演のパンフレットだったか思い出せないが、誰かとの対談のなかで、彼が「離見の見」(りけんのけん)を語っていたことをよく思い出す。
こんな内容だったと思う。
舞台では、女形である彼は、酔って取り乱した姿や、嫉妬にかられ怒りで取り乱す女性の姿を演じる。観客には、しっかりと、酔ってふらふらしているように見えなければならないし、あるいは怒りの感情が伝わらなければならない。しかし、どんなに醜く取り乱しているように見えても、その姿はあくまでも美しくなければならない、という。
そのために、どんなときにも「離見の見」が必要だというのである。
取り乱していても、どこかでコントロールされている。意識が自分を離れて、自分を見ている。そのまなざしが離見の見。そういう視点が必要だと言うのだ。
自意識を強く持てばコントロールできるかというと、そうではない。自意識だけではコントロールできない。自意識から離れて、自分をいろいろな角度や距離から見ることができなければ、演戯を完成させることはできないということだ。離見の見は単なる「俯瞰」などではない。

離見の見は、世阿弥が能楽論書『花鏡』で説いている言葉である。
700年前の藝術論、世阿弥の「離見の見」は、ぼくには少し抽象的でわかりにくい。けれど、玉三郎が、どこか別の場所から自分を冷静に見つめながら演戯する様は想像しやすい。
舞台の上の玉三郎の美しい舞い姿と、対談の言葉が重なることで、離見の見というものが腑に落ちた気がした。
構想力にもこの離見の見が必要なのだ。
そういう視点のとり方を身につけなければならないし、鍛えていかなければならない。
世阿弥はこんなふうに書いている(現代語訳)。
舞には「目前心後」という心得がある。「目は前につけ、心は後に置け」という意味だ。これは、前述の五智の中の、舞智の舞い方をする際の心がけである。観客側から見る演者の舞い姿は、演者自身の目を離れたよそからの見方である。それに対し、演者自身の目で見る自己の姿は、主観的な我見であって、客観的な離見による見方ではない。離見という客観的な見方で見るということは、すなわち観客と同じ心で見る事であり、そうすれば自分の舞い姿を見極めることができる。自己の姿を見極め得れば、自分の舞い姿の左右前後をすっかり見ることになるわけだ。しかし、厳密に言えば、見所同心の見で見るだけでは、前方や左右までは見られるが、自己の後ろ姿だけはまだ見極めえないことになろうか。後ろ姿を見極められなければ、舞い姿に俗な所があっても自覚できないことになる。
したがって、主観を離れた客観的な離見の見方によって、観客と同じ眼で自己の姿を見、さらに肉眼では見ることのできないところまで心眼で見極めて、五体のすべてが調和した優美な舞い姿を保たねばならぬ。これがすなわち、「心を後ろに置く」ということなのだ。くれぐれも、「離見の見」ということをよくよく理解し体得し、自己の眼は眼自体を見ることができない道理を悟って、舞い姿の前後左右を明確に心眼で把握せよ。そうすれば花や
玉に比すべき美しい舞い姿になりうることは疑いなく、目前にその証拠を見ることができよう。(『日本古典文学全集[88]能楽論集 花鏡』)
なるほど「離見の見」とともに「目前心後」という心得があるのだな。主観的な「我見」と、観客と同じ心で見る「離見」と、肉眼で見ることのできないところまで見る「心眼」。これらによって自分の舞い姿を見極めることができるということだ。
それにしても、いったいこんなふうに厳密に、精細に、自己を見ることが、忙しい現代人の人生のなかでどれほどあるだろう。何かを期待して遠くばかり見ている、あるいは近くの見たいものだけ見ている自分たちの姿が、離見の見によってむしろ浮き彫りにされるようだ。
◇ 人類学の「はるかなる視線」
世阿弥の「離見の見」からインスパイアされたのが、20世紀を代表する文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースである。エッセイ集のタイトルを『はるかなる視線』としたのもそのためだという。
私たちの社会とは大きくかけ離れた社会を直接知ることによって、それらの社会がみずからに与えている存在理由を、一方的にこちら側の理論で批判し弾劾するのではなく、多少とも評価できるようになった。自分が属する文明の価値だけを認めるように教育されがちな観察者は、全く異なる文明が固有の価値を開発していると、その文明には価値が存在しないと思ってしまう。彼にとっては、自分のところでだけ何かが起き、自分の文明だけに特権として、事件が次々に起きて累積される歴史があり、その歴史だけに意味(sens)──意味すると、目標に向かうの2つの意味にとる──がある。そして、他にはどのような場合にも、歴史は存在しない、あるいは、そこまで言い切れなくても、歴史は停滞している、と信じている。
しかし、この錯覚は、自分が属している社会で老人が持つ錯覚に似ているし、新しい体制の反対者にも同じような錯覚がある。年齢や政治的な選択が原因で、四囲の状況から置き去りにされたこれらの人々は、自分たちが積極的に参加していない時代の歴史は停滞していると感じる。同じ時代を力強く生きている若者や政権の座にある活動家の場合とは全く異なり、歴史としての事件をいわば動きの止まった状態としてみる。
(『はるかなる視線〈1〉』三保元訳、みすず書房新装版、pp.12-13)
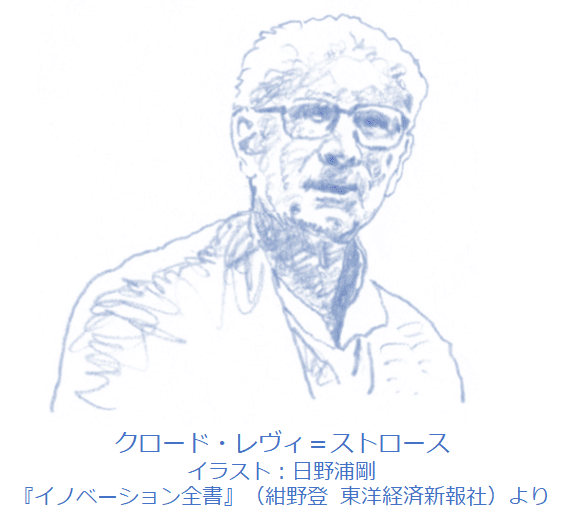
20世紀の思想界にイノベーションを起こしたレヴィ=ストロースの、こんな文章を読むと、21世紀のいま、ぼくらがどんな錯覚や錯視から逃れなければならないかがはっきりとわかる。
◇ パースペクティビズムと近代の錯視
近代という時代は何よりも視覚を大事にしてきた。視覚こそが精神と結びつく最も高貴な感覚だとされてきた。「精神の目」や「心の目」はよく使う言葉だが、「精神の耳」や「精神の口」なんて言ったりしない。
そしてその最も高貴な視覚についての考え方を支配したのが、遠近法主義(パースペクティビズム)であった。
遠近法は、ルネッサンスで開発された描法で、初期ルネッサンス時代のイタリアの建築家ブルネレスキが、現代にも通じる透視図法(一点透視図法)を世界で初めて完成させたといわれている。
これは建築や絵画の世界における一大イノベーションであったわけだが、それにとどまらず、遠近法こそ正しい世界の眺望であるというふうに、人間の視覚が支配されていったのである。
いまのぼくらだって支配されている。カメラのファインダーをのぞけば、そこに写し出される像は、遠近法による画像なのだから。
「世界はつねに特定の視点から特定の見方によってしか見られえないものであり、いかなる視点にも限定されない絶対的な世界認識などはありえない」(Japan knowledge)というパースぺクティビズムは、なかなかパワフルな思想だ。それを引き継いだのはニーチェだった。
ところで、このような遠近法のもとで、その視線を自分自身に向けようとすると、どこに視点を置いたらいいのか。視覚の主体でありその内部にいる自分を、自分が外から見るということができるのか?
これは大きな課題だった。
世阿弥の「離見の見」は、この近代思想が抱えてきた大きな課題に、やすやすと解を与えている。
くれぐれも、「離見の見」ということをよくよく理解し体得し、自己の眼は眼自体を見ることができない道理を悟って、舞い姿の前後左右を明確に心眼で把握せよ。そうすれば花や玉に比すべき美しい舞い姿になりうることは疑いなく、目前にその証拠を見ることができよう。(世阿弥『日本古典文学全集[88]能楽論集 花鏡』)
よくよく読むと、これはわれわれが通常思っている、「目で見る」ということ自体を離れて、「目で聞く」と言うようなことに近いのではないだろうか。目でただものを見るのでなく、周囲の音を耳を澄まして聞くように、自分を見ることなのではないか、と思った。
◇ 越境する感性
今日の日記は、構想やイノベーションのための「POV=視点」をめぐる、世阿弥とレヴィ=ストロースの時空を超えたダイアローグのようになってしまった。レヴィ=ストロースにせっかく登場いただいたので、ごく最近のぼくの活動について紹介しつつ、その背中を押してくれた彼の言葉を最後に記しておきたい。
ぼくはこの9月1日から、ポッドキャスト「越境する感性~Noboru Konno’s “Cross Border Talk”」を始めた。まだ2話しかアップされていないが、果たしてその反響は?
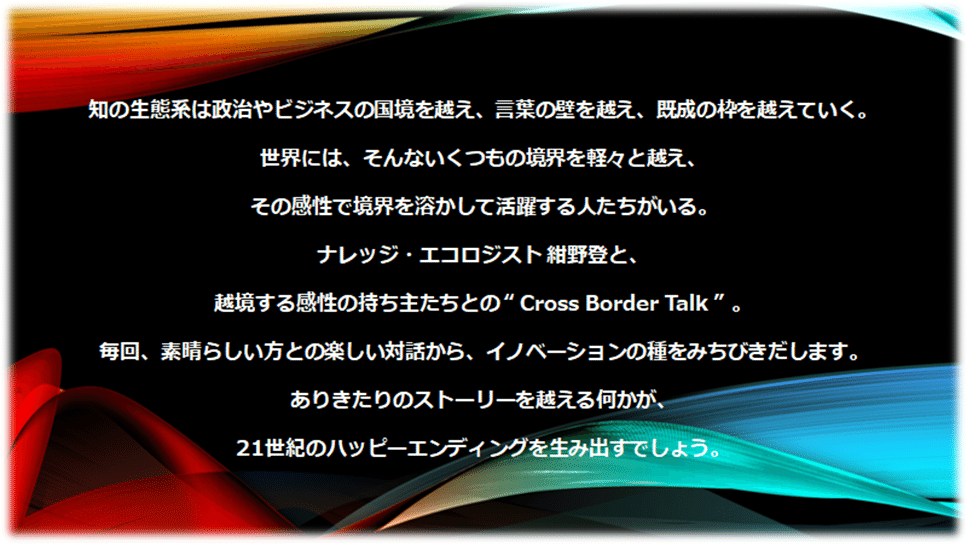
越境する感性は、越境する視点でもある。
レヴィ=ストロースは人類学という学問領域に新風を吹きこんだのだが、それはまさに越境する感性によるものだったと思う。
人類学の独創性は、それぞれの時代において人間性の臨界と見なされている地点に立って、人間を研究することにある。……
人間性というものが永遠である限り、人間の可能性と不可能性を分かつこの境界を探索することを運命づけられている「隙間をつく」科学として、人類学の探求が終わることはないだろう。人類学が自分とは異なる社会に抱く(そして抱き続ける)執拗な関心は、かつて存在しこれからも存在するであろう、すべての社会への人類学の関心の一形態にほかならない。(『パロール・ドネ』中沢新一訳、講談社、p.41)
ポッドキャストでの対話で、できるならぼくもその「人間の可能性と不可能性を分かつ境界」の探索と、その超え方、解き方、溶かし方のリアリティに迫っていきたいと思っている。(つづく)
紺野 登 :Noboru Konno
多摩大学大学院(経営情報学研究科)教授。エコシスラボ代表、慶應義塾大学大学院SDM研究科特別招聘教授、博士(学術)。一般社団法人Japan Innovation Network(JIN) Chairperson、一般社団法人Futurte Center Alliance Japan(FCAJ)代表理事。デザイン経営、知識創造経営、目的工学、イノベーション経営などのコンセプトを広める。著書に『構想力の方法論』(日経BP、2018)、『イノベーターになる』(日本経済新聞出版社、2018)、『イノベーション全書』(東洋経済新報社、2020)他、野中郁次郎氏との共著に『知識創造経営のプリンシプル』(東洋経済新報社、12年) などがある。
Edited by:青の時 Blue Moment Publishing
