
ウクライナとロシアの交点キエフ・ルーシ:無免許解剖#2
こんばんわ。こたろうです。日本語では、「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」と訳されるもので、ウクライナ侵攻が始まる半年前の2021年7月に、ロシアのプーチン大統領が出した論文、ちょっと読んでみたいですよね?でも、机に向かいたくないですよね?
ぎゃーーーー離れないで。せめてスキ!押して!!!できれば読んで!面白いから絶対、面白くなかったらコメントで叩いていいから!
よし、話を戻して。あらゆる参考文献を横断しながら、プーチン論文「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」を素人が解剖していきます。そうです、無免許解剖です。そんな自分が偉そうに、添削して、文句を言いながら、「プーチンの論理」を浮かび上がらせ、「ゼレンスキーの論理」を対比させ、地域としてのウクライナの歴史的複雑性を示す試みです。
強く主張しておきますし、とてつもなく当たり前なことですが、あくまで「ロシアの論理」「プーチンの頭の中」を理解するための営みであり、これが真実などと言うつもりは毛頭ありません。
今、最も大切なことは、プーチン大統領の論理を解釈し、誤謬を指摘し、なぜあのような蛮行に臨んだのかを明らかにする努力をすることだと感じるため、一市民=納税者の私が素人解剖実習を行うのです。

今回は4段落目から無免許解剖。
あ、あんまり#1は人気がなく、、おもしろなくない、、そうなので。
このまま先に進んでもらったほうが良いかもです。今回はきっと面白い。
«Об историческом единстве русских и украинцев»「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」
4. キエフ・ルーシとギリシア正教
ロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人は、ヨーロッパ最大の国家であった古代ルーシの後継者である。ラドガ、ノヴゴロド、プスコフ、キエフからチェルニゴフに至る広大な地域に住むスラブ民族やその他の部族は、1つの言語(現在では古ルーシ語と呼ばれる)、経済的な結びつき、リューリク朝によって、そして、ルーシが洗礼を受けて以降は正教という一つの信仰によって統合されていた。ノヴゴロド公でもありキエフ大公でもあった聖ウラジーミルの宗教的選択は、今日でも我々の親和性を決定する大きな要素の一つとなっている。
まず、大前提として、ベラルーシ人やウクライナ人がいくら文化・言語・宗教などの共通性を持っているといっても、だからロシアとの統一を望むとは限りません。
インド・ヨーロッパ語族に属するスラヴ人が、各地に移動した結果、東スラヴ人、西スラヴ人、南スラヴ人に分かれていきました。そのうち、現在のロシア西部〜ベラルーシ〜バルト三国にわたって居住したのが東スラヴ人でした。
この東スラヴ人による国家がキエフ・ルーシです。そして、この東スラヴ人こそ、現在のロシア人、ベラルーシ人、ウクライナ人になっていきます。

ルーシとは、9世紀から13世紀の前半まで存在していた東スラブ人国家の名称です。キエフを中心としていたので、キエフ・ルーシと後代に呼ばれます。
そして、その建国期には、東スラヴ人同士が喧嘩して仕方なかったので、ノルマン系のヴァイキングの首領リューリクを指導者として招聘したという『リューリク招聘伝説』が残されています。このキエフ・ルーシは、ロシアもウクライナも認める国で、現在のロシア、ベラルーシ、ウクライナの源流となっています。
988年、そのキエフ・ルーシの大公であったウラジーミル1世が、ビザンツ帝国からキリスト教を受容しています。これにより、東ヨーロッパ平原が東方正教会の文化圏に入っていくことになるわけです。
ここでいうキリスト教とは、ビザンツ帝国のキリスト教(東方正教・ギリシア正教)です。
ヨーロッパには、カトリックとギリシア正教の対立がありました。
これの原因を辿れば、かつてのローマ帝国が分裂したことに遡れます。そして、重要なことは、ローマ帝国は東西に分裂後、すぐに西ローマ帝国が滅亡してしまったことです。東ローマ帝国(ビザンツ帝国)というローマ帝国の伝統を引き継ぐ政治権力に守られる形にあったギリシア正教の方が遥かに権威がありました。

ですが、この10世紀は、カトリックの権威がどんどん上昇し、ギリシア正教の権威が下がっていく時期でした。特に、962年にはオットー1世という人が、ローマ教皇から皇帝の冠を被せられます。神聖ローマ帝国という、一見伝統がありそうな名前の帝国を復活させます。その後11世紀には、vsイスラム・vs東ローマ帝国で有名な十字軍遠征などを始めていくわけです。
この10世紀よりも前から、ビザンツ帝国内部では、イエス・キリストの絵や像を作って良いのか?ダメなのか?でめちゃくちゃ揉めて、多くの人々が死傷する内乱が何度も起こっていました。なんで、こんなんで喧嘩するんやろ?と思う人もいるかと思いますので、このへんは後日別のnoteにまとめます(フォローしておいてくださいね!)。

西欧世界(ラテン語世界圏)はどんどん権威も権力上昇していっているにも関わらず、内乱の影響もあり東欧世界(ギリシア語世界圏)は遅れをとっている。そんな状況の中での打開策が、スラヴ人に対する伝道だったわけです。
ここで、強調しておきたいのは、スラヴ諸語の聖典による伝道だったことです。西欧世界のように、お上の言語(ラテン語)で訳がわからん説教をするのではなく、民衆が理解できる言葉で布教を進めていきます。
キエフ・ルーシはユダヤ教、カトリック、ギリシア正教、イスラムといった一神教世界の端っこに地理的に位置していましたが、東ヨーロッパ平原は東方正教会の文化圏に入っていくことになるのです。
実は、スラヴ民族で最初にギリシア正教を受け入れたのはブルガリア人でした。バルカン半島の南のブルガリアで、スラヴ語での典礼が普及していたのです。
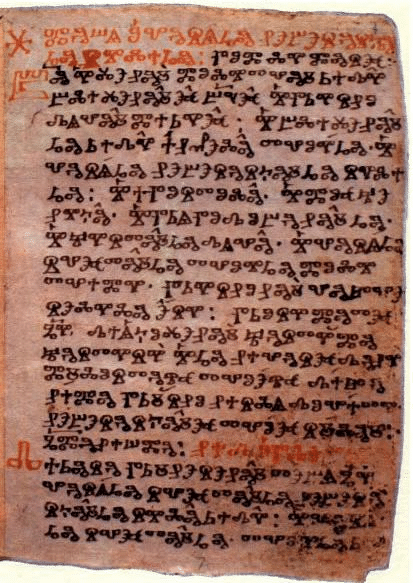
では、誰が、ブルガリアで根付いたスラヴ語のギリシア正教文化をキエフ・ルーシに運んだのか?東スラヴ人の言語の型となった古代教会スラヴ語を運んだのか?
これまた。ヴァイキングの活動なのです。9〜13世紀の温暖化の際に、農業生産が活発化していました。そして、ヨーロッパ各地に商品をお届けしていたのがヴァイキングだったのです。だから、このnoteも読んで!
ロシアをはじめとする東方正教会の世界観と西欧キリスト教の世界観の違いとして、三浦清美さんは、
1. 世界構造の理解
2. 過去への姿勢
3. 暦のあり方
4. キリストの捉え方
5. 言語への態度
で捉えていますが、これについても別noteで。
5. 土地私有の概念が生まれると、人類は弱い
キエフの王座は、古代ルーシにおいて支配的な地位を占めていた。それは9世紀末から続いてきたものである。「キエフをすべてのロシア都市の母にしよう」という預言者オレグの言葉は、『過ぎし年月の物語』によって後世に残された。
ちなみに、『過ぎし年月の物語(原初年代記)』は、この東スラヴ人版『日本書紀』。
キエフ・ルーシは、いくもの公国に分かれていて、そうした諸公国をキエフの大公が統合するという国あり方でした。
もう少し細かくいうと、領土は公の共有財産だったんです。そして、その公の一族のトップがキエフの大公でした。ある種の社会主義っぽい土壌が見られますね。
ですが、地方の諸公がだんだんと台頭して、ある地域の領地が、特定の公の私有物=所有物だという感覚が広がってしまいました。そして、その領地は、公の長男に相続されていってしまったわけです。こうやって、土地私有の概念が生まれると、人類は弱い。限りある土地を巡って血みどろの争いが行われていきます。日本の戦国時代もそうでしょう。
ちなみに、織田信長が天才だったところは、土地という有限なものを争い合い続ける限り戦国時代は終わらないことに気づいたことです。だからこそ、彼は茶の器などに目をつけた。「これは侘び寂びがあって、伝統があって、プライスレスだね〜」と言いながら家臣に茶器をプレゼントする。千利休によるお墨付きは無限ですからね。いくらでも渡せる。小室直樹さんはこのような土地への執着により争いが絶えない状況を「土地フェティシズム」と表現していました。
そして、何よりここで最も重要な点は、
「キエフをすべてのロシア都市の母にしよう」という箇所。
この表現の狙いが、ロシアがウクライナへの領土侵略の正当化にあることは『ウクライナ現代史』においてアレクサンドラ・グージョンさんも指摘されています。
そもそも、この時代に「ロシア」という国はないのだ。「ロシア」という名が現れるのは18世紀以降です。。。ここで言われている「ロシア」は「ルーシ」のことであり、ロシア=ルーシとして捉えるのは誤りなのです。
よって、添削すると、
「キエフをすべてのロシア都市の母にしよう」ではなく、
「キエフをすべてのルーシ都市の母にしよう」が正しい。
単に、当時のスラヴ人の都市(=ルーシ)の首都は「キエフ」だよと言っているだけなのであります。
6. 希ガス
その後、当時のヨーロッパの他の国家と同様に、古代ルーシも中央権力の弱体と分断に直面した。その一方で、貴族も一般民衆も、ルーシを共通の領土及び祖国として認識していた。
話は戻して。次第に諸公らが大公の地位を巡って争うようになり、分裂していった。そんな状況下で、13世紀にモンゴル軍の侵攻を受けて、キエフは陥落していきます。
その一方で、貴族も一般民衆も、ルーシを共通の領土及び祖国として認識していた。
とありますが、本当ですか?これ。
国境線もないし、国民国家という概念もないんですよ?そんな時代に、共通の領土や祖国の感覚があるんでしょうか?
ただの線が、「境界線」のような意識の対象となるのは、例えば、畳のへりを踏んじゃいけないことに民俗学が説明を与えているように、そこに意味づけが行われているから。じゃあ、ただの線が国境という「境界線」として機能するには、どのような意味づけが行われてきたのかって気になる。#国境 https://t.co/QTWZC9wON6
— こたろう (@kotaro_seminar) February 17, 2025
だから、その一方で、貴族も一般民衆も、ルーシを共通の領土及び祖国として認識していた(希ガス=気がする)。
『ロシアの源流』が指摘する3つの淵源
三浦清美さんは、著書『ロシアの源流』で、ロシアが国民国家になりきれない淵源(=一番のおおもと)が三つあると指摘しています。
僕なんかは、プーチン自体は、極めて国民国家と主権の枠組みで思考していると考えているのですが、確かにロシアという国そのものが国民国家になりきれない、もっと言えば、その枠からはみ出してしまうというご指摘は感覚的にも理解できます。
そして、その三つの淵源とは、
・第一段階は、キエフ・ルーシが988年に、ウラジーミル大公の下でビザンツ帝国からキリスト教を受容したこと。
・第二段階は、13世紀前半のモンゴルの来襲
・第三段階は、17世紀末のピョートル大帝が、地理的関係から西欧文化を早くから受け入れたウクライナ、ベラルーシの知識人の影響の下で、西欧化改革を進め西欧列強の一部になっていくこと
うん、ここで全くわからなくても大丈夫です。笑いけます、この記事を読んでいってくれれば。
とりあえずは、この枠組みになんとなく従い、今回の#2では「第一段階は、キエフ・ルーシが988年に、ウラジーミル大公の下でビザンツ帝国からキリスト教を受容したこと。」までに関連する、論文「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」の六段落目まで読みましたとさ。
ぎゃーーーー離れないで。せめてスキ!押して!!!
現在運営している読書会や勉強会、ゼミについて。
おっと。告知を忘れていました。おっと。告知を忘れていました。
私奇才に憧れる凡才「こたろう」と「承服亭しかねる」との二人体制でnoteの運営、読書会や勉強会を開催しております。
笑いながら、でも少し踏ん張りながら勉強できる環境が欲しい方。
ぬーんとふかーく、のんびりたかーく、読書をして語り合いたい方。
ガチガチで歴史や言語を勉強するゼミに参加したい方。
旧帝・早慶等志望の受験生でパキパキに指導されたい方。
ちなみに、「こたろう」は英語と世界史の予備校講師でもあります。(なんと指導歴は約10年!よ!アラサー!)
というガッツリとした宣伝にご興味沸いた奇特な方は、以下noteを見てみてください。
そんな宣伝なんか興味ないけど、「こたろう」の素性も知りたいという奇特な方は、以下noteを見てみてください。
一緒やないかい!ということで、お後がよろしい様で。
日本語訳は笹川平和財団安全保障研究グループによるロシア関連情報専門サイト「ロシアと世界」から引用。リンクはこちら。
