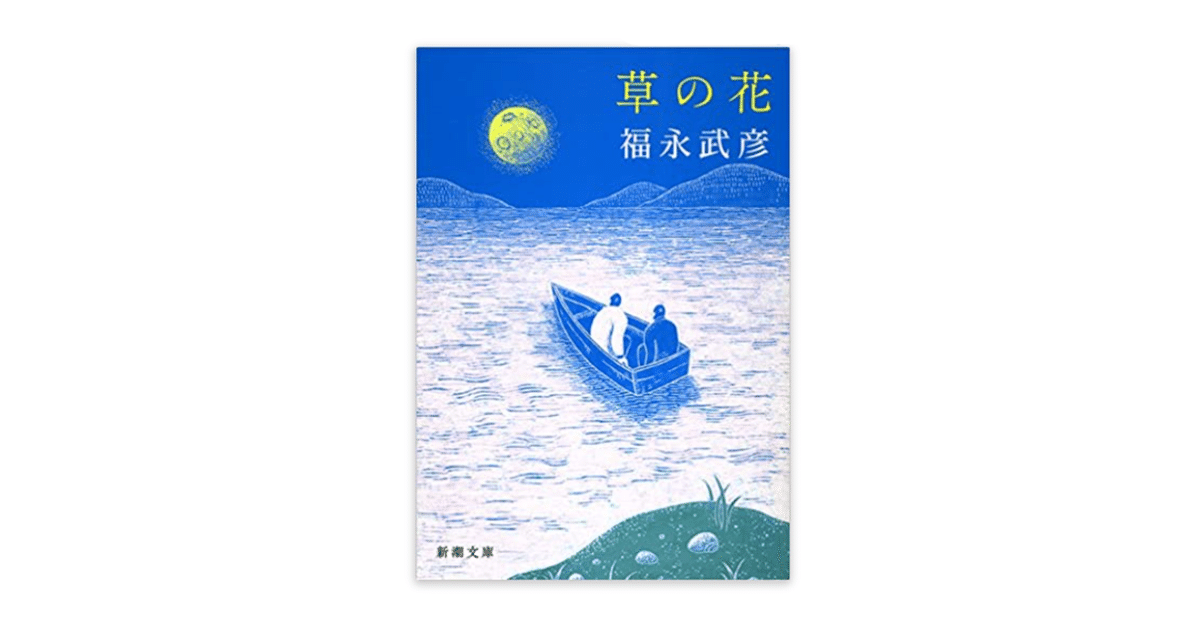
愛にやぶれ、恋にやぶれ―書評『草の花』福永武彦
福永武彦という名前を聞いて、どれぐらいのひとがピンとくるでしょうか。池澤夏樹の父親、といったところで、そもそも池澤夏樹をしらないひと(とくに若い世代?)だって少なくないかもしれません。
わたしが福永武彦をしったのは、もっている文庫本の版から察するに、おそらく10年くらいまえのこと。最初に読んだのが、今回紹介する『草の花』、そのつぎに読んだのが『忘却の河』でした(いずれも新潮文庫)。
正直、当時読んだそっちょくな感想としては、ひとこと。むずかしい。
究極まで知的に洗練された文体であることはわかるのですが…なにより、静謐すぎる。勝手な偏見かもしれませんが、福永武彦をはじめ、古井由吉とか堀江敏幸とか、「学者肌」の作家の小説には、どこか、わたしのような一般大衆を寄せつけない高尚なたたずまいがある。
ハタチそこそこで読んだわたしは、ろくに消化ができないまま、以来、本棚のすみで福永の本は静かに眠りつづけていました。
それが、今回たまたま再読をして、知的。静謐。そういう印象は変わりませんでしたが、20~30ページ読みすすめた時点ですぐに、「はあ、これはたいした作品にちがいない」と襟がただされるおもいがしました。
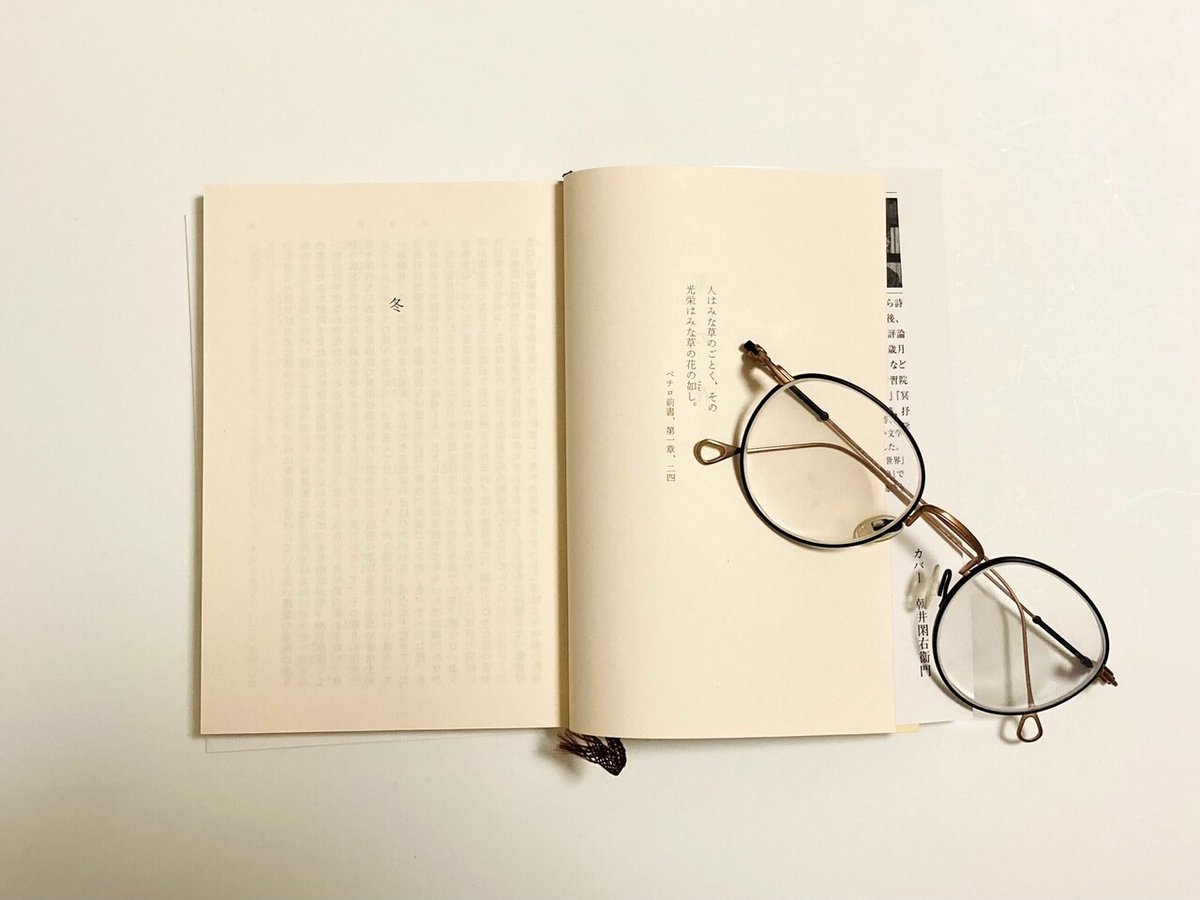
話の筋としては、サナトリウムに肺病で入院していた「私」が、同じ病室に起臥している汐見茂思という男から、死にぎわにノートを託されるというもの。汐見は、ほとんど自殺にもひとしい手術をみずから望むのですが、そのノートには、愛と恋にやぶれた汐見の過去が記されていたのでした。
たしかに、この小説では、観念的(あるいは哲学的・抽象的)なテーマがあつかわれています。「愛」「生(死)」「孤独」「信仰」。そのひとつを取ってすら難解になりそうなのに、それらテーマが入れかわり立ちかわり、物語の前景へと姿をあらわします。
けっして「簡単」な小説ではありません。小説にエンターテイメントをもとめる読者には、おそらく不向きな一冊でしょう。
ですが、「ただでさえ日常雑事に追われ、俗世のホコリにまみれた日々を送っている。せめて読書をしているそのあいだだけでも、敬虔な気もちにつつまれたい。」
そういうひとには、きっと、心のしずまる時間を約束してくれる一冊だとおもいます(わたしは久しぶりに、そういう読書体験ができました)。
でも、福永武彦をふくめ、戦後世代の「生きることへの真摯な姿勢」というのは、やはり戦争体験があってのことなんだろうとおもいます。
社会的な「傷」から文学が生まれなくなるとき、ひとは個人の「傷」から物語をつむぎだすようになる。
戦争の記憶がいよいよ希薄になっていく現代、文学はどこからどこへと舵を切ってゆくんでしょうかね。
いいなと思ったら応援しよう!

