
多発する災害の中で被災文化財をどう守るか 熊本史学会が最新の知見を報告 熊大生も参加
6月1日、熊本市中央区の「くまもと県民交流館パレア」で熊本史学会と地方史研究協議会が主催する合同企画例会(協力:熊本被災史料レスキューネットワーク)が開催され、県内外から研究者・学生・市民など約50人が参加した。
合同企画例会は「被災文化財の保存と活用—熊本から考える—」と題したもので、未指定文化財の把握、指定文化財の活用のあり方、被災文化財の復旧などの課題を共有して知見を深めるために開催された。2016年4月の熊本地震における文化財の甚大な被害と保全運動、2019年の文化財保護法改正による地域の文化財をめぐる環境が変容していることを踏まえ、熊本で被災文化財の保全活動に携わってきた最前線の3人が報告した。

思い通りに進まぬ被災古墳の復旧と課題 「三次元データ」蓄積の必要性
熊本大学文学部の杉井健教授(考古学)は「熊本地震で被災した古墳の復旧—その現状と課題—」と題し、復旧が遅れる被災古墳の現状に関して報告を行った。熊本地震の特徴として文化財の被害が多いことを挙げ、特に益城町では文化財の6割が被災したとして、特に熊本城、阿蘇神社、通潤橋、井寺古墳など、地表で目に見える形の構造物が多数被害を受けたと述べた。
地震で被災した古墳のほぼ半数が現在に至るまで復旧できていないのが実情であるとした上で、古墳の復旧が困難な理由として、
① そもそも古墳は修復されるものではなく、経年変化に合わせて放置されるもの(逆に言えば当時の姿のまま、経年変化を経て現在に至るまでそのまま残っている存在)
② 古墳は埋葬施設と墳丘の両方を持つ構造物である
③ そうした構造物が被災した場合(特に石室)に復旧しようとすると、外部(上部)の墳丘があまり被災してなくても、墳丘ごと解体しないといけなくなり、建造当初の姿が破壊される。そのため、復旧の実施に非常にハードルが高い
④ 内部の石材の温湿度管理のハードルの高さ(特に装飾古墳)
⑤ コンクリート製の石室保護施設が逆に邪魔になり、内部の石室や石棺を復旧しようとしても困難な場合がある
⑥ 古墳が位置する自治体が概して小規模で、専門の担当職員が少ない(またはいない)などで復旧作業に注力できない
などを挙げた。また、専門人材の不足などもあって報告書や修復書類、の整備も進んでおらず、以前の古墳整備時の設計図が不十分な場合、そもそも「修復方法に関する調査」から始めなければならない現状もあるという。
具体的には地震直後に直接的な被害を確認できなくとも、その後の豪雨災害などで地震時に形成された亀裂などから内部に水が侵入する例(江田船山古墳・塚坊主古墳)、豪雨災害による古墳の被災も発生していること、石室内部が崩落していると内部で作業することすら危険な例(井寺古墳)、石室を覆うコンクリート製保護ドームによって内部の石の積み直しや内部石材の引き出しが困難となっている(釡尾古墳・塚原古墳群石之室古墳)など、様々かつ複合的な要因で復旧が困難・遅延している、と指摘した。特に装飾古墳の場合、温湿度の変化で石材や装飾に悪影響が及ぶこともあって慎重な対応が求められ、技術的・資金的課題も相まって地震から8年を経た現在でも復旧できない古墳が多い、とした。
石棺が破損するも覆屋を追加して復旧した例(天水経塚古墳)もあるが、熊本市の二軒小屋古墳(未指定)のように悪意がなくとも正当な手続きや技術をとらずに不適切な「復旧」が行われる例もあるという。
こうした実情を踏まえた上で、杉井氏は「三次元データ蓄積の重要性」を指摘する。被災状況・程度の判定には三次元データが極めて重要であり、考古学的な図面・写真では全ての部位や情報が網羅的に反映されているとは限らないのに対し、三次元データは特に構造物には有効であることから、従来からの実測図制作や写真の撮影に加え、三次元計測も測量・発掘調査手法の一つに位置付けられるべき、とした。
その上で杉井氏は「災害時に備え、平時の調査からこうしたデータ蓄積を行っておくことが大切だ」と指摘した。
未指定文化財と国指定文化財の「間」
同大文学部の三澤純教授(日本近代史)は「被災史料が語る井寺古墳—未指定文化財と国指定文化財との間—として、井寺古墳と被災史料に関して報告。「指定・不動産」で国指定文化財として保護される「井寺古墳」と、それとは対照的に「未指定・動産・個人コレクター所蔵」という、最も脆弱で散逸するリスクが高い「有馬家文書」とが結びつき、井寺古墳の復旧作業に貢献した経緯を述べた。
「有馬家文書」は上益城郡鯰手永砥川村(現・益城町)の庄屋を務める家に伝わり、井寺古墳が位置する井寺村の庄屋を兼帯していたことから、同地域に関する多くの文書が含まれていた。三澤氏によれば、熊本地震で所有者が被災したことで三澤研究室に持ち込まれ、調査する中で井寺古墳の内部が江戸後期に発見された際の詳細な記述を発見したという。
既存の研究では井寺古墳が1857年(安政4年)の地震によって石室の扉が開いた、とされていたが、具体的な記録がなく不明な所も多かった。新たに発見された有馬家文書の記述からは住民が古墳の土を肥料にするために採集していたところ崩れて石室が発見された、とされており、古墳各部の寸法を列記した上で「絵之様成物彫、朱附居申候」「骸骨三人分」などの記述があることも判明した。また、熊本大学に寄託されている細川家・熊本藩の文書群「永青文庫」に所蔵されている「安政四年 御在国日記」を調査した結果、有馬家文書の草稿が清書されたものが写されており、出土した鏡の図面も掲載されていた。

大正年間の『上益城郡誌』の記述では「地震により発見」されたとされており、その後に発行された『熊本藩年表稿』や平凡社版『熊本県の地名』などでも記述が継承されていた。しかし、実際には住民による山土採取の過程で発見されたことが明らかになり、井寺古墳の発見過程や埋葬品に関する画期的な情報を得ることができたという。 こうした成果を踏まえ、三澤氏は「民間所有の未指定文化財から(地域社会の歴史を塗り替えるような)何が出てくるか、まだ計り知れない可能性がある。近世中期以降の熊本の地域史の特徴は、藩政文書と民間文書が双方膨大な量で保存され、連動していることで、これらを保存してきた『家』制度が衰退する中で、県単位で行政的に保護する機関が求められる」と結論づけた。
細川家藩主甲冑の発見と被災文化財研究の可能性
最後に同大永青文庫研究センターの今村直樹准教授(日本近世史)が熊本被災史料レスキューネットワーク(熊本史料ネット)による被災文化財の保護活動と、そこから判明したことについて報告を行った。
今村氏は熊本地震の後に熊本史料ネットが結成され、未指定動産文化財(古文書など)の救出や保護活動を実施した実績を紹介し、特に「初動レスキュー」と呼ばれる災害発生直後の行動では現地の文化財関係者のボランタリーな活動が重要となり、能登半島地震でも同様の活動が現地で行われた、と述べた。
そうした活動を行う中、2017年に旧家から甲冑の一時預かりが依頼された。附属していた木札を調査したところ、熊大寄託の永青文庫細川家文書に1872年(明治5年)の細川宣紀(細川藩第4代藩主)甲冑預かり証書が発見された。これは廃藩直後に旧家臣が預かったものであることが明らかになった。
今村氏が調査した結果、こうした預かり証書は全203通にもなり、廃藩直後に細川家は多くの甲冑類を家臣に預けていたことが明らかとなった。従来は熊本城天守に甲冑・鉄砲・刀槍類や兵糧・銀子などが保管・手入れされており、ここに歴代藩主の甲冑も含まれていたという。
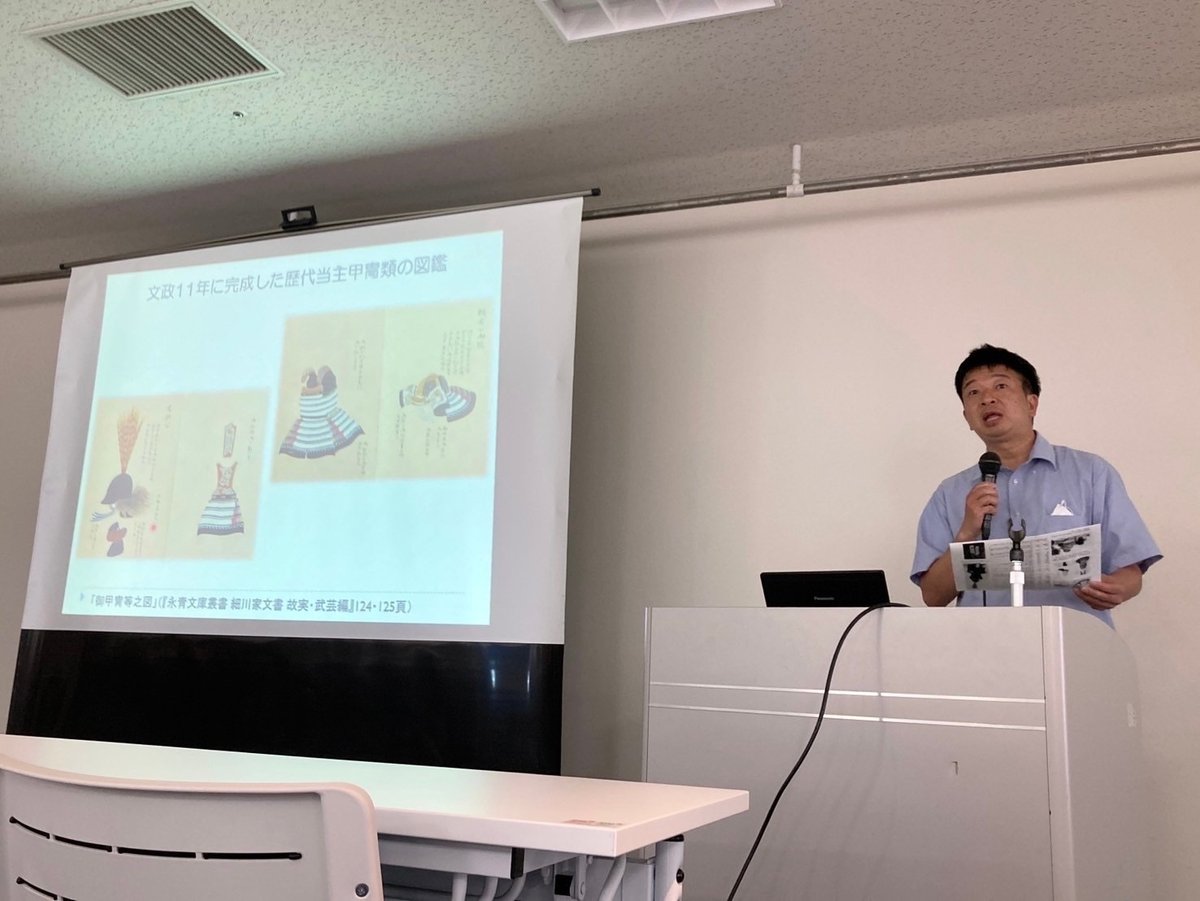
しかし、1871年に廃藩置県が断行され、熊本城は鎮西鎮台本営用地となり、それまで城内に居住していた細川家一族や旧家臣らは退去することとなった。そこで従来城内で保管されていた書類・武具類の処遇が問題となった。東京や熊本の別邸宅への移動や売却は不可能とされ、多くの旧家臣からの預かり願いの申請も踏まえ、「甲冑類の保管場所を失った細川家と、御家の『宝』を預かることを望んだ旧家臣の利害が一致」(今村氏)した結果、旧家臣への下げ渡しが行わ
れた、と指摘した。
現代において美術館や公的機関に保管されている歴代当主甲冑は旧家臣による預かりによって保存・伝来された可能性が高く、今村氏は廃藩後の細川家と旧家臣間の「旧誼」の強さが窺える、と指摘。熊本藩関係資料を理解する上で有効な視点である、と述べた上で、「文化財は意識的に努力され守り抜かれた存在で、残るべくして残ったものなどない。地域の文化財をめぐる環境が激変する中、特に被災文化財における建造物・美術工芸品・文献資料を横断する知見・専門性を
共有していく必要がある」とした。
質疑応答では熊本地震や能登地震の結果から「墳丘盛り土があった方が地震などには強い(石室が剥き出しだと倒壊のリスクが高まるのか」「井寺古墳の位置(重臣・松井家の所領)が熊本藩まで報告されることに影響しているのか」「文化財保護における文献資料と考古学と連携について」など、熊大生をはじめ参加者から活発な質問が行われた。
質疑応答の中で杉井氏は三澤氏が発見した有馬家文書などの記述から、「現在、井寺古墳の盛り土が薄いのは、文書に記載されているように『肥料』として採取されていることが影響している可能性も高い」と指摘し、学域の相互協力の重要性を示唆した上で、「目立つ熊本城だけでなく、未指定文化財にも可能性が秘められていることを知ってほしい」と述べた。

本報告会を共催した地方史研究協議会の野本禎司准教授(開智国際大学教育学部)は「文化財保護行政の公的な枠組みの中で、民間(市民)・学術機関のレスキュー活動を取り込んでいく熊本の先駆的な事例を見習う必要がある。全国の事例や取り組みを共有して協力する動きを行いたい」とコメントした。
熊本大学の稲葉継陽教授(永青文庫研究センター長)は「県主導の調査事業では分野単位で対応されおり、特に遅延している民俗分野が特に最優先となっている。古文書はまだ取り掛かられていないところがあるが、現実の災害対応の中でノウハウが積み重ねられて現在の体制が成り立っている」と述べ、「普段どれだけ大学や機関の外で社会で活動しているか、また文化財の価値を所有者や管理者と共有できているかがレスキュー活動は重要となる。また文化財は文書・美術工芸品・建築物
がセットで伝来していることも多い。レスキュー活動の中でそれぞれの専門家が知見を共有して協力していく可能性がある」と結語した。
参加した熊本大の学生は「非常に興味深い内容だった。こうした研究を参考に、自分が学んだことを将来的に社会に還元したい」と感想を述べた。熊本大からは学部学生・大学院生約10人が参加した。
(2024年6月1日)
#熊本 #熊本城 #熊本地震 #被災 #災害 #レスキュー #文化財 #日本史 #古墳 #歴史学 #歴史 #刀剣 #甲冑 #国立大学
