
【読書】本を読む人だけが手にするもの。藤原和博No.006(日本実業出版社)
2025年、5冊目は藤原和博さんの「本を読む人だけが手にするもの。
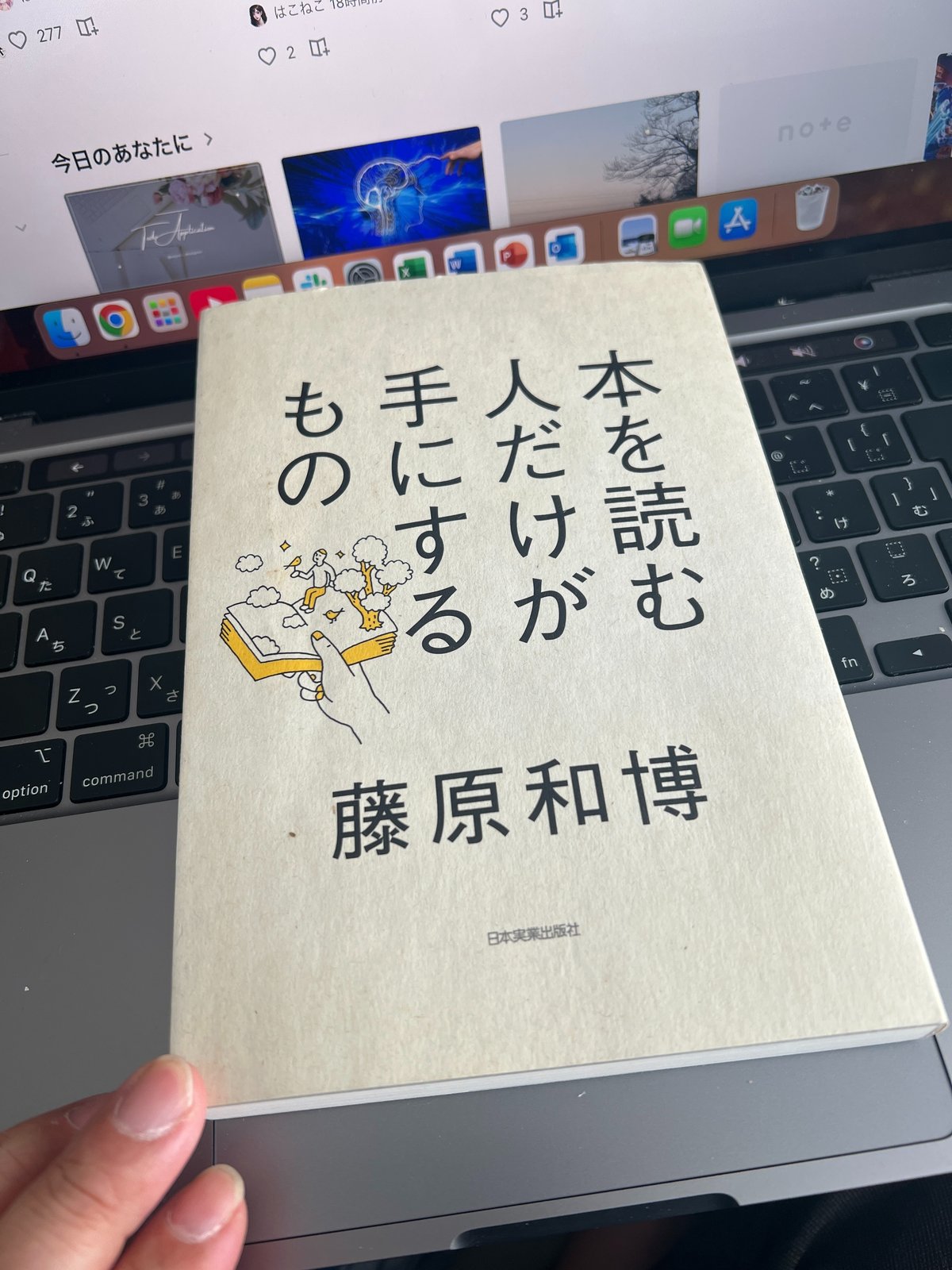
どんな本か。
この本はなぜ本を読むといいのかについて書かれた本だ。
というか今の時代の人々になぜ、読書が良いのかを書いた本だ。
読書自体の良さのみを単品で紹介しているというよりは今の時流と照らし合わせながらの考察なのが興味深かった。
この「今の時代」というのがポイントで著者の藤原さんも今がどういった時代なのかを考えさせるところから描き始めている。
成長社会と成熟社会
文中で成長社会と成熟社会という区分が出てくる。
成長社会とは、高度経済成長からバブルの崩壊までの右肩上がりの時代。
成熟社会とはその後、つまり私たちが生きている今の時代のことを言うのだという。
成長社会というのは幸福がわかりやすかった世の中、成熟社会は幸福がわかりにくい世の中だ。
例えば、一流企業への就職が代表的で、つまりは幸せを国や組織が与えてくれていた時代だ。
一方今はどうなのかというと、今は自分で考え幸せになる時代だ。終身雇用の崩壊、価値観の多様化、社会的格差の広がりを考えると納得できた。
この本はそんな成熟時代を生き抜くには読書が必要だということを言っているのだ。
幸福の実現のために。
企業や組織が幸福へと辿り着く道をさし示してくれなければ、誰が導いてくれるのか?親や友達だろうか。
それは自分自身である。下記本文からの引用だが
人生のとらえ方とは、いわば人生の幸福の実現のためにどういうテーマを持ち、どういうベクトルに向かって進んで行くかということだ。
誰も教えてくれないのである。
でもテーマとかベクトルとか言われてもどう考えていけばいいのかさっぱりわからないという声が聞こえてきそうだが、その時に必要なのが教養だということを定義している。
教養を得るために読書をする。
教養を得るためにはどうしたらいいのだろうか。
それは読書だ。
世界中の他人から知恵を借りて、自分の方向性を見出せばいいと私は思う。
知識がなければ、方向性も計画もへったくれもないのだ。
なので私は乱読することにしている、そしてこうしてnoteにアウトプットしているのだ。
教養があれば自分の意見が言える。
知識の蓄積がないと自分の意見も出てこない。新しい知識を日常的に取り入れてその知識と自分の考えを戦わせて自分なりの意見を紡ぐ。
更に別の知識を入れまた考えて・・の繰り返しだと思う。
そうすることで自分自身が確立していくのだと思う。
教養もないのに、俺は私は言うのは、なんとなく狭い世界の中の空気感を表現しているのにすぎず、誰もそんな話は聞いてくれないのだ。
まとめ
一部を紹介しましたが、本当にほんの一部だ。
これから読書を始めたい方、すでに読書をライフワークにしている方にもぜひ読んでいただきたい。
