
読書録/大黒屋光太夫
◼️大黒屋光太夫(上)(下) 吉村昭著 毎日新聞社 2003年
島国である日本には、海難にあって漂流し、外国へ流れ着いてしまったという漂流民のたどった歴史がいくつも残されている。その中で双璧といっていいのが「ジョン万次郎」と、今回読んだ「大黒屋光太夫」だろう。大きな違いは、漂着後の運命である。ジョン万次郎は太平洋の鳥島に漂着し、アメリカの捕鯨船に発見されて渡米した。大黒屋光太夫は、ロシアが支配下におくアリューシャン列島のアムチトカ島に漂着し、ユーラシア大陸を踏むことになった。
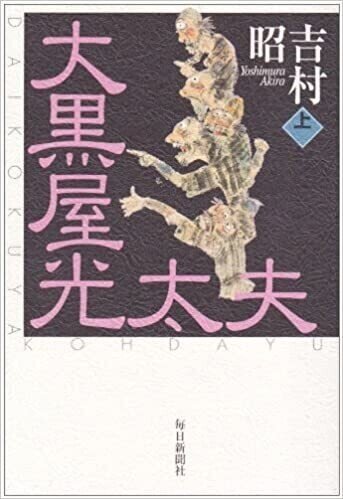
大黒屋光太夫は、17人を乗せた船で、江戸に御用米その他を運ぶため、鈴鹿の白子港から江戸へ向けて出航する。当時の船には羅針盤などはなく、陸地を見ながら場所を確認しつつ航行するのが常だった。鎖国していたため、外洋に出るような船の装備や航海術は禁じられていたのである。そのため、ひとたび時化がきて、陸地の見えないところまで船が流されてしまうと、その後の航海は非常に困難となる。
大黒屋光太夫の乗った神昌丸は遠州灘で嵐に遭い、陸地から遠く離れて遠洋へと流されてしまう。7ヶ月の漂流ののち、アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。そこで、ラッコの毛皮をとるために滞在していたロシア人、彼らに使役する原住民と出会ったところから、日本へ戻るという、壮大な冒険が始まってゆく。
大黒屋光太夫が際立っているのは、彼らが進んでロシア語を会得しようとしたことである。ロシア人と原住民との関係がどんなものであるのかを見抜き、島を脱出しようとするロシア人と協力して船を造ることで運命を切り開いた。そうした彼らの能動性に、わくわくと先を読みたい気持ちを刺激されて、上下巻2冊を一気読みしてしまった。
しかし、そうした運命を切り開こうとする個々の力を上回る、圧倒的な力がはたらく。一つが、オホーツク・シベリア地域の極寒の気候である。冬は凍結してしまう川や海、穀物が育たない寒冷な気候は容易に人々を飢餓状態へと追い込んでゆく。そしてもう一つが、ロシア帝国と江戸幕府、それぞれの国家体制と外交姿勢である。本来漂流民である大黒屋光太夫らを帰国させる方針なら、数千キロも離れた首都ペテルブルクに連れてゆくのでなく、日本に近い沿岸に留めおけばよいはずだ。しかし、帰国したいというなら、エカチェリーナ2世に謁見して申し出なければならない、という。そこには、この漂流民を利用して外交交渉を持ちかけたいロシアの事情があり、一方に、厳しいキリシタン禁制を行う日本の事情がある。
大黒屋光太夫らは、ロシアを横断する旅の途上で、彼らと同じくロシア領に漂着し連れてこられ、キリスト教徒となって日本語教師をしている日本人と出会うことになる。そこに、著者は彼らを利用して日本語を習得させ、ロシアの南下政策を有利に進めようという政治的な目的を見出し、本当は彼らを日本に帰すつもりのない帝国の冷酷さをも描いている。その視点が新しいと感じた。
そんな中、日本に帰りたいという彼らの気持ちを慮り、生活の手段をまったく持たない彼らを助けるロシアの人々のやさしさにも心動かされる。遭難した17人は自然と国家によって引き裂かれてしまうけれども、最後まで彼らを支えたのは、その時々の人が示す愛ではなかっただろうか。
(ヘッダー写真は北海道から見た夏のオホーツク海)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
