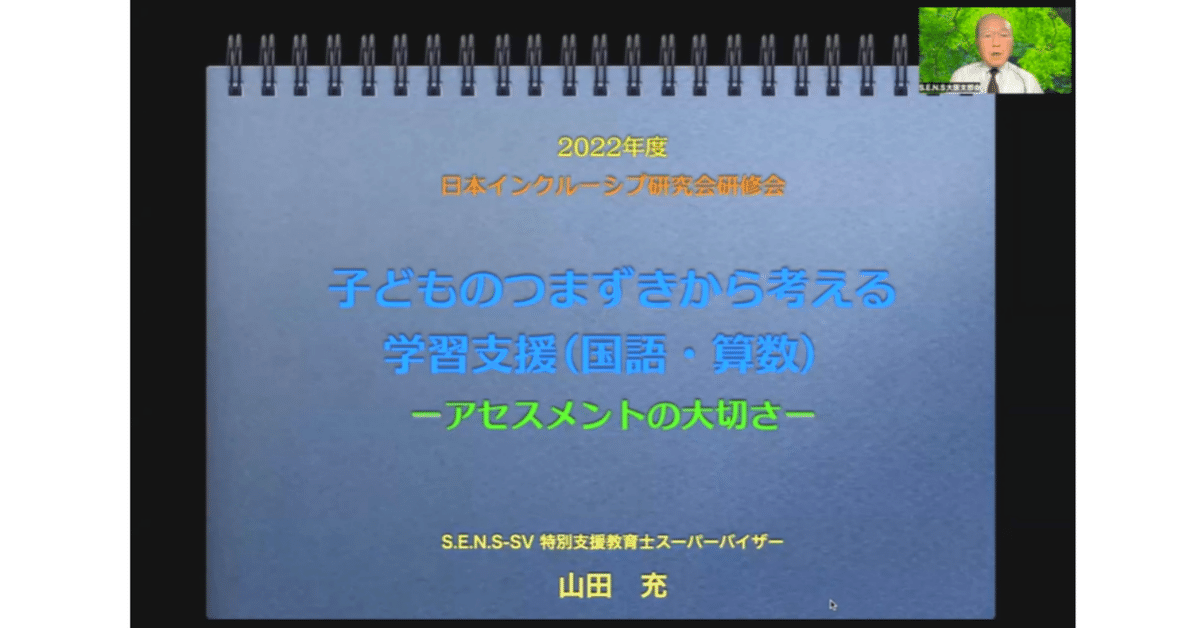
子どものつまずきから考える学習支援(国語・算数)
こんにちは。NPO法人日本インクルーシブ教育研究所の石井綾子です。先日、動画で学ぶ講座『子どものつまずきから考える学習支援(国語・算数)』を開催しました。こちらは第7期学習・発達支援員養成講座の中で、どなたにでも受講いただける公開講座(全20講座)の最後となりました。
講師は特別支援教育士スーパーバイザーの山田充先生でした。山田先生は、大阪府堺市で20年間通級指導教室を担当された後、広島県廿日市市教育委員会で特別支援教育のアドバイザー、大阪府堺市教育委員会で特別支援教育の専門家チームとして活動され、通級指導の先生方への研修もされておられます。
それでは受講生からいただいた感想を紹介します。
・最後に紹介していただいた「漢字イラストカード」や「かなカナパズルゲーム」「算数文章題イメージトレーニング」など5年前に本校の通級指導教室開設に際して購入した教材のほとんどが山田先生が監修されたものであることがわかり、大変驚きました。20年間の通級指導教室での豊富な経験から子どもたちに効果のある教材が生み出されたのだと納得致しました。事例を数多く上げながらお話していただけたので、大変わかりやすく、うちの学校のあの子にもこんな風に指導すればいいのかもしれないと子どもたちの顔を思い浮かべながらお話を聞かせていただきました。どんなことにつまづいていて、どのような支援をしていかなければならないのか考えることが大切なのだと改めて感じました。ありがとうございました。【教員】
・アセスメント無しでだと子供が不幸になるだけですね。失敗を経験させるのではなく課題を絞り関わりたいと思いました。何でも少しの手間をかけることでテストの点がアップしやる気に繋がるのではないかと思います。ユーモアと工夫も必要だと思いました。イメージ化の重要性も改めて考えることができました。視覚からの情報を丁寧に伝えていけたらと思います。【保育士】
・アセスメントし、なぜ?と原因を探って対応する。試行錯誤して、失敗をさせてしまっている…の部分で、自分だと感じました。色々な指導法を様々な人から学んで、あれこれ理解した気になって使っていた自分。いちばん大切なところをぬかして、わかったふうな気持ちになっていた自分がいたことを素直に反省することができました。先生の具体例や具体的な支援について話を聞き、アセスメントする目をこやしていくことができそうです。特別支援は、科学だと、改めて思います。講義を聞きながら、あっ、あの子のあのことだ、あっ、この子のあのことだと思う時がたくさんありました。きちんと、子どもをみてアセスメントし、特性に合った指導をしていこうと思います。クラスルームでさまざまな情報を共有できるので有難いです。【教員】
・まだまだ聞きたい内容の講座でした。「見方を変える」と違った子どもの良さがみえてくる...本当にそうだと感じます。自分の経験や経験からくる感なども大切ではありますが、目の前の子どものアセスメントをし、子どもの行動の因果関係を分析し対応を考え、科学的に支援を考えていきます。【特別支援教育アシスタント】
・この度の講座を受講して引き出しが増えたと思っていましたが、支援の引き出しを増やして行くだけではいけないと言われ、耳が痛いです。子どもたちひとりひとりのアセスメントが足りないと反省しています。かえって子どもを苦しめることに、ならないように支援員同士協力しあってしっかりアセスメントをしたいと思います。【放課後児童支援員】
・アセスメントの重要性を感じました。課題やつまずきの捉え方も間違っているところや、支援法の方向性が違うことで、子どもたちが学習に後ろ向きになっていってしまうこともあるなと感じました。これからの指導に向けて、子どもたちが前向きに学習に取り組めるように指導の在り方を見直していきたいです。子どもたちが、学習に前向きに取り組めなくなった時の声がけやサポートの仕方について学ぶ機会が欲しいです。【教員, 特別支援教育アシスタント】
・国語と算数のアセスメント方法と、支援の方法を詳しく教えていただきました。算数に置いては掛け算、筆算、など細かいつまづきの特徴を知ることができ、見える視点がまた増えた気がします。直近の仕事に活かしていきたいと思います。【学童職員】
・山田先生が、講義で言われていたように「見方を変える」「アセスメントは必要である」ことが大切であると痛感しました。先生の実例はとても参考になり、手当たり次第の教育は無意味なことだったのだと反省しました。子供にとって最善の支援は、子供の状態を明らかにし、子供の特徴や状態の因果関係を明らかにし、今後の支援に繋げていきたいと思いました。【ふれあい推進員, 学習サポーター】
・今回の山田先生のお話しを楽しみにしていました。私の職場にも山田先生の漢字イラストカードがあります。子供達は視覚化されててカードゲーム感覚で楽しんで取り組む姿が見られます。山田先生が実際に実践された内容なのでとても具体的で分かりやすかったです。教わった内容を全て試したいところですが、子供の特性に沿ったアセスメントを考えて対応できたらと思います。ありがとうございました。【特別支援教育アシスタント】
・様々な事例を紹介してくださり、その対応法もあり、盛りだくさんでとても学べた講義でした。現在働いている療育施設で学習も行っていますが、まさに算数の誤り分析のsくんと同じで、0が入る計算になると違う方法で計算してしまい、そこから抜け出せない子がいて、指導に苦戦しております。他にも文章問題が難しく、苦戦している子への指導法も迷っていたので、先生が紹介してくださったイメージトレーニングの本を使ってトレーニングできたらと思いました。立式への支援では、まさに「みんなで」「ぜんぶで」という言葉に注目させていました。掛け算のとき混乱が起こるとは思いもせず、間違って指導していて子どもに申し訳ないです。もっと様々な事例をお聞きしたいと思ったほど、とても楽しい講義でした。ありがとうございました。(sくんの事例の件ですが、私が担当している子は、足し算引き算などは指で計算しないと分からず、九九はなんとかできるという感じです。本当は割り算の筆算(4年生の最初に習うレベルのから)をやっていたのですが、そこで掛け算の筆算で解き方が違うことを発見し、試しに掛け算の筆算の学習をしたら判明しました。何度も0が入る時の掛け算の筆算のやり方を教えていますが、また次になると忘れてしまいます。やり方を忘れてしまうのは割り算の時も一緒ですが…その繰り返しで先に進めません。今5年生です。あとはどのように指導していけばよいのか悩んでいます。教えていただけたら嬉しいです。紹介してくださった本の中に、指導法が書かれていますでしょうか?)【児童指導員】
山田先生からの回答:該当のお子さんは、5×0みたいなの 5つ入ったお皿が0枚 という設定がイメージ出来ず、0かけたら0が理解出来ないのだと思います。なので、0かけたら0だよと教えるだけでなく、具体物を使って、かけられる数が、いくつ分を、普通の計算から、具体物で教えて行く流れの中で、0皿とか言うことをイメージさせないと難しいかも知れません。普通の足し算引き算を100玉そろばん等を使って、視覚的に確認しながら、素早く出来るまで、何度も100玉そろばんで練習するなどと言うのも、合わせてする必要があるかもしれません。
・具体的な指導法をたくさん教えていただき、ありがとうございました。学童では、宿題支援も行うのですが、躓きのある子に対して今まで間違った指導もしていたと思います。手当たり次第の指導を行っても、不成功体験の積み上げで子ども達の自己肯定感を下げるだけと知り、反省です。問題文に「合わせて」「みんなで」「ぜんぶで」って出てきたら、足し算をするんだよ。と安易に教えていました。大反省です。自分自身が習得してきた勉強方法だけが正ではないですし、困り事別の指導方法がもっとたくさんあるのでしょうね。奥が深いです。様子から観察して困り感を見つけ、どこをどのように躓いているのか分析し、適切な支援を行うことができるように、もっと知識を深めていきたいです。【保護者, 放課後児童支援員】
・その子のアセスメントの必要性は、これまでも多くの講師先生から語られていました。今日の講義は、その子のアセスメントが学びをツールにして国語の言語や算数の概念との関連で、どのような特徴が発生してくるのか、課題につながっていくのか、具体例を挙げて解説していただきました。又、その子どもが何に躓いているのか、間違い方を探す誤答分析がいかに大切なのかを教えていただきました。誤答分析ができるためには、相当の教科の理解が必要で、日本語の習得や、数の概念など、私たちの生活に直結した学びにおいて、どのような教科の概念を把握しなければならないのか、学ぶことができました。しかし、それは、個人が一朝一夕にはとらえられず、子どもの間違いを分析的にとらえようとする教師集団の方向性と、対話による気づきなど、原因や要因の考える習慣や文化を学校に持ち込むという先生の私的に納得をしました。やはり、特別支援教育は、チーム力であり、科学的にとらえようとする私たちの専門性がとても重要なのだと改めて感じました。具体性のある講義でした。分量もたくさんあり、さらに学んでいかなければという意欲をかき立てられました。たくさんの参考資料を紹介していただきありがたく思いました。その道の研究の第一人者が講師として選定され、本当に学びがいがある講座だと改めて感じました。ありがとうございました。【不登校教育支援センタースタッフ】
・アセスメントをきちんと行い原因や要因を考え、一人一人の発達特性や行動の特性を理解し特性に沿った対応をすることが大切。それぞれの支援方法はとても参考になります。特にイメージ化の支援方法の「絵から文章を考える」トレーニング、娘にしてやりたかったです。現在中学生、すごい点のテストを持って帰るので、脳を使う学習方法を伝授してみようと思います。【子育て支援センター職員】
・豊富な特別支援教育の経験から、国語や算数につまずく子供たちの具体的なつまずきポイントや、それぞれのつまずきの要因、対応策まで丁寧にご指導下さり、すぐにでも実践できる内容がたくさんありました。「試行錯誤を繰り返し」「ゆっくり丁寧に」等一見聞こえのいい「指導方針」は、問題の本質を把握せず闇雲に子供のつまずきに対応している言い訳でしかなく、子供のつまずきの場面をしっかり観察し的確にその背景を分析することが前進への大前提となることがよく分かりました。指導する側もされる側も、「脳を使って」考える・勉強することが非常に大切であることを実感しました。病院勤務の立場では普段の子供の様子を知ることが難しい面も多々ありますが、保護者さんや学校の先生とも情報を共有しながら、子供が学習のどの部分でつまずいているのかを探る努力をしていきたいと思います。先生の関西弁が耳に心地よく、児童とのやり取りの言い回しが面白くてクスッと笑ってしまう場面もあり楽しい講義でした。具体的な教材や参考文献もたくさん紹介していただきありがとうございました。【言語聴覚士】
・読み書きに障害のある児童に対して、まずは適切にアセスメントを実施し、どこにつまずきがあるかを認識した上で支援を行うことの大切さを学びました。読み書きの学習に関して一人一人の困難さは異なっており、集団の中での学習だけでなく、個々の特性に合わせた支援をアセスメントをもとに、必要に応じて専門家の意見も聞きながら効果的な学習環境が提供できるような体制づくりが必要だと感じました。【行政職員】
・まず、冒頭の、「試行錯誤」が失敗前提で、子供に失敗体験を積ませるだけ。それではダメージが大きくなってやる気になるわけがない、というところで、自分も子供のダメージを大きくしただけではなかったか、最適最善の方法を提供できていたかどうかと考えると、子供に対して申し訳ない気持ちになりました。これまで、「できない」を積み重ね過ぎてしまったから「やる気」が出ないという点は非常に納得です。毎日、次男と課題を一緒にしていて、子供の学びやすいように工夫してきたつもりでしたが、今後は更に次男と対話をしながら、次男の困っている原因要因に沿った方法で、脳を使うことを意識して、やってみます。いつも素晴らしい講座をありがとうございます。【保護者】
・アセスメントが大事とよく言われますが 検査や診断だけでない「子どもをよく観察すること」が大事であるとあらためて思いました。できないとしたら何が原因なのか 子どもの行動 表情などよく見ること 支援者が勝手に思い込まないこと 決めつけないこと ふだんの実践でも気をつけていきたいと感じました。ありがとうございました。【フリースクールスタッフ】
・アセスメントというと、すぐに心理テストや知能検査が思い浮かぶが、動画講義を聞いて「(その子の)漢字の間違い方や、その子の様子を観察することこそアセスメントのスタート地点なのだ」ということが理解できました。「アセスメントをせずに支援方法を考えることは、子どもを苦しめる結果になる」ということを、支援者としてもしっかり肝に銘じたいと思います。支援者として活動するときに、参考になりそうな実践例が多くて良かったと思います。【保護者】
ーーーーー
さて、自閉症の人達の認知特性を理解し、伝わりやすい文章の書き方を練習する講座の用意ができました。講師はいんぐりもんぐりの原田潤哉氏で2023年6月スタートします。詳細はホームページからご覧ください。NPO法人日本インクルーシブ教育研究所
不定期ですがメルマガを発行しています。日本インクルーシブ教育研究所の事業や講座情報等について書いています。メルマガご希望の方はこちらからお申込頂けます。購読は無料です。NPO日本インクルーシブ教育研究所メルマガ登録フォーム
