
和歌山と熊野古道と、南方熊楠
2023年の日本帰国の際にいつも通りふらりと寄った半田ファームのお母さんとおしゃべりをしていて、半田さんに
「熊野古道に行ってきたんよ〜 山林さんたちは好きだと思う」
と言われたのがずっと脳内に残っていて、気になりつつもそのままにしていました。
noteでたまたま見かけたcool な kumanoさんをフォローしつつの数ヶ月
そして年末、伝さんのところで見た南方熊楠(みなかたくまぐす)という人になぜか惹きつけられる。
オーディブルで「未完の天才 南方熊楠」を聞き始めるまで、和歌山、熊野古道と関係が深い人とは知らずにいたので、本当にこの世はご縁なのですね。広告でも3回広告を見ると買いたくなるとか聞いたようなことがあるような気もするので、何かしらの無意識下に引き寄せがあったのには間違いありません。
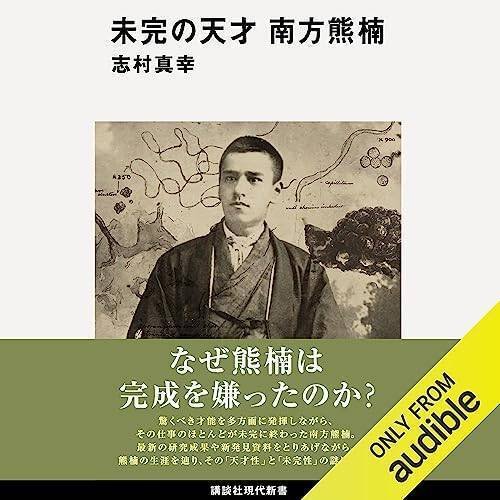
熊楠(くまぐす)さん、(くま鈴じゃないよ)というお人が何しろ興味深い。熊楠は知の巨人、世界で一番字を多く書いた人と言われています。幼少時にすでに百科事典を隅から隅まで書き写していたそうです。この百科事典が、和漢三才図会。和漢三才図会の編集者は大坂の医師、寺島良安という人で、「医者たる者は宇宙百般の事を明らむ必要あり」と言われたことが動機であったというので、同じ職業を名乗るものとしてはもう恥ずかしいばかりであります。
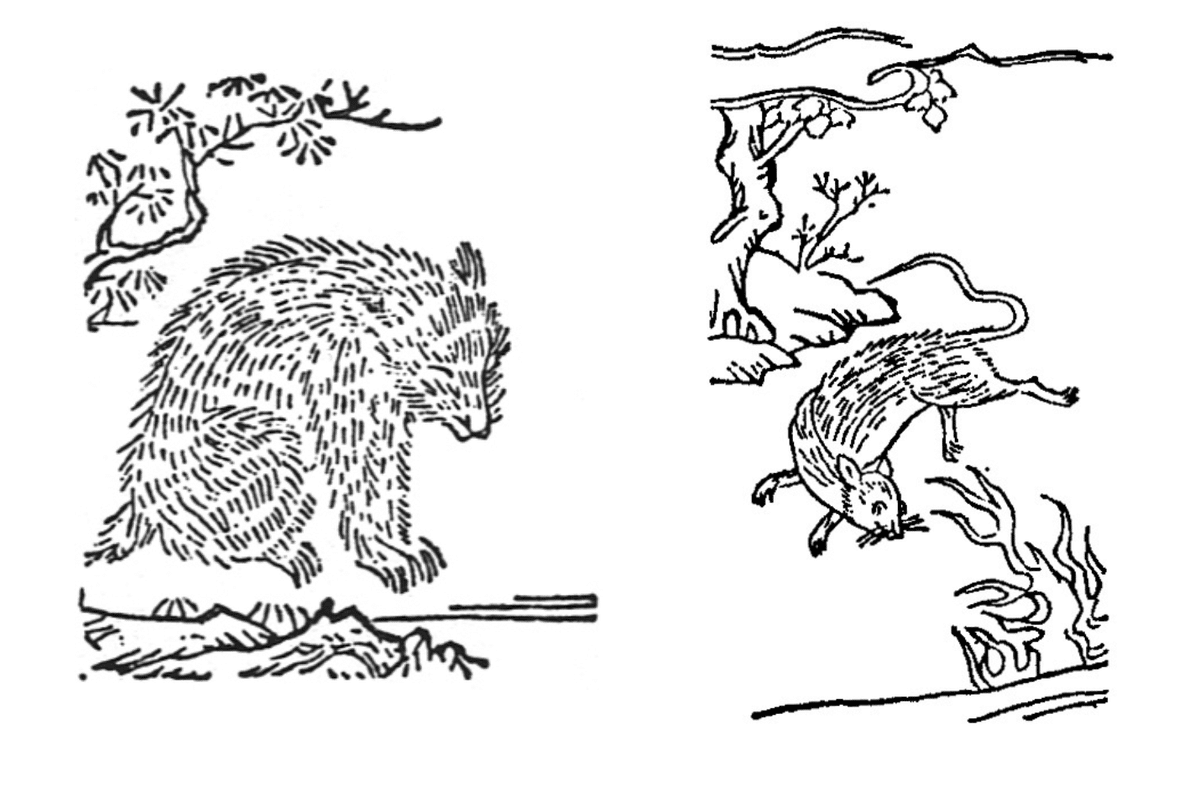

百科事典といえばうちにもあった。有名なのはEncyclopedia Britannica(ブリタニカ百科事典)、ブリタニカは1768年から1771年にかけて、エディンバラで発行されたのが始まりというし、私の夫は日本在の時に、講談社の百科事典編集に関わっていたこともあり。インターネットが普及する前はいちいち知らないことは百科事典を出してきて見ていたなあなどと様々な記憶が蘇ります。

13歳の時にはすでに英文・漢文・日本文の本を参考にしてや自作の「動物学」の教科書を書き上げたそうです。「宇宙間物体森羅万象にして実に涯限あらざるなり」と子供の時にすでに世界のありとあらゆるもののその多様さ、限りなさ、複雑さ、に目を見開いて驚いているのです。すごいなあ。
個人的に熊楠が興味深いのは、グローバルであること。10代に英語が堪能になり、20歳でアメリカにわたり、読書と植物採集、ギアレクタ・クバーナという新種の地衣類を発見し、そしてロンドンへ。大英博物館で助手になり、かの有名な雑誌Natureへの掲載論文は生涯で51本。語学に関して言えば、日本語・中国語・英語以上の何ヶ国語も勉強し、その語学知識ゆえにのちに比較民俗学のグルとなるのです。

比較民俗学で言えば、日本語の語源、例えばポルトガル語の語源の言葉は
コロッケ(croquete)パン(pão)ボーロ(bolo)ビスケット(biscoito)カステラ(castella)金平糖(confeito)カルメラ(caramelo) かっぱ(capa)じょうろ(jarro)シャボン(sabão)などなどあるそうですが
ボタンはポルトガル語のbotãoか英語のbuttonかで争ったりしたそうです。
物価の高いロンドンで学問一筋の生活を続けることは容易ではなかったのは想像に難くなく、実家(兄)からの仕送りも厳しく、33歳の時に日本に帰国したのだそうです。木箱に詰まったものすごい数の植物標本と、くたびれた洋服に、無一文。なんともドラマチックで、ある意味、典型的な学者さん、もう、こういうところに心臓をぐいっと掴まれます。
この後、和歌山、原生林も残る熊野で藻類、キノコ、様々な植物や昆虫、小動物など、熊野の生命の世界の採集に明け暮れる日々だったそうです。熊楠はこの中で、この世の森羅万象は互いに関連し合いながら存在していること、丹念に物事を観察していけばそれらの現象をすべて理解することが可能であることなどの彼なりの世界観を形成して(曼荼羅、南方マンダラと呼ばれているそうです)、今では「エコロジー」と呼ばれている、「=生態系」の全体像をとらえようとする思想につながっていく、環境問題の先駆者です。
そうなのか。
僭越ながら、私も個人的には(絶滅寸前のトキを守ろうとか、オオサンショウウオを守ろうとかよりも)、木々も、湧き水も、草花も、笹も、苔も、虫も、その土も、その土に住む微生物も全て丸ごとひっくるめて生態系全部を守るということが大事だと常々思っています。当たり前かもしれませんが、そのためには専門家として鳥類専門などの特定した興味を追求するよりも、生命の世界全てにオープンでありたいと思って山林の管理をしています。120年も前にそうやって森羅万象を知ろう捉えようと人生の全てを賭けた人物がいたということに深く深く尊敬の念を覚えました。
私の尊敬するBenとちょっと似通ったところがあります、Benも植物(樹木含む)も知衣類も幅広く奥深くの知識人です。
もう一つ面白いなと思ったのが、熊楠は神社の鎮守の森の保護活動に深く関わっていたということでした。ご存知の方も多いと思いますが、神社といえばこの方、レオchanです。
noteで神社の鎮守の森を深く理解し、深く愛する人を知ってる。ここでもつながった気がして、もう他人事ではない。南方熊楠によって守られた神社や森、樹木は今も和歌山に多く残っていますが、奮闘むなしく樹木は伐採されたところも多くあったということです。

ということで、現在、和歌山、熊野は一生に一度は行きたいところのナンバーワンにあげたいと思います。
1941年12月29日に、熊楠は74歳の生涯を閉じた。亡くなる前日、床に着く際に、「天井に紫の花が一面に咲き実に気分が良い。頼むから今日は決して医師を呼ばないでおくれ。医師が来れば天井の花が消えてしまうから」と言い残したという。
熊楠が最後に見た一面に咲く紫の花は、何の花だったんでしょうね。
私はスコットランドで2月になると一斉に出始めるクロッカスが待ち遠しいです。

いいなと思ったら応援しよう!

