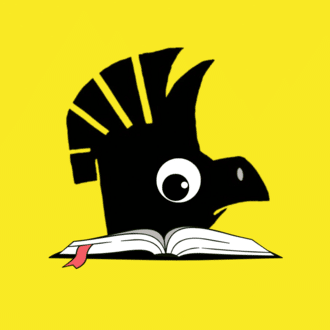学びの本質にせまる隠れた名著『私たちはどう学んでいるのか』レビュー
学校で何年も英語を学んでも、さっぱり話せないという話はよく聞きます。(自分もそうでした)
一方で、海外に住んでいた日本の子供たちは、親よりも優れた英語力を身につけることがあります。
その理由は簡単で、日本の学校で学ぶ英語は「身体化」されていないから。
英語の文字に触れるだけで、それを生活のなかで使うことがありません。
より具体的には、「Appleはりんご」という記号同士のつながりができるだけで、ほかの感覚とむすびついて身体化されていないのです。
今日紹介する『私たちはどう学んでいるのか』は、このような「学びの本質」に迫る一冊。
そもそも知識とはなんなのか?を教えてくれます。
知識ってなに?
知識には3つの性質があります。
(ちょっと説明的で退屈かもですが、つぎの箇所で大切になる概念なので、読んでいただけたらと思います。)
1つは、一般性。いろいろな場面で使えるということです。
たとえば、「りんご」という知識は、スーパーでりんごを買うときだけでなく、料理をするときや、絵を描いたりするときにも役立ちます
2つ目は、関係性。知識は、他の知識とつながっている必要があるということです。
たとえば、「トルストイ」という知識は、「小説家」という知識や、「ロシア」、そして、「戦争と平和」の内容と意義など、関連する知識が結びついていることです。
3つ目は、場面応答性。知識は、それが必要とされる場面で使える必要があるということです。
たとえば、「自転車の乗り方」という知識は、実際に自転車に乗るときに必要になります。
学ぶってなに?
このように知識を捉えると、ある事柄が伝えられただけでは、それは定着しないことがわかります。
本に含まれているのは単に情報であって、知識ではありません。
教室で先生が教える内容も、ただの情報であって、そのままで知識ではありません。そして、それを丸覚えしたとしても、それはただの記憶であり、知識ではありません。
本や学校で学んだ内容が「どの範囲をカバーするのか(一般性)」、「ほかの知識とどう関連するのか(関係性)」、そして「どこで使われるのか(場面応答性)」を考えない限り、たんなる情報や記憶にとどまり、知識にはなりません。
このような考え方を、「構成主義(constructivism)」といいます。
知識とは、自分で構成していくものなのです。
知識はあくまでも「個人的なもの」であり、構成するのはあなた次第。
ここまで学んで、アメリカの哲学者・デューイの『経験としての芸術』という本を思い出しました。
芸術とは、作品を制作する芸術家と、その作品を鑑賞する人々の共同作業。
そして本当の芸術は、作品を見た人の中で生まれる経験なのだと語られています。
「経験」と「知識」は似ているのかもしれません。
「型」の模倣で学びを加速させる
本書では、学びを加速する模倣についても説明されています。
模倣には2種類あります。
1つは「結果の模倣」で、とにかく同じようにやることが目的です。
もう1つは「原因の模倣」で、なぜそうなのかという原因を真似ることで、結果として師のアウトプットを真似ることになります。
前者は形の模倣、後者は型の模倣と言えます。
師匠と生活をともにすることは、身体全体を通して、師匠の発言の意味するところ、つまり原因を自然と理解することにつながります。
まとめ
学びとは、単に情報を記憶するだけでなく、その知識を自分の経験と結びつけ、身体化することが大切です。
そうすることではじめて、本当の意味での知識を獲得でき、さまざまな場面で活用できるようになります。
模倣するときも、形ではなく、型を真似ることが重要。
この本を読んで、自分が本当に学びたいことを学ぶためには、積極的に学ぶことが大切だと感じました。
『私たちはどう学んでいるのか』は、「学び」の本質をわかりやすく解説してくれる名著といえます。
いいなと思ったら応援しよう!