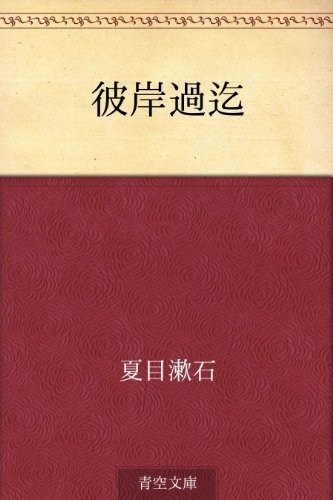滅法面白い小説〜夏目漱石「彼岸過迄」
以前、「虞美人草」について書いたが、その後もポツリポツリと夏目漱石を読んでいる。「三四郎」、「それから」、「門」を再読し、未読だった「彼岸過迄」に進んだ。
1910年(明治43年)、「門」を書き終えた漱石は病気療養に入る。2年弱のブランクの後、1912年(明治45年)1月、漱石は朝日新聞紙上で「彼岸過迄」の連載を始める。
それにあたって、「彼岸過迄に就いて」という序文を書いている。病気で休んだことに触れ、<久しぶりだからなるべく面白いものを書かなければすまないという気がいくらかある>とする。そして、文壇における<空疎な流行語>を使ったレッテルを批判的に表現しながら、<ただ自分らしいものが書きたい>と主張。「彼岸過迄」というタイトルは、<元日から始めて、彼岸過まで書く予定だから>付けた、<空しい標題>と表している。
そして、<個々の短編を重ねた末に、その個々の短編が相合して一長編を構成するように仕組んだら、新聞小説として存外面白く読まれはしないだろうか>というアイデアを持っていたが試みる機会がなく、本作でその思惑を実現したいと書く。
その序文通り、本作は“風呂の後”と題された短編から始まる、全七篇で構成される。まず、このスタイルが素晴らしい。それぞれ、独立した面白さを持ちながら、全体が大きな世界を描く。漱石の目論見通り、<存外面白く>読むことができる。
中でも好きなのは、二つ目の“停留所”。ちょっとミステリー仕立てで、ユーモア性もあり、読んでいて楽しい一編である。
そして、100年以上も前の小説であるにも関わらず、古臭い印象は全くなく、むしろ新しさする感じる。本当に今さらなのだが、「やっぱり漱石はすごい」と思わせる作品である。こんな面白いものを今まで読まなかった私は、一体何をやっていたのか。
さらに、登場人物が動き回る、神田須田町、小川町、明神下。さらには、内幸町、神楽坂上の矢来などなど、私にとって極めて身近な場所が登場することも面白さを倍化させる。街の様子は、明治時代からは大きく変化しているのだが、小説の中の人々が身近に感じられるのだ。
身近に感じる、もう一つの理由は、結局人間の本質は変化していないということ。それを漱石が的確に表現していることにより、明治の人と我々の共通項がテキストを通じて私の中に入ってきたのだ。
伊集院静の「ミチクサ先生」で刺激された、夏目漱石へのアプローチ、まだ半ばである