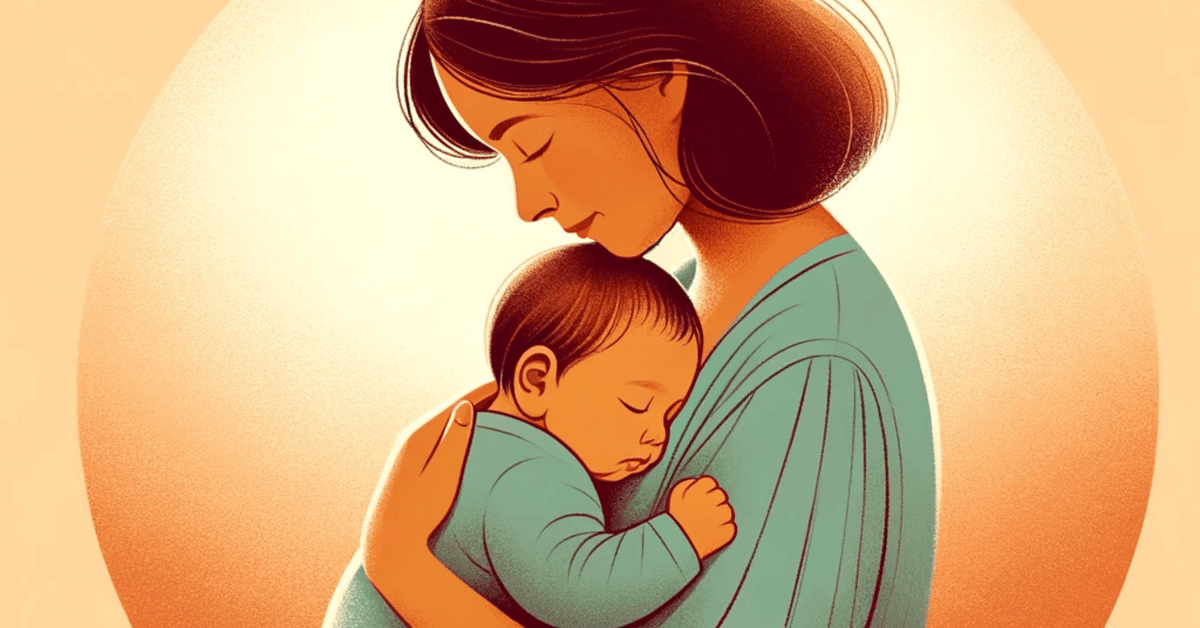
著…松永正訓『運命の子トリソミー 短命という定めの男の子を授かった家族の物語』
小児外科医として染色体異常の子どもやその家族と伴走してきた著者の葛藤が伝わってくる本。
染色体異常を持つ子どもは、残念ながらお母さんのお腹の中にいるうちに命を落としてしまうことが多いです。
また、無事に生まれてこられたとしても、長く生きられないことがほとんど。
「ダウン症」と呼ばれる21トリソミーの子どもは医学の発展によって長く生きられる世の中になってきましたが、この本に登場する13トリソミーの子どもや18トリソミーの子どもは、悲しいことにどうしても短命な傾向があります。
そのことを知っていながら、短い命を医療によってほんの少し長くする…。
この本を読むと、そのことの意味について改めて考えさせられます。
勿論、医療を行えば、その分、子どもと家族が一緒に過ごせる時間を延ばせます。
けれど、短命という現実までは変えられません。
なのに、医療という、自然界から見ると不自然と言える行為を加えることに、どんな意味があるのか…?
…この本から、家族や医療従事者のそうした葛藤が伝わってきます。
治してあげたい。
けれど、治してあげられない…。
また、家族だって全員が同じ考えというわけではなく、一人ひとり、受け入れられる部分と、受け入れられない部分とがあります。
同じ人でも、子どもの体調や自分自身の状況によって、少し前まで考えていたことが揺らぐことだってあります。
子どもや家族の苦しみをそばで支える医療従事者も、子どもや家族にどんな言葉をかければ良いのか、或いは不用意に言葉をかけないべきなのか、何をすべきで何をしないべきなのか、といった正解も見つかりません。
この本を読んでいるわたしにも、結局「どんな意味があるのか」「何が正解なのか」という答えは出せませんでした。
おそらく人間には永久にその答えを出すことは出来ない気がします。
…けれど、一つだけはっきりと言えることがあります。
それは、短命だからといってその子どもの命に意味がないわけではないということ。
綺麗ごとかもしれませんが、短いなら短いなりの人生があるはず。
そもそも、その子が生まれてきてくれることがなかったら、家族はその子と出会えなかったし、その子を愛することも出来ませんでした。
きっとその子の視点から見てもそう。
生まれてくることがなければ、苦しみを知ることはなかったかもしれませんが、生まれてきたからこそ、家族に愛されることを知ることが出来たはず…。
だからわたしはこの世に生まれる全ての赤ちゃんに「生まれてきてくれてありがとう」と言いたいです。
今後ますます医学が発展して、今はまだ助けられない命が、やがては救えるようになることを祈るばかりです。
また、わたしは特に、この本の中の、快斗くんという子のお母さんの言葉が忘れられません。
意味って言われるとよくわからないんですけど、私って、快斗を産むために自分が産まれてきたのかなって思います。
快斗が先にいるんです。それで、私が選ばれて、私が産まれたんです。
わたしには難しいことは分かりませんが、子どもが親を選んで生まれたのではなく、子どもを生むために親が選ばれて生まれたという考え方が素敵だと思います。
〈こういう方におすすめ〉
トリソミーに関心がある方。
〈読書所要時間の目安〉
4時間くらい。
いいなと思ったら応援しよう!

