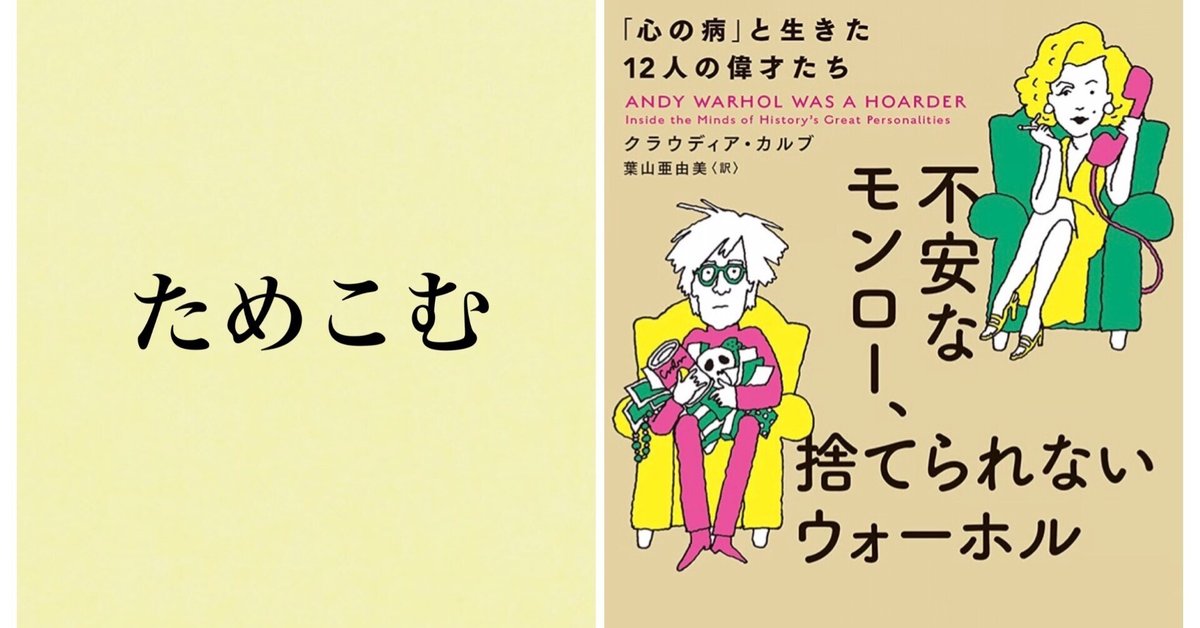
ためこむ
先日、京都市京セラ美術館で開催の「アンディ・ウォーホル・キョウト」展に足を運んだ。
私は、熱心なウォーホル・ファンではないが、彼の著作や彼のプロデュースした音楽には度々触れてきた。京都にいながら、ウォーホルの作品に直接触れられる機会は少ないと思い、久々の美術鑑賞に出かける。
「京都」に関連する作品が展示されていたのが、個人的に面白かった。「京都ドローイング」と題し、清水寺や僧侶、舞妓などが描かれている。また、有名なキャンベル・スープの缶の作品が見れたことも、興奮ポイントの一つである。
*
特別展を訪ねたときの常として、その展示に関連する書籍を読むようにしている。今回も、ウォーホルに関する書籍を一冊手に取った。『不安なモンロー、捨てられないウォーホル』である。
本書は、マリリン・モンローやチャールズ・ダーウィン、エイブラハム・リンカーンといった、世界的に著名な人物たちが、どのような「病」と向き合いながら日常を生きていたかが詳述されている。
12の人物と疾患が紹介されているが、その内の一人がアンディ・ウォーホルである。では、彼が抱えていた「病」とはどんなものだったのか。
「彼はカウンターカルチャーの申し子であり、ポップアートとそれが擁する大量消費社会の顔だったが、カメラやカンバスの裏側にはウォーホルのあまりよく知られていない別の顔があった。彼は歴史上稀に見る「収集家」だったのだ。買い物が大好きで、時間があればいつも安売り雑貨店でもアンティークショップでも高級ギャラリーでも、どこへでも足を運んだ。「彼はどんなものでも貪欲に欲しがっていました」と、ウォーホル美術館のチーフアーキビストのマット・ウビカンは言う。」
(クラウディア・カルブ著、葉山亜由美訳『不安なモンロー、捨てられないウォーホル』日経ナショナル ジオグラフィック、P71〜72)
「量の多さ」へのこだわりは、ウォーホルの制作活動から垣間見えるが、それは彼の生活全体を覆っていた。「ウォーホルは、所謂"ためこみ症"だった」と言われても、何ら違和感がないのはこのためである。
ここで一つ気になるのが、集めたものの扱い方である。もし集めたものを、何らかの方針をもって分類・整理・保存しているのであれば、量がどうであろうと、立派なコレクションであり、「ためこみ症」ではなく「コレクター」なのではないか。
この点について、本書はこう説明している。
「100個のティーカップをガラス棚にきれいに並べるのがコレクターで、100個のバッグにガムの銀紙や小切手、新聞の切り抜きを詰め込むのがためこみ症だ。ウォーホルのタイムカプセルがその最たる例で、レアな写真と座薬の箱が一緒くたになって入っていることもあった。しかも、それぞれの保存状態にはお構いなしだった。「ウォーホルはものの状態をまったく気にせずに箱の中に投げ入れていました」と、アーキビストのウビカンは言う。」
(クラウディア・カルブ著、葉山亜由美訳『不安なモンロー、捨てられないウォーホル』日経ナショナル ジオグラフィック、P80)
集めたものの中には、干涸びたピザの生地や腐ったパンも混ざっていたというから、それを「コレクション」と呼ぶには無理がありそうである。
ウォーホルも、自身のためこみ癖を肯定していたわけではなく、「みんな、何もない広々とした場所に住むべきだ」「こんなゴミだらけの暮らしはもうたくさんだ。それでも、いつも家に何か持って来てしまう」(以上、P81)と、苦しい胸の内を語っていた。
「混沌」と表現しうるウォーホルの収集物は、その混沌さゆえに、結果的に一つの芸術作品として評価され、海外のギャラリーに出展されたものもある。「大量消費社会を自ら体現したアーティスト」と呼べば聞こえはいいが、そこには、常に物に囲まれる生活の中で、もがき苦しむ一人の人間がいたことも確かである。
*
ウォーホルの「ためこみ症」に関する文章を読み終わったあと、私は自身の部屋を見回した。そこには手つかずの未読本が、山のように積まれている。
「私はウォーホルとは違う。なぜなら、"本"に絞って、買い集めているから」
そう自分に言い聞かせたあと、私は読書の続きに取り掛かった。
※※サポートのお願い※※
noteでは「クリエイターサポート機能」といって、100円・500円・自由金額の中から一つを選択して、投稿者を支援できるサービスがあります。「本ノ猪」をもし応援してくださる方がいれば、100円からでもご支援頂けると大変ありがたいです。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
