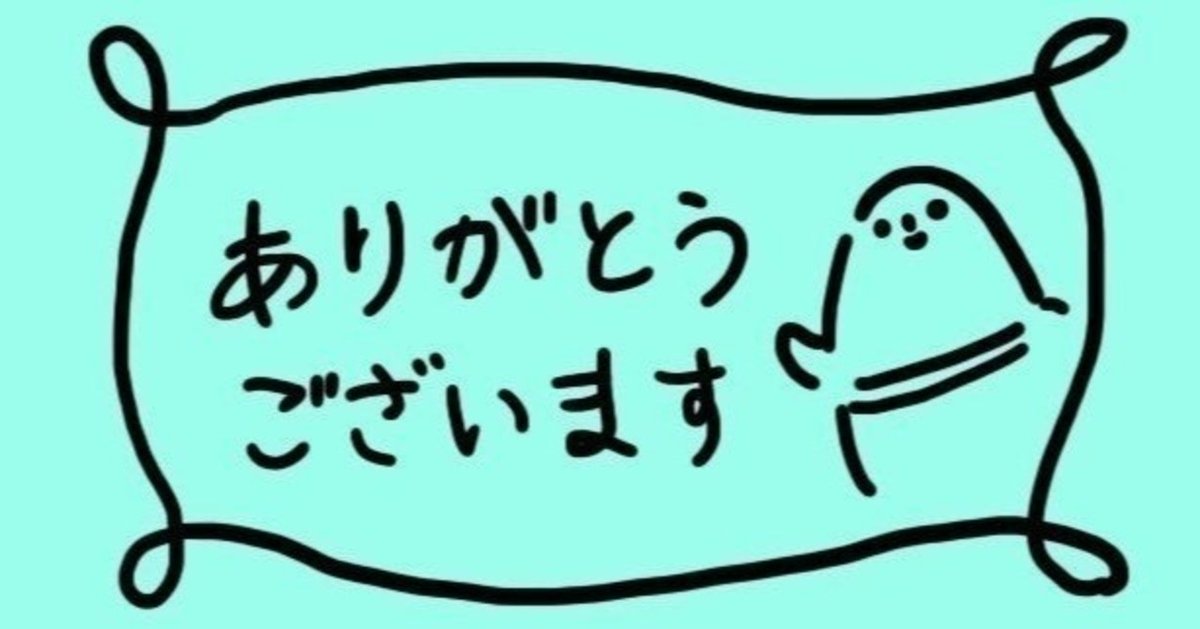
「想いを形にする」ために「考えを言葉にする」べし!-オンライン授業を構想するまで②
こんにちは、いわたつです!
今日は、前回の記事の続きを書きたいと思います!
前回の記事のおさらいとして、いわたつの現在の立場について書きます!
・元小学校の教員で、現在は企業に所属している
・企業では休校期間中に、オンラインの授業を提供していた
・現在は放課後に、企業が「探究学習」のプログラムを提供している
・「探究学習」のプログラムのサポートをしている
こんな立場で、これまで生活科や総合的な学習の時間を研究してきた身ですが
「こんな時どうする?」と言われて、「サッ」と答えを出しません。
というか
出せません!
それはどういう意味かというと、こんなことを考えているからです。
探究学習を創るときに考えていること
探究を創るときに考えていることは、例えば
・出会う教材と子どもとの距離感はどうか
・どのような出会いなら、子どもと教材の距離が近づくか
・出会った教材と、より距離が近づくための体験活動はないか
・調べ学習をするときに、どんな視点をもつことができそうか
・アウトプットはどのようなものがいいか
・アウトプットを一時的なゴールだとして、どんなフィードバックを与えられるようなものにつなげていくか
これだけのことは、考えていても伝えなければ意味がありません。つまり、「言葉にする」ということ
です。
では、これは誰に伝えるのか。
探究の意味を伝えるのは誰か?
子ども?同僚?保護者?
順序的にいうなら、同僚(今回で言えば企業さんの人々)、保護者、子どもでした。(これ、企業さんだからかも)
子どもたちは、授業で直に関わることができるので、自分の思いを1分あれば伝えることができます。
同僚さんたちには、とにかくミーティングしてもらい、相手さんが考えていることを徹底的に言ってもらう。僕自身も一緒に悩む。
すぐ答えが出せること、とりあえずやらないとわからないこと、タネを撒いて待たないといけないこと…
そんなことを共有します。結果論ですが、
この共有に時間を使ってよかった!
が感想です。終わった後に
「これまでで一番創るの大変だったけど、すごいやってよかったー!」
というお返事をもらったからです。(僕から見ても、企業さんのスタンスがどんどん変わっていかれるのを見て、とても嬉しかったのです。)
私たちの想いと保護者の間を考えないと!
探究って「瞬時に答えが出ないときがある」学習ですよね?
この「瞬時に答えが出ないとき」が実はもの凄ーーーーーーーく、大事にしたい時間です。
どうしてかというと、
・わからなくって、うーんうーんって悩んでいる時間
・何かヒントないかなーって、身の周りを見渡している時間
・何かわかりたい!と思って調べ物をしている時間
こんな風にじっくり考える時間って、大人でも結構楽しかったりしませんか?
理論的にも、「答えを出すまでの時間が長い」ことは「考えられる時間を伸ばす」ことにも繋がっていき、
子どもの考える力を(能力的にも耐久力的にも)伸ばすのに、ぴったりだと思うのです!!
と、いうことをおうちの人にも伝えます。
このとき、案外大事なのは
「子どもは子どもの論理の中で生きている」
ということです。
まとめた時、調べた時、子どもたちは、ときどき大人からすると
「そんな論理破綻してるやん!」
ということを言ってきます。
それでも
「アナタはそう考えたんだね!」
とクッションを置くことをすごく大事にしています。
だって、この論理はきっと探っていけば
「子どもの中で一貫しているから!」
です。
自分たちの思いを修正していく
さてさて、そんなこんなで、ワンクール1ヶ月の探究を終えて、
「テーマについて詳しくなれた!」
と大満足の子どもたちで、ひっそり私も嬉しかったです。
これで満足することなく、自分たちの想いと、子どもたちの取り組みのハードルを適切に調整することを、これからも怠ってはいけないなと思う。
いわたつなのでした!
結論
どんなことでも形になっていくのは楽しい。タネを撒いて水をあげて、ワクワクしながら待つことが、形になるまで必要なのだ。このプロセスが、慣れていないと、ソワソワしちゃって実は少し大変。焦って芽を出させようとしても逆効果。
楽しみにしていてあげることが、1番の特効薬!
なんちゃって。
いいなと思ったら応援しよう!

