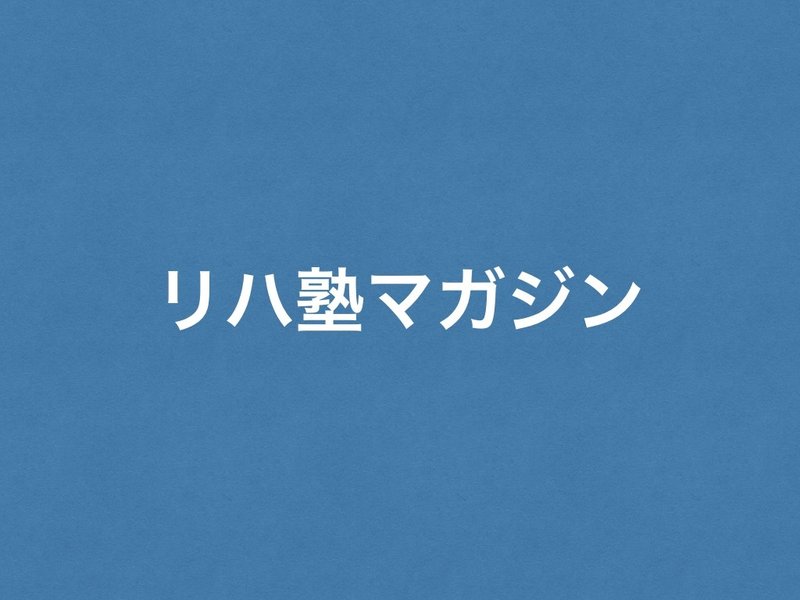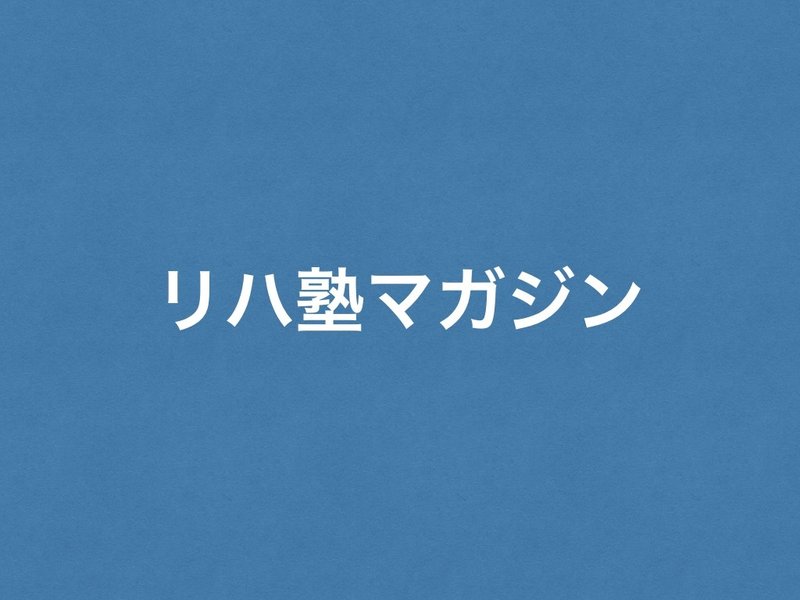大腿筋膜張筋の代償運動を抑制するために必要なこと
火曜日ライターの松井です!
股関節疾患、あるいは股関節以外の下肢の障害において個人的に多いと感じるのが、大腿筋膜張筋(Tensor fasciae latae:TFL)の過緊張によるマッスルインバランスです。
TFLは股関節屈曲・外転・内旋に作用する股関節屈筋群の1つですが、屈筋群においては腸腰筋が機能低下に陥りやすく、TFLに代償的な過緊張が認められやすいです。
腸腰筋はいわゆる股関節のインナーマッスルの1つで、腸腰筋とTFLのマッスルインバランスにより、変形性股関節