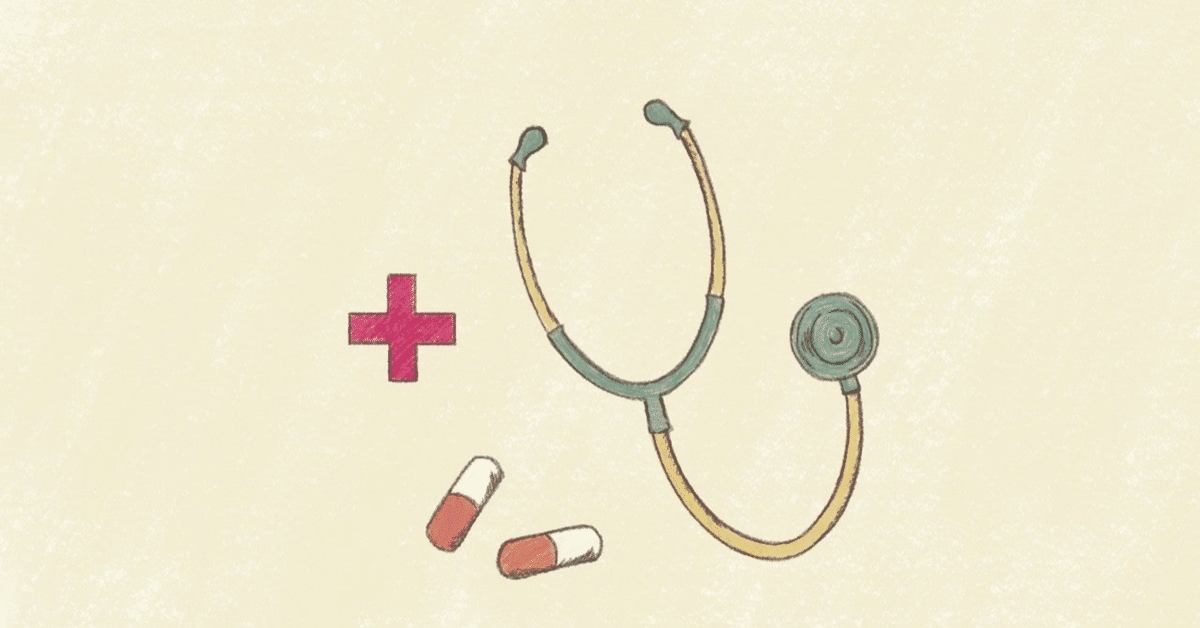
「寄生虫なき病」を読んだ中三女子の感想
この「寄生虫なき病」。
三秋縋さんの小説、「恋する寄生虫」に出てきたんですよ。
それで読んでみたのですが、すごいなぁと。
寄生虫、というよりも、「医学の本」として印象に残りました。
アレルギーや喘息、自己免疫疾患の原因には、寄生虫や病原菌や細菌などに触れる機会が少ない、現代社会にあるのかもしれない・・・という、ざっくりそんな感じの内容なんですよ。
寄生虫が体内にいないという状況は、人類史上初めてのことで。
だから免疫の制御が利かなくなっているのでは・・・。
と、誤解を招くと怖いので、内容に関してはこの辺で止めておきます。
作者のモイセズ・ベラスケス=マノフさん自らも寄生虫療法を試みていらっしゃるんですよ。
そして「本の中には寄生虫や菌の中でも、「旧友」と呼ばれる旧石器時代から人類に寄生していた種類は人の役に立つのかもしれない」という考え方の根拠となるような実験や観察がたくさん出て来ます。
それでも、慎重なんですよねぇ・・・。
そこが凄いなと思って。
モイセズ・ベラスケス=マノフさんはどこまでも冷静ですし。
医学にとってはその慎重さが必要なのかもしれませんがそれでも、というか、それならそれで、また凄いなぁと思うんですよ。
この本を読んで、なのですが、じゃあ結局どうすればいいんだろう?とそう思う心も0ではないです。
多くの有用細菌に曝露した方がいいのか?という問いにも、遺伝子によって色々な答えがあるようですし。
結局アレルギーやら花粉症やらがなくなるためには、医療の進歩を待つしかないのだろうか・・・。と。
(自ら寄生虫に感染して寛解したというケースも出てきたことは出てきましたが・・・。)
ただ、頭の隅には置いておこうと思いました。
他にも人類の歴史と感染症の関係、現代人の生活が腸内細菌叢に与えている影響など、色々と感じたこともあるのですが、この本の感想はざっとこんな感じです。
分厚くて黒い表紙で、難しそうな見た目なのですが中身は根拠と主張が明確でわかりやすい文章でした。
面白かったです。
三秋縋さんの小説、「恋する寄生虫」の感想はこちら↓
この他の寄生虫の本の感想はこちら↓
