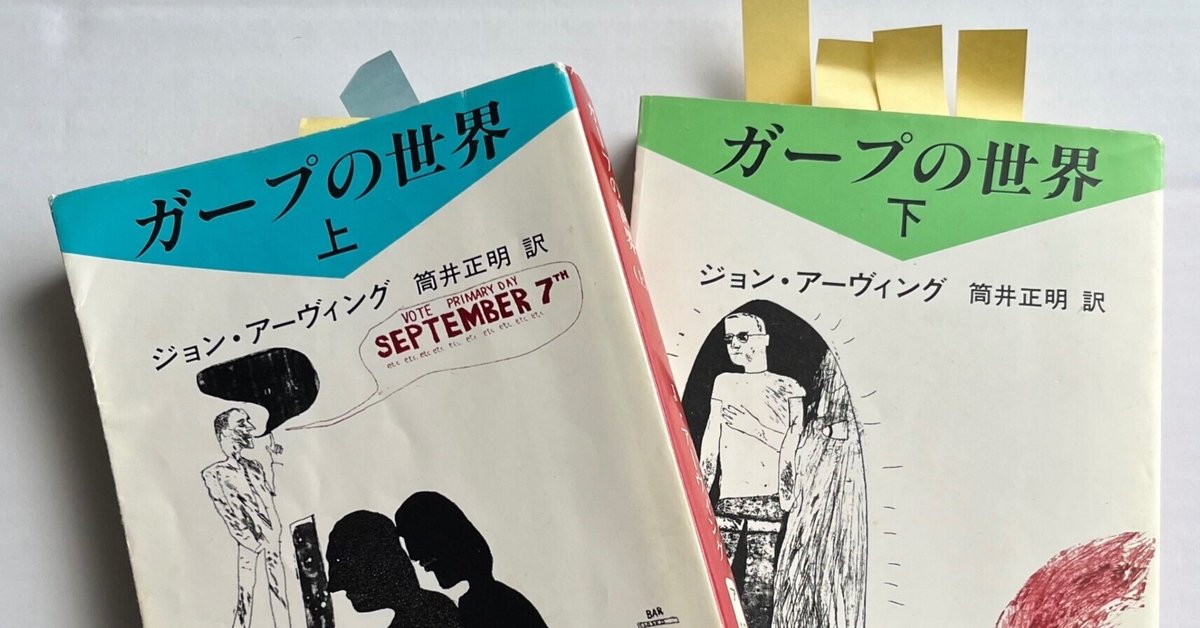
ジョン・アーヴィング『ガープの世界』 その4(全6回)
その4 「小説の中の小説」と「作家論」
※ 物語の決定的な部分はなるべく言及しないように気をつけていますが、説明上どうしても、多少のネタバレをしてしまうと思います。少しでもダメな方はご遠慮ください。
私が『ガープの世界』を繰り返し読むほど好きな理由。
三つ目は。
「小説の中の小説」と「作家論」。
小説の中の登場人物が文章や物語を書くというお話。結構あります。
ミステリーなどに時々見かけます。
そもそも世界でいちばん有名な名探偵(と言っても差し支えないでしょう?)シャーロック・ホームズ。その事件は友人のジョン・H・ワトソンが記録するという体裁をとっています。この場合小説ではなく事件記録ですが、架空の事件記録です。
アーヴィングと同じ国アメリカでは、名探偵エラリー・クイーン。(作者もエラリー・クイーンです。エラリー・クイーンが書いた推理小説の主人公エラリー・クイーンは人気推理小説作家で名探偵という設定。面白いです。時々再読します。)
作中では、彼の推理小説が存在してそれを読む熱心な読者がいて人気作家で、ということに。
ミステリーだけでなくファンタジーにも。ミステリーとファンタジーの境目のようなお話で、作中作と本編が混ざり合って虚構と現実の境界がわからなくなって謎が深まるみたいな不思議な物語もありますね。(結構好きです。)
他には。架空の小説そのものを題材としたものもありますね。
スタニスワフ・レムの『完全な真空』とか。
これは架空の小説の、あくまでも書評集ですけど。(かなり好きです。)
『ガープの世界』の場合。
ガープは作家ですから、当然彼が書いた小説が存在するということになります。
そしてアーヴィングは、ガープはこんな小説を書いていますよと、簡単に紹介して終わらせるのではなく、その作品をちゃんと書いて実在させてしまいます。
あらすじや創作過程だけでなく(それもかなり詳しくて書かれているのですが)、小説そのものを。
これがとても面白いのです。
全文、読めるものもあります。
いくつか紹介します。
1. 『ペンション・グリルパルツアー』
ぼくの父はオーストリア観光局に勤めている。
『ガープの世界』 新潮文庫 1988年。
上巻 p.205
ガープのデビュー作。冒頭の一文です。
『ガープの世界』本編の冒頭の文章(その2で引用しました)「ガープの母、ジェーニー・フィールズは一九四一年、映画館での傷害罪のためボストンで逮捕された。」と比べると、全然雰囲気が違って、私としては「さすがアーヴィング」となりますが。
内容は。
オーストリア観光局に務める父親とその家族がホテルやレストランを訪れ、それらを査定するお話です。
作品の物悲しい優しさ、人間に対する豊かな憐れみと穏やかな暴力性
が溢れ、素晴らしい物語です。
あとこれ。
ガープは途中まで書いて結末部分をどうしようかと悩みます。
そのため前半と後半に分かれ、この間にガープのウィーンでの生活の記述が入ります。
彼はウイーンでマルクス・アウレリウスの英語版『自省録』を買って読んだり、ウイーンの作家フランツ・グリルパルツアーの部屋が博物館で再現されたものを見てジェニーとジョークを言い合ったりします。(この二人の会話。グリルパルツアーには申し訳ないほど言いたい放題です。不謹慎で皮肉が効いてて面白いですけど。)
題名の『ペンション・グリルパルツアー』のグリルパルツアーはこの作家の名前から取ってきたのだろうと思われますが。
フランツ・グリルパルツアーは一八七四年に死んだオーストリアの詩人・劇作家で、オーストリアの外にはほとんど知られていない。十九世紀ののちまでも名声を残すことのない十九世紀の作家のひとりであり、のちにガープは、彼が名声を残さなかったのもけだし当然だと論じている。
とか言ってます。
その後
マルクス・アウレリウスのわびしい省察のテーマは間違いなく、大部分のすぐれた作品のテーマとなっているものである。グリルパルツアーとドストエフスキーの違いはテーマにあるのじゃない。違いはそのテーマを扱う知性と洗練度にある。その違いがつまりは芸術だ、とガープは結論した。
などと実在の人物たちの名前をあげながら、ガープの作家論、芸術論が出来上がっていく過程が語られます。
もちろん、彼はウイーンで、他にもたくさんの体験、というか主に母親ジェニーやウイーンの娼婦たちとの関わりから多くを学ぶのですが。それは次回、その5でもう少し詳しくお話しする予定です。
さて。
ウイーンの体験から彼は、物語にどのような結末を与えるのことになるのか。
ああ、なるほど。
となります。素晴らしいです。
2. 『用心怠りなく』
「作家特有の嫉妬心から」(同上 下巻 p.33)妻ヘレンのために書いた短編。
でもヘレンからは「軽すぎるの。」とか「大したことないわね。」とか言われ、果ては『ペンション・グリルパルツアー』の「十分の一の価値すらないわ」とか言われてしまいます。
かわいそう。
まあ、この時のヘレンの辛辣さには理由があるのですが。
3. 『ベンセンヘイバーの世界』の一章全部。
辛く厳しく残酷な物語です。 ガープとその家族を襲ったある悲劇の後、彼が作家として書かざるを得なかった小説ということなので、かなり辛い物語です。
ジェニーの自伝とガープの本すべてを出版してくれた編集者ジョン・ウルフは
”腹に応えるようなガープの文章表現の迫真性”などの長所にもかかわらず、二流のメロドラマであると結論した
のですが。
確かにそうかもしれませんが、それでもたまに私は読み返します。
その理由はある登場人物が代弁してくれるのですが。私はその言葉に、
ああ確かにそうだな。
と思いました。
この代弁者についても、その5でお話しする予定です。
ジョン・ウルフはこの作品をなんとか売れるよう努力してくれますが、内容が内容だけになかなか難しく、いくつか工夫を凝らします。そのせいでまた大変なことになるのですが。
その辺り。現代の出版事情に対する皮肉な状況などもわかって面白いです。
小説の中に小説が書かれると。
単純に、一度にいくつもの物語を読むことができる楽しさがあります。
さらに『ガープの世界』では。
主人公ガープの人生の諸段階に合わせ、それぞれの作品の主題もテイストも変化したり。
ガープ自身も、その妻ヘレンや編集者ジョン・ウルフや母親ジェニーも、そのほかたくさんの登場人物が、作品を批評し、いいとか悪いとかコメントして様々な作家論や創作論が展開されたり。
『ペンション・グリルパルツアー』のように、彼の創作論、作家論が出来上がっていく過程も描かれ、それが作品にどのような影響を与えたかがわかったり。
架空の作中作と登場人物たちによる作家論。
それらがよくできていればいるほどリアリティは増し、物語全体を確かなものにすると思います。
そうして次第に。
まるで本当にガープという作家が実在しているような感じ。が、増幅されていきます。
そこで。
「あれ? ガープって架空の作家だよね?」となって。
私はこの、架空であるのにまるで実在するような錯覚を起こさせる仕掛けの数々が楽しく、その細部にまでこだわり作り上げるアーヴィングの筆力に舌を巻くのです。
架空の作家の架空の作品をリアルに存在させること。
これ。読んでいると
「でもこれ、架空なんですよね?」と尋ねたくなります。
そのたびに、小説が虚構であることを却って強く意識させられて。その遊び心みたいなものが楽くて。
こういう感じ面白いと思いませんか?
ちなみに。
訳者である筒井正明氏の巻末解説から。
アーヴィングが実際に『ガープの世界』を書き上げるまでに書いた作品と、ガープが『ガープの世界』の作中で書いた小説を比較すると。
「単に作品の数が一致しているだけでなく、作品の内容もかなり相互に符合しあっている。」
そうです。
面白いです。
次回は
その5 『失われた登場人物──映画化に伴って① 』
前回 その3 『「のちに彼はこう書いている」式文章。』
その1 『狂気と悲哀。だけでなく』はこちらから
いいなと思ったら応援しよう!

