
本日の読書 #065 「自分が当事者のテーマで書く」

参考書籍:『スマホで「読まれる」「つながる」文章術』 奥山晶二郎
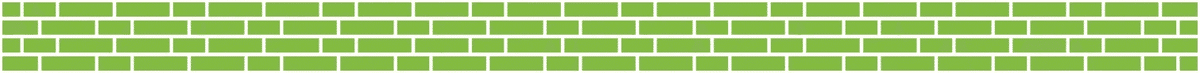
第三章 つながる文章には、まず「自分を出す」 より

自分が当事者のテーマで書く。
「私」がした体験、「私」が出会った人、「私」が見たこと、感じたこと。
文章の「当事者性」が高ければ高いほど、発言の説得力は増し、発信は価値的になる。
例をあげてみる。
私は最近、まつむらnoteさんの記事をよく読ませていただいている。
国際結婚をされて、アメリカに住みながら二人の子どもを育てているnoteクリエイターさんだ。
たとえば私が「アメリカの生活について本で読んだら、これこれこう書いてあったよ」と発信しても、それはあくまで「インターネットに転がる情報」の域を出ない。
今回の話で言えば「当事者性が低い」ということになる。
一方で、まつむらnoteさんの書く「当事者性が高い」文章はどうだろう。
「今日アメリカのスーパーに行ったら〜」から始まる文章。
同じアメリカのことを書いていても、読者に与える印象や魅力、そして説得力は、同じ土俵に立ってすらいないぐらいに異なってくる。
さて、ここまで読んで、勘の良い方ならお分かりの通り、この話には「当事者性の高さ」の他にもう一つ、重要な要素がある。
それは「テーマの希少性」だ。
つまり自分が「何の」当事者なのか、ということ。

「当事者」は、一つではない。
たとえば私なら、
「男性」「父親」「30代」「薬剤師」「転職経験者」など複数ある。
もっと細かく分ければ、「私」という人間は、「無数の当事者」で構成されている。
「唐揚げが好き」とか「神経衰弱が得意」とかもそれにあたるからだ。
当然、その「当事者」全てが同価値ではない。
たとえば「私は、男性であることを活かした発信をします!」と言っても見向きもされないだろう。
なぜなら「男性」という要素に希少性が無いからだ。
つまり、発信を価値的にするためには、自分の中に複数ある「当事者」の中から、より求められるものを探す必要がある。
そのためには自己理解、いわば「メタ認知」が大切だ。
自分の中に存在する「当事者」たちが、集団の平均からそれぞれどの程度、離れているか。
それを考えることが、自分の発信を価値的にするのだと思う。

いいなと思ったら応援しよう!

