
【レビュー】『なぜ自殺は減らないのか - 精神病理学からのアプローチ』大饗広之
地球全土で繰り広げられた弱肉強食の世界で勝利し、生存に困らない生活を見事勝ち取ったと思われた我々人間だが、奇しくも「自殺」を切望する人が後を絶たない。
19世紀西洋で急増した自殺傾向を分析したデュルケームはこう説いている。
(近代になって)自殺が増えたのは、生活を維持するうえで一層つらい努力を強いられているからでもなければ、人びとの欲求が以前ほど満たされなくなったからでもない。むしろそれは、人びとがもはや正当な欲求がどこで留まらなければならないかを知らないからであり、自らの努力に方向をみいだすことができないからである。
最終的に彼が辿り着いた結論はこれだ。
人は貧しさゆえに死ぬのではない。
………………….
我々人間は「わたし」という物語を生きていて、それぞれがその物語の主人公であるのだから、富の有無に関わらずとも死を望んで自ら物語の幕を降ろすことができてしまうのだ。
しかし、自殺が本人だけでなく周囲をまきこむほどの悲惨さを招くという事実からすれば、否が応でも自殺は容認できない。
特に将来の無限の可能性を秘めた小中高生たちが、学校という小さな社会を世界の全てだと思い込んで自らの命に手をかけるなんてことは決してあってはならない。
では日本は、この問題に対しどんな対策をしてきただろうか。
そう、
いじめ対策という名の下で、生徒を徹底的に管理する
ということである。
この対策のおかげか、教員がすぐに気付けるような「わかりやすいいじめ」は減った。
しかし一方で、自殺者は減るどころか増え続けた。
なぜか。
…
今回は、そんな問題を精神病理学的アプローチから分析した『なぜ自殺は減らないのか』(大饗広之)という本を紹介する。
著者である大饗広之先生は、精神科医及び大学教授のご経験を持っていらっしゃる。
精神科医特有のアプローチといえるだろうか、本書では自殺増加を原因-結果という単純な線的関係ではなく、いじめや虐待、自傷行為や乖離を含めた「心的・社会的複合」の一つの兆候とみなし、論が展開されていく。
特にこの「心的・社会的複合」というのが、「気分性」「物語性」「攻撃性」の3つの側面からじっくり切り込まれていくのだが、それらの関係性によって自殺につながる社会的要因や精神的変化が説明されていく感覚は見ものだ。
また本書では、実際に自殺願望を抑えられないなどして診療に来た患者との対話が複数取り上げられており、自殺願望をもつ学生の言葉がリアルに描かれているのも特徴の一つである。
中には精神障害のような兆候がどうも見つからない、いわゆる「ふつう」の学生があっけなく命を終わらせてしまうという事例もあり、改めて自殺の恐ろしさを痛感した。
彼らの症例を元に、まずは現代の自殺の特徴が「不可解な死」という題材で紹介される。
1.気分性
以前は「自分の人生の物語がうまくいかなくなって、何もかも嫌になってしまった」というように、いわゆるうつ症状から起因する自殺が一般的であった。
ところが現代では、「生きている意味が分からない」「不満はないのだが、時にひっそりと死にたくなる」といった古典的なうつ病とは異なるニュアンスの精神状態から起因する自殺が特徴的であるそうだ。
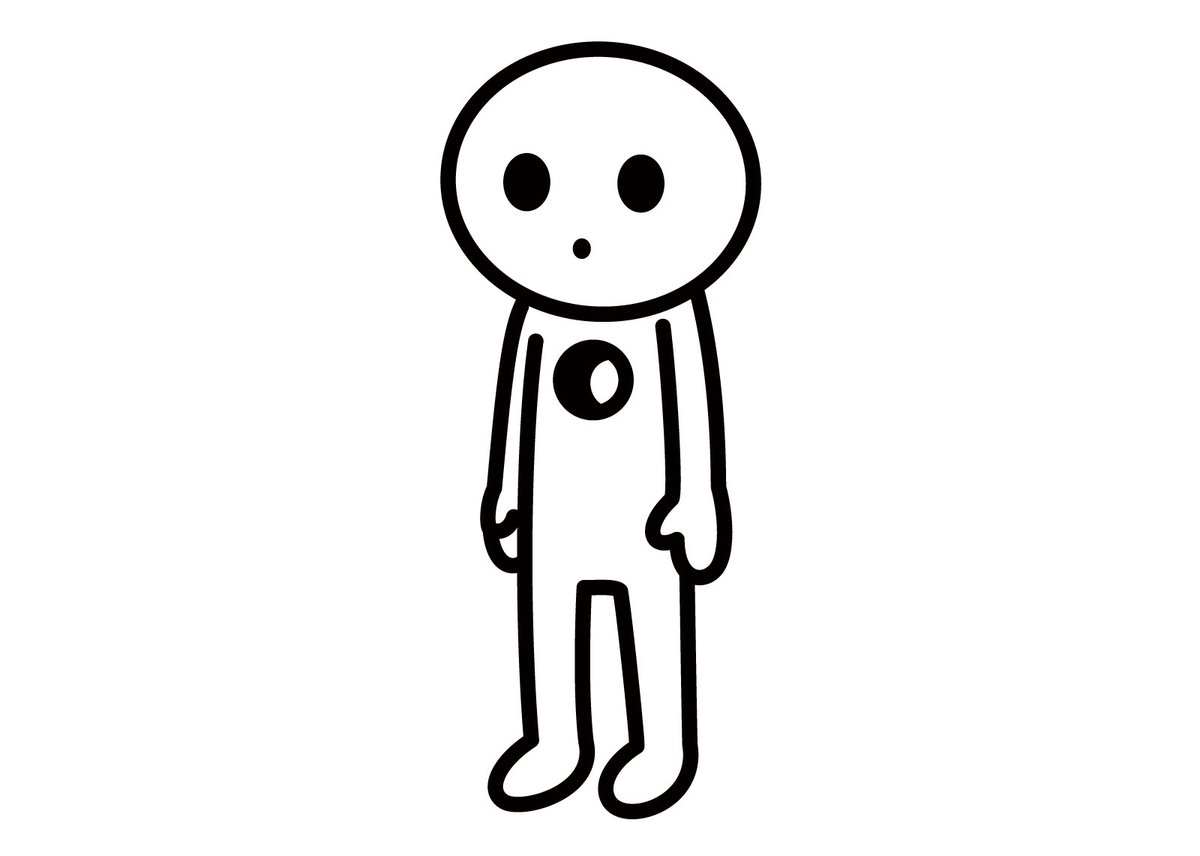
喪失感、とでもいうだろうか?
彼らの自殺の兆候となる「気分性」が変化したのである。
この背景を、筆者は「物語」という言葉を用いて説明する。
2.物語性
突然だが、日常生活の中でこう感じたことはないだろうか?
家族の前、学校、部活… さまざまなコミュニティの中で、自分は異なる(求められる)キャラを演じている。

自分がいるその時の場面によって、Aモード、Bモードといったようにキャラを切り替える感覚。
自分の気分が少し暗くても、このメンバーといる時は「明るいいじられキャラ」を演じなければならない感覚。
多くの人が感じたことのあるであろうこの傾向も、現代社会の立派な特徴であり、実は前述した「気分性」の変化の一要因なのである。
本書では、そんな自分がキャラを演じる舞台となるステージそのものやその中で培われる社会を「小さな物語」という言葉で説明している。
この「小さな物語」が一度形成されると、その物語には学生の唯一の救いの手である学校の教員さえ介入できなくなる。
いくら教員側がいじめ対策として生徒を監視しようと、今のいじめは教員の目の届かないネット上などで陰湿に行われるものであったりするため、見つけ出すのはやはり困難なのである。
そう、これがいじめとそれによる自殺がなくならない理由のうちの一つだ。
3.攻撃エネルギー
ただし、いじめは「小さな物語」だけで説明できるような簡単な問題ではもちろんない。
筆者はさらに、戦後からの自殺者数の推移を年ごとの社会問題に基づいて読み解き、新たな指標「攻撃エネルギー」を説く。

人間誰もが持っている、攻撃性の一面。
すなわち、いじめる側がいじめられる側に発散しているものだ。
この攻撃性を消滅させようと、いじめを外側から徹底的に管理しても、いじめる側の攻撃エネルギーは止むことはない。
ネットなどの監視の届かないところへ、小さな物語の中へと発散される。
それでは、いじめられる側の攻撃エネルギーはどこへ行くのだろうか?
いじめられるばかりでどこにも発散できず、溜まりに溜まったエネルギーは、そう、自分へ向いてしまうのである。
終わりに
本書では、ここで紹介した3つの側面「気分性」「物語」「攻撃エネルギー」の複雑な関係性が、病理学的観点から巧妙に紐解かれている。
以前は「小さな物語」はそこまで顕著ではなかった。なぜか?
以前は「攻撃エネルギー」はどこに発散されていたのか?
自殺はどのような条件が揃ったときに起きてしまうのか?
いじめの徹底管理ではいけないのであれば、いじめによる自殺をどう減らすべきなのか?
いじめに限らず、「小さな物語」だらけの現代をどう生きるのが術なのか?
気になった方はぜひ、本書を手に取ってもらいたい。
