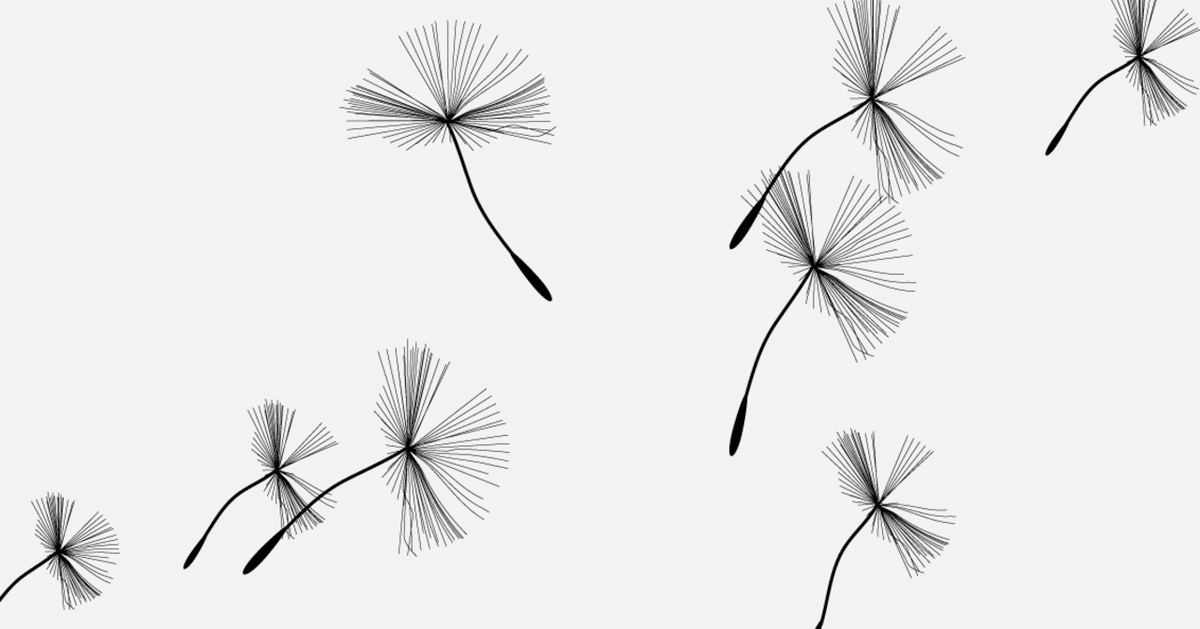
Photo by
air_mezzanine
“100人の召使い”を、一人ひとりが解放してゆく
小川幸司氏の『世界史との対話〈下〉―70時間の歴史批評』(地歴社、2016年)を、最近ふと読みかえしました。
〈上〉〈中〉〈下〉に渡って、大きな世界史の流れを講じられたなかで、最終講「トリニティからチェルノブイリとフクシマへ」の最後の箇所が、5年前にはじめて読んだときから、私にとって大切な文となっています。
月尾嘉男『縮小文明の展望』(東京大学出版会、2003年)を参考にされながら、以下のような指摘をされています。
・かつて狩猟採集をしていた頃の人類は、自分の身体を維持するだけの、1日2000kcalくらいのエネルギー消費量で生活したと思われる
↓
・現在では、1日に25万kcalを越えるエネルギーを、私たち一人一人が消費している
↓
・古代の王侯貴族の召使の1日の食事が2500kcalだとすれば、私たち一人一人が、約100人の召使を抱えて生活しているようなもの
こうした指摘を受けて、小川幸司氏がどのような“問い”を読者に投げかけているかは、本書に直接あたっていただくとして、
私にとってやはり、“約100人の召使い”という表現がとても身に迫ってくるものがあります。
したがって現代における「自由」の問題には、私たち一人一人の“100人の召使”の「解放」というテーマが視野に入らなくてはならないはずなのです。
と、小川氏が記しているように、「自分自身がいかに生きるべきか」などを考えていく上で、まず目には見えない隠れた“召使い”を一人ずつ解放してゆくことが、自分の生き方を変えていく上での一歩になるような気がしています。
そうすれば、きっともっと“身軽”に過ごしてゆくことが可能になるのでは?と思っています。
