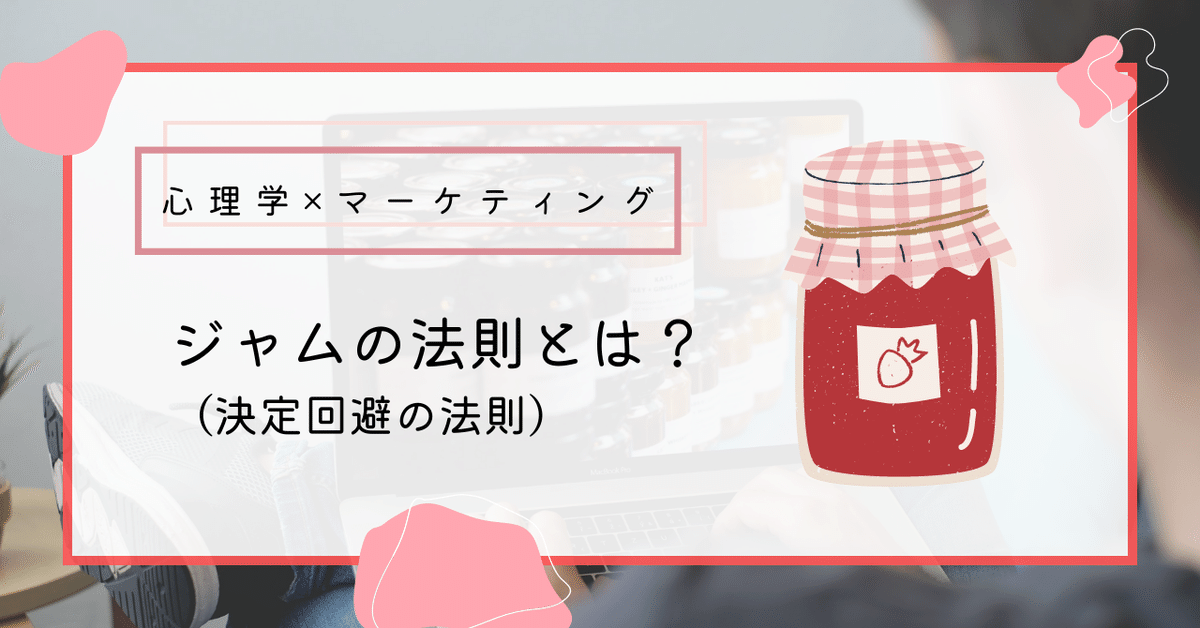
「ジャムの法則」とは
みなさんは、レストランやカフェに行った時にメニューの選択肢が多くて選べないと思ったことはありませんか?
このような状況を心理学用語で「ジャムの法則」といいます。
今回は、「ジャムの法則とは何か?」から「どのように活用するのか?」まで実用例を含めてご紹介いたします。
ジャムの法則とは?
ジャムの法則とは、
選択肢が多すぎると、選べなくなってしまう心理現象のことで、別名「決定回避の法則」とも呼ばれています。

冒頭で挙げたカフェを例に考えてみましょう!
カフェに入って何にしようか選ぼうとした時に、メニューを見たらドリンクやフードが30種類くらい書かれていると、「えっと、どれしようかな、、、」と選ぶのに疲れて負担がかかってしまいますよね。
逆にメニューが少ないと選択する負担がなくなり、食べたいものや飲みたいものが選びやすくなることで、選択自体を回避する確率が低くなるのです。
なぜジャムなのか?
選択肢が多すぎて選べない状況はたくさんあるのに、なぜジャムなのか不思議に思いませんか?
それは、この法則を発表した、『選択の科学』の著者で知られるコロンビア大学のシーナ・アイエンガー教授が、実験でスーパーのジャムを使ったからなんです!
実験内容
シーナ・アイエンガー教授が行った実験は、
スーパーマーケットに買い物に来たお客さんに対して、ジャムの試食販売をする単純な実験です。その中で被験者を2つのグループに分け、それぞれジャムの種類の数を変えて、どれだけ売れたかを観察しました。

被験者グループAでは、6種類のジャムを用意。
被験者グループBでは、24種類のジャムを用意。
実験結果
6種類のジャムを用意していたAグループでは、試食をした人が40%、試食後に実際に購入した人が30%いました。
すると全体の購買率は12%となります。

ところが、24種類のジャムを用意していたBグループでは、試食をした人が60%だったのにも関わらず、試食後に実際に購入した人が3%しかいませんでした。
全体の購買率は1.8%となり、6種類のジャムを用意していたAグループに比べて、約7分の1程度と大きく購買率が下回りました。

選択肢が少ない方が多く売れた原因は、意思決定(選択)する際に人間はエネルギーを必要とするため、その選択肢が多すぎると考えることにストレスを感じてしまい、「選択をやめる」という決断に至る可能性が高くなるからです。
この結果から選択肢はあればあるほど良いなどの考えは正しくないことがわかります。
選択肢は〇個に絞るべし!
それでは、いくつ選択肢があったら最適なのでしょうか?
それは、人が一度に処理できる情報の限界を数値化した数「マジカルナンバー」によって、明確に個数が決められています。
長年「7±2」が最適であるとされてきましたが、2001年に心理学者ネルソン・コーワン氏が提唱した新マジカルナンバーは、「4±1」となっています。
つまり、3~5個が最適な選択肢の数と言えます。
情報量が多くなるにつれて、人は情報処理を簡略化していく傾向があることがわかります。
ここでいう”最適”とは、人が自信を持って選択しようという気持ちになり、選択した結果について満足できることを指しています。
マーケティング活用方法
マーケティングとして活用するには、選択肢を絞ることが重要です。
どのように選択肢を絞るかは以下をご覧ください。

<アイテム数で選択肢を絞る方法>
そもそものサービス数(商品数)を少なくする。
複数あるものを1つまとめて提示する。(松竹梅など)
<機能で選択肢を絞る方法>
フィルター機能
レコメンド機能(手動)
レコメンド機能(自動)
実際に私はWEBサイトのマーケティングでカテゴリやタグの数を減らしたり、レコメンドするものを制限したり、ユーザーに選択肢を絞らせる工夫をしています。
注意点
しかしジャムの法則は、あくまで購買率のような成約率(コンバージョン率)のみ適用された法則であるため、時と場合によって結果は変わります。
販売数 = 機会数(アプローチ数)× 購買率(コンバージョン率)
例えば、先ほどのジャムで言うと、
6種類のジャムを用意していたAグループに100人が試食した場合は12人が購入するが、24種類のジャムを用意していたBグループに1,000人が試食した場合は18人が購入します。
その場合は24種類のジャムを用意していたBグループが販売数や売上が高くなるのです。
この場合、機会数(アプローチ数)も含めて目を向ける必要があるため、目的や集客状況によって使い分けなければならないのです。
まとめ
みなさんも実は身近に感じていたあの「選び疲れ」。
心理学では「ジャムの法則」と呼ばれ、選択肢は3〜5(4±1)が最適だと学びました!
活用事例は探してみると、意外にも身近なところにもあるかもしれませんので、選び疲れを感じた時はぜひ周りの人に自慢してみましょう(笑)自分が他の人に選択を促すときも、相手に選び疲れをさせないように心がけましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
いいなと思ったら応援しよう!

