
【読書note6/新書】『信長の城』
大河ドラマ『どうする家康』を見ていると、「え、これ、城なの?」と思うことがあります。「〇〇城では…」とのナレーションが入っても、「館にしか見えない…」と思ってしまうのです。
「城」と言って思い浮かべるのは、名古屋城とか、暴れん坊将軍な姫路城とか。ああいった壮麗な雰囲気の建物です。現在、1560年代真っ只中の『どうする家康』ではまったく見かけない形状をしています。
でも、それが正解。
多くの人が「城」と言われて思い浮かべるのは、近世に入ってから建てられたものなのです。で、それはあくまで「近世」に入ってからの話であって、大河ドラマで描かれている1560年代にはまだ出現していませんでした。
そう、あの織田信長公のアタマのなかにさえも。
そんな「城」の変遷を、織田信長公の関わった「城」を軸に丁寧に紐解いていくのが、今回ご紹介する『信長の城』です。
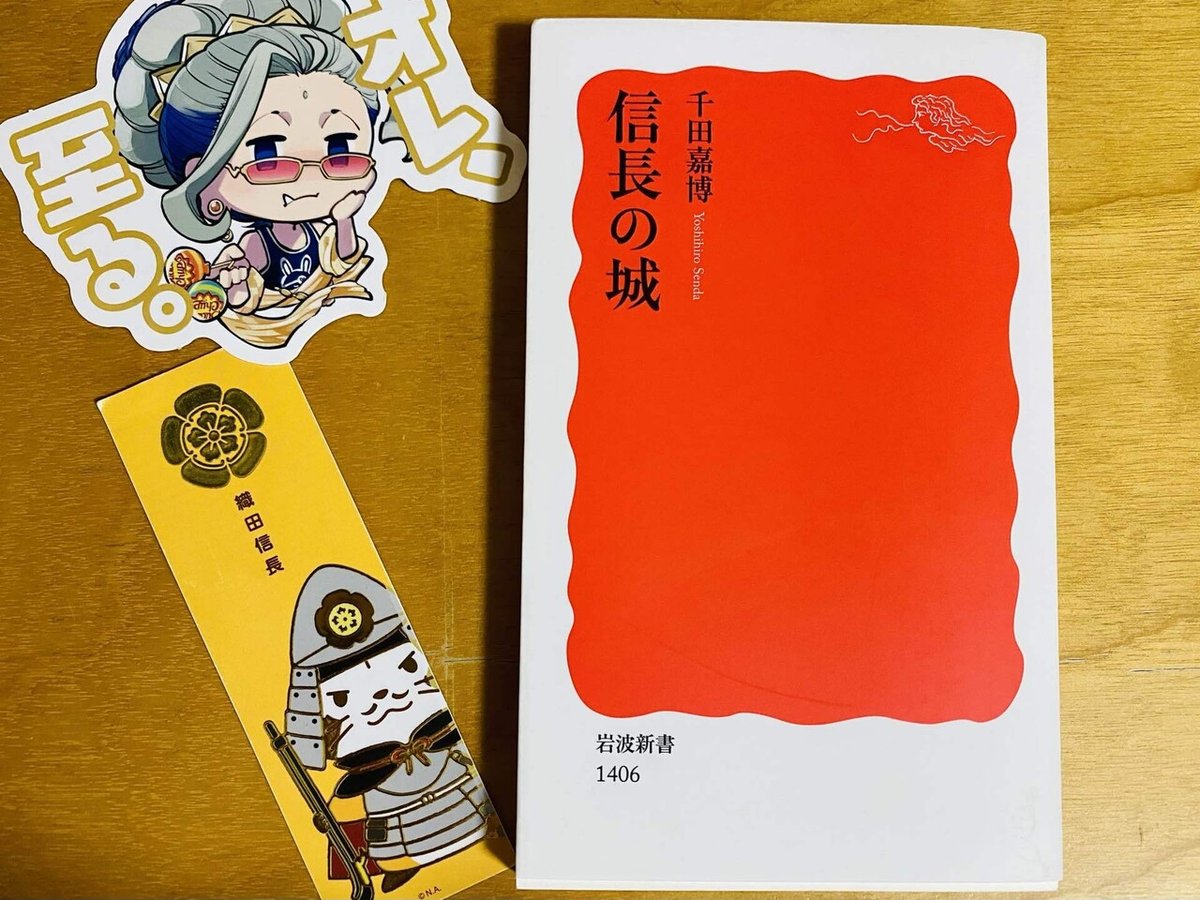
*こちらは有料記事です。
マガジン【えりた書店】に収録しています。
よろしければ、そちらも御覧ください。
■『信長の城』について
■千田嘉博著
■岩波新書(赤1406)
■2013年1月
■880円+tax
信長の天下取りへの道が、その城からわかる! 謎だった信長誕生の城はどこか。築城後、五年で移された小牧山城は仮の城にすぎなかったのか。岐阜城や、壮麗な天主をもった安土城の構造から読み解く、信長の意思とは。近年とみにすすんだ発掘成果をふまえ、絵図や宣教師の手記などの文字史料を総合、進化しつづけた城を楽しく解説する。
■近世の曙
※ワタクシ、名古屋おもてなし武将隊の織田信長さまを推しております。そのため、「織田信長」という人物を呼び捨てにすることができません。この記事では、最愛の推しさまと区別するため、「織田信長公」とお呼びします。
*織田信長さまについてはコチラを御覧ください♡
・ ・ ・
織田信長公という人物を顧みるとき、最近の研究では徐々に変化してきているとはいえ、「革新的」とか「型破り」とかそういった言葉がアタマを駆け巡ります。
その下地があるからこそ、1560年に起きた桶狭間の戦いを「近世の曙」と称することに異論が出ないのでしょう。
でね。私、「近世の曙」という語ってすっごく秀逸だと思うんです。
この「近世の曙」という語が示すのは、信長公が桶狭間の戦いで勝利されるまで、日本という国は近世ではなく「中世」だったということであり。それは単に歴史事象というだけでなく、人々の環境だったり、価値観だったり。
公を取り巻くすべてが「中世」だったということ。
もっといえば。
信長公自身も「中世」の価値観を有していたということだと思うんです。ただし、彼はそこに留まろうとはしなかった。もがいてあがいて、自分を取り巻く理不尽なモノを根本から変革しようとした。
それを総称して「近世の曙」って言えるのだと思うんですよね。
でね。
それは「築城」という面においても同じだったのです。
記事をお読みいただき、ありがとうございます。いただいたサポートはがっつり書籍代です!これからもたくさん読みたいです!よろしくお願いいたします!

